小児心身医学会ガイドライン集 改訂第3版【電子版】
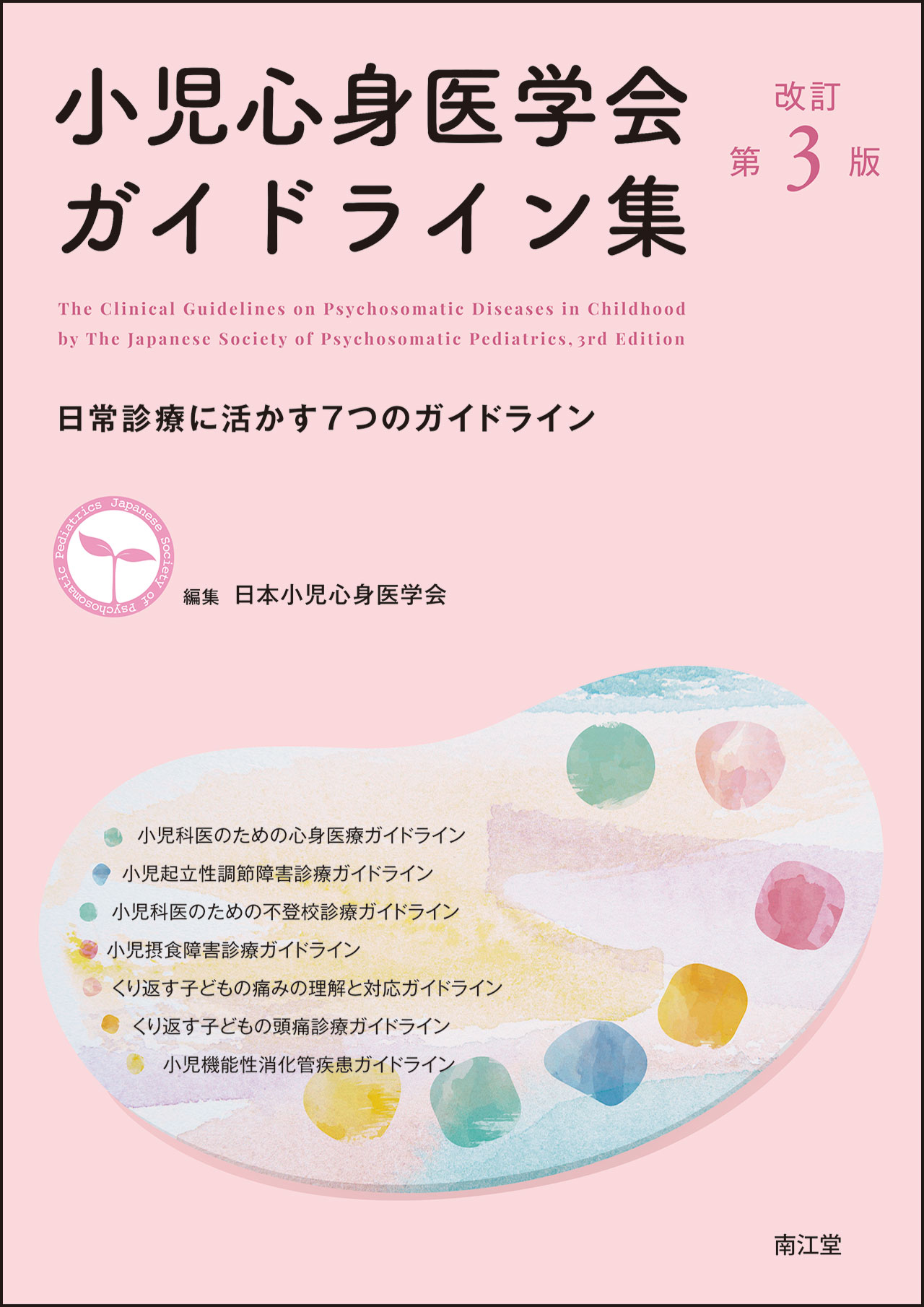
- 出版社
- 南江堂
- 電子版ISBN
- 978-4-524-27247-1
- 電子版発売日
- 2025/09/29
- ページ数
- 324ページ
- 判型
- B5
- フォーマット
- PDF(パソコンへのダウンロード不可)
電子版販売価格:¥5,280 (本体¥4,800+税10%)
- 印刷版ISBN
- 978-4-524-20472-4
- 印刷版発行年月
- 2025/10
- ご利用方法
- ダウンロード型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 3
- 対応OS
-
iOS最新の2世代前まで / Android最新の2世代前まで
※コンテンツの使用にあたり、専用ビューアisho.jpが必要
※Androidは、Android2世代前の端末のうち、国内キャリア経由で販売されている端末(Xperia、GALAXY、AQUOS、ARROWS、Nexusなど)にて動作確認しています - 必要メモリ容量
- 60 MB以上
- ご利用方法
- アクセス型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 1
※インターネット経由でのWEBブラウザによるアクセス参照
※導入・利用方法の詳細はこちら
この商品を買った人は、こんな商品も買っています。
概要
目次
小児科医のための心身医療ガイドライン
本ガイドラインについて
子どもの心身症の定義
A. 心身症の病態
1. 心身相関
2. 心理社会的因子
B. 心身症の治療
1. 心身症の初期対応
2. 心身症治療の進め方
3. 心身症治療のゴール
C. 小児科における心身症診療の実際
1. 外来診療における心身症
コラム 赤ちゃんからの心身医学的関わり
2. 子どもの摂食障害
3. 入院治療について
D. 専門医へのステップ
小児起立性調節障害診療ガイドライン
本ガイドラインについて
A. 診断アルゴリズム
1. ODガイドライン診断アルゴリズム
2. ODのサブタイプ
3. 新起立試験法
4. 新起立試験法によるサブタイプ判定
5. 身体的重症度の判定
6. 「心身症としてのOD」診断チェックリスト
B. 治療アルゴリズム
1. 重症度・心理社会的因子の関与に応じた治療的対応の組み合わせ
2. 初診以後の通院について
C. 解説
第1章 病態
1. 機序
2. 疫学
3. 思春期のOD
4. ODサブタイプ
5. 起立時循環調節機構
6. ODにおける循環調節機構の障害
コラム INOHとPOTSの病態異同について
7. 海外の診断基準
8. 類縁疾患の定義とODとの異同
BQ1-1. ODの発症および症状の増悪に影響を与える因子にはどのようなものがあるか?
第2章 診断
1. 一般小児科医を受診する際のODの愁訴
2. 診断アルゴリズムの注意点
3. ODのなかで心身症といえるものがどの程度存在するか
CQ2-1. 小児ODの評価に能動的起立試験とヘッドアップティルト試験のどちらが有用か?
FRQ2-2. ODの診断基準を満たさない場合,どのように対応するか?
第3章 治療
1. 治療の進め方
2. 重症度・心理社会的関与に応じた治療的対応の組み合わせ
3. 各治療法の解説
4. 心身医学的対応における注意点(一般外来向け)
5. 重症ODに対する心理社会的対応(専門医向け)
6. その他の治療法
7. 実際のOD診察においてたびたび使う言葉と「禁句」の例
BQ3-1. 小児ODの治療に神経発達症への配慮は有用か?
CQ3-2. 小児ODに非薬物療法は有用か?
CQ3-3. 小児ODに運動療法は有用か?
CQ3-4. 小児ODに水分および塩分摂取は有用か?
CQ3-5. 小児ODに薬物療法は有用か?
CQ3-6. 小児ODに漢方薬治療は有用か?
BQ3-7. 小児ODに心理療法は有用か?
第4章 併存疾患・予後
1. 併存疾患
2. 予後
D. 子ども・家族用ガイド(Q&A)
Q1. 起立性調節障害(OD)とはどんな病気ですか?
Q2. なぜ起こるのでしょうか?(病態生理)
Q3. だらだらして怠けているのではないですか?
Q4. 発症しやすい年齢や頻度を教えてください
Q5. 日常生活や学校生活で注意することはありますか?
Q6. どのような治療がありますか?
Q7. いつ頃に治るでしょうか?
Q8. 朝起きが悪いのですが,起こしたほうがよいのでしょうか?
Q9. 不登校が続いていますが,どうすればよいのでしょうか?
小児科医のための不登校診療ガイドライン
本ガイドラインについて
A. 不登校への対応の基礎
1. 小児科医としての不登校への関わり方
2. このガイドラインの内容について
3. 不登校に対する診療の流れ
B. 初診段階での診察手順
1. 登校できない,しないことを主訴に受診した場合
2. 登校できないこと,しないこと以外の主訴で受診した場合
C. 不登校の診療にあたり知っておきたい知識
1. 身体症状の治療に有用な心身症の知識
2. 身体症状が基本となるもの
3. 身体症状症および関連症群
4. 精神疾患や配慮を要する状態
5. 神経発達症
6. その他
7. 不登校に推奨される検査
8. 薬物の使用について
9. 保険診療について
コラム 不登校のきっかけとして多いものは何か?
コラム 不登校になるリスクとしては何があるか?
D. 当初1ー2ヵ月の経過観察
1. 診察と情報収集の要点
2. 生活の様子や生育歴についての情報収集
3. 合併する疾患や神経発達症の確認
E. 1ー2ヵ月を過ぎた後の経過観察
1. 長期的な経過観察の基本
2. 診療の再評価と専門診療施設への紹介
3. 不登校の状態評価
4. 不登校状態の変化過程
5. 毎回の診察の進め方
6. 状態に応じた対応の要点
F. 学校との関わり
1. 学校と連携する目的
2. 学校との情報交換までの手順
3. 子どもと学校とのつながりについて話し合う
4. 学校との情報交換で確認する事項
5. 学校と連携するときの注意
G. 不登校の予後
H. Q&A
Q1. 小児/思春期の不登校状態を評価する主観的尺度はあるか?
Q2. 小児/思春期の不登校状態を評価する客観的尺度はあるか?
Q3. 不登校児に対して登校刺激は推奨されるか?
Q4. 不登校児治療において学校連携は推奨されるか?
Q5. フリースクール利用は推奨されるか?
Q6. 不登校児に対して入院治療は推奨されるか?
Q7. 不登校児の家族に対して心理療法は推奨されるか?
小児摂食障害診療ガイドライン
本ガイドラインについて
A. 摂食障害の概要
1. 摂食障害とは(総論)
2. 摂食障害への対応フローチャート
3. 摂食障害の治療(総論)
4. 小児の摂食障害におけるトピックス
B. 外来治療
1. 治療概要
2. 神経性やせ症(AN)の外来治療
3. 回避・制限性食物摂取症(ARFID)の外来治療
4. 神経発達症が併存する場合の対応
5. 晩期合併症
6. 診療のコツ
7. 治療におけるピットフォール“べからず集”
C. 入院治療
1. 総論
2. 各論
D. Clinical Question
CQ1. 経口リン製剤はリフィーディング症候群の予防に有効か?
CQ2. family based treatment(FBT)は介入として有効か?
CQ3. 小児の摂食障害において心理介入(FBT以外)は有効か?
CQ4. 栄養バランスより総カロリーを重視した再栄養療法は有効か?
CQ5. 身体的危急がない場合,入院加療と外来加療の介入効果に差を認めるか?
CQ6. 入院の再栄養計画はどのように行うべきか?
CQ7. 入院の再栄養として経管栄養や末梢静脈栄養,中心静脈栄養は有効か?
CQ8. 再栄養の合併症として想定すべきものは何か? その予防に有効な対応は何か?
くり返す子どもの痛みの理解と対応ガイドライン
本ガイドラインについて
Q&A
1. くり返す痛みとは
Q1. 痛みの定義とは?
Q2.「 くり返す痛み」と慢性疼痛との関係とは?
Q3. 子どものくり返す痛みの頻度は?
Q4. くり返す痛みを多面的に診る際のチェックポイントは?
2. 痛みとこころ
Q5. 痛みと気持ちの関係は?
Q6. 痛みによる疾病利得とは?
Q7. 痛みのコントロールはどのようにして行うか?(マインドフルネスの観点から)
3. 痛みの評価
Q8. 痛みはどのように伝達されるか?
Q9. ストレスは痛みに対してどのような影響を与えるか?
Q10. 子どもの痛みの評価はどのように行うか?
4. 痛みとトラウマ
Q11. 逆境的小児期体験と痛みの関連性やそれが生じるメカニズムは何か?
Q12. 心的外傷後ストレス障害(PTSD)と痛みとの関連性やそれが生じるメカニズムとは?
Q13. 被虐待体験と痛みの関係とは?
Q14. トラウマ関連による痛みへの対処法は?
5. 学習性疼痛と身体不活動
Q15. 学習性疼痛とは何か?
Q16. 回避学習性疼痛とは何か?
Q17. 身体不活動と痛覚過敏の関係は?
6. 疼痛性疾患
Q18. 線維筋痛症とは何か? またその痛みのメカニズムは?
7. 変換症(転換性障害)・作為症(虚偽性障害)と痛み
Q19. 変換症,詐病,心因性疼痛の関係とその対応は?
Q20. 古典的なヒステリーはDSM-5ではどう扱われていますか?
Q21. 身体症状症とくり返す痛みの関係は?
Q22. 変換症(転換性障害:機能性神経学的症状症)とくり返す痛みの関係は?
Q23. 作為症/虚偽性障害とくり返す痛みとの関係は?
くり返す子どもの頭痛診療ガイドライン
本ガイドラインについて
解説
第1章 疫学
1. 総論
2. くり返す一次性頭痛
3. くり返す二次性頭痛
4. 慢性連日性頭痛(CDH)
第2章 診断
1. 総論
2. くり返す一次性頭痛
3. くり返す二次性頭痛
4. 頭痛診療に役立つツール
第3章 慢性化の仕組み
1. 総論
2. 片頭痛の慢性化と変容化
3. 睡眠
4. 環境調整
5. 共存症
6. その他
第4章 治療
1. 総論
2. 非薬物療法
コラム Let’s心理療法
3. 薬物療法(片頭痛)
4. 慢性連日性頭痛(CDH)
小児機能性消化管疾患ガイドライン
本ガイドラインについて
A. 総論
1. 定義
2. 病態の解釈
3. 診察
4. 機能性身体症候群(FSS)における他の疾患群との合併
5. 養育環境について
6. 神経発達症との併存について
B. 上部消化管疾患―機能性ディスペプシア,胃食道逆流症
1. 機能性ディスペプシア(FD)
2. 胃食道逆流症(GERD)
C. 下部消化管疾患―過敏性腸症候群,機能性便秘,機能性下痢
1. 定義
2. 疫学
3. 診断
4. 薬物治療
5. 心理的介入(心理療法・心身医学的対応などを含む)
6. 予後
D. 周期性嘔吐症候群
1. 概念・定義
2. 病態
3. 症状
4. 疫学
5. 診断
6. 薬物療法
7. 心理的介入(心理療法・心身医学的対応などを含む)
8. 予後
索引





