
薬物治療コンサルテーション
妊娠と授乳 第4版
妊娠と授乳,待望の改訂4版が完成しました.●『妊娠と授乳』とは ●妊婦・授乳婦へ薬の投与が胎児・乳児に与える影響について,疫学情報や薬剤特性など,多くのエビデンスをもとにまとめられた書籍.2010年の初版発行以来,医師や薬剤師をはじめとする多くの医療従事者の支持を経て,今や妊婦・授乳婦の薬物治療に欠かせない1冊となりました.● 改訂4版のポイント ●・医薬品の一般名(和文/欧文)・商品名,添付文書情報,オピニオンリーダーによる総合評価を一覧で確認.・安全性に関する総合評価の分類を再検討し,さらに適した表現に変更.・COVID-19治療薬,ADHD治療薬の項目を追加.・より読みやすく,必要な情報にアクセスしやすいよう誌面デザインをリニューアル.
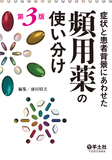
症状と患者背景にあわせた頻用薬の使い分け第3版
風邪,頭痛,めまい,咳,便秘など,よく出合う症状別に頻用する薬の特徴を比較して解説.患者背景や本人の希望などを考慮した薬選びのコツや使い分けがよくわかる.処方例も充実し日常診療にすぐ活かせる一冊!
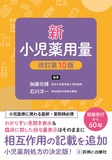
新 小児薬用量 改訂第10版
3年ごとに改訂される「小児薬用量」の最新版.初版発行から60年を迎える今回の改訂では,白衣に入るポケットサイズ,かつ成人量と小児量を並べてみることができる見開きの構成は引き継ぎつつ,新たに相互作用を追加しました!
薬物間相互作用一覧も掲載し,阻害薬や誘導薬が一目でわかる,より便利なポケットブックになっています.小児医療に携わる医師・薬剤師に,臨床の現場でぜひ活用いただきたい1冊です.

実践 小児薬用量ガイド 第4版
●小児の処方量/体重kgが一目でわかる!
●小児の処方・監査に欠かせない好評書最新版!
小児への処方・調剤の拠り所になる書籍が欲しい――そんな現場の切実な声に応えて生まれた本書が、10年目を迎えてさらにパワーアップ。体重kgあたり用量と添付文書の記載を一覧できる特長はそのままに、前版以降の新薬・小児適応が加わっただけでなく、「作用,注意事項,製剤のポイント」欄がさらに見やすいレイアウトに。
第一線で奮闘する医師・薬剤師が臨床現場の視点で、臨床現場に必要な情報にこだわってまとめた実践書。小児に向き合う全ての医療従事者必携です。
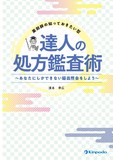
薬剤師の知っておきたい型 達人の処方鑑査術 ~あなたにしかできない疑義照会をしよう~
今、薬剤師の取り巻く環境の変化は激しく、業務の中心が、対物から対人へ変わってきています。その対人業務の中で、処方鑑査・疑義照会は重要な業務の一つとなっています。しかし、処方鑑査・疑義照会は、きちんと教えてもらう機会がありません。「添付文書と違う時はどうしたらいい?」「腎機能が分からなくても処方鑑査はできる?」など、迷う場面も多くあることでしょう。
また、現場ではレセコンなど機械化が進んでいますが、処方鑑査・疑義照会は機械では対応できないこともあり、薬剤師がしっかり対応しなければならない仕事の一つです。
本書は、現役薬剤師による、薬局薬剤師向けに処方鑑査・疑義照会について解説した書籍です。著者の実体験をもとに、論理的かつ効率的な処方鑑査の方法や疑義照会のポイントを紹介しました。
第1章「処方鑑査の本質『疑義照会』」では、処方鑑査・疑義照会の基本を伝えます。
第2章「処方鑑査を素早く間違いなくする方法」では、“4分類法”による論理的な処方鑑査が学べます。
第3章「よくある処方ミスの『型』分析」では、薬剤師の知っておきたいよくある処方ミスの型(パターン)を解説します。
そして、第4章「実践的な処方鑑査トレーニング」では、実践的なトレーニング問題を30問、用意しました。新人からベテラン薬剤師まで学べる処方鑑査の問題になります。
本書を通して、薬剤師として知っておくべき・押さえておくべき処方鑑査・疑義照会の方法やポイントが身につきます。また、処方鑑査に役立つツールもダウンロードでき、自習に役立つ一冊です。
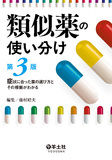
類似薬の使い分け第3版
症状に合った薬の選び方とその根拠がわかる
類似薬を比較しながら,患者に応じた薬の使い分けが学べる,好評書の改訂第3版!豊富な症例と処方例で,症状や患者背景に応じた薬の使い分けのコツがわかる.疾患別に薬の系統と類似薬が一覧できる便利な分類図付き.

あらゆる診療科で役立つ皮膚科の薬 症状からの治療パターン60+3 改訂版
診断と治療の型が身につく!
63の皮膚症例を厳選し,症状からの治療のパターンを伝授!診断のパターン,治療のコツ,落とし穴,専門医へのコンサルトなど,すぐに役立つ知識が満載!クイズ形式で,診断と治療の「型」が楽しく身につきます.

調剤報酬点数表の解釈 令和6年6月版
『薬局関係者必携、保険調剤のすべてを収載した定本』
『調剤報酬の算定・請求に必要な情報を徹底網羅』
◆調剤報酬の算定・請求に必要な情報を、実務上活用しやすいよう編集し、法令上の根拠とともに示しています。
◆調剤報酬点数表に関する疑義解釈(Q&A)については、今回改定関連に加え、従来示されたものの内容を整理して掲載、調剤薬局での実務に必要な情報を網羅しています。
◆医療機関の薬剤部でも有効にご活用いただけるよう、「薬剤使用に関する保険診療上の取扱い通知」や、診療報酬点数表(医科・歯科)の薬剤関連部分も掲載。幅広い視点からの編集が魅力です。
◆「関係法規・通知編」では、保険調剤や病院薬剤部に関連する保険情報(療養担当規則、施設基準等)をまとめるとともに、処方箋や介護保険までの関連情報を掲載しました。
◆各審査機関にも長年愛用されてきた、調剤報酬算定業務のための信頼性を誇る一冊です。

薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100
【第50回日本薬剤師会学術大会先行販売にて完売,売上 1位達成!】
「この薬,前の薬とどこが違うの?」と聞かれて返答に困ったことはありませんか?本書は,類似薬の違いを約730点の参考文献を明記して解説.医師の処方意図がわかり,服薬指導や疑義照会,処方提案にも自信がもてます!

コンパス調剤学[Web動画付][電子版付] 改訂第4版
実践的アプローチから理解する
実践面を意識して構成した学生向けの調剤学の教科書.患者対応や調剤の実践例等を動画として収載(Web公開)し,実地で困らない力を養成する.今改訂では薬剤や法規等の情報更新を行うとともに薬剤師業務に関連するDX化についての解説を追加した.さらに今改訂より電子版付とした.薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版/平成25年度改訂版)対応.

ここがツボ!患者に伝える皮膚外用薬の使い方(第3版)
処方箋には“ツボ”があります。「ここがツボだ」と見破れば、医師の処方意図が理解できます。本書は、調剤薬局の薬剤師が処方箋のツボを理解し、患者さんに正しくわかりやすく服薬指導できることを目的としています。
著者自身が開業医としての10数年の経験を生かし、実地診療に役立つ処方箋を紹介。新たな皮膚外用薬の情報更新、外用治療のノウハウ、ワンポイントアドバイス、「患者さんからの質問・疑問にどう答えますか? これまで学んだ知識を生かして対応しましょう」など、実践に即したQ&Aも満載です。
薬剤師の皆様、本書を参考に処方箋を正しく読み解き、処方箋を見て「ここがツボだな」とわかったら服薬指導の腕の見せ所です!

面接から組み立てる!
向精神薬処方ストラテジー マスト&ベスト
「マスト&ベスト/ミニマムシリーズ」第3弾!
治療効果を上げるには目の前の患者さんの病状をしっかりと理解し,的確に診断することが大切です.しかし1人ひとりに時間をかけて向き合うのは難しい…….そんな忙しい臨床ですぐに役立てていただけるよう,本書では,いかに面接から向精神薬処方を組み立てるかのポイントとピットフォールをコンパクトにまとめました.これから精神科医になろうという医師の方だけでなく,薬剤師の方にも実践的で役立つ内容になっています.

患者に合わせた処方意図がわかる!
同効薬・類似薬のトリセツ
同効薬・類似薬を比較して違いを示すだけでなく,処方箋で具体的な事例を挙げながら使い分けについて解説。診療科別に臨床で頻用する薬剤をピックアップし,各薬剤の特徴や使い分けるための要点を端的に示しつつ,添付文書・インタビューフォームを参照した比較表を掲載し,代表的な商品名や副作用,代謝経路など,必要な情報が満載。薬剤師が複数の処方箋を見比べた際の疑問に対して,医師が答える構成で,薬剤師が知りたい処方意図が理解できる充実の117テーマ。
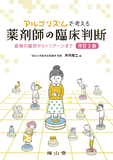
アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断 第2版
症候の鑑別からトリアージまで
薬局窓口で症状を訴える患者に対して,「どう対応すべきか分からない」「判断が難しい」といった悩みを感じたことはありませんか? 薬剤師による「臨床判断」とは,心身の異常や症候を訴える来局者の健康相談に適切に対応し,疾患や病状を推測したうえで緊急対応,受診勧奨,OTC薬の推奨,生活指導などから妥当な対応方法を選択(トリアージ)する,この一連の臨床推論・判断の流れのことをいいます.本書では,薬局で活用できる臨床判断アルゴリズムをもとに15症候の臨床判断を解説しました.

薬剤師のための 精神科の薬 処方の意図を読む
薬局が応需する「精神科の薬」の処方箋。多剤大量処方、適応外使用、同効薬の併用なども多く、医師がどんな意図で処方したのか読み取りにくい、分からないと感じている薬剤師も多いのではないでしょうか。精神科処方の第一人者が豊富な症例に基づき、5疾患(大うつ病性障害、双極性障害、神経症性障害、統合失調症、認知症)の処方の意図を解説します。

はじめる とりくむ
災害薬学
災害時における薬剤師のニーズが,近年高まっている.被災地で,薬剤師は何ができるか,限られた患者情報や医療資源の中,薬をどう使うのか,災害時の医薬品供給や法律・制度等,本書では災害時の薬剤師業務についての基礎知識から災害時における薬物治療の考え方までをまとめた.「いざ」というときに備え,薬剤師として読んでおきたい一冊.
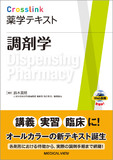
≪Crosslink 薬学テキスト≫
調剤学[Web動画付]
薬剤師を目指す学生のために講義,実習,臨床をリンクさせて学べる新しいスタイルの教科書シリーズが登場!
本文は噛み砕いた表現を用いて詳しく解説。また,図表を多用し視覚的にも理解しやすい紙面となっており,各剤形における実際の調剤手順ついては写真を多く掲載し説明している。調剤業務全体の概略から,薬局薬剤師・病院薬剤師の視点で解説する臨床現場における細やかなアドバイスまで盛り込まれている。
各見出しごとに「POINT」を設けて重要事項をまとめ,どこに重点を置いて学習すべきか,一目でわかる。また「基礎へのフィードバック」「専門分野へのリンク」「臨床に役立つアドバイス」「学習の要点」などの囲み記事を設け,知識の漏れを防ぐとともに,さまざまな角度からの情報を盛り込んでいる。
テキスト内容の理解を深めるWeb動画を収載!臨床における調剤手順や服薬指導など,現場での実践を具体的にイメージできる。
国家試験合格を最終目標とするだけでなく,臨床実習やその先の臨床の場でも活用できる学習の強い味方!
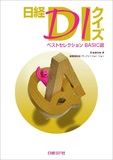
日経DIクイズ ベストセレクション BASIC篇
創刊号から続く大人気連載「日経DIクイズ」から、基本的なQ&Aをセレクトした書籍が、ご要望にお応えしてついに誕生!
「日経DIクイズ」1巻~10巻から、より基本的な問題を100題厳選して収録。既に絶版となっているシリーズ1巻~4巻からは44題をセレクト、内容をアップデートして掲載しました。実務現場のケーススタディをQ&A形式でわかりやすく解説します。
日経DIクイズシリーズの入門書として最適です。また、若手の基礎学習からベテランの知識の再確認まで、薬剤師必携の1冊です。
<本書に掲載しているクイズの一部をご紹介します>
熱性痙攣を引き起こすかぜ薬の成分とは
不妊症に出されたステロイド
下痢を訴える過敏性腸症候群患者
肺癌患者に漢方薬が処方された理由
緑内障治療薬とビタミン剤の相互作用
パーキンソン病患者への追加処方
睡眠薬切り替え時の注意点
「術前」を理由に中止された薬剤
肥満を気にする糖尿病患者の食事指導
発作寛解薬が変更された片頭痛患者
プレドニゾロンはなぜ朝に服用するのか
咳が止まらない患者にPPIが処方された理由 など

薬局ですぐに役立つ薬剤一覧ポケットブック
調剤、処方鑑査、服薬指導で使える便利な一覧と知っておきたい必須知識
「粉砕不可一覧」「一包化不可一覧」「疾患併用禁忌一覧」など,便利な薬の一覧が充実の57項目!わかりやすい解説も必読.調剤,処方鑑査,服薬指導の重要ポイントが学べます.ポケットに入れておきたい必携の1冊

在宅医療のいろは
ストーリーで学ぶ訪問薬剤師業務
薬剤師のための,在宅医療の入門書が登場!本書は小説パートと解説パートの二部構成.小説パートでは,新人薬剤師いろはが,在宅医療の経験が豊富なタイガー薬剤師とともに,在宅医療に挑戦していくストーリーが展開されます.物語を通じて,在宅医療の流れや算定の考え方を楽しく学ぶことができます.解説パートでは,在宅医療に関する制度やサービス,調剤報酬について,基礎からわかりやすく解説していきます.さらに,復習に役立つ章末問題も掲載.在宅医療に興味のあるすべての薬剤師におすすめの一冊です!
