
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第3版
大好評参考書がオールカラーになって大改訂! 実習でよく出合う78疾患について,看護過程の展開に必要な医学的知識,病期・治療に沿ったアセスメント,看護計画とケアの「根拠」「留意点」がますます充実.好評の「関連図」では発症から病態生理学的変化,治療経過,看護問題の抽出までを図式化し,患者の経過が一目でわかる.さらに第2部以降で「治療別看護」「経過別看護」「感染症看護」「臨床検査値一覧」を収載し,患者の状況に応じたアセスメントと臨床判断ができる.看護学生や新人看護師の「なぜ・どうして」に応える,実習で役立つ頼れる味方!

臨床判断ティーチングメソッド
高度化、また地域へ移行が進む医療現場では、看護師の臨床判断能力の向上が求められています。本書は、タナーが開発した臨床判断モデルをもとに、学習者が実践的な思考を獲得する方略をわかりやすくご紹介します。学習者中心の考え方や、生涯学習を続けるためのかかわりなど、教育学の最新の知見とともに、基礎教育から新人、エキスパートへと、看護師の熟達を橋渡しする1冊です。

まんが 医学の歴史
医学の歴史は、人類の誕生とともにはじまり、いつの世もらせん状に続いてきた泣き笑いの人間ドラマがあった。世界初! 臨床医であり漫画家である著者による、まんがでみるわかりやすい医学の通史、堂々の刊行。古代の神々からクローン羊のドリーまで、『看護学雑誌』2003~2005年の連載に大幅描き下ろしを加えた。

ユマニチュード入門
「この本には常識しか書かれていません。しかし、常識を徹底させると革命になります。」――認知症ケアの新しい技法として注目を集める「ユマニチュード」。攻撃的になったり、徘徊するお年寄りを“こちらの世界”に戻す様子を指して「魔法のような」とも称されます。しかし、これは伝達可能な《技術》です。「見る」「話す」「触れる」「立つ」という看護の基本中の基本をただ徹底させるだけですが、そこには精神論でもマニュアルでもないコツがあるのです。開発者と日本の臨床家たちが協力してつくり上げた決定版入門書!

根拠がわかる症状別看護過程 改訂第4版
こころとからだの69症状・事例展開と関連図
身体症状に加え心理・社会的症状を含む69の症状について,モデル的な看護診断と,事例に基づく具体的な看護過程について関連図を交えて解説.今改訂では新たな編集体制のもと,看護計画を見やすい表形式としてより多くの根拠・留意点などを示すようにしたほか,イラスト多く用いてよりビジュアルにわかりやすい紙面とした.看護の視点から人間を捉えた「症状別看護」の決定版.

≪NursingTodayブックレット 23≫
看護をめぐる「業務」と「ケア」
「業務はしているがケアをしていない」を分析する。
新人看護師が抱える「業務」と「ケア」のもやもやを解きほぐす一冊!
新人看護師からよく聞かれる、「業務はしているがケアをしていない」「業務が忙しくてケアができない」という言葉。
なぜ看護師たちはそう感じるのか、「業務」「ケア」とは一体何なのか、「業務」を「ケア」に転換するためにはどうすればよいのか―。
ベテラン看護師3人が、そのもやもやを分析し、解きほぐします。
≪本書は第1版第1刷の電子版です≫

悲嘆とグリーフケア
家族、遺族、およびケアにかかわる看護師自身のグリーフケアをまとめた1冊。好評書『看護カウンセリング』の著者が本書では、個人カウンセリングでの語り、サポートグループでのつながりを通して、答えのない問題と向かい合う。緩和ケアに携わる看護師をはじめ、患者の死、家族の死など人の悲嘆に接するすべての人にお勧めしたい。

対話と承認のケア 増補版
ナラティヴが生み出す世界
ナラティヴ・アプローチ探求の金字塔『対話と承認のケア』の増補版!
多くの方に愛読されている『対話と承認のケア──ナラティヴが生み出す世界』の増補版。補遺(ほい)にて、ナラティヴ・アプローチの有効性とこれからの展望を初版から一歩進めて解説。巻末には索引が付き利便性もアップ。研究職のみならず、臨床の医療職にも有用な1冊となって再登場!

転機 新任看護部長の1年
外部から来た新任看護部長の1年目の物語から看護管理の実践を学ぶ!
大学病院の看護部長に応募し、選ばれた筆者が就任1年目を振り返り、いかにして新しい組織になじみ、看護部長としての振る舞いを考え、役割を果たしていったのかを丹念に記述したノンフィクションです。
新任看護部長としての実践に意図して用いた理論や概念をコラムとして紹介し、実践と理論の関係を明らかにしていきます。
新任看護部長の1年目の物語には、看護管理やキャリア開発のヒントがぎっしりと詰まっています。

患者の意思決定にどう関わるか?
ロジックの統合と実践のための技法
さあ、意思決定のテーブルへ。「患者の意思決定」の理論と実践を1冊にまとめました
意思決定の連続である医療職の仕事。臨床倫理、EBM、プロフェッショナリズム、SDM、ナラティブなど、これまで様々な切り口で示されてきた理論をもとに、「患者にとって最善の意思決定」に専門家としてどのように考え、関わっていくかをまとめた渾身の書。AIの発展、新型コロナの流行など、社会が変わっていくなかで、これからの患者-医療者関係の在り方を示す1冊。さあ、意思決定のテーブルへ。

基本の101語の語源から学ぶ医学英語 第2版
病棟で役立つ英語表現・英文例
「語源学習法」で、医学用語を効率的に学ぶ! 病棟で役立つ英語表現・英文例が満載!
英単語を効率的に覚える語源学習法(単語を語源に沿って分解し、接頭語・語幹・接尾語ごとに学ぶ方式)が注目を集めています。本書はその語源学習法を用いて、難しい印象のある医学用語を楽しく簡単に覚えるコツを解説します。取り上げた基本的なパーツは101語ですが、各々を組み合わせることにより、その何倍・何十倍もの語彙力が身につきます。
第2版では、「病棟で役立つ英文例」として、入院の経過に沿った英文例を紹介する新章を追加しました。
豊富なエクササイズと文字が隠せる暗記シート付きなので、自分の理解度がチェックできます!
看護学生の皆さんから臨床現場のナース、医療従事者の方々まで、幅広くご活用いただけます。

はたらく看護師のための自分の育て方
キャリア選択に活かす気づきのワーク17
仕事は覚えた。後輩もいる。次の「私」は、さてどうする? ナースが新しい扉をひらく本
プラチナ世代の先輩ナースと、ビジネススクールで大人を育てる経営学者が共鳴した、人生の岐路に直面する世代のための知恵と勇気をこの1冊で。専門職である看護師ならではのライフサイクルに添って構成する第I部で学び、現場あるある事例に基づく17ワーク[MBA式思考トレーニング]の第II部で心がまえを養ってみてください。休み休みでいいんです。あなたが自ら選ぶ扉のその先へ、本書はご案内します。

≪シリーズ【看護の知】≫
わが子のケアの達人になる 「医療的ケア児」のママたちの奮闘
医療的ケア児の母親へのインタビューを通して、わが子に行う医療的ケア技術の修得までのプロセスと、子どもの障害を知って苦悩する段階を経て、在宅療養に慣れ子育ての喜びを感じるようになるまでの心理的変化を明らかにしました。また、医療的ケア児の両親や在宅療養に関わる専門職のリアルな声も掲載。看護職、医療的ケア児等コーディネーター、ケアマネジャー、相談支援専門員等、小児医療にかかわる人にぜひ読んでいただきたい一冊です。≪本書は第1版第1刷の電子版です≫
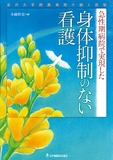
急性期病院で実現した 身体抑制のない看護
金沢大学附属病院で続く挑戦
「抑制=患者の安全」と誤解している人がいるが、患者が抑制された結果、身体状況が悪化したり、感情を暴発させる、不穏になるなどして、かえってケアの困難さが増すケースも多い。また患者を抑制することで、本当は必要な看護師の手、目、心が患者から遠ざかることを招いてしまう。高度急性期病院では難しいとされてきた身体抑制件数の減少に挑戦し、ゼロ化を達成した金沢大学附属病院の取り組みと成果を紹介した本書は、次に続こうとする挑戦者たちの精神的な拠り所になるだろう。

≪シリーズ ケアをひらく≫
傷の声
絡まった糸をほどこうとした人の物語
現在の精神科医療に不足している視点を教えてくれる。
本書は複雑性PTSDを生きた女性が、その短き人生を綴った自叙伝である。過酷な家庭環境に育ち、複雑性PTSDを持つ著者が、ふり幅の大きな人生を描く。なぜ自分を傷つけるのか、という疑問への回答と、傷ついた人に必要なのは、権力や物理的力で抑え込むことではなく、ケアであるべきではないかという気づきとヒントを医療者に与えてくれる。

国家試験をギリギリ合格したナースが英語論文を読めるようになった理由
【ハルジローが英語論文の読み方を伝授!】SNSの総フォロワー数14万人の看護系インフルエンサー・ハルジローが贈る、これから看護研究を始める人のための超入門書。ハルジローならではのポップなノリで、本を1冊読み切ったことがない人でもスラスラ読め、いつのまにか英語論文も理解できるようになっている!

看護師のための文章ノート
読んでもらえる“仕事の文書”が書ける! 作文技術が身につく! ワークシートで自分の文書の傾向をつかめる!
しばしば「冗長」「わかりにくい」などと言われる看護師の文章。「看護」という仕事の本質が「個別性」を対象とし記述的になりがちなためですが、仕事の文書(論文や各種報告書、レポート、依頼文書、看護記録など)は読んでもらわなければなりません。本書は“読んでもらえる仕事の文書”を書くための作文技術を紹介したコンパクトな良書。思考が整理でき、添付のワークシートを使えば自分の文章の傾向がつかめます。今日から「より、読んでもらえる文章」を書いてみませんか。

≪シリーズ ケアをひらく≫
あらゆることは今起こる
私の体の中には複数の時間が流れている。
眠い、疲れる、固まる、話が飛ぶ、カビを培養する。それは脳が励ましの歌を歌ってくれないから?──ADHDと診断された小説家は、薬を飲むと「36年ぶりに目が覚めた」。私は私の身体しか体験できない。にしても自分の内側でいったい何が起こっているのか。「ある場所の過去と今。誰かの記憶と経験。出来事をめぐる複数からの視点。それは私の小説そのもの」と語る著者の日常生活やいかに。SFじゃない並行世界報告!

症状を知り、病気を探る
病気とは何か、患者さんの痛みや苦しみは何に由来するのか―――病理医ヤンデル先生が、患者さんがよく訴える5つの症状の“みかた”を語る!インターネットで「病理医ヤンデル」として有名な著者が、最もポピュラーで、出合う頻度の高い5つの症状である「おなかが痛い」「胸が苦しい」「呼吸がつらい」「熱が出た」「めまいがする」の“みかた”を語ります。

スピリチュアル・コミュニケーション
医療者のための5つの準備・7つの心得・8つのポイント
スピリチュアルケアの最も核心的な部分は「コミュニケーション」である。本書は、終末期や高齢者医療の現場で日々患者に向き合う医療者のために、日々のケアのなかでスピリチュアル・コミュニケーションをどう実践すべきかを、わかりやすく解説。具体的な臨床事例、著者らの経験を紹介しつつ、医療者が行うべき準備・もつべき心得、そして具体的なコミュニケーションのポイントを示す。
