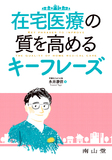
在宅医療の質を高めるキーフレーズ
著者が提唱している在宅医療の質を高めるために大切な3つの柱,「理念」「システム」「人材」のなかでもとくに「理念」をまとめた書籍.2000年に在宅医療専門の「たんぽぽクリニック」を開業して以来,著者が経験したエピソードとともに日本の在宅医療について著者の思いを語ります.また,在宅医療に携わる医療従事者への後押しになるような著者の格言(キーフレーズ)をテーマごとに記載.現場で行き詰まったときの悩みをそっと解決してくれるような一冊に仕上がりました.

高齢者総合機能評価(CGA)に基づく診療・ケアガイドライン2024
超高齢社会を迎えたわが国では,CGAによる包括的・全人的な評価と,それに基づいた個別化された医療・ケアの提供が求められている.多職種協働により取り組む必要があり,CGAはその共通言語となる.本ガイドラインは,医師だけではなく高齢者に関わる医療介護福祉関係の多職種向けに作成した.診療やケアに幅広く活用いただきたい.
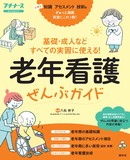
基礎・成人などすべての実習に使える!
老年看護ぜんぶガイド
基礎・成人・老年などすべての実習で求められる老年看護の知識を、これ1冊でおさえることができます。
Part1では高齢者を受け持つうえで欠かせない老年期の身体的変化、心理・社会的変化をはじめとする基礎知識がまとまっており、Part2では具体的なアセスメント項目を豊富に掲載。Part3では高齢者に特徴的な症状や疾患について、最新知識とともに学べます。Part4では、看護技術を写真入りで解説しており、高齢者に援助するときのポイントをおさえられます。

ユマニチュード入門
「この本には常識しか書かれていません。しかし、常識を徹底させると革命になります。」――認知症ケアの新しい技法として注目を集める「ユマニチュード」。攻撃的になったり、徘徊するお年寄りを“こちらの世界”に戻す様子を指して「魔法のような」とも称されます。しかし、これは伝達可能な《技術》です。「見る」「話す」「触れる」「立つ」という看護の基本中の基本をただ徹底させるだけですが、そこには精神論でもマニュアルでもないコツがあるのです。開発者と日本の臨床家たちが協力してつくり上げた決定版入門書!

あなたにもできる スピリチュアルケア
死を前にした人が穏やかになるために、誰もができることがあります。
「もう死んでしまいたい」「迷惑をかけてばかり」──死を前にした人の言葉に、応え続けることができますか。そこでは励ましも説明も、力を持ちません。私たちにできるのは、相手にとって「わかってくれる人」として対話を重ね、大切な「支え」を強めること。それが “スピリチュアルケア”です。スピリチュアルケアは、一部の人だけができる難しいケアではありません。わかりやすい言葉で、真似しやすい方法で、すぐに実践できるスピリチュアルケアがここにあります。

認知症看護スタンダード
いま、認知症を“あたりまえ”のことととらえ、認知症のある人とともに暮らすことが求められている。
そのためには、認知症という疾患をよく理解し、現れてくるさまざまな症状や訴えを科学的に解釈し、人として尊厳をもって接する看護が必要になってくる。
認知症の医学的基本を踏まえ、認知症の人と家族を支える具体的な方法を知り、そのベースにある倫理的側面を理解するための「認知症看護の標準的な教科書」が本書である。
技術や知識に偏ることなく、「人と人の関係」をしっかりと作っていくための基本がぎっしり詰まった1冊である。
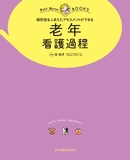
個別性をふまえたアセスメントができる
老年 看護過程
10疾患の看護過程をまるごと解説
幅広い領域の看護過程を、すべて老年期の事例(65歳~87歳)で収載。
疾患の基礎知識から評価の視点まで、看護過程の一連の流れをていねいに解説しています。
頻度の高い7症状の標準看護計画を収載
摂食・嚥下障害やスキン-テア、せん妄など、高齢者によくある症状をピックアップ。
根拠や注意点もわかるから、明日のケアにすぐ役立つ!
個別性が“ちゃんとある”看護計画が立てられる!
高齢者のマルチモビディティ(多疾患併存状態)に対応。
患者さんに基礎疾患や背景がある場合(例:糖尿病など)の方向性も示しました。
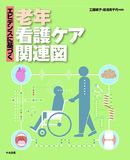
エビデンスに基づく老年看護ケア関連図
せん妄、熱中症、レビー小体型認知症、老衰、貧血、大腸がん、腸閉塞、COPD、誤嚥性肺炎、腎不全、大腿骨頸部骨折、白内障など、25疾患の病態生理・症状・治療・看護ケアについて解説。看護の目標と評価ポイントも示し、看護の振り返りにも活かせる視点を収載した。

誤嚥性肺炎の包括的アプローチ 診断・治療から,栄養管理・呼吸リハ・嚥下リハ・口腔ケアまで
●多職種で攻略!誤嚥性肺炎の治療・マネジメント
●高齢者に発症する誤嚥性肺炎は抗菌薬のみで治療することは困難で,リハビリテーションや栄養管理,嚥下訓練,口腔ケアなどを適切に組み合わせ,多くの職種がかかわって包括的に治療に取り組む必要があるが,各職種間の相互理解も不十分なのが実状である.
●本書では,誤嚥性肺炎のきっかけとなる嚥下障害の治療と,リハビリテーションや栄養療法について,理学療法,作業療法,看護ケアなどそれぞれのエキスパートがやさしく解説している.
●職種の相互理解を深め,より効果的な誤嚥性肺炎の治療・マネジメントの可能性を追求する一冊である.

看護・介護で使えるナーシングマッサージ[Web動画付]
「触れる」をケアにする
触れること、さすることは確かにケアになる
目の前にいる苦痛を抱えた人をなんとかしたいという思いで研究されてきたナーシングマッサージは、ケア場面で触れることがどんな意味をもつのかという原点に立ち戻り、試行錯誤を繰り返した結果、軽擦法(さする技術)を中心とする手技に進化した。本書では、触れることの意味をはじめ指圧マッサージの基本から安全に実施できる手技までを紹介。手技は35本の動画で確認できる。看護師・介護士の手はケアの道具になる!

講義から実習へ 高齢者と成人の周手術期看護2 術中/術後の生体反応と急性期看護 第3版
●好評の「周手術期看護」シリーズ,待望の大改訂!オールカラー化でさらに見やすく,よりビジュアルに!
●改訂では,麻酔・手術体位等の手術室内の看護,手術侵襲と生体反応,術後看護の知識を整理し,リニューアル!
●手術体位の写真,ガウンテクニックの動画を新規収載.
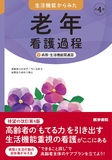
≪からみた看護過程≫
生活機能からみた
老年看護過程 第4版
+病態・生活機能関連図
高齢者の“もてる力”を引き出す! 老年看護過程の決定版
生活機能の視点から高齢者を捉え、“もてる力”を引き出すための方法とコツを解説。カルテが読める「目でみる疾患、症状、診断・検査値、合併しやすい症状、治療法」、ケアがみえる「情報収集・分析、アセスメントの視点、ケアプラン」、高齢者の全体像がみえる「病態・生活機能関連図と看護問題」で構成。ほしい情報が満載、実習記録に悩まないオールインワン!

「残された時間」を告げるとき
余命の告知Ver. 3.1
患者に余命を告知する方法をバージョンで分類して解説!
患者の自己決定権の尊重,情報開示や説明義務遵守という背景のなかで,たとえ患者本人にとって悪い情報であっても,「告知」するということがなされるようになってきている。「がん告知」についても,今ではほとんどの患者に行われるようになってきており,それと同時に予後の見通しや余命についても告知されるケースも増えてきている。
「余命の告知」については,国内外でさまざまな研究が行われており,海外の論文や教科書では,告知の方法や考え方についての指針や報告もある。しかし,日本では,「余命の告知」に関する日本人の特性や考え方,価値観などを加味した指針といったものはないのが現状である。
本書では,このような現状をふまえ,前半では,日本における「余命の告知」について,余命を患者と考える「End-of-Life-Discussion(EOLd)」の考え方や進め方,日本人の死生観や行動経済学などを総論としてまとめている。後半では,余命の告知を類型ごとに分類し,告知の方法,細かい手技を示している。また,「オムニバスまんが」により,医師が実際に患者に余命を告知するシーンをそれぞれの場面で類型ごとに具体的にわかりやすく示している。これまで余命の告知をしたことがない医療者には,入門書として,今まで余命の告知をしてきた医療者には,告知方法を考える1冊として,必読の書である。

ウェルネスの視点にもとづく 老年看護過程 第3版 生活機能に焦点をあてたアセスメント
老年看護実習に臨む学生向け好評テキストが,「高齢者の生活機能に関連する5つの側面」を見直し,さらに内容充実し,リニューアル!
●高齢者の生活機能に関連する5つの側面(食事,排泄,清潔・身だしなみ,活動・休息,コミュニケーション)をウェルネスの視点から情報収集・アセスメントし,高齢者の全体像・価値観を捉え,看護展開する老年看護の好評書が,5年ぶりに改訂!
●第3版では,ゴードンやヘンダーソンなどの既成の枠組みにとらわれず,高齢者をより深く理解し,より“その人らしい”生活を送るために,高齢者のもてる強みを活かした支援ができるように,リニューアル.

最新 老年看護学 第4版 2025年版
最新データに更新した2025年版! 時代の変化に応える「老年看護」の本質・基本的な視点を学ぶことができます。
最新のデータや国家試験出題基準を基に内容を更新!
第4版から文字を大きくして読みやすくなっています。
10年後、20年後の社会を見据えて、看護専門職として求められる知識を強化し、時代の変化に応える「老年看護」の本質・基本的な視点を学ぶことができる教科書です。
〇老年期を生きる人の理解から説き起こし、倫理的課題にも触れながら、加齢変化と健康アセスメントや健康障害の看護など、基本事項を丁寧に解説しました。
〇老年期に特有な健康障害とその看護は、エビデンスを示しながら実践に求められる知識・技術の理解を促しています。
〇「厚生統計からみる高齢者像」「認知症高齢者の看護」「高齢者の人生の最終段階における看護」は、章を立てて詳しく解説しています。
≪本書は第4版2025年版第1刷の電子版です。≫

アセスメントとケアが変わる
褥瘡エコー診断入門
褥瘡のエコー診断についてまとめた、本邦初の本格的な実践書。エコー機器が小型化・高性能化するなか、DTI、ポケットの正確な評価など、褥瘡診療の分野でのエコーの活用に注目が集まっている。本書では、先進的に褥瘡エコー診断を行なっている著者らの実践事例とノウハウを紹介する。

ナラティブホームの物語
終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ
超高齢・多死社会を迎えたこの国で、人が安心して死ねる住まいをめざしたチームが富山県砺波市にある。家庭のような病院をめざした医師と、患者固有の物語に添ったケアを追求する看護師と介護福祉士たち。2010年開設以来、全国から熱い注目を集めるナラティブホームはどのように誕生し、日々運営されているのか。さらにその診療、看取り、エンゼルメイク、葬儀、アルバム作りまで、医療者の実践の詳細を1冊にまとめた。

自立と生活機能を支える
高齢者ケア超実践ガイド
最新の研究、長年の経験・知識・技術が融合した高齢者ケアにかかわる専門職必携のガイドブック。
高齢者ケアの現場で直面する具体的問題とエキスパートならではの解決策がつまった1冊!
超高齢社会の現代日本において、介護予防、健康問題の早期発見・介入が重要です。
医療従事者やケア提供者には、病気を治療するたけでなく、その人らしい生活を支え、尊厳を保つためのケアが求められています。
本書は、高齢者が直面する機能変化、特に老年症候群や認知症、低栄養、筋力低下などに焦点を当て、適切な評価とケアの方向性を解説しています。
さらに後半では、実践的なケア技術にスポットを当て、フィジカルアセスメント、睡眠、排泄、食事、スキンケアといった日常生活の基本から、緩和ケアやエンド・オブ・ライフケアまでを網羅しました。
高齢者ケアにかかわるすべての専門職が活用できるガイドブックです。
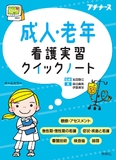
成人・老年看護実習クイックノート
各領域の実習で「必要とされる知識」に絞ってまとめています。
ケアやアセスメントのとき、指導者に質問されたときに役立つ知識をつめこみました。

≪認知症plusシリーズ 21≫
認知症plus身体拘束予防 第2版
抑制に頼らない組織の実現へ
待望の改訂版! 「身体拘束は本当に患者さんの安全のため?」
人の尊厳に対する意識や感性を鈍麻させてしまう身体拘束。
転倒・転落、チューブ抜去などの“困った行動”→“拘束”を選ぶのではなく、行動の理由にアプローチし、安心できる代替案を見つけるプロセスを提示します。
看護管理者、病棟・外来、医療安全、認知症ケアチームなど様々な視点から「多職種・部門間連携」「せん妄の悪化予防」「環境調整」「薬剤の適正使用」のほか、認知症ケアをみつめ直した実践を、第2版ではさらに具体的に紹介しています!
≪本書は第2版第1刷の電子版です≫
