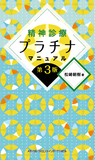
精神診療プラチナマニュアル 第3版
わかりにくい精神科を、さらにわかりやすく
精神医療に必要かつ不可欠な内容をハンディサイズに収載、臨床における迷いを払拭するコンパクトマニュアル。4年ぶりの改訂に際し、精神医療に最低限必要な知識に加えて、「もう少し踏み込んで知っておきたい知識」も記述。原則として『DSM-5-TR』に疾患名を統一し、またDSMにない概念も取り上げた。全編アップデート、30頁増。拡大版(Grande)も同時発売。精神科専門医・専攻医はもちろん、他科の医師、初期研修医、看護師、薬剤師、さらには臨床心理士・公認心理師、精神保健福祉士など、幅広い職種に。

DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル
精神疾患の国際的な診断基準、9年ぶりのアップデート!
米国精神医学会(APA)の精神疾患の診断分類、第5版のText Revision。DSM-5が発表された2013年以来9年ぶりに内容をアップデート。日本精神神経学会による疾患名の訳語も大幅にリニューアルとなり、全編新たな内容としてリリースする。

せん妄診療実践マニュアル 改訂新版
せん妄診療の定番書が,「ハイリスク患者ケア加算」に合わせて内容を刷新!現場に即した診療フローと豊富な図表を用いた解説で,効果的・効率的なせん妄対策のために「いま,何をすべきか?」がすぐわかる!

うつ病――診断・治療から病態の理解まで
うつ病診療の必須知識と実践的経験則を網羅できる唯一無二の1冊
DSMなど概念の変遷から,多岐にわたる症状,診断や検査,治療までのすべてを包括的にわかりやすく解説.精神科医はもちろん,研修医,かかりつけ医などうつ病患者をみることのあるすべての医療者に役立つ必携書.ガイドライン等の必須知識をしっかりおさえつつ,それだけではうまくいかない実臨床の多彩な患者へ対応するための,エキスパートの経験値と実際にどうするかを伝授!

精神科の薬がわかる本 第5版
精神科全領域の薬がこの1冊で丸わかり! ざっと広くのことを知りたい方へ。
精神科全領域の薬に関する最新かつ正確な情報を、第一線で診療を行う著者が厳選して紹介。精神科を専門とする医師、研修医、精神科看護師はもちろん、精神科以外の科の医療者で「精神科の薬」を使用する機会のある方にとっても有益な1冊。第5版では、なぜその薬が効くのかを知ることで、「精神科の薬」の誤用と乱用を防ぐことに注力しています。

研修医・総合診療医のための
精神科ファーストタッチ
●コンパクトだけど精神科の悩みを解決できる1冊!
●向精神薬の選び方・心のケアのポイントがシンプルにわかる!
●「スタンダードな治療のながれは?」「向精神薬のリスクと限界は?」「副作用?それとも増悪?」一度でも悩んだことのある人必読!
精神疾患への向き合いかたに迷子になっているすべての研修医へ。せん妄や抑うつなどの精神症状を一度でも診たことがある人なら知っておきたい診断・治療のエッセンスをまとめました。重要なポイントにしぼって、スタンダードな治療のながれをぎゅっと解説。数値・画像でとらえづらい疾患・症状でも、パッと引いてすぐに実践できます。さらに、よく使われる向精神薬の適応症や適用外使用がサッと確認できる一覧表付き! コンパクトながら、疾患・薬・副作用を網羅的にカバーした万能な1冊です。

認知症のみかた,考えかた
認知症診療に必要な知識の整理とアップデートを1冊で!
日本にはすでに400万人を超える認知症者がいるとされ,認知症は稀少疾患ではなくコモンディシーズとなり,認知症を正しく理解することは必須のいま,日常診療ですぐに役立つ実践的マニュアル!
診察のコツや,早期発見・正しい判断のための検査,認知症を来す疾患それぞれについての解説から,レカネマブなど最新の抗体療法を含む具体的な治療,法律・社会制度まで,体系的にすべてをまとめた必読書

双極症 第4版
病態の理解から治療戦略まで
双極性障害から双極症へ! 決定版的入門書が新たなタイトルでリニューアル!
好評書『双極性障害』がDSM-5-TRの訳語変更に合わせタイトルを『双極症』としリニューアル。臨床・基礎のあらゆる情報を網羅する方針はそのままに、概念の歴史から疫学、症状、診断、治療、治療薬の薬理、ゲノム研究、病態仮説の現状まで幅広くカバーしている。単著とは思えない圧倒的な情報量ながら、随所に症例を交えた記載は読みやすく、理解もしやすい。この一冊で双極症の全体像を把握することができるだろう。

しくじり症例から学ぶ精神科の薬
病棟で自信がもてる適切な薬の使い方を精神科エキスパートが教えます
レジデントノートの好評連載が単行本化!入院患者さんが精神症状を発症したとき,起こりうる「しくじり」を防ぎ,病棟トラブルを解決!研修医・非専門医が精神科の薬を使うなら必ず読んでおきたい一冊
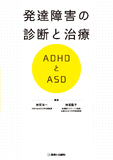
発達障害の診断と治療 ADHDとASD
小児科医×児童精神科医のコラボ!発達障害(ADHDとASD)の診断と治療,疫学や併存症,ライフコースに沿った経過や生物学的病態,障害概念の歴史的経緯などを,最新のエビデンスに基づいてわかりやすく解説.さらには,著者らの熱い思いが詰まったコラムも必見!発達障害研究・臨床の最前線をいく著者らによる,渾身の一作です!

精神科医もできる! 拒食症身体治療マニュアル 第2版
神経性やせ症(拒食症)は、精神疾患の中で最も死亡率が高く、低栄養や合併症が主な死因です。加えて、栄養療法に伴うリフィーディング症候群(再栄養症候群)は致死的となるため、精神科医が治療を敬遠する傾向があります。そのため従来の治療体制は総合病院に限られてきましたが、精神科病床の減少により限界が見え始めています。
こうした課題を受け、浜松医科大学精神科神経科では、精神科単科病院でも活用可能な身体管理マニュアルを開発しました。栄養療法開始日を基に検査内容や投与量、薬剤選定まで明確に規定しており、当直帯でも質の高い医療を提供することが可能となりました。導入後はリフィーディング症候群の発生ゼロ、検査の漏れや苦情の減少、入院期間の短縮と大きな成果が得られました。
初版出版当時は、リフィーディング症候群の予防策として摂取カロリーが極端に低い食事で栄養療法を開始することが推奨されていました。しかし、近年では低栄養状態が遷延することの弊害も考慮されるようになり,より高い摂取カロリーでの栄養療法が提唱されつつあります。そのため、今回の改訂では患者のBody mass indexに応じて投与カロリーを増加させ、一部の薬品をより病態に適したものに切り替えました。また、治療を簡略化し、より簡便に運用できるマニュアルを目指しました。
本書がより多くの現場で活用いただけることを願っております。

みんなの心療内科
心療内科は内科です
「精神科としばしば混同されていますが,心療内科は内科の一分野です」(本文より)と著者が言うように心療内科は心身症などの社内心理的背景が関わる心身症を扱う診療科である.本書は,そのような心療内科の意義や目的,具体的なスキルなどを著者の豊富な経験をもとに初学者にもわかりやすく解説.生活習慣病をはじめとする幅広い疾患への対応能力やコミュニケーションスキルの向上など,日々の診療現場で必ず役に立つ知識が満載の書.

機能性神経障害診療ハンドブック 脳神経内科,精神科,総合診療科のギャップを埋める
器質的原因がわからなくても,治すべき症状がある.
プライマリケア・総合診療科でもCommonな痛みやしびれ,歩行障害など,「特に器質的原因がなく,わからないですね」「気持ちの問題ではありませんか」で終わらせない!
脳神経内科と精神科の境界領域にあるFND,運動異常症,精神・神経疾患を正しく理解し,適切な診療をするための本邦初の診療マニュアル.神経変性疾患や精神科で使用される薬剤によるさまざまな運動異常症など,正しい診断・鑑別ができれば対応が変わります.ドクターショッピングを繰り返していた患者から「先生のおかげではじめて治ることへ希望が持てました」と言われるようになる1冊です.
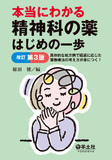
本当にわかる精神科の薬はじめの一歩改訂第3版
具体的な処方例で経過に応じた薬物療法の考え方が身につく!
非専門医のために,精神科の薬の基本と実践をやさしく解説!豊富な図表で作用機序や特徴,副作用などの押さえておきたい要点をパッと確認.症例では具体的な処方のコツがみえてくる!大人気の入門書が待望の大改訂!

てんかん学ハンドブック 第4版
てんかんなら、『てんかん学ハンドブック』てんかん診療の第一人者による、その診療哲学と最新の情報をギュッと詰め込んだミニ百科全書、6年ぶり待望の改訂! 「てんかんは難しい」「どこから手をつけたらいいかわからない」と悩む若手医師、非専門医には最良な入門書として、経験豊かなてんかん専門医にも必ず気づきをもたらす奥深い1冊。「新規抗てんかん薬」はもちろんのこと、ILAEの「2017年分類」および『てんかん診療ガイドライン2018』にも言及。

ジェネラリストのための 向精神薬の使い方
★内科医の先生方が向精神薬の薬理作用をきちんと理解し、根拠を持って処方できるよう解説しました。
★向精神薬を作用機序で分類し、「なぜこの薬剤が使われるのか」を掘り下げて説明しています。
“作用機序から考える”向精神薬の使い分け
【現在の薬剤治療においては、うつ病に抗精神病薬を用いる、慢性疼痛に抗うつ薬を用いる、といったように、診断横断的な使い方が目立ちます。「統合失調症ではないのに抗精神病薬を使う」「うつ病ではないのに抗うつ薬を使う」ということにイマイチ納得できない先生方もいるのではないでしょうか。この疑問に答えるには、向精神薬を作用機序により分類し直して理解する必要があります。そうすることで、向精神薬の選択に合理性をより持たせることが可能になると考えています】(まえがきより)

精神科医と診る精神疾患ミミック / 内科医と診る器質性精神病
「うちの科じゃない!」から脱却するヒント
精神症状をきたすが精神疾患ではない「精神疾患ミミック」という言葉は,内科臨床でなじみ深いと思います.一方で,現在では正式な用語でないにもかかわらず「器質性精神病」は精神科臨床でよく使われます.それぞれ似たような一群を表していますが,内科医と精神科医では見ている世界が大きく異なります.ある側からすると,“原病のコントロール不良による病態や治療による有害事象は原則的に主科が診療すべき”と考えているかもしれません.一方で別の側からは,“身体的な問題は身体を診る科が診療すべき”と譲らないかもしれません.「器質疾患を除外しよう!」のスローガンから始まる精神科と内科のミスコミュニケーション.それを回避するための方法論をぜひご覧ください.

≪シリーズ・高次脳機能の教室≫
記憶障害の診かた
記憶障害をどう診るか、記憶のしくみから検査法まで、やさしく深く丁寧に解説!
《シリーズ 高次脳機能の教室》第1弾! 認知症をはじめとするさまざまな疾患で生じる記憶障害=健忘を、誰にでもわかる言葉で丁寧に解説した最良の入門書。記憶にはどんな種類があり、それが障害されると何が起こるのか? 脳のどの部位が損傷すると記憶が失われるのか? 診断や検査の方法は?臨床に必要な知識を網羅しながらも、やさしく深く楽しく解説。記憶の仕組みと記憶障害のメカニズムを学びたいすべての人へ。

もしも「死にたい」と言われたら 自殺リスクの評価と対応
「死にたい」とだれかに告げることは,「死にたいくらいつらい」ということ.だから,もしもこのつらさを少しでもやわらげることができるならば,「本当は生きたい」のである.「死にたい」という患者を前にして医療は何ができるのか,何をすべきなのか.自殺企図,自殺未遂患者の自殺リスクをどう評価して,どう対応すべきなのか.この難しいテーマに真っ向から取り組んできた筆者がこれまでの経験と知識を元に書き下ろした一冊.

小児てんかん重積状態・けいれん重積状態治療ガイドライン2023
6年ぶりの改訂版である2023年版では,小児救急医療で高頻度に遭遇するけいれん重積状態の病院前治療・初期治療から難治性病態への対応まで日本における治療選択肢等の医療事情を考慮しつつ.システマティックレビュー5項目を加え,実臨床に即してアップデート.適応外使用となる薬剤はその適切な使用を注意喚起のうえ解説し,発作時の患者に対して最善の治療が施せるよう,よりわかりやすく解説した1冊に.
