
脳波判読オープンキャンパス
誰でも学べる7STEP
病態の多様化が進む中で,より複雑化してきている脳波検査について, 本書は初学者が脳波判読の基礎からしっかりと学ぶことができるよう, 読者の判読スキルに応じて読み進めるべき項目を紹介.また,脳波所見を判定していく手順をデジタル脳波の使い方も含めて丁寧に説明し,最終的な脳波レポートの作成ができるように手順をわかりやすく解説した.臨床脳波に携わる初学者の医師や臨床検査技師にとって必携の一冊.

脊椎脊髄・神経筋の神経症候学の基本―日常診療での誤診を防ぐ初めの一歩
「脊椎脊髄ジャーナル」で最速完売の特集号をアップデート&新規10項目を追加!
脊椎脊髄疾患・神経筋疾患の診断においては、症候学が出発点となるべきだが、MRIを筆頭とする画像診断の発達と普及の中で、この原点がしばしば忘れられているのではという懸念がある。MRIは確かに有用だが、それのみに頼って症候学的検討を疎かにすると、容易に誤診に陥る。
本書では、関連各科を志そうと考える初期・後期研修医、あるいは各科の専門医受験前後の若い医師を対象に、expertから脊椎脊髄疾患の病歴聴取・診察のtipsをわかりやすく解説した。各論では実際に誤診しやすい疾患について実例を挙げながら論じた。
学んだtipsを実際に臨床応用して診断に役立つことを実感してもらい、脊椎脊髄・神経筋領域にさらに興味をもってもらえれば、とても嬉しいことである。
なお、内容は、主に「脊椎脊髄ジャーナル」の特集号「脊椎脊髄疾患診断のための神経症候学の基本」(2014年の27巻1号:最速完売)、「脊椎脊髄疾患と間違えられそうになった症例・疾患」(2018年の31巻2号)などの関連論文をもとにアップデート・加筆を行い、新規10項目も追加した。

特発性正常圧水頭症診療ガイドライン 第3版
特発性正常圧水頭症(iNPH)ガイドラインの第3版。
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「特発性正常圧水頭症の診療ガイドライン作成に関する研究」班と日本正常圧水頭症学会の共同事業として実施された今回の改訂は、従来と同様にEBMの考え方に従い「Minds診療ガイドライン作成の手引き」2014年度版に準拠。前半では従来の教科書的な内容を踏襲し、後半に18項目のクリニカルクエスチョン(CQ)に対する回答と解説を掲載。
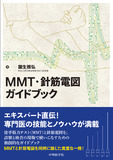
MMT・針筋電図ガイドブック
徒手筋力テスト(MMT)と針筋電図検査について同時に解説されており、神経内科医や脊柱・末梢神経外科医がこれらの検査法を用いて神経疾患や脊椎脊髄疾患の診断を行うために最適なガイドブック。針筋電図とMMTは密接に関係しており、特に神経生理検査の計画を立てる際の神経診察の中核はMMTである。各論では写真をふんだんに用い、各筋ごとに診察-検査の流れに沿って解説。この一冊で筋電図室での神経診察の習熟に大いに役立つ本となった。

脳神経画像解剖ナビゲーション
脳神経の基本的な解剖構造や機能,正常画像を理解して読影するために―地図のように広域アトラスから詳細解剖へアプローチできる,新しい画像解剖書が完成!
各論では,臨床的に異常をきたしやすい解剖構造・機能を,正常・変異・異常を比較して解説.

神経症状の診かた・考えかた 第3版
General Neurology のすすめ
気概、情熱、好奇心。General Neurologyの必読書、待望の改訂!
脳神経内科学の肝である神経症状の診かた・考え方を、本領域の第一人者である著者が、その経験を踏まえてまとめた実践的な教科書。診断への道筋を著者がどのようにたどったかがわかる臨場感のある記載が多くの読者に支持され、 初版以来、幅広い層に読まれた定番書。今回の改訂では、「臨床力とは何か?」「肩こり」の章が追加。さらに新たな症例、知見を盛り込み、全体にわたってアップデート。

改訂2版 脳脊髄血管撮影 超実践マニュアル
【脳血管内治療専門医の試験対策に必携!】
脳神経血管内治療専門医試験の受験生必携書として親しまれてきた書籍の改訂版。脳脊髄血管撮影(DSA)に必要な血管解剖からセッティング、アプローチの実際とその注意点・テクニックまで詳しく解説。改訂にあたり、橈骨動脈アプローチ、エコーガイド穿刺、TRバンドなどを追加。解説Web動画も充実。

脳血管内治療スタート&スタンダード[Web動画付] 改訂第2版
脳血管内治療の不朽の名著が7年ぶりの改訂。橈骨動脈アプローチなど最近の情報にアップデートされた「スタート編」,「脳腫瘍の塞栓」「慢性硬膜下血腫の塞栓」を加えてさらなる充実を図った「スタンダード編」,そして完全新規の「トレーニング編」ではガイディングやデバイス使用のトレーニング方法と上達のコツについて動画も交えて解説する。

顔面神経麻痺診療ガイドライン 2023年版
『顔面神経麻痺診療の手引2011年版』を、Bell麻痺・Hunt症候群・外傷性顔面神経麻痺を対象に、『ガイドライン』として大改訂。
日本顔面神経学会認定の「顔面神経麻痺治療医」、「顔面神経麻痺リハビリテーション指導士」のテキストで、リハビリテーション治療・形成外科的治療・鍼灸治療・その他の治療内容を詳説。システマティックレビューに基づいたCQも充実。

ケースで学び病態を理解する 頭部外傷の診かた
頭部外傷に出合うことのある救急専門医・脳外科専門医・研修医らに捧げる一冊! 頭部外傷治療をどうとらえ、どう対応すればよいのか、実際にあった症例をあげながら、解説しました。頭部外傷への苦手意識を本書で克服しませんか?
「頭部外傷の病態は、複雑であり不安定である」というフレーズがある。これは急性期の損傷脳が相対的虚血状態にあり、興奮性神経伝達物質やフリーラジカル、炎症性サイトカインなどの放出や、細胞内カルシウムの増加などが誘導され二次性脳損傷が生じることから謳われるようになった。また、経時的に変化するため、先読みの対応も求められる。そのような頭部外傷の治療は煩雑なうえに予後が悪いため、これまで治療に関わった先生方の中には、治療意義を感じられないという方もいらっしゃるのではないだろうか。
頭部外傷の形態は時代と共に変化し、以前は脳神経外科診療の多くを占めていた重症頭部外傷は減少し、軽症・中等症頭部外傷の割合が増加している。これは高齢者の転倒、スポーツやレクリエーション活動における頭部外傷が主となっている。これらは時に日常生活に支障をきたす高次脳機能障害が後遺し、復職が妨げられ、結果的に社会的孤立者を生み出す。
近年、治療ガイドラインなどマニュアル本が溢れ、ある症候に対して無為に対応することが増えている。実臨床において単純作業的な治療では、逆に病態悪化へ移行することがあり得る。これは前述のような病態を理解していないことが原因である。
頭部外傷の治療は頭蓋内圧管理をすることではなく、病態を踏まえた脳循環代謝の安定化が目標である。と同時に二次性脳損傷の予防も重要である。つまり我々は多くの因子が関与した原因と病態を正確に理解し、未然に二次性脳損傷を防ぐ治療戦略を練る必要がある。
このテキストはまさに現役世代のエキスパートの先生方が、実に複雑な頭部外傷の病態をわかりやすく説いている。この解説を読めば私と同様に“頭部外傷の治療は面白い!!”と興味を持ち、治療ガイドラインやマニュアル本の真意が理解できるのではないだろうか?
サイエンスに基づいた教育を得てこそ応用が可能である。応用力を要する頭部外傷治療の質の向上に、少しでも貢献できれば本望である。
頭部外傷と聞くと、重篤な状態を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、重症頭部外傷だけでなく、軽症から中等症まで様々です。実際、救急外来では軽症・中等症頭部外傷に頻繁に遭遇するでしょう。その患者さんも近年では、小児から高齢者まで年齢層が幅広くなってきています。後遺症をのこすことなく回復させられるか、できないなら何がベストかなども頭部外傷診療の重要なポイントです。何を最優先にしてみるべきか、頭部CTは必要か、頭部MRIも撮ったほうがいいのか、日々の診療での悩みは尽きません。
本書では初期対応から長期的な対応も含め、第一線で活躍している著者たちが経験した症例をもとに、丁寧に、そして徹底的に解説します。
本書は、人工呼吸管理に苦手意識をもっている医師や医療従事者向けに、日本呼吸ケア教育研究会が行っている好評な人工呼吸管理のワークショップを書籍化しました。人工呼吸管理を基礎からしっかりと体系的に伝えた内容で、また、そのワークショップで伝えている内容もWEB動画で学べるようにしました。本書を読み、WEB動画をあわせて見ると、独学で、人工呼吸管理がしっかり学べる1冊になっています。

脳腫瘍臨床病理カラーアトラス 第5版
最新のWHO分類に基づいた、世界最高品質の脳腫瘍アトラス
日本脳腫瘍病理学会編集による定評あるアトラスの改訂第5版。脳腫瘍の臨床像と病理所見を、大判かつ美麗な写真と簡潔な文章でまとめている。今版も2021年に発表されたWHO分類第5版の改訂に呼応しており、最新の分子生物学的知見をできる限りアップデートし、画像や病理の写真も可能な限り前版と重複しないように心がけた。専門医を目指す若手からベテランまで、脳腫瘍に携わるすべての医師必携の書。

てんかん専門医ガイドブック 改訂第2版
2017年の国際抗てんかん連盟の分類に依拠し,概念や分類,病因,診断,検査,治療などの総論から,新生児から高齢者までの各年代別の重要なてんかんや遺伝子研究結果に基づく特殊てんかんの最新知識,外科治療などを解説した各論,さらには妊娠,運転,生活支援についても具体的に紹介.
てんかん専門医に必要な知識をできるだけ偏らず,かつ過不足なく編集.さらに過去の専門医試験50問を厳選し解説も収載した,専門医試験を受験する医師のみならず,てんかん診療にかかわるすべての医師必携のガイドブックです.

脊髄腫瘍診療ガイドライン2025
脊髄腫瘍に対する診断と治療の最適解を導くガイドライン
脊髄腫瘍は中枢神経系腫瘍の中で比較的まれな疾患であり、発生部位・病理診断により治療法が異なるため、診療には高度な専門性が求められる。本ガイドラインは、脊髄腫瘍の診断・治療に関する最新のエビデンスをもとに、臨床における最適な意思決定を支援することを目的として策定された。これにより、診断精度の向上、治療効果の最適化、副作用の軽減を図り、患者および医療従事者の双方に有益な情報を提供することを目指している。
総論では疫学・自然経過・遺伝的要因・診断・治療を、各論では発生頻度が高く、主に硬膜内髄外に発生する神経鞘腫と髄膜腫、主に髄内に発生する血管芽腫、海綿状血管腫、上衣腫、星細胞腫・膠芽腫、悪性リンパ腫を取り上げた。
脊髄腫瘍は脊髄あるいは脊髄近傍に発生した腫瘍の総称である。発生部位により髄内腫瘍、硬膜内髄外腫瘍、硬膜外腫瘍に分類され、病理学的には脊髄・脊髄神経・髄膜・血管・リンパ組織・椎骨などに由来するもの、転移性のものなどが知られている。
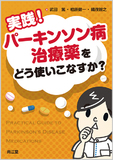
実践! パーキンソン病治療薬をどう使いこなすか?
パーキンソン病領域の第一人者である著者らが、非専門医を対象に、パーキンソン病薬物治療のHow toを伝える。治療薬の基本事項から、治療の実際(運動症状、非運動症状への対応)、さらに問題症例の解説を加えた構成。『パーキンソン病診療ガイドライン2018』の内容を反映した上でガイドラインでは触れられない実践的な部分まで、具体的な処方例を交え解説。薬剤の選択、複数薬の併用方法、減薬方法、副作用への対応など、患者一人ひとりの症状・状況に応じたきめ細やかな薬物治療について学べる一冊。

パーフェクトマスター脳血管内治療 第3版
必須知識のアップデート
脳血管内治療の基礎から実際までを網羅した待望の第3版。
進歩が著しい治療技術,機械器具の最新情報を「Cutting-edge Knowledge」として紹介し,また押さえておきたい難しい手技を「Technical tips」で解説。脳血管内治療の専門医を目指す医師の教科書として役立つ書籍となっている。
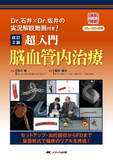
Dr.石井×Dr.坂井の実況解説動画付き! 35本・100分収載(WEB)
改訂2版 「超」入門 脳血管内治療
【再開通・FD等を追加、充実度さらにアップ】大人気シリーズの全面改訂版、ついに登場!初学者向けに、手技のコツとその根拠を会話調でわかりやすく解説。最新、必須、注目のデバイスを使用目的別に比較した「Side Note」も収載。WEB動画は、著者・監修者による、ポイントがわかる音声実況解説付き。

頭痛の診療ガイドライン2021
頭痛に携わる医療者必携の診療指針、最新のエビデンスをもとに大幅改訂!
頭痛診療のバイブル『慢性頭痛の診療ガイドライン2013』が8年ぶりの改訂。二次性頭痛についてのCQが加わり、頭痛に携わる医療者のニーズにさらに幅広く対応。

必携 脳卒中ハンドブック 改訂第4版
「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」に準拠し,臨床における各段階の必要事項を網羅した脳卒中診療の決定版.ガイドラインの列挙と解説に留まらず,脳卒中の基礎,診断,治療,予防,リハビリと幅広い分野が効率的にまとめられており,現場ですぐに役立つ.
今版では,塞栓源不明の脳塞栓症(ESUS)や硬膜動静脈瘻,遺伝性脳卒中,stroke mimicsなどの項目を追加.脳卒中診療に携わるすべての医師にお勧めの1冊.

脳腫瘍診療ガイドライン 成人脳腫瘍編 2024年版
成人脳腫瘍で比較的発症頻度が高く、ある程度のエビデンスが蓄積されている膠芽腫、転移性脳腫瘍、中枢神経系原発悪性リンパ腫(PCNSL)の3分野について、2019年版をもとに部分改訂し、今回新たにGradeII・III神経膠腫を収載した。
推奨決定に関して統一性が得られるよう、Minds2007に準拠して作成された既存の3分野についてもMinds2014による推奨方法に変更した。関連学会、患者団体にもご協力いただき、脳腫瘍診療に臨む医療者に役立つ内容となっている。

脳神経外科 ザ・ベーシック
根拠を理解してマスターする脳神経外科の基本手術
脳神経外科専門医になるために必要な基本知識と若手の脳神経外科医が経験しておきたい手術を網羅的・ 系統的に解説。
すべての手術に共通する開頭手技やシャント・ドレナージ手技などの基本手技,さらには研修期間中および専門医取得後間もない時期に経験しておきたい基本となる手術についてイラスト・写真を多用してビジュアルな紙面構成で丁寧に詳述。
最新情報も満載で,脳神経外科の扉を叩いたその日から,きっと役に立つ一冊!
