
レジデントのための これだけ輸液
みんながつまずくポイントを「わかりやすさ最優先」で解説!
初学者が最初に読むのに適した本になるよう徹底的に考え、執筆しました。
この一冊をきちんと理解すれば、自信を持って輸液を行うことができます。
◎臨床で必ず経験する症例を提示。
◎具体的な治療法を時系列で解説。
◎病態を省略せず、しっかり説明。
◎製剤名・液量・投与速度が一目でわかる。

≪こういうことだったのか 3≫
こういうことだったのか!! CHDF
ますます筆が冴え渡る小尾口先生の「こういうことだったのか」シリーズ第3弾。CHFの濾過原理と、CHDの透析
原理をしっかりマスターすればとっつきにくいCHDFも驚くほど簡単に理解できる。

≪レジデントマニュアル≫
血液病レジデントマニュアル 第4版
血液疾患全領域の知識を定期的に更新するために
研修医、内科医、血液専門医を目指す医師に向けて、血液領域の知識を1冊にまとめた定評あるマニュアル、5年ぶり改訂第4版。新規治療薬、診断基準や診療ガイドラインの改訂をふまえ全面的に記載内容を見直した。これまでと変わらず単独執筆によるもの。生成AIの進歩が著しい時代とは言え、今しばらくは本書を上回るマニュアルは出てこないであろう。限られた医療資源を有効活用するために、医療費についても記載。
*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です。

臨床に直結する血栓止血学 改訂3版
血栓止血学の最高の入門書かつ最強の実践書 待望の改訂3版
前版(2018年)からのアップデートや最新のホットトピックを完全網羅.血栓止血学を専門としない読者にもわかりやすく,すぐに役立つ知識を中心に解説した入門書の改訂3版。内容はボリュームアップしながらも,「ポイント」「ここがコンサルトされやすい!」「症例紹介」「ピットフォール」「お役立ち情報」の記載などにより,「臨床に直結」した内容をコンパクトに網羅しました.血液専門医はもちろん,一般臨床医,他科専門医,研修医,臨床検査技師,薬剤師,医学生,保健学科学生の方々にも役立つ一冊です.

ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023
顕微鏡的多発血管炎(MPA)・多発血管炎性肉芽腫症(GPA)に今回より好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)を加えANCA関連血管炎の3疾患を網羅.Part 1:診療ガイドラインとPart 2:基礎と臨床の診療マニュアルの構成となっている.新たなクリニカルクエスチョンを加えた診療ガイドラインと,近年のANCA 関連血管炎における基礎・臨床医学研究の進歩を反映した診療マニュアルを診療現場でご活用ください.

血液内科 ただいま診断中! 第2版
第2版は“ちょっと難しい”がちょうどいい.すべての診断領域を全面的にアップデート!
「読みやすい」と好評だった初版のコンセプトをベースとして最新の知見や改訂されたガイドラインを反映しつつ,第2版は“ちょっと難しい” をテーマにしてすべての診断領域で全面的に内容をアップデート.初版では記載の少なかった「初期治療・治療前評価」に関してもボリュームアップされ,将来,血液内科を目指す医師や血液内科専門医も納得の読み応えのある内容に仕上がった.まずは手に取って内容をご覧ください

多発性骨髄腫の診療指針2024 第6版
CAR-T細胞療法や二重特異性抗体(BsAb)など,新たな薬剤や併用療法の進歩が著しい多発性骨髄腫.本書では,骨髄腫の定義から臨床所見,診断基準,治療,類縁疾患の診断と治療に至るまで,最新の知見を踏まえて解説する.“臨床現場で気軽に手に取り,参照できるガイドライン”を目指し,診療に関する膨大な情報を図表で整理しつつ,治療アルゴリズムや開発中の薬剤など,最新の動向も取り入れた.

血液製剤の考え方,使い方 ver.3
唯一無二の血液製剤解説書が大幅改訂.楽しく自然に血液製剤の基礎が身に付くバイブル.
医療関係者なら知らないではすまされない,血液製剤.本書では,その現況と展望,そして「使い方」の根拠となる「考え方」を楽しみながら確実に理解できるように作られた唯一無二の血液製剤解説書です.ユニークなキャラクターの会話と2匹のウサギのつぶやきを楽しく読んでいるうちに,血液製剤の基本が自然と頭に入ります.専門医や製造会社協力のもと作成したQ&Aでさらに理解度アップ.また,製剤の添付文書が電子化された今,逆に手元で比較するのにも便利です.学びやすく使いやすい,まさに血液製剤のバイブルです.

血液専門医テキスト 改訂第4版
「血液専門医研修カリキュラム」に則った,日本血液学会編集による専門医テキストの改訂第4版.主要な徴候と検査値異常などの基礎的事項から,腫瘍性・非腫瘍性疾患の病因・病態・診断・治療,患者教育,形態学までの幅広い内容を網羅し解説.今改訂では,進歩の著しい血液領域の診療動向を反映し内容アップデートをはかったほか,細胞療法や免疫関連リンパ増殖性疾患,COVID-19関連の凝固系異常など新規項目も追加し内容を拡充.巻末付録には「血液専門医試験過去問-解答と解説」を収載.専門医を目指す医師必携の一冊.

血液内科 ただいま回診中!
血液内科病棟での感染管理や輸液テクニックなど患者管理の基本はもちろん,血液内科領域の疾患を病態の解説+指導医と研修医の会話形式でわかりやすく紹介.また本書最大の特長としてレジメンや抗がん剤の投与量,スケジュールを見える化した血液チャートを多数収載.臨床経過で出会うイベントと合併症に備えるためのノウハウを『血液内科 ただいま診断中!』の著者が書き下ろした血液内科病棟の必携書!

WHO分類第5版による白血病・リンパ系腫瘍の病態学
造血器腫瘍診療に欠かせない好評書、WHO分類の最新改訂に準拠した待望のupdate
WHO分類に従い,白血病・リンパ系腫瘍の各疾患について定義,疫学,浸潤部位,臨床像,病因,形態学,免疫マーカー,染色体・遺伝子,細胞起源,予後等をエキスパートが解説し,読者の支持を得てきた本書が,WHO分類のアップデートに基づき2019年以来5年ぶりの大幅改訂.最新のWHO分類第5版に完全準拠して構成を改め,各疾患の典型写真を豊富に掲載し,臨床の場や検査室で活用できるよう図った.WHO分類改訂の要点について知り,あらゆる造血器腫瘍の正確な診断と疾患の理解に役立てられる,すべての血液内科医に贈る必読書.

造血細胞移植ポケットマニュアル 第2版
好評頂いた初版を大幅アップデート。移植に携わる全ての医療者に役立つ充実の改訂版。
造血細胞移植について具体的にわかりやすくまとめた実践的マニュアル。移植医、移植スタッフはもちろん、血液内科医にも参考になる書。6年ぶりの大幅改訂になるが、初版同様、基礎知識から臨床の現場で役に立つ細かな注意点までを網羅。さらには移植適応の考え方だけではなく予後予測、移植までの治療、移植前処置、移植後再発対策も含めて解説。移植を成功させて完治へ繋げるために病棟・外来の診療現場で広く役立てて頂きたい。

血液内科治療のトリセツ
京都大学病院の最新プロトコールを余さず解説。血液内科治療のすべてが分かる!
京都大学病院の血液内科診療チームが満を持して贈る「治療のトリセツ」が登場.単なるケモレジメンにとどまらず,すべての治療について京都大学病院で実際に行っている最新治療プロトコールが,疾患ごとの解説でよくわかる.薬物療法だけでなく,細胞療法や放射線療法,緩和ケア,リハビリテーションなど造血器疾患にかかわるあらゆる治療を包括的に解説し,医師のみならず看護師,薬剤師,臨床検査技師,PT,OTなど血液内科のチーム医療に携わるすべての人に必須の内容となった.これ1冊で血液内科治療のすべてが分かる!
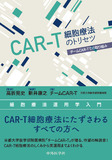
CAR-T細胞療法のトリセツ
チームCAR-Tでの取り組み 細胞療法運用学入門
注目の最新治療「CAR-T細胞療法」の本邦初となる解説書!
事前準備から細胞調製の実際,適応判断から投与後の合併症管理まで,紹介元施設やCAR-T実施施設で行うすべてのプロセスを,医師・看護師・臨床検査技師など多様な職種からなる本治療のトップランナー「京大病院『チームCAR-T』」が丁寧に解説.最新知見をふまえ,CAR-T細胞療法の将来展望についても解説.多職種が有機的に関わりあう細胞療法の運用・管理を体系的に捉える試みとして,筆者らが提唱する「細胞療法運用学」の実践入門書としても最適.

血液内科医にアクセスする前に読む
”血液疾患もどき”鑑別症例帖
Diagnosis for Mimics of hematologic disorders
内科で多く潜むCommonな“血液疾患もどき(ミミック)”の症例を集めた一冊。リンパ節腫大や白血球,血小板異常などの症例を基に,研修医と指導医の会話形式で若手がつまづきやすい点を整理しながら検査値,身体・画像所見,症候の見極めを解説。もどきを見抜くポイントを知ることで鑑別診断が捗り,容易に血液内科にアクセスできない状況でも自己解決できるようになる。また除外診断に直結する頸部エコーのコツや画像のみかた,鑑別すべき疾患等の関連がわかるコラム解説も充実。
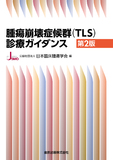
腫瘍崩壊症候群(TLS)診療ガイダンス 第2版
多数の新規分子標的治療薬の登場により、腫瘍崩壊症候群(TLS)は大きく変貌した。造血器腫瘍だけでなく、様々ながん腫においてTLS診療の重要性が高まっている。新規治療薬の導入毎にリスクを再検討する必要が生じたこと、また2015年に英国においてTLS panel consensusを踏まえた新たなガイドラインが公表されたこと、さらにTLSの治療薬であるラスブリカーゼの臨床導入によりTLSの病態が高尿酸型から高リン型へ質的に変化したことなどから、8年ぶりの大改訂が行われた。

ER・ICUの適正輸液[Web動画付]
輸液負荷は無意潜行に蓄積されやすく,“fluid creep(忍び寄る輸液)”として警鐘が鳴らされている。欧州で輸液監視システム構築と運用の取り組みが始まっている流れを受け,国内での「輸液の適正使用」(Fluid Stewardship)の実現に向けて,具体的な輸液適正化モデルを示す一書である。輸液療法の動向,一般的な基礎理論と急性期生理学・体液組成・感染や栄養管理,輸液反応性を適切に評価するためのパラメータの解釈,個別の疾患・病態における輸液削減のポイントを網羅する。特に最終章では症例ベースで輸液量の振り返り,in outを可視化したうえでさらなる適正化の可能性と模索の具体策を示す。

白血病治療マニュアル 改訂第4版
白血病患者の治療方針を立てるために必要な治療選択から各種プロトコール、支持療法、合併症対策までを盛り込んだマニュアル書の改訂第4版。今改訂では、分子標的治療薬を用いた最新のプロトコールを盛り込み、内容をアップデート。また白血病治療において重要性が増している「微小残存病変の評価と対応」について、1章を割いて解説。ベッドサイドマニュアルとして、血液内科医必携の一冊。
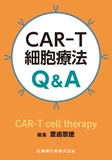
CAR-T細胞療法Q&A
CAR-T細胞療法について知りたい全ての疑問にQ&A形式で答える最新刊!
●CARとはキメラ抗原受容体の略.がん細胞の表面にある抗原に対し,通常のT細胞の受容体は結びついて攻撃するものもあるが,素通りしてしまうものもあり,自然免疫のみでがん,特に血液のがんを効率良く殺すことはできない.そこで患者のT細胞を取り出し,効率良く血液のがん細胞の抗原に結びつくよう受容体を遺伝子改変したCAR-T細胞を体外で作製し,患者の体内に戻すことでがん細胞を倒す,という最新の免疫療法が「CAR-T細胞療法」である.
●2019年の初承認以来,現在5製剤が承認され,最近では専門の認定施設だけでなく紹介施設も関わることが多くなってきた.本書は血液のがん診療の現場で知っておきたい必須の知識についてQ&A形式で解説.
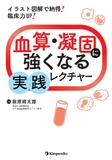
イラスト図解で納得! 臨床力UP! 血算・凝固に強くなる実践レクチャー
イラストだから全体像がイメージしやすい! 症例で検査値異常の読み方と診療の進め方がよくわかる!
本書は、臨床の現場で日々奮闘している医師、検査技師、看護師のみなさん、これから医療・医学を志す学生のみなさんが、「血算・凝固に強くなる!」ことを目指して執筆しました。
血算と凝固検査の「きほん」から「実践」までを、できるだけ多くのイラストを用いて、「イメージ」として、全体像が理解できるように工夫しています。
本書を読まれた皆さんが、「なぜ、その数値になるのか?」「どのような疾患が隠れているのか?」「患者はどのような全身状態なのか?」など様々な問いを自ら解決できるように、お手伝いできれば幸いです。
はじめに
血算と凝固検査は、身体の状態を反映する基本的な検査です。
しかし、基本的な検査である反面、結果の解釈に悩むことも多いのではないでしょうか?
また重要な意味がある数値を、見過ごしていることもあるかも知れません。
血算は、造血能力、内分泌機能、炎症や感染症、栄養状態、悪性腫瘍などを反映します。
凝固検査も、肝機能、栄養状態、炎症や感染症、薬剤など様々な状況に影響を受けて数値が変化します。
本書は、臨床の現場で日々奮闘している医師、検査技師、看護師のみなさん、これから医療・医学を志す学生のみなさんが、「血算・凝固に強くなる!」ことを目指して執筆しました。血算と凝固検査の「きほん」から「実践」までを、できるだけ多くのイラストを用いて、「イメージ」として、全体像が理解できるように工夫しています。
本書を読まれた皆さんが、「なぜ、その数値になるのか?」「どのような疾患が隠れているのか?」「患者はどのような全身状態なのか?」など様々な問いを自ら解決できるように、お手伝いできれば幸いです。
2022年3月
執筆者代表 萩原將太郎
