
腎不全の緩和ケア
腎不全には透析や腎移植などの腎代替療法が複数あり,それらの導入や,場合によってその見合わせにより,予後もそれぞれ大きく変化する点が,他の臓器不全と異なる特徴です.さらに近年では高齢化に伴い,透析の見合わせによる保存的腎臓療法(CKM)や,意思決定に迷う場合の期限付き透析の実施(time limited trial)といった,考慮すべき選択肢も増えており,関わる医療者も腎臓内科や泌尿器科,透析医療,在宅医療や緩和ケアなど多領域・多職種にわたります.本書では,腎代替療法の有無を問わず,保存期から末期腎不全、そしてエンドオブライフ期に至るまで患者さんのたどる道のりを念頭に,ふまえておくべき背景知識を解説し,多様な状況への対処法を豊富な事例とともに探ります.患者さんに最期の時まで自分らしく穏やかに過ごしてもらうための方法を,関係者皆で考えていくための一冊です.

がん疼痛緩和の薬がわかる本 第4版
なぜこの薬? 副作用は? アセスメントのポイントは? 第4版ではさらにわかる!
好評書として定着した本書が、取りあげる薬剤をさらに充実させた。がん疼痛緩和の薬の効用や副作用、アセスメント、選択・使用の考え方がわかりやすく解説され、症例が豊富にあげられているので、より理解が進む。がんの痛みの理解から、非オピオイド鎮痛薬、オピオイド、鎮痛補助薬まで取りあげた、臨床のエッセンス満載の1冊。

緩和ケアレジデントマニュアル 第2版
最期まで患者の望む時間を提供するために。緩和医療スタッフ必携の書、改訂!
次々に起こる症状への対応、予後予測、ACP、家族のケア、リハビリテーション……、最期まで患者の望む時間を提供するために、何をするのか。エビデンスをアップデートしつつ、経験も重視して、より実践的に改訂。病棟でも外来でも在宅でも、がんでも非がん疾患でも、すべての患者の苦痛緩和をめざす医療スタッフに必携の書!
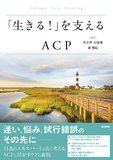
「生きる!」を支えるACP
31名のエキスパートと共に考える,ACPに活かすケアの真髄
一定期間の臨床実践を重ねた今だからこそ見えてきた、31名のエキスパートによる実践知を結集。ACPの現在地とこれからを多角的に展望する。おさえておくべきエビデンスから、多様な疾患・病期・ケアの場の最前線の実践、システム構築までをカバー。「患者との話し合いの手引き」など、明日から活用できるコミュニケーションスキルも丁寧に解説。ACP実践の道しるべとなる一冊。

あなたにもできる スピリチュアルケア
死を前にした人が穏やかになるために、誰もができることがあります。
「もう死んでしまいたい」「迷惑をかけてばかり」──死を前にした人の言葉に、応え続けることができますか。そこでは励ましも説明も、力を持ちません。私たちにできるのは、相手にとって「わかってくれる人」として対話を重ね、大切な「支え」を強めること。それが “スピリチュアルケア”です。スピリチュアルケアは、一部の人だけができる難しいケアではありません。わかりやすい言葉で、真似しやすい方法で、すぐに実践できるスピリチュアルケアがここにあります。

緩和ケア 即戦力ノート
あなたにもできる、やさしい緩和ケア
【①基本的緩和ケアに特化】
緩和ケアの専門家ではないけれど,苦痛を抱える患者のために緩和ケアのことを知りたい.そんな医療者のための実用的入門書!
【②必要なときにサッと見て、即使える知識が満載】
豊富な図表と処方例,要点を押さえた解説が,日常臨床でカンペのように役立ちます.
【③Webサイトと連携】
緩和ケア情報サイト「緩和ケア オンラインポータル(PCOP)」とリンクしており,本書の内容をスマホやタブレットでいつでもどこでも復習・確認できます.

終末期の褥瘡
適切な予防やケアを行っていてもなお不可避な,終末期に特徴的な褥瘡があることは知られつつありますが,終末期でも褥瘡予防やケア自体は有効で,それを行うことが無意味ということでは決してありません.また一言で終末期といっても,その経過はさまざまで,注意すべき点も異なります.本書では,これまでの海外およびわが国の褥瘡対策をふまえて,終末期を「超急性」「がん」「超高齢」の3つに大きくわけて考えました.それぞれ終末期の病態,褥瘡発生リスクや予防,治癒を目指せないような状況で本人の苦痛を減らすために何ができるかなどについて解説し,さらに,在宅での対応や,今後の展望についても示しています.終末期のケアは無意味じゃない,適切にケアを行っていても褥瘡ができてしまった時は自分を責めず,チームの仲間たちと患者さんの尊厳を保つケアを続けましょう,安心してそんな実践ができる環境を皆で整えていきましょうという,多職種プロフェッショナル達からのエールの詰まった一冊です.

アルゴリズムで身につける
がん緩和ケアに活かす 5大症状診断術
●エキスパートの診断術がアルゴリズムでわかる!
緩和ケアの最前線で活躍する著者が、臨床で感じている「こんな情報がまとまっていれば……」を形にしました。緩和ケアの現場で医療従事者、患者・家族を悩ます5大症状(痛み、せん妄、悪心・嘔吐、呼吸困難、倦怠感)へ的確にアプローチするためのコツを解説。エキスパートは何を診て、どう判断するのか――医師の思考のステップをアルゴリズムでわかりやすく紹介するほか、必要な情報が多忙な現場でもすぐ理解できるよう、さまざまな実践的ツールを掲載しています。
緩和ケアに携わる医師をはじめ、すべての医療スタッフ必携の1冊です。

死を前にした人に あなたは何ができますか?
看取りの現場では、答えることのできない問いを突き付けられる。「下の世話になるくらいなら、いっそ死にたい」「どうしてこんな目に合うの?」。そこでは説明も励ましも通用しない。私たちにできるのは、相手の話を聴き、支えを見つけること。言葉を反復し、次の言葉を待つこと。それは誠実に看取りと向き合ってきた在宅医がたどりついた、穏やかに看取るための方法。死を前にした人に、私たちにはできることがある!

いのちに驚く対話
死に直面する人と、私たちは何を語り合えるのか
多文化都市ニューヨークでホスピス緩和ケアに従事した日本人による「対話」の指南書
ニューヨーク訪問看護サービス(Visiting Nurse Service of New York)でホスピス緩和ケアに従事し、スピリチュアルケア・プログラム・マネージャーも務めた日本人による指南書。多文化都市ニューヨークで、多くの「死に向き合う人」とどのように出会い、いかに語り合ってきたのか。目の前に広がる患者さんと著者との物語と、言語や文化を超えた「対話」の現場感覚が味わえる1冊。

死亡直前と看取りのエビデンス 第2版
亡くなる過程を科学する
「亡くなる過程(natural dying process)を科学する」という視点を国内で初めて提供した書籍の第2版。今改訂では、初版刊行以降の国内外における新たな研究知見をふんだんに盛り込み、著者自身の経験に根差したわかりやすい解説とともに、新たな知見がどのように臨床に役立つのかにも重点が置かれている。「死亡直前と看取り」に携わるすべての医療職者に向けた待望の改訂版、ここに堂々の刊行!

これからはじめる
非がん患者の緩和ケア 第2版
●これから非がん患者の緩和ケアを始める人へ
●「がんと何が違う?」「いつから始める?」「どう説明したらよい?」--疾患の進行にあわせた症状緩和への対応・処方がわかる!
●ACP、退院支援、社会的支援など、地域医療ともつながる緩和ケアの実践書
非がん患者の緩和ケアって? 患者さんに何ができる? そんな疑問に答える実践書です。
一言で「非がん」といっても、心不全・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・慢性腎臓病(CKD)・肝硬変・認知症・神経難病など、疾患によって病態や経過、患者が苦痛と感じる症状や状況は異なり、治療の目指すところや対処方法もさまざま。そこで本書では、各疾患の標準治療、病期に伴う治療方針の転機、薬物療法・非薬物療法による緩和ケアの基礎をしっかり押さえ、ACP(Advance Care Planning)を行うタイミングや、患者とのリアルな会話事例を紹介します。
第2版では、急性期医療から地域医療へつなぐ退院支援のポイントなどを追加。本書を読んで、今から、明日から、非がん患者の緩和ケアを実践してください!

患者と家族にもっと届く緩和ケア
ひととおりのことをやっても苦痛が緩和しない時に開く本
“難治性”と決めつける前に、できることがまだまだある!薬も増やした、あれもこれもやってみた、でもまだ痛みが取れない。もしかしてその痛み、がんのせいじゃなくて筋肉の虚血のせい? 非オピオイド鎮痛薬を飲んでいないから? レスキュー薬が来るまでに時間がかかりすぎ? 痛みの原因に気付けば、今できる工夫がきっとあります。「これをやれば苦痛が取れるかも?」という着眼点を、細かく丁寧に書きためた1冊。

一歩進んだ緩和医療のアプローチ
その難しい症状,どう緩和する?
薬物療法のほか,従来のガイドラインやテキストではあまり記載されてこなかった神経ブロックや放射線治療,IVRなどの非薬物療法まで,一歩進んだ緩和ケアのアプローチを包括的に紹介.フローチャート化された症状別の治療戦略,難治例におけるチャンピオンケースを読み進めることで,“標準治療でうまくいかない場合の次の一手”が身につく.各専門科のエキスパートによる実践知と工夫を結集し,緩和医療の可能性を広げるヒントとなる一冊.

エビデンスからわかる
患者と家族に届く緩和ケア
オピオイドを拒否する患者さんには、その理由を尋ねてみる。終末期の患者さんの、つじつまの合わない言葉に付き合う。現実とかけ離れた希望も、否定せず大切にする。そんな1つひとつのケアが、患者さんと家族の大きな助けになる。日常のケアを裏付けるエビデンスから「今、できる緩和ケア」を考える本。
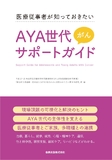
医療従事者が知っておきたい
AYA世代がんサポートガイド
AYA世代とは思春期・若年成人を指す。小児期と成人期の間にあたるAYA世代の患者は「病気の治療が生殖機能に及ぼす影響」「晩期合併症」「通勤や通学に及ぼす影響」「多感な時期に病気に罹患することによるさまざまな精神的ストレスや将来への不安」などの問題を抱えている一方、サポート情報が少ない。本書は医療従事者だけではなく、教育、就労支援など多方面の専門家が、治療から妊孕性、メンタルケア、経済問題、教育、栄養、コミュニケーションなど幅広く論じた。
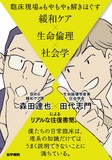
臨床現場のもやもやを解きほぐす 緩和ケア×生命倫理×社会学
僕たちの日常臨床は、理系の知識だけではうまく説明できないことに満ちている。
患者は余命を知りたいのに、家族が反対するのはなぜ?患者が頑なに貫いてきた面会拒否は、亡くなった後も続けるべき?緩和ケアの日常臨床は、答えに辿りつかない「もやもや事例」に満ちている。悩める緩和ケア医・森田達也と、生命倫理学者兼社会学者・田代志門によるリアルな往復書簡が、臨床のもやもやを解きほぐす!文系×理系の視点で「それでどうするの?」から「なんでそうなるの?」までを考える、ゆるくて深い越境の書。

ペインクリニックナースのための 神経ブロックケアマニュアル
NTT東日本関東病院ではこうしている! 神経ブロックケアの極意
看護師のための神経ブロックケアマニュアルが完成しました.神経ブロックを進めるうえで確認しておきたい適応,必要物品,手順,合併症と副作用,看護のポイント,トラブルシューティングをコンパクトにまとめました.30を超える神経ブロックを網羅すると同時に,痛みの評価方法,心理的サポートの重要性などの要所も押さえ,基礎を学びたい初学者から,アドバンスドなケアを求められるエキスパートまでをカバーした一冊です.NTT東日本関東病院のスタンダードをぜひ体感してください.

救急・集中治療領域における緩和ケア
救命ができても死が避けられなくても、がんだけではなく心不全でも外傷でも、緩和ケアニーズは存在する。救急外来やICUにおける緩和ケアニーズのアセスメント、患者・家族とのコミュニケーション、苦痛症状に対するケア──時間が限定された救急外来やICUだからこそ、提供できる緩和ケアがある。「救命か、緩和か」ではなく、「救命も、緩和も」かなえるために、領域を越えて編まれたはじめての書。
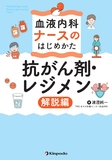
血液内科ナースのはじめかた 抗がん剤・レジメン解説編
看護師が配属時に読む本として好評を得ている『血液内科ナースのはじめかた』の続編.本書は抗がん剤・レジメンに特化した内容で,血液内科では薬物治療が主であり,看護師にとって抗がん剤・レジメンや副作用の知識は不可欠である.また血液内科の看護師に特化した類書はなく,本書はわかりやすい表・イラスト,親しみやすい文章で血液内科で使用する抗がん剤・レジメンを理解し,患者のケアに役立てることができる一冊.
