
みんなの急性期リハビリテーション・栄養療法
ICUやHCUでの多職種連携によるリハビリと栄養がわかる!
ICUやHCUなど多職種が協働する急性期病棟でのリハビリテーション,栄養療法について医師看護師のみならず,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,薬剤師,管理栄養士など多くのスタッフが実際の現場でどのように協働していくべきか,またそれによっていかにPICS(集中後症候群)を減らすことができるのかを,臨床の流れにそったわかりやすい解説と理解を助けるイラストとを交えて解説.急性期病棟スタッフ“みんな”のための入門書.

≪プロメテウス解剖学≫
プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第4版
解剖学を美しく学ぶ。定番書にして最高峰の一冊
言わずと知れた解剖学アトラスの最高峰が待望の改訂。第4版では、「筋膜」や「肘関節の画像診断」など、近年の医療に合わせた項目が新規に収載。読者の理解を深めるため、イラストの美しさを追求する姿勢はとどまることを知らず、少しずつ解釈が変遷する細かな変化にも対応し、内容面にもさらなる磨きがかかっている。職種を問わず、人体の構造を学ぶすべての人に──。
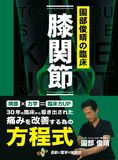
園部俊晴の臨床 膝関節
数多くのプロスポーツ選手や著名人が集まるコンディション・ラボの理学療法士、園部俊晴の初の単著がついに発売。
伝説の理学療法士、入谷誠の一番弟子としてスタートした30年の臨床の中で培った技術と知見を余すことなく詰め込んだ膝関節書籍の決定版。

≪臨床家シリーズ≫
園部俊晴の臨床 徒手療法ガイドブック 腰部殿部股関節大腿編
1万部を超えたベストセラー『園部俊晴の臨床』シリーズの最新作!
■「滑走」と「伸張」をキーワードに、 腰部・殿部・股関節・大腿の機能障害に 効果的にアプローチする、 独自のメソッドを公開。
■多くの一流アスリートや著名人を相手に結果を出している徒手治療の技術を、 豊富な写真とわかりやすい解説で完全網羅。
---ポイント---
慢性痛を引き起こす原因となる「滑走性」と「伸張性」の重要性について解説。
痛みの評価と治療に役立つ「第3水準の評価」について詳しく解説
腰部、殿部、股関節、大腿の各部位に対する具体的な徒手療法テクニックを、豊富な写真とわかりやすい解説で紹介。
多裂筋、腸肋筋、梨状筋、大腿筋膜張筋など、主要な筋肉へのアプローチ方法を網羅。
坐骨神経、大腿神経など、神経に対するアプローチ方法も解説
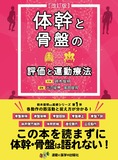
体幹と骨盤の評価と運動療法 改訂版 2版
この書籍を読まずに体幹・骨盤は語れない!
ベストセラーとなった『体幹と骨盤の評価と運動療法』がリニューアル!
[概要]
身体のどの部位の治療に当たるにしても、体幹の機能が大きく関与することは臨床を通して、漠然と感じていたことだと思います。その漠然と感じていたものが、本書の分かりやすいイラストや写真によって、イメージすることが可能になっています。さらに、膨大な論文や研究データを基に、臨床で求められる体幹機能の改善方法について分かりやすく解説したことで、1年目のセラピストでも体幹の機能が深く理解できるようになっています。
[改訂版について]
今回のリニューアル改定では、特に4章「座位における体幹・骨盤の機能と運動療法」と、5章「立位における体幹・骨盤の機能と運動療法」に力をいれております。各動作の項目(4章では4動作、5章では3動作)ごとに対する運動療法のポイントを、臨床に即した形で解説しています。各動作に必要な筋活動と動作の捉え方が理解出来るようになれば、体幹の機能を高めながら身体の各部位の治療を展開することも可能です。臨床の幅が広がり、目的をもった運動療法を展開するためにも、本書を読み進めて頂ければ幸いです。
-各章のポイント-
第1章
体幹の解剖運動学
体幹・骨盤の筋の性質や機能を理解するための『解剖学的知識』『力学的知識』『動作時筋活動知識』を学ぶことができます。
第2章
体幹の構造と機能
体幹・骨盤を構成する骨格や筋のより詳細な解剖学的知識に加え、臨床でよく見る様々な動作時の筋活動が詳細書かれています。
第3章
運動と現象
体幹・骨盤の『運動』と『現象』の捉え方に加え、これらに関与する各筋の筋緊張亢進・低下がどのような影響を及ぼすのかを解説しています。
第4章
座位における体幹・骨盤の機能と運動療法
座位における様々な動作の体幹・骨盤の機能に関する研究に加え、座位での運動療法を展開する際、体重移動がどのように生じ、どのような筋活動が起こるのかという筋電図学的な視点を取り入れることができます。
第5章
立位における体幹・骨盤の機能と運動療法
立位における体幹・骨盤の機能、さらに足部における機能について説明しています。立位における体重移動練習時において、体幹・骨盤周囲筋の機能を理解した上で運動療法を実践していく時に役立ちます。

運動学習の知識を活かす神経リハビリテーション実践
回復への最適解を探る
理学療法士や作業療法士にとって「運動学習」はなじみのある言葉ですが、養成教育のなかで体系的に学ぶ機会はほとんどありません。
本書は、リハビリテーションの観点から「運動学習」について網羅的・体系的にまとめ、臨床での課題設定や介入方法を提示し、具体的な症例を通して実際の運用でのポイントを示した、たいへん学びやすい一冊です。
運動学習の知識を学び、リハビリテーションの実践に活かすことを第一としてまとめられた本書は、「運動学習」についてきちんと学びたい理学療法士・作業療法士にとって最適なテキストです。

≪関節拘縮シリーズ≫
肩関節拘縮の評価と運動療法 改訂版
▶肩関節治療の決定版が10年ぶりにリニューアル
もっと軽く!もっと自由に!
肩関節をさらに解き放て!
▶イラストと写真を刷新。さらにわかりやすく!
▶著者の実技映像を59本追加!
本書は、10年前に出版された『肩関節拘縮の評価と運動療法』の改訂版です。
シリーズ5万部を越えている『拘縮』シリーズでも特に人気の本書に新たに実技映像を追加し、読者がより効果的に学ぶことができるようになっています。改訂版では、イラストや図が一新され、より解説がイメージしやすくなっています。
また、肩関節拘縮の評価方法から、運動療法の実施方法までを詳しく解説し、運動療法に興味がある理学療法士やスポーツトレーナー、医師、学生などに向けた内容となっています。
QRコードを読み取ることで、本書で紹介された運動療法を実際に実践している著者の解説映像を59本視聴することができます。本書を読むことで、肩関節拘縮の適切な評価と効果的な運動療法の実際を学ぶことができます。前作を読んだ読者はもちろん、新たに知見をブラッシュアップしたい方にもオススメの書籍となっています。

成田崇矢の臨床 腰痛
評価に"確信”を、治療に"革命”を
▶“機能的腰痛”の大半は4つの病態に分別できる!
▶各病態の評価と治療の真髄を一流治療家が徹底解説!
▶"非特異的腰痛”という言葉に逃げていい時代は終わった。
運動器疾患の治療で避けては通れないのが腰痛改善。しかし、その治療結果に相手が、そして自分自身が納得していない臨床家は多いはず。様々な治療法を学んだり、文献を読み漁ってもなぜ、結果につながらなかったのかが本書を読めば納得できるはずだ。
本書では腰痛治療の極意を次のように示した。それは、『痛みを発生させている組織を仮説し、その組織および、その組織への負荷を改善させる』だ。言葉にするとシンプルだが、実際には多くの治療家が『原因組織の仮説』の段階でつまづいている。なぜなら、一般的に腰痛の85%は「非特異的腰痛」と呼ばれ、原因が特定しきれないと言われ、かつその言葉に逃げてきたからだ。
しかし、筆者の成田崇矢はこれらを「機能的腰痛」と名付け、大半の腰痛は機能を変えれば痛みも変わると断言している。さらに、この『機能的腰痛』は「椎間関節障害」「仙腸関節障害」「椎間板障害」「筋・筋膜障害」の4つの病態に収まるとしている。それぞれの鑑別・評価・治療法を体得することで、その場で改善することが可能になった。本書を通じて適切な仮説と、適切な検証の方法を学べば、腰痛患者に対し、「何をすべきか」がみえてくるはずだ。
さあ、今こそ圧倒的な結果を出すための“確信”と“自信”を手に入れよう。

運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学 第2版
徒手療法がわかるWeb動画付
「なぜ?」シリーズの元祖本にWeb動画がついてパワーアップ!
臨床あるあるの疑問や理由が解剖学ですっきり解決! 実際の徒手療法がWeb動画で見てわかる! 頸椎症由来の頭痛はなぜ起こるのか? 投球動作を解剖すると? くり返す足関節捻挫後の不安定感にはどう対応すればよいか? 遭遇頻度の高い運動器疾患のメカニズムや痛みの原因、運動療法の選択を症例にそって解説。筋・神経の構造や動きを把握することで、痛みの原因や治療法が解明されます。実践的解剖学、待望の改訂です。

≪関節拘縮シリーズ≫
股関節拘縮の評価と運動療法
「拘縮」を深く理解し、臨床の実践で追求していくと、疼痛とのかかわりが診られるようになり、多くの病態を理解できるようになります。
この林典雄先生の言葉は、運動器疾患を診る上であまりに重要な意味を持っているんです!
股関節疾患を良くするためには、硬くなっている組織を見つけて、それを改善していかなければいけません。
なぜなら、関節拘縮が股関節疾患の基盤となっているからです。
評価をしっかりとして硬くなっている組織を見つけなければ、いくら動きにくい方向にストレッチしても動くようにはなりません。
しかし、評価をしていないと言うと、よく言われることがあります。
「評価ぐらいしていますよ。毎回、角度や痛みのでる動作を確認して、動作分析もしています。」と。
確かに、評価はしているかもしれません。
しかし、その評価は関節可動域を測ったり、筋力を確認したり、痛みの出る動きを確認する程度にとどまっています。
それも確かに大切です。
しかし、医療機関に来る股関節疾患の患者は主に痛みがあるために来院します。
そのため、痛みの原因となっている組織を特定して、なぜその組織が痛みを出してしまっているのかを評価しないといけないのです。
動きにくい方向に関節可動域練習やストレッチを、筋力が低下している筋の筋トレを行っていればいいというわけではないのです。
まずは原因となっている組織を特定しなければいけません。
そのためには、機能解剖、バイオメカニクスなどの基礎知識をもとに、疼痛、拘縮、異常歩行など様々な評価をもとに解釈しなければなりません。
その中でも、拘縮は他に及ぼす影響か大きい為、「関節拘縮の評価と治療」は特に重要といっても過言ではありません。「関節拘縮の評価と治療」を行うためには、解剖学と運動学を熟知すると共に、正確な触診技術や関節操作が必要です。
だからそれをしっかり学ぶ必要があります。
股関節のことをしっかり学びたい・・・
拘縮を改善して痛みを改善したい・・・と思った、 あなたに、
ぜひ『股関節拘縮の評価と運動療法』を読んで頂きたいです!!
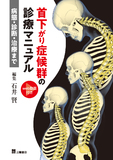
首下がり症候群の診療マニュアルー病態・診断・治療まで
治療経験が豊富なエキスパートによる「首下がり症候群」の教科書
首下がり症候群は、過去においてまとまった症例数の報告が少なく、国内外において、その病態や治療戦略などが確立していないのが現状である。
今回、本書では、高齢社会や生活習慣の変化で増え続ける、首下がり症候群に対する日常診療に役立つよう、首下がり症候群の治療経験が豊富なエキスパートの医師と研究者の執筆により、現時点での国内外の最新治療・最新知見を書籍としてまとめた。病態・診断・治療の全体像を網羅的に示しており、首下がり症候群の診療に携わる脊椎脊髄外科医、整形外科医、脳神経外科医、脳神経内科医を含むすべての内科医、リハビリテーションスタッフ、看護師、診療放射線技師などの医療従事者が標準的な知識と技術を習得できるバイブルである。

こんなときどうする!? 整形外科術後リハビリテーションのすすめかた
術後リハの臨床場面で起こるどんなイレギュラーにも慌てない
腰椎椎間板ヘルニア、変形性股関節症、橈骨遠位端骨折…本書は、整形外科領域のリハビリテーションを担当する療法士に馴染みの深い代表的な疾患について、術後のリハビリテーションに焦点を当てて、時系列に沿いながら多角的に解説する。また、多くの療法士が持つ悩みをよくわかっている臨床経験豊富な執筆陣により、臨床で誰しもが一度は遭遇するであろう“こんなときどうする!?”をピックアップし、具体的な解決策を提示する。

目でみる嚥下障害 第2版 Web動画付 嚥下内視鏡検査(VE)・嚥下造影検査(VF)の所見を中心として
嚥下造影検査(VF)と嚥下内視鏡検査(VE)の解説テキストが待望の改訂!
●嚥下障害の病態を把握して治療方針を立てるためには,VFとVEが大変役に立つ
●本書では,著者らが長年臨床に携わるなかで集めてきたVFとVEの所見を駆使して“みえない嚥下障害”を“目でみえる”ようにわかりやすく解説した
●Web動画152本,カラー画像332点を収載
●テキストとWeb動画を併用することで,より理解を深められる
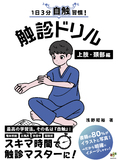
触診ドリル 上肢・頚部編
1日3分自触習慣!
触診ドリル。
それはペンもノートもいらない、究極の学習法。
■触診は大事!...だけど...
時間がない...
練習相手がいない...
場所がない....
■そんな人におすすめな学習法が“自触(じしょく)”
自触とは、『 “自”分の身体を“触”診する学習法』です。
自触は触れる感触・触れられる感触を同時に体感できるため、他人に対して触診するよりも効果的に学習できます。 ・
■自触の3つのメリット
いつでもどこでも気軽にできる。
触れる・触れられる感触を同時体感できる。
必要なのは自分の身体と手だけ。
➡1日3分の自触習慣で触診マスターに! ・
【本書の3つの特徴】
いつでもどこでも効率よく練習できる
自触は1人でどこででも行うことができます。また、他人を触れるより、自分自身を触れるほうが、対象が良く分かる為、効率的に練習できます。自分自身を触れるのに遠慮は要りません。どんどん触れていきましょう。
専門用語を使わない分かりやすい文章構成
本書では、可能な限り解剖学用語や運動学用語を知らないでも肢位や運動が理解できるような文章構成にしています。そのため、初学者でもイメージしやすく、楽しく読めるように工夫しています。
臨床応用につながる知識も多数掲載
本書では各部位の初めに、対象部位の機能解剖学と臨床との接点についての解説があります。そのため、習得した触診技術をどのように臨床に応用するのかをイメージしながら練習できるので、効果的に学習できます。
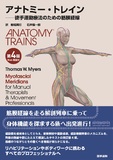
アナトミー・トレイン [Web動画付]<訳> 第4版
徒手運動療法のための筋膜経線
身体の筋膜経線をたどる旅へ、解剖列車に乗って出発進行!
人体を走る筋膜経線によって、姿勢制御や運動連鎖のしくみを、列車の路線(lines)や駅(stations)にたとえて解説したテキストの改訂第4版。筋膜のつながりとその驚くべき機能が明らかになる。2019年より、アナトミートレイン・ストラクチュラルインテグレーション(ATSI)認定プログラムが日本でも開始され、国内での資格取得が可能となった。リハビリテーションやボディワークに携わるすべての人々へ。
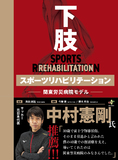
下肢スポーツリハビリテーション-関東労災病院モデルー
■中村 憲剛氏(サッカー元日本代表)推薦!
-----------------------------------------
『39歳で前十字靭帯損傷。
そのまま引退かと言われた僕の40歳での復活劇を支え、
導いてくれたのは関東労災病院のみなさんでした。』
-----------------------------------------
■このプロトコルは“競技力”を変える。
日本一の『実績』と『復帰戦略』を誇るスポーツリハ集団が、
全17項目におよぶ超ボリュームで最前線の治療技術を公開!
■“ 怪我 ” はさらなる“ 進化 ” の始まりだ。
理学療法士は、単なる治療家であってはならない。
選手の未来を創り、
パフォーマンスの限界を押し広げる
可能性を秘めている。
そのためのヒントが本書にある。
本書は関東労災病院の圧倒的な症例数をもとに
術後リハビリから保存療法までの技術と知識を詳しく解説し、
スポーツリハビリテーションにおける
最前線の知見を取り入れている。
ただ痛みを取るだけのリハビリではない。
機能回復とともに、競技力向上を見据えた戦略的な介入。
トップアスリートが全国から集まり、
多くの選手のキャリアを支えてきた理由を
本書から学ぶことができるだろう。
マイナスをゼロへ、
ゼロをプラスへ。
あなたの技術が
アスリートにとっての “ 試練 ” を
“ 進化 ” に昇華させる。
この一冊が、あなたの知見を進化させ、
未来のアスリートをさらなる高みへ導く力
となることを願う。
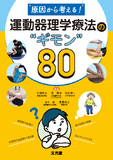
原因から考える!運動器理学療法の“ギモン”80
「脊椎」「肩関節」「股関節」「膝関節」「足部・足関節」において,理学療法士が臨床で遭遇することの多い80の障害を取り上げている.それぞれの障害を引き起こす原因を細分化して考え,適切な理学療法評価に基づいて障害の原因を特定することで,原因に応じた,より効果的なアプローチの実践を1つにつき見開きで解説している.できる限り難解な説明は割愛し,写真をふんだんに掲載して理解しやすくなる構成となっている.

関節機能解剖学に基づく
整形外科運動療法ナビゲーション 下肢 改訂第2版
症例を通して整形外科運動療法の知識と技術を学び,よりよい結果へ導く道しるべ『ナビゲーション』。臨床に役立つ内容を凝縮・満載して高い評価を得た初版の形式を踏襲しつつ,超音波解剖,新しい術式など最新の知見を反映し全面刷新,更なる充実化を遂げたオールカラー改訂第2版。『下肢』には,「股関節」「膝関節」「足関節・足」を収載した。
整形外科疾患に対する運動療法は,観血的治療であればその手術が決して一つではなく,各手術に応じて適切に展開される必要がある。保存療法であっても,急性外傷,変性疾患,スポーツ障害等,時期に応じた病態考察と,病態に見合った運動療法の選択が良好な結果を生む。また同じ診断名であっても,症例ごとにバリエーションが非常に多く存在し,その対応には多くの知識とともに,症例を通して考察し治療した豊富な経験が必要である。「症例から学ぶ」ことは臨床家の最も基本的なスタイルであり,症例を通して何を学ぶかが,臨床家としての成長に必要なのである。
本書では,治療に必要な整形外科的知識,治療,機能解剖学の応用,具体的な運動療法の技術と留意点について,症例解説を通して学ぶことができる。

脳の機能解剖とリハビリテーション
エビデンスに基づく脳と臨床のつなげかた
脳の機能解剖の基礎知識に加え、「観察ポイント」と「臨床へのヒント」を通じて、臨床症状をどう観察して同定し治療するか、豊富なイラストや図表で分かりやすく解説します。また、脳画像の読み方を40時間のYoutube講義動画で学ぶこともできます。大脳・小脳から脳幹・脊髄まで網羅し、明日からの臨床に活かしたくなるノウハウも満載。新人から中堅まで脳神経リハビリテーションに関わる医療従事者必携の一冊です。
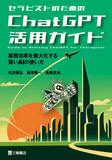
セラピストのためのChatGPT活用ガイド 業務効率を最大化する賢いAIの使い方
初心者でも簡単! ChatGPTで業務効率が劇的にUP!!
リハビリ現場で役立つAI活用術を今すぐマスター!!!
本書は、リハビリテーション現場でのChatGPTの効果的な活用法を分かりやすく解説するガイドです。セラピストの業務をサポートするために、AIツールを使って日々の作業効率を最大化する方法を紹介します。基礎的な知識から実践的な使い方まで、初心者にもわかりやすく解説します。リハビリテーションプランの作成、経過報告書の作成、プレゼン資料作成など、多様な業務での活用例も豊富に掲載しています。AIを使って現場の負担を軽減し、より良いリハビリテーションを提供したい方に必携の一冊です。
