
頭痛治療薬の考え方,使い方 改訂3版 3版
種類の多い頭痛治療薬の選び方・使い方を1冊で!
頭痛治療の必携書 待望の改訂3版!最新ガイドライン・国際頭痛分類に準拠し,新薬の情報も多数追加!ラスミタジンやゲパントによる急性期治療,新規CGRP関連抗体薬での予防療法 など国内外の最新エビデンスとリアルワールドデータで解説!開発治験中の新薬やニューロモデュレーション,認知行動療法など今後の動向も網羅.必要な情報を見やすくわかりやすくまとめた,頭痛診療の幅と深みが増す1冊

脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕
最新のエビデンスを反映させるなどの目的で、例年、全面改訂から2年後毎に追補版を発売してきたが、近年の本領域の進歩は長足であり、今回は全140項目中66項目を改訂した。エビデンスレベルの高い新しいエビデンスを加えたほか、新しいエビデンスはないものの推奨度が現実と乖離しているものなども見直したため、「追補」ではなく「改訂」として発売した。
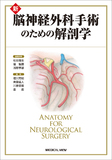
≪手術のための解剖学≫
新 脳神経外科手術のための解剖学
脳神経外科手術書のスタンダードとして親しまれてきた『脳神経外科手術のための解剖学』待望の改訂新版。脳神経外科医が押さえておくべきアプローチに加え,神経内視鏡,バイパス手術,CEAを追加。
開頭から硬膜切開,顕微鏡下手術へと順を追い,病変の立体像を捉えるための病変周囲の解剖から,病変の形状・位置によってどの角度(方向)からのアプローチが最も安全で効率がよいかを豊富なイラストを中心に解説。手術計画の最も基本となる手術イメージをつくりあげる際に役立つ実践的解剖書。
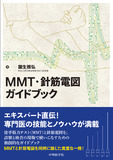
MMT・針筋電図ガイドブック
徒手筋力テスト(MMT)と針筋電図検査について同時に解説されており、神経内科医や脊柱・末梢神経外科医がこれらの検査法を用いて神経疾患や脊椎脊髄疾患の診断を行うために最適なガイドブック。針筋電図とMMTは密接に関係しており、特に神経生理検査の計画を立てる際の神経診察の中核はMMTである。各論では写真をふんだんに用い、各筋ごとに診察-検査の流れに沿って解説。この一冊で筋電図室での神経診察の習熟に大いに役立つ本となった。

脳神経内科 改訂 5版
神経学の魅力を余すところなく伝える,進化し続けるスタンダードテキスト,改訂第5版.
神経系は美しい論理に貫かれた臓器だ.本書は,長きにわたり神経学に真摯に向き合ってきた著者が独自の視点で説き起こし,その魅力を余すところなく伝えている.全篇フルカラーで,重要度によって強弱をつけた紙面は視覚的にも見やすく,理解が進む.前版からの進歩を踏まえ,内容をアップデートした改訂第5版.脳神経内科指導医や一般内科医にとっても有用な内容となるよう工夫された,進化し続けるスタンダードテキストである.

≪画像診断の勘ドコロNEO≫
頭部 画像診断の勘ドコロNEO
「画像診断の勘ドコロNEO」シリーズ第2弾は頭部。
「なぜそうみえるのか」がわかるモダリティの最重要ポイントに加え,スペシャリストたちが読影室で「どこを見て」「どう鑑別し」「どう診断しているのか」,多数の写真と明快な文章で解説する。項目別の「ここが勘ドコロ」など,スペシャリストたちからのアドバイスも満載し,頭部の勉強にも読影室で困ったときにも使える充実の一冊。
発展を続ける画像技術の要点やCOVID-19脳症を含めた最新の知見も網羅。執筆陣渾身の実践知が冴える,白熱の神経放射線読影教室。

脳神経外科レジデントマニュアル
定評あるレジデントマニュアルシリーズ、待望の脳神経外科版。脳神経外科診療の現場においてレジデントレベルで必要とされる全般的事項を、実践的かつコンパクトにまとめた。実際の診療手順や処方例、患者管理、救急対応など具体的な記載にあふれ、本書を開けばすぐに知りたいことを確認できる。脳神経外科研修医はもちろん、脳神経外科疾患に携わる機会のあるすべての医師にお勧めしたい、ポケットサイズの頼りになる1冊。
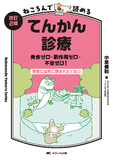
改訂2版 ねころんで読めるてんかん診療
【「ねこてん」、8年ぶりに待望の改訂!】てんかんは有病率1%の「ありふれた病」。その診療を担う多くは非専門医で、診療科も多岐にわたる。患者は小児から高齢者まで幅広く、脳波の判読は難しく、薬剤の処方は悩ましい。そんな医師たちに愛読された本書が、満を持して改訂! 2017年分類での用語改訂に準拠し、大幅に「薬剤」解説を追加。EpiPick日本語版も紹介し、治療や生活なども最新知見にアップデート。ねころびながら、てんかん診療の最前線がわかる!

脳腫瘍診療ガイドライン 成人脳腫瘍編 2024年版
成人脳腫瘍で比較的発症頻度が高く、ある程度のエビデンスが蓄積されている膠芽腫、転移性脳腫瘍、中枢神経系原発悪性リンパ腫(PCNSL)の3分野について、2019年版をもとに部分改訂し、今回新たにGradeII・III神経膠腫を収載した。
推奨決定に関して統一性が得られるよう、Minds2007に準拠して作成された既存の3分野についてもMinds2014による推奨方法に変更した。関連学会、患者団体にもご協力いただき、脳腫瘍診療に臨む医療者に役立つ内容となっている。

自己免疫性脳炎・関連疾患ハンドブック
従来原因不明の難病とされてきたが,研究の発展によって救命・予後改善が期待できるようになってきた自己免疫性脳炎と関連疾患の診断と治療について解説.睡眠病,認知症,精神症状の原因も自己免疫性脳炎だった?治療可能な見過ごされている疾患,自己免疫性脳炎の本邦初のハンドブック.自己免疫性脳炎の歴史から抗体の種類,各種疾患群の病理・検査・治療法.各種抗体の特徴を本邦の専門家が執筆・網羅しています.

改訂2版 血栓回収療法 Technical Tips
【今すぐ脳卒中の臨床現場で使えるワザ満載!】2019年に刊行した好評書の大改訂版。急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の実践にあたっては確実なカテーテルテクニックが求められるが、経験豊富な臨床医しか知り得ないTipsも多く存在する。分野の最新トピックスを網羅しつつ、テクニック/ワザに特化した指南書。WEB動画付き。

神経眼科診療のてびき 第3版
神経眼科は、眼を中心とした所見から原因となる神経疾患の診療を行う分野である。神経眼科疾患はそのすべてが理論的に説明でき、症状を正確に把握すればその病巣までも知ることができる。最新の診断機器や画像診断は必要ない。問診と身体所見のスキルで所見を捉え、神経解剖の知識から病巣局在に迫れ! 第3版では鑑別疾患のさらなるアップデートはもちろんのこと、治療についても詳細に記述。薬物治療ではその投与量や投与方法も具体的に解説した。診断から治療まで。神経眼科のすべてがここにある。

脳梗塞診療読本 第4版
脳梗塞診療の「現在」を知るための好評書,最新版!
脳梗塞診療の基本からアドバンスまで、専門医を目指す神経内科医師,脳神経外科医師.脳梗塞の診療に携わる後期研修医から入局5〜10年目の医師までを対象に解説した脳梗塞診療のバイブル的書籍の全面改訂!最新のガイドラインを反映するのはもちろん,超音波診断や急性期リハビリ,脳保護療法と細胞治療,構造的心疾患カテーテル治療など最新のトピックスを追加.気鋭のエキスパートによる活きた知識を1冊で.

脳神経外科 M&Mカンファランス
脳神経外科手術はトラブルや合併症との戦いである。狭く,デリケートな組織を扱う手術がゆえに,わずかな操作が思わぬ障害を発生させたり予後に悪影響を与えたりする。あるいは画像に写りにくい疾患,再発例,難治例などが立ち塞がる。こうしたケースに対応する能力を身につけるために最も適した教材は「経験」である。
本書では,「南十字星脳神経外科手術研究会」の参加者を中心に,各種の脳神経外科手術における困難に遭遇した医師たちがどう向き合い,悩み,工夫し,成功あるいは苦い思いを得て,そこから汲み取った知見や技術,手技や機材の進歩を武器に「問題点」の洗い出しと「対策」の構築を行って,次の手術にどう活かしていったのかという「経験」を集積している。先人たちの貴重な症例報告集である。

SCUグリーンノート 改訂2版
脳卒中の救急対応・急性期管理・早期リハビリテーションなど実践的内容を1冊で!
公益社団法人日本脳卒中協会理事長 峰松一夫先生ご推薦
ますますニーズの高まる急性期脳卒中診療体制のための必携書!データベース管理,医療経済,退院後の脳卒中医療連携などの追加,最新のガイドラインを反映し,2018年に成立した脳卒中・循環器病対策推進基本法や2025年問題にも配慮した内容にアップデート.脳卒中集中治療室で行う脳血管障害の診断と治療,管理を学ぶうえで欠かすことのできない知識をわかりやすく解説した,脳血管障害の診療に携わる神経内科医師,脳血管内科医師,脳神経外科医師,研修医,看護師や理学療法士など全てのメディカルスタッフに役立つ1冊.

必携 脳卒中ハンドブック 改訂第4版
「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕」に準拠し,臨床における各段階の必要事項を網羅した脳卒中診療の決定版.ガイドラインの列挙と解説に留まらず,脳卒中の基礎,診断,治療,予防,リハビリと幅広い分野が効率的にまとめられており,現場ですぐに役立つ.
今版では,塞栓源不明の脳塞栓症(ESUS)や硬膜動静脈瘻,遺伝性脳卒中,stroke mimicsなどの項目を追加.脳卒中診療に携わるすべての医師にお勧めの1冊.

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン2018
日本神経学会監修による、エビデンスに基づいた脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン。疫学、病態、検査、診断、治療、リハビリテーションなどの診療上問題となるクリニカルクエスチョン(CQ)に対して明確に回答し、治療においては一部のCQでは推奨グレードを明記し対応の指針を示している。

dAVF・AVM(硬膜動静脈瘻・脳動静脈奇形)のすべて
【dAVFとAVMのすべてがこの1冊で学べる!】好評を博した『硬膜動静脈瘻のすべて』を大幅改訂。臨床で遭遇し得るあらゆるタイプのdural AVF(硬膜動静脈瘻)とAVM(脳動静脈奇形)を完全網羅。疫学から病態、最新のデバイス、治療法まで学べ、血管内治療専門医試験の学習にも最適。治療の実際がよく分かるWEB動画●本付き!

モノグラフ
臨床脳波を基礎から学ぶ人のために 第2版
基礎から臨床まで一冊で学べるとの初版の志はそのまま,重要な新知見のほか,基本的知識の記載もさらに充実させた.また,初学者はもちろん臨床脳波に関心のある皆さまが楽しみながら学んでいただけるよう,各章にトリビアとして脳波に関する豆知識や逸話を盛りこんでいる.解説は,各分野の精鋭のエキスパートが執筆する臨床脳波に関する解説書の決定版である.

パーキンソン病診療ガイドライン2018
治療に特化していた前版「パーキンソン病治療ガイドライン2011」から7年、名称を“診療”ガイドラインに変更した改訂版が、満を持して登場! 最新治療はもちろん、新たに国際的な診断基準や画像検査、病因なども網羅した。厳選したクリニカルクエスチョン(CQ)と50のQ&Aで、臨床の課題を徹底解説する。
