
ジェネラリストのための内科外来マニュアル 第3版
内科外来のトップマニュアルに待望の第3版が登場!
内科外来のトップマニュアルとして不動の地位を得た『ジェネラリストのための内科外来マニュアル』(ジェネマニュ)に待望の第3版が登場した。6年ぶりの本改訂では、診療情報をアップデートすると同時に、手薄だった主訴・症候についても大幅に記載を増やし、さらに網羅性を高めた。目の前にいる患者への診断アプローチ、鑑別疾患から具体的な処方例までを一覧できる、さらにパワーアップしたスーパーマニュアルが誕生した。

内科レジデントの鉄則 第4版
多くのレジデントに読まれてきました。研修医になったらまずコレ!
本書は、臨床現場で一番大事なこと──備えた知識を最大限に活かし、緊急性・重要性を判断した上で、適切な対応ができるか──に主眼を置いて構成されています。第4版では、前版同様に教え上手の著者らが研修医にアンケート調査を行い、これまでの改善点を徹底的に洗い直し、分かりやすい解説を心掛けるとともに、少しアドバンストな内容や参考文献を充実するなど、さらに読者目線で役立つ本をめざしました。

研修医のための内科診療ことはじめ 救急・病棟リファレンス
研修医の先生に向け内科診療での重要テーマを豊富な図表でわかりやすく!救急や病棟で出合う症候や疾患へのアプローチを病態・解剖から診断・治療まで解説.よく使う薬剤や検査についてもフォローした手厚い1冊.

治療薬マニュアル2025 アプリ
ダウンロード型アプリケーションタイプ
『治療薬マニュアル2025』に準拠した医療従事者のための“くすり”のデータベース!
添付文書情報を整理した「薬剤便覧」に,専門医による「臨床解説」を加えた,圧倒的な情報量と網羅性が好評の治療薬年鑑です.
●2024年11月22日付薬価基準収載分までの医療用医薬品を収載(2024年7月以降に収載された後発医薬品および一部の配合剤を除く)
●薬剤便覧は2024年9月末日入手分までの添付文書,医薬品安全対策情報,公表された薬価などに基づいて改訂
●1997年に通知された記載要領に基づく添付文書を旧様式,2017年に通知された記載要領に基づく添付文書を新様式と記載
●「薬物療法の基本的注意」では,肝障害時・腎障害時・妊婦・授乳婦・高齢者・小児などの薬物療法における注意事項を掲載
●「図解薬理作用」では,病態生理と薬理作用をまとめて図示し,わかりやすく解説
●各章の冒頭にある「薬効別分類表」で,薬効群ごとの薬の特徴が一目でわかる
●専門医による総論解説(「治療の基本戦略」「最新の動向」など)を各章に掲載し,薬物治療のさらなる理解が可能
●「臨床解説(適応外使用や使用目的など)」「妊婦・授乳婦への投薬リスク」「公知申請」などの添付文書以外の有用な情報を収載
●「錠剤・カプセルの粉砕・開封可否の基準」や「製剤の味・風味一覧」など,実用的な付録を19本収録
●使いやすく便利な「識別コード検索」機能を搭載

ジェネラリストのための内科診断リファレンス 第2版
エビデンスを根拠に、病歴、身体所見から検査まで、診断学の流れを網羅したテキスト。
10年の歳月をかけ、何と3万本以上もの論文に目を通し徹底的な文献吟味を経て、遂に完成したまさに待望の改訂版。今版では、外部リンク(QRコード/ハイパーリンク)を採用し論文などに掲載されている教育的な画像や動画にアクセスできるようになった。また指定難病の診断基準・調査票へのリンクも掲載。若手医師、総合診療医のみならず、全ての内科医にとって臨床の現場で必ずや役立つ一冊。医学生にもおすすめ。

ステロイドの虎
初学者にとってステロイド処方は難しい。これほど臨床で使われているにもかかわらず、薬物動態について不明瞭なことが多く、実際の処方についてのエビデンスも充実しているわけではない。患者さんのなかには副作用について強い不信感を持っている人も少なくなく、ICはとても憂鬱。もちろん実際に副作用は生じるので対策を念頭にいれないといけない。
しかし目の前の患者さんは不調を訴えている、あるいはそれどころかここでパルスをしなければ最悪の転帰になるにもしれないときにステロイドを躊躇する理由はないのではないでしょうか。
本書では基本となるステロイドの使い方を、明瞭にわかりやすく、今すぐどうしたらよいのかを示します。リウマチ専門医や血液内科専門医を指向する方は成書でさらに勉強をしていただく必要がありますが、いま患者にステロイドを処方できるのはあなた一人です。一匹の虎になり、診療ジャングルを駆け抜けていくのは今なのです。
序文
「ステロイドを使えるようになりたい」
このような気持ちは、初学者でなくても日頃ステロイドを処方し慣れていない臨床医なら、誰しも持っていると思います。ところが、「ステロイドの使い方」というのはいくら教わっても本を読んでもいまいち掴めた気にならないという人が多いようです。
その理由を考えてみました。それは、「総論が頼りない」からだと思います。医師は割と、「キチッとした総論」を体系基盤にしてそれを拠り所にしたい人が多いと思います。ステロイドに関しても、総論や原理・原則をきっちり理解すればその先に、応用があると信じているのでしょう。しかし実際には、いくら勉強しても盤石な理論とは程遠い総論記述がそこにあることがわかり、結局実地臨床では、臨床家の“さじ加減”に委ねられることに不安を覚えることになります。
実際、ステロイドの作用・効果には謎が多く、その使い方はただの慣習が普及してしまっている部分も多いです。にもかかわらず、あたかもそれなりの根拠があるかのように語れることも多いです。理論で攻めても結局は、詰めて行けばいくほど、つまりきちんと誠実に書けば書くほどエビデンスが示せないことがわかり、最後の核心的なところになってごまかした形になったりします。
すると残るは実践派の実践内容を知りたいところです。しかし、ちゃんとしている先生ほど、「根拠を示せないから」「なんとなくでやっているからとても公表などできない」などと言い、明るみになってきません。施設ごとの格差も大きいと聞きます。
ただ実地の臨床諸家たちは、言うほど盤石な理論を望んではいません。ステロイドの処方が頭をかすめたときに、すぐにとりあえずの解が欲しいものです。それは忙しいからです。臨床家はいつでも忙しいです。それなりのロジックは欲しいけれども、困っているまさに今、それなりの解が欲しいのです。あの人 or この施設ではこうやって使ってるのか、じゃあ私たちもこうしてみようみたいなサンプルを求めているのだと思います。ちゃんと伝えたいからこそ無難なことしか書けない著者(という立場の者。多くが専門家)と実地の臨床諸家たちとの間に、こうしてすれ違いが生まれるのです。
そこで本書です。というか、そこで國松です。私はこれまでそこかしこで、単著で本を書くというのは公衆の面前で全裸になるくらいの行為であり、単著を仕上げるには「いったん正気を失う」必要があると説いてきました。臨床ステロイド界隈のそうした“モヤっと感”を本などで著せるのはまあ自分かなという 全裸になれる勇気 謎の使命感が湧いてきたのです。これが本書執筆の初期衝動でした。
本書『ステロイドの虎』(ステトラ)では、それなりの理論も記述しました。これは私見も多く含みますが、ちゃんと分けて記述したつもりです。「真理!」のようなものではなく、しなやかなロジックを心がけました。
また、ある程度は「あんちょこ本」のように使えるようにも記述を工夫しました。具体的な処方箋を示し、その解説をしました。理論の部分が理屈っぽくて鬱陶しく感じる人は「あんちょこマーカー」なるものを國松自ら施しました。時間のない人、手を抜きたい人、とにかく大事なところだけ読みたい人、などは、見出しや囲みの他は、この「あんちょこマーカー」のところだけ読んでください。ロジックや情報も書きましたが、「安直」な利用の仕方で構わないと著者は思っています。ぜひぜひ、安直にこの本を使ってみて欲しいです。
この本「売り」をもうひとつ。ステロイドの処方というくらいだから重症例、つまり入院患者を想定していると思うかもしれませんが、外来患者さんにも十分利用できるという点です。かなり色々な診療科でステロイドは処方されます。大病院でも、クリニックでも。特に実地医家という“種族”は、(自分もそうだからわかりますが)何でも自分でやれたらいいなと思うものです。外来でステロイドを自分でうまく処方できたら、世界が広がります。
この本は、「エビデンスなんていいから、処方や処方の仕方を教えて欲しい」という読者に寄り添いたいと思って書き始めましたが、かなりの文献読んでいるうち、ちゃんとした解説をすることも大事だなと思い始め、その結果「あんちょこ本」にはなりませんでした。ただ、この本を読んでいただければ、ステロイドってこうやって使うんだという一例を垣間見ることはできるはずです。かつてまったくステロイドの使い方を教わらなかった先生、あるいは今は使っていないが自分でも使ってみたい臨床諸家のすべての先生にお役に立てるものと思っています。
医療法人社団永生会南多摩病院
國松淳和

國松の内科学
國松淳和は内科医である。臨床の傍らで数々の医学書を執筆し、その独創的な切り口は多くの人を惹きつけてきた。はたして、彼の頭のなかには広大な内科学の世界がどのように収まり、出力し続けているのだろうか。
本書はたったひとりの総合内科医の脳内を、たったひとつの本に著したものである。國松淳和、医書書き10年間の集大成。全編1700ページ超。200以上の内科疾患を網羅。一切の駄文なし。新しい内科学テキストの地平がいま開く。
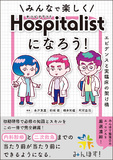
みんなで楽しくホスピタリストになろう!
エビデンスと実臨床の架け橋
●初期研修で必修の知識とスキルをこの1冊で完全網羅!
●みんほす勉強会のエッセンスを厳選濃縮!
本書は、初期研修終了時までに必要な内科診療と二次までの救急診療の「当たり前のことが当たり前にできる」、「常に患者さんを中心に考え、行動できる」が身につく1冊で、生粋のホスピタリストや、そのマインドをもった医師たちが、他のどの書籍よりも実践的な知識を提供することを最も大切にして執筆しています。エビデンスに基づきながら、実際の現場で「どのように考え、どのように行動すべきか」を詳しく解説し、初学者でも「明日から実践できる」内容となっています。
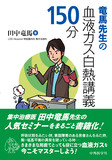
竜馬先生の血液ガス白熱講義150分
なんとなく使っているだけだともったいない血液ガス.その読み方を短時間でマスターできる田中竜馬先生の人気セミナーの内容をまるっと書籍化しました!

小児感染症のトリセツ 2025 抗菌薬編
あの『小児感染症のトリセツ』が帰ってきた! 前版の構成を一新し『抗菌薬編』と『疾患編』の2部作となってさらにバージョンアップ。
『抗菌薬編』では、小児感染症における問診・診察の方法、微生物検査の使い方や各抗微生物薬別の解説まで、抗菌薬の切り口で小児感染症を理解できる。
「薬剤」から小児感染症を学びたい方はまずはこちら。姉妹本の『疾患編』もあわせて読めばさらに盤石! 圧倒的な情報量と現場で何をすべきかを両立した小児感染症マニュアルの決定版。

ジェネラリストの道具箱~外来に役立つ総合診療スキルブック~
これでだれでもジェネラリスト(#だれジェネ)
総合診療・家庭医療のスキルとフレームワークを一問一答形式で網羅しました.エキスパートジェネラリストの外来には,診断・治療はもちろんのこと,「患者さんとの関係性の築き方」「多職種との連携」「診断がつかないときの対応」などの技と知恵が凝縮されています.これらを実践するためのエビデンスや汎用的フレームワークを知ることで,外来での「これってどうしたらいいの?」に対する引き出しが増えることを実感できるでしょう.さらに学びたい読者のために,「もっと詳しく知りたい」で参考書籍や文献を示し,まさに総合診療の入り口かつハブとなる一冊です.
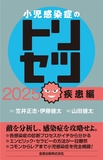
小児感染症のトリセツ 2025 疾患編
あの『小児感染症のトリセツ』が帰ってきた! 前版の構成を一新し『抗菌薬編』と『疾患編』の2部作となってさらにバージョンアップ。
『疾患編』では、頻出のコモンディジーズから知っておきたい重症感染症の対応まで、小児感染症の診断名別に診療のプロセスが分かる。「病名」から小児感染症を学びたい方はまずはこちら。
姉妹本の『抗菌薬編』もあわせて読めばさらに盤石! 圧倒的な情報量と現場で何をすべきかを両立した小児感染症マニュアルの決定版。

検査値を読むトレーニング
ルーチン検査でここまでわかる
検査値の推移と組み合わせから、「病態を読み解く力」を身につける本。「RCPC」の手法では、病歴や身体所見の情報なしで、検査所見のみから病態を推論する。本書はこれに時間軸と複数検査値の組み合わせを加え、患者の病態を13の基本項目に分け、全39症例の検査値の推移から病態の変化を読み解いていく。「患者の体に何が起こっているのか?」を推論する力を磨きたいすべての医師、臨床検査技師に。

消化器がん薬物療法 副作用マネジメント プロのコツ 第3版
お待たせしました、第3版!
標準治療をできるだけ長く・患者負担なく継続するための『プロのコツ』を解説した好評シリーズの最新版。
5年ぶりの全面改訂で, 最新のレジメン・ガイドラインに対応。より使いやすく, よりわかりやすく!
改訂ポイント
1.最新の標準治療レジメンに項目と内容を一新。
どの副作用にいつごろ注意すべきか、どの薬剤から減量すべきか、チャートもさらに充実。
2.副作用対策編も最新のエビデンスに更新。新しく登場した支持療法薬についても解説。
3.免疫チェックポイント阻害薬の副作用(irAE)の項目もさらに充実。
4.新たに「緩和医療薬の副作用対策」の章を追加。特徴的な副作用とその対策がわかる。
ますますパワーアップしたこの1冊で、副作用マネジメントにはもう悩まない!

誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた 感染症診療12の戦略 第2版
『誰風邪(だれかぜ)』の愛称で親しまれる大ベストセラー書が、満を持して7年ぶりの大改訂。初版で圧倒的な支持を得た、プライマリ・ケア現場における「風邪と重篤な疾患との見極め方」に磨きをかけたのみならず、高齢者の風邪診療や薬剤耐性菌など診療現場を悩ませる重要課題にも明快に処方箋を示した。プライマリ・ケアの足元で感染症診療の定説が揺らいでいる今、日々の「風邪」診療における12の戦略が明日の医療を変える!

ポケット呼吸器診療2024
【2024年版のポイント】
・特別付録→電子書籍版(PDF版)の無料ダウンロード権が付いています。
※1冊につき1ライセンスです。ライセンス使用済みの中古書では利用できません。
・「2024年版になってどこが変わったの?」がわかります→改訂部分を色付け
・各種ガイドラインの改訂に対応など→最新情報にアップデート
【本書のポイント】・臨床で使える小さなマニュアル(新書版)
・呼吸器疾患の診療手順/処方例/診療指針
・ガイドラインを掲載
・患者さんへの病状説明のポイント、よくある質問の解答例も
◆著者より
このマニュアルは「できるだけコンパクトかつ有用な安い書籍」を目標にしていますが、限りなく最新の文献に基づいた疾患情報を提供できるよう心がけています。実臨床で使用することを最優先に、不要な贅肉を極限までこそぎ落としているつもりです。

サルコイドーシス診療の手引き2023
主要臓器病変として呼吸器、眼、皮膚、心臓、神経の項を設けている。多臓器に病変が及ぶことがあるので臓器病変、特殊病態などの項を設け、診断と治療を解説している。

卒後20年目総合内科医の診断術 ver.3
内容もボリュームも大幅にバージョンアップした総合診療新時代の進化するバイブル.
「どうしたら正しい診断にたどりつくことができるのか」.誰しもが求める総合内科診療の実践力を,明快かつ詳細にまとめて好評を得た「卒後15年目総合内科医の診断術」が,「卒後20年目〜」と改訂改題し大幅リニューアルしました.この5年の間に新たに培われた著者の知識と技術をあますところなく盛り込み,内容もページも大幅に増量.さらに読み応えのある1冊になりました.初診時に診るべきことはもちろん,ピットフォールの対処法も充実.改訂ごとに進化し続ける,総合診療時代のバイブルです.

胃炎の京都分類 改訂第3版
●胃粘膜の変化を語るうえで最も重要で,最も難解なのは正常の胃粘膜をどう定義するかである.改訂第3版では正常の内視鏡所見とともに,正常の胃粘膜の組織像についても取り上げた.正常胃粘膜の基本構造を理解することにより,内視鏡所見として表現される胃粘膜変化を正しく理解することができる.
●改訂第3版では白色光観察ともに画像強調(IEE)を提示し,その内視鏡所見を裏付ける病理組織像も加えた.
●本書から良く引用されている,表「胃炎の京都分類」も改訂.
★改訂第3版で追加・加筆修正された項目につきましてはホームページをご覧ください
ホームページ https://www.nmckk.jp/nmckk/bookDetail.php?bookkey=b0664

明日からの診療にきっと役立つ!医学のトリビア
エビデンスに基づく患者さんからのシンプルな質問への答え方
そのトリビアは、単なる迷信ではなく、医学的根拠があるのです!
雑誌「総合診療」の好評連載を単行本化。日常診療におけるシンプルかつ素朴な疑問には実は医学的な価値の高いものが少なくありません。いわば医学トリビアについて、科学的根拠をもとに解説することで、理解や知識を深め、好奇心を満たして頂きたい。またそのトリビアを披露することで、患者さんとのコミュニケーションや生活指導にもぜひ役立てて頂きたい。看護師、栄養士、薬剤師などメディカルスタッフの方々にもおすすめ。
