
≪「看護管理」実践Guideビギナーズ≫
事例でわかる看護リフレクションの支援
経験からの気づきや学びを看護実践に活かす
「私の行った看護は、患者にとってどんな意味があったのか…」
自分ひとりでは難しい「看護の言語化」を支援し、次の実践につなげる!
看護リフレクションで重要なのは、振り返りから得た気づきや学びを次の実践につなぐことです。そして、自身の行った「看護」が患者にもたらした効果や意味は、支援者の力を借りることでより明確になります。
本書では「経験から学ぶ」というリフレクションの基本的な考え方から、支援のあり方と理論、研修・OJT・面談等での具体的な対話事例、支援者の育成・成長までをわかりやすく紹介します。
≪本書は第1版第1刷の電子版です≫

臨床判断ティーチングメソッド
高度化、また地域へ移行が進む医療現場では、看護師の臨床判断能力の向上が求められています。本書は、タナーが開発した臨床判断モデルをもとに、学習者が実践的な思考を獲得する方略をわかりやすくご紹介します。学習者中心の考え方や、生涯学習を続けるためのかかわりなど、教育学の最新の知見とともに、基礎教育から新人、エキスパートへと、看護師の熟達を橋渡しする1冊です。

チームステップス[日本版] 医療安全
チームで取り組むヒューマンエラー対策
チームステップス(Team STEPPS;Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety=医療の成果と患者の安全を高めるためにチームで取り組む戦略と方法)は,アメリカ発信の,良好なチームワークを形成することによって医療の安全推進と質の向上に成果を上げるためのチーム戦略(行動ツール)で,エビデンスに基づく方法である。Team STEPPSで重要な(1)チーム構成,(2)リーダーシップ,(3)状況観察,(4)相互支援,(5)コミュニケーションの5つを詳解している。このプログラムをいち早く学び,わが国の医療現場に則して改良を加え効果を上げてきた東京慈恵会医科大学附属病院の,医療安全対策ならびに各臨床分野での取り組みの実際を余すところなく紹介。

看護教育 電子別冊「発達障害など,対応が難しいと感じる学習者への教育・支援」
教育者が対応に難しさを感じる学習者への教育・支援のヒントがここに『看護教育』2021年1月号から12月号までの全12回にわたり連載した内容を、電子別冊として1つにまとめました。「学習者支援のゴールは、多様性のある学習者が生きがいをもって社会で役割を果たせることへの支援」と考える著者が、Q&A形式で教育・支援のあり方のヒントや、支援のアイディアをご紹介します。

看護学の概念と理論
看護学を構成する概念を学ぶ上で欠かせない諸人物・諸理論が簡潔に無駄なく整理されたテキストとして、教育現場をはじめ多くの看護職に支持されてきた『看護学基礎テキスト第1巻』を単行本としてリニューアル。
理論家の再評価や倫理綱領など、目まぐるしく変化する社会の姿を反映した看護の姿を歴史的な視点からとらえ直しています。

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
看護師・医師を育てる経験学習支援
認知的徒弟制による6ステップアプローチ
認知的徒弟制の6ステップで経験から学ぶ力を引き出す!
「自ら考え、学び、動く人材」を育てるために、後輩や部下の経験からの学びをどのように支援すべきか悩むあなたへ──経験学習サイクルを適切に回す手助けとなる認知的徒弟制の6ステップ(①モデル提示、②観察と助言、③足場づくり、④言語化サポート、⑤内省サポート、⑥挑戦サポート)を解説。新人看護師・新任副看護師長・医師(心臓血管外科医)については、6ステップの優れた指導例とそのポイントを示す。

臨地実習ガイダンス 第2版
看護学生の未来を支える指導のために
看護学生の臨地実習指導と支援のための教員・指導者必携ガイドブック、待望の改訂版
患者との出会いとふれあいが初学者を現場ではたらく看護師に変貌させていく。学習者が「その場に立ちどまって」考えられるような活き活きとした学びを導くために、睡眠不足になりがちの学生たちを指導者が萎縮させずに支えられるように、教員は何を考え学びをしかけ、指導者は何を望み学生を受け入れるのが効果的か。熟練の編者のもと中堅若手の3世代の教える人が結集した好評書、第5次指定規則改正に対応した待望の第2版に。
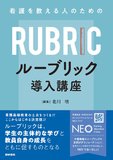
看護を教える人のための
ルーブリック導入講座
ルーブリックは、学生の主体的な学びと教員自身の成長をともに促すものとなる
看護基礎教育の土台をつくる! ここからはじめる決定版! 現代の高等教育機関において標準的に導入され、看護師養成機関においても看護実践能力を評価するツールとして普及が進んだルーブリックづくりの入門書、待望の刊行。構成として第I講から第VI講に分かれ、初学者向けに段階を踏んでルーブリック全般の説明からその作成と導入に至る具体的な手順を、各領域別・汎用型それぞれで詳細に紹介している。

看護学テキストNiCE
成人看護学 急性期看護II クリティカルケア 改訂第4版
ICUや救急外来における看護を解説したテキストの改訂第4版.主要な急性症状・緊急度の高い疾患について、11の事例を通して,患者の受け入れ時の看護、ICU移送までの看護、ICUにおける看護を,実際の診療の流れに沿って解説.今版では、ICUや救急外来における生命の危機状態にある患者の看護をクリティカルケアとしてとらえ直して再編.アセスメントや臨床判断の解説がさらに充実した.

発達障害のある看護職・看護学生支援の基本と実践
発達障害の特性がみられる看護学生や看護スタッフの学修や臨床実務における困難さへの支援を解説する実践的テキスト。
基礎知識に加え,学校や病院などの現場において,場面ごとに課題につながる障害の特性と関連要因を丁寧にひもとき,どう支援すべきが具体的に理解できる。また発達障害に併存しやすい二次障害の予防やその対応などについても解説し,合理的配慮に基づく支援と評価の手がかりとなる手順やマニュアル類も充実している。

看護学テキストNiCE
母性看護学II マタニティサイクル[Web動画付] 改訂第3版
母と子そして家族へのよりよい看護実践
妊産褥婦・新生児のアセスメントと援助に対する思考過程が理解でき,豊富な写真やイラストがビジュアルでわかりやすいと好評なテキストの改訂版.今改訂では,序章を追加し,ライフサイクルとの関係,さらには世代間の継承も含めた母性看護の長期的な視点を解説.心理・社会的に特別な配慮・支援を必要とする妊産褥婦への支援の章も新設した.退院支援や無痛分娩の解説も充実.新たに動画を多数収載し,技術演習や実習にいっそう役立つテキストとなった.

看護管理者のための概念化スキル ステップアップ
【課題解決に活きる概念化スキルが身につく!】抽象的で実践に活かすのが難しい概念化スキルを、密接な関係のあるフレームワーク・思考法を併用しながら解説。より効果的に活用する方法を、組織管理場面や教育・指導場面など具体的な事例を通してわかりやすく紹介する。

目でみるからだのメカニズム 第2版
からだの構造と機能を豊富なイラストで絵解き、病態生理も平易に解説
「人体の構造と機能」として医療系学生が学ばねばならない内容を網羅。カラー化でさらに分かりやすくなった豊富なイラストと文章により、楽しみながら複雑な人体のしくみを学ぶことができる。器官系統別に正常な解剖・生理学を解説しながら、正常な機能が障害されておこる代表的疾患についても言及。各臓器におこる病気の成り立ちも理解できるように工夫されている。章末のコラムは、最近のトピックスを楽しく学ぶことができる。

LGBTQ+ 医療現場での実践Q&A
LGBTQ+当事者と、さまざまな専門職で考えたQ&A集
LGBTQ+当事者が医療現場で直面するさまざまな場面を紹介し、誰もが安心して診療を受けられる環境づくりと、医療者が多様な性のありかたを理解するための知識を提供します。
すべての医療職をはじめ、政策立案者や行政に携わる人々、そして医療機関を受診する当事者にとって大切な情報が満載!
≪本書は第1版第1刷の電子版です≫
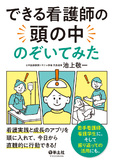
できる看護師の頭の中のぞいてみた
看護実践と成長のアプリを頭に入れて、今日から直観的に行動できる!
「できる看護師はどう考えて,どう行動しているのか?」をとことん見える化しました!本書のフレームどおりに実践するだけで,できる看護師の頭(臨床判断能力や対応力)と心が身につきます.若手看護師,看護学生におすすめ! 〔付録の特典PDF(教育理論の追加解説)は看護教育にもご活用ください〕

看護教員ハンドブック 第2版
授業や実習指導、研究において看護教員に最低限必要となる情報・知識・技法を、前版同様コンパクトで簡潔な記述スタイルでまとめたハンドブック。今版では、2022年度施行の看護教育新カリキュラムに対応して改訂した。第1章では最新の法令などを反映し、第2~4章では、教員の各業務で使える、より実践的な内容を加筆した。第5章では、指導の際に留意しなければならないパワーハラスメントについても触れている。

NEW実践!看護診断を導く情報収集・アセスメント第7版
1章:データベース,看護理論,そして看護診断へ
2章:看護診断を導く「データベース」のアセスメントのためのヒント
3章:間違えやすい診断名の鑑別診断
付録:NANDA‐Iの領域に沿った看護記録用紙の実際例

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
コーチングマインドを極めると,マネジメントがもっと楽しくなる
コーチングマインドを学び、看護管理者自身も、スタッフも患者もみんな元気に!
より良い組織をつくるため、患者により良い看護を提供できるスタッフを育てるために…。日々、看護管理者は自分自身を奮い立たせ、頑張っているのではないだろうか。本書の主人公、話すとなぜか元気をもらえる山原看護部長。その理由とは? 本書では、山原看護部長によるコーチング研修をストーリー仕立てで展開。看護管理者がコーチングマインドを身につけると、管理者自身も、スタッフも明るく元気になれる。

看護教育学 第8版
看護教育のすべてを収めた1冊
1988年の初版発行以来、看護教育学の最も標準的なテキストとして改訂を重ねてきた本書。第8版では、これまでの内容を整理し、第1部と第2部に再構成した。前版でも言及していた看護基礎教育や看護卒後教育等を新たに章として独立させ、詳述している。加えて、看護教育に関連する最新の法規と制度改正を反映して解説。日本の看護教育の変遷のすべてが分かる1冊となっている。
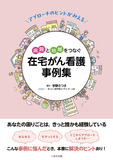
アプローチのヒントがみえる 病院と地域をつなぐ 在宅がん看護事例集
27の事例で語り尽くす――がん看護×訪問看護・がん看護×地域連携・がん看護×病診連携
がん患者の多くが在宅で療養する現在、がんの治療・療養の場は外来・在宅への移行が進んでいます。がんならではの困りごとや課題を抱えた患者もまた、在宅・地域で多く暮らすようになっています。
本書では、療養の場を在宅へと移したがん患者へのかかわりを、架空の事例を通して振り返り、困った場面ごとの解決のヒント、かかわりの工夫をまとめました。
在宅でのがん患者とのかかわりに特有の5テーマ
◆症状マネジメント
◆多様化・複雑化するケア対象
◆在宅医療に関する制度・仕組み
◆多職種連携、チーム連携
◆在宅での緩和と看取り
こうした事例に出会い悩んだら、ぜひ本書にヒントを探してみてください。あなたの困りごとは、きっと誰かも経験しています。
