
米国緩和ケア専門医が教える
あなたのACPはなぜうまくいかないのか?
コミュニケーションとは生来のセンスでするものではない。手術手技と同様に,なぜそうするのか明確な理由があり,誰もが身につけることのできる「スキル」である――。
日本での外科研修を経て渡米し,紆余曲折を経て米国日本人緩和ケア医となった著者が,あなたのACPはなぜうまくいかないのか,「3ステージプロトコル」に沿って解き明かす。自分が今,会話のどの時点にいて,何をしなくてはならないかを客観的に理解し,緊張したり混乱しがちなACPの場面で冷静に対応することができるアプローチである。相手の理解力を確かめる,病状は2分以内にまとめる,医療者は会話の50%以上話してはいけない,質問にはワンワードワンセンテンスで答える……,「何をすべきで,何をすべきでないのか」をスキルとして明快に解説。
米国で直接指導する研修医だけではなく,もっとたくさんの人を教育できればとSNSでも日々発信する著者のプロフェッショナリズムを体系的にまとめた待望の書籍である。
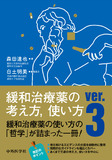
緩和治療薬の考え方,使い方 ver.3
痛み,吐き気,食欲不振,呼吸困難,消化管閉塞,便秘,倦怠感,眠気,不眠,不安,抑うつ,せん妄……患者さんの苦痛の訴えに適切に対処し,効果的な緩和ケアを行うための考え方と薬の使い方について,エビデンスと著者の長年の臨床経験に基づき明快にまとめました.第3版では定番の薬のオーソドックスな使い方を中心としつつ,増え続けるエビデンスの大局を俯瞰的に整理し,最新の国際ガイドラインも幅広く網羅しました.

専門家をめざす人のための緩和医療学 改訂第3版
日本緩和医療学会編集による,専門家をめざす人のためのテキスト改訂第3版.「日本緩和医療学会緩和医療専門医 研修カリキュラム」に準拠した内容で,専門医をめざす医師のみならず,緩和医療を専門的に学ぶ医療従事者が臨床実践する際の指針となる一冊.改訂第2版刊行から5年間の新薬の登場やガイドライン改訂の進歩・変化を受けて,最新の情報を盛り込んだ.また「骨転移」「AYA世代のがん」「がんサバイバー」「自殺予防」の項目を新設し,昨今の本領域における動向を踏まえて内容を見直し,より実践に即した内容となっている.

免疫関連有害事象irAEマネジメント mini
前著『免疫関連有害事象irAEマネジメント』が膠原病科医の視点から網羅性を重視したもののため,検索性,携帯性をそぎ落としてしまったので,逆にマニュアル化,チェックリスト的な側面を前面に押し出し,ベッドサイドや手軽に読めるようハンドブック形態とした.がん病棟の医師・看護師・薬剤師など多職種に参考になるB6サイズのコンパクトな一冊となりました.

緩和ケア ポケットマニュアル 第3版
医師・看護師・薬剤師などが必要な事をその場でサッと確認できる緩和ケアの定番書!最新版ではあらたに「緩和戦略」が追加され,現場で必要とされる「考え抜く力」を身につけることができます.病棟・外来・在宅など,さまざまなシーンに対応した豊富な処方例・指示例を中心に,本当に必要な情報を持ちやすく見やすいサイズにまとめました.ポケットサイズながら,通読すれば緩和ケアに必須の知識を一気に獲得することも可能です.
・スマートフォンと同じサイズ感!
・手帳のようなソフトカバーでポケットに入れても使いやすい!

緩和ケアレジデントマニュアル 第2版
最期まで患者の望む時間を提供するために。緩和医療スタッフ必携の書、改訂!
次々に起こる症状への対応、予後予測、ACP、家族のケア、リハビリテーション……、最期まで患者の望む時間を提供するために、何をするのか。エビデンスをアップデートしつつ、経験も重視して、より実践的に改訂。病棟でも外来でも在宅でも、がんでも非がん疾患でも、すべての患者の苦痛緩和をめざす医療スタッフに必携の書!
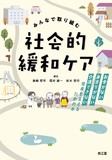
みんなで取り組む 社会的緩和ケア
お金がない・身寄りがない・介護できない患者を支えるための本
お金や仕事,介護,身寄りに関する社会的問題は,患者・家族にとって時に身体や病状のことよりも悩みの種となる.本書はそのような社会的苦痛に対する緩和ケア(略して「社会的緩和ケア」)を,医療者が現場で実践するための本である.医療者以外の様々な専門職も執筆陣に迎え,1章では実践のための基礎知識,2章では各専門職によるサポート内容,3章ではケースファイルを掲載.社会的緩和ケアの実際を知り,適切な介入と幅広い支援・ケアに繋げられるようになる一

Onco-cardiologyガイドライン
がんと循環器疾患が重なる領域を扱う新しい臨床研究分野であるOnco-cardiologyに関する本邦初のガイドライン.CQ(clinical question)について,最新のエビデンスに基づく推奨を提示しつつ,エビデンスが不足しているが,今後の重要な課題と考える内容については,現状の考え方をFRQ(future research question)として記載し,さらに基本的な知識で臨床上広く行われている内容についてもBQ(background question)と位置づけ概説した.がんと循環器疾患を合併する患者の診療の指針となる一冊.

頭頸部がん薬物療法ハンドブック 改訂3版
頭頸部がん薬物療法に特化したマニュアルとして好評を博した書の改訂第3版.専門病院のスタッフのみならず,一般病院のスタッフにも役立つよう,頭頸部がんの薬物療法に特徴的な臨床上のコツや支持療法を平易にまとめている.今版では近年の新薬の導入を踏まえ,転移・再発がんに対する治療法を重点的に加えた.執筆陣には経験豊富な各エキスパートを集め,実際の現場での治療立案・実践および副作用管理に役立つ実践書である.

ようこそ緩和ケアの森
オピオイドの使い方
緩和ケアという森にはさまざまな木(テーマ)が生えている.そんな森に足を踏み入れようとしているあなたに,初心者時代の記憶新しい著者らが記す,<緩和ケアの“超入門書”シリーズ>!!
本巻ではオピオイドの基本から使い方を?み砕いて解説.使用の手順・考え方,副作用マネジメント,困ったときの対応,他職種との連携を軸に記し,一見とっつきにくいオピオイドがより身近に感じられる.
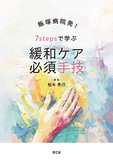
飯塚病院発!7stepsで学ぶ 緩和ケア必須手技
緩和ケアや在宅医療の現場で「手を動かす」機会は多く,苦痛緩和や症状コントロールのために避けては通れない手技がある.本書ではそのような手技の実際とコツを,飯塚病院で研鑽を積んだ経験豊富な執筆陣が伝授.「7steps」(適応と禁忌, 処置説明,準備,手技,成否判断,合併症,記録)の手順に沿った解説のほか,緩和ケアならではの配慮や工夫,経験談までを紹介し,手技が苦手な読者でも読めば自信をもって実践できる一冊である.

ここが知りたかった緩和ケア 改訂第3版
緩和ケアの定番書が改訂!意外に知られていない薬剤の使い方やケアのコツを,各項目冒頭の「概念図」でつかみ,その場で教えてもらっているようなわかりやすい解説が大好評.今版では新しい便秘治療薬,睡眠薬,鎮痛補助薬や悪液質の新薬のほか,前版からの臨床上の進歩を盛り込んだ.臨床家が日々直面する問題・疑問に答えた内容で,“今”の緩和ケアの現場で“本当に使える”実際書.

制吐薬適正使用ガイドライン 2023年10月改訂 第3版
がん薬物療法により発現する悪心・嘔吐を適切に評価し抑制することは、がん患者のQOL改善と治療完遂のための重要な課題である。8年ぶりの全面改訂となる今版は、Minds2017に準拠し作成した。
各章の総論・Questionを充実させ、非薬物療法による制吐療法、患者サポート、医療経済などについても新たにQuestionや解説を追加し、制吐療法における、患者と医療従事者の意思決定支援に必要な情報提供を目指した。

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2020年版
緩和ケアの重要課題である「がん疼痛」に対する治療法のうち、最も使用頻度が高い薬物療法についてのガイドライン。6年ぶりの改訂となった本書では、この間に上市された新たな薬剤の情報や、海外ガイドラインの最新情報などを十分に取り込んだ。推奨では、前版の構成と臨床疑問を全面的に改訂し、より現場の状況に即した指針を提示している。緩和ケアに携わる医療者必携の一冊。
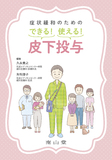
症状緩和のための
できる!使える! 皮下投与
終末期患者の補液・投薬手段として重用されている薬剤の皮下投与方法は比較的低侵襲であるが,ほとんどの薬剤において添付文書範囲外の投与方法となり,有害事象や配合変化などへの対応・配慮も必要となる.本書では,終末期患者の症状緩和において皮下投与をより安全に,より有効に活用するための知見を整理して紹介する.

抗悪性腫瘍薬コンサルトブック 改訂第3版
薬理学的特性に基づく治療
主な抗悪性腫瘍薬の適応・副作用,作用機序・耐性機序,投与スケジュールのほか,各薬剤の臨床薬理学的特徴と,それに基づく使用上のノウハウまでをコンパクトかつ明快に解説.さらに各がん種における代表的なレジメンも掲載.今版では分子標的治療薬が94剤と前版から2倍以上に増えたほか,新たに内分泌療法薬18剤を加え,現在のがん薬物療法でカバーすべき薬剤を網羅.抗悪性腫瘍薬を使いこなすための知識を凝縮した一冊.

がん治療のための緩和ケアハンドブック
症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の使い方から心のケアまで
「くり返す痛み,適切な処方は?」「言いづらいこと,どう切り出す?」薬の使い方に加え,つらさを癒す声かけやICの具体例が満載!ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き!
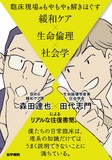
臨床現場のもやもやを解きほぐす 緩和ケア×生命倫理×社会学
僕たちの日常臨床は、理系の知識だけではうまく説明できないことに満ちている。
患者は余命を知りたいのに、家族が反対するのはなぜ?患者が頑なに貫いてきた面会拒否は、亡くなった後も続けるべき?緩和ケアの日常臨床は、答えに辿りつかない「もやもや事例」に満ちている。悩める緩和ケア医・森田達也と、生命倫理学者兼社会学者・田代志門によるリアルな往復書簡が、臨床のもやもやを解きほぐす!文系×理系の視点で「それでどうするの?」から「なんでそうなるの?」までを考える、ゆるくて深い越境の書。
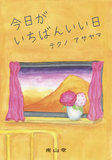
今日がいちばんいい日
緩和ケアと僻地医療を経た後,総合診療に従事しながら哲学の研究を行っている著者が,生きることと死ぬことを見つめながら綴ったエッセイ.緩和ケアとは何か,病とともに生きるとはどういうことか,倫理的であるにはどうすればよいのか.死んだことのない私は,死にゆく人のとなりで何ができるのか.「じぶん」と「じぶん以外の人」の間には何があって,何がないのか?答えのない問いを抱えながら,前に進むための一冊です.
※本書は,2018年より日経メディカルOnlineにて連載中の「今日がいちばんいい日」を再構成および改題し,加筆修正を行ったものです.

今夜からもう困らない!夜の症状緩和
夜間の一般病棟における終末期患者の精神症状,身体症状等の問題を取り上げ,日中とは異なる環境でどのように対応するかといった「夜間の症状緩和」について解説.人手がなくてもこのように/ここまでは対応するという“朝までの乗り切り方”や,夜間帯ならではの治療・ケアのコツを示し,随所に症例提示やコラムを散りばめ,読み飽きない構成とした.“患者をただ眠らせればよい”では済ませない個々の患者背景を踏まえた対応ができるようになる一冊.
