
フローチャート 眼科外来 初診・再診マニュアル
本書はPART1からPART4の構成となっており、まず「診断学の基本的な考え方」を解説することで、眼科診療における診断の思考プロセスを明確にします。続くPART2では、見えづらさや眼痛、視野異常など、患者の主訴ごとに診断の進め方を整理し、即座に活用できるフローチャートを掲載。PART3では成人の疾患を、PART4では小児の疾患を詳しく解説し、日常診療に役立つ情報をコンパクトにまとめています。
本書は、著者が欲しかった辞書的に外来診療で困ったときに、すぐに役立つ実践的な本を目指して作成されており、初学者から経験豊富な眼科医まで、臨床の現場で頼れる存在となること間違いなしの一冊です。
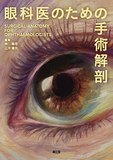
眼科医のための手術解剖
眼科手術全般において,低侵襲あるいは無駄のない合理的な手術を実現するためには「局所解剖の熟知」が必須である.本書は各専門領域のトップサージャンの視点から,手術解剖を究めるために必要な写真と数百枚に及ぶリアルな解剖図で満たした最高の指南書である.基本的なアプローチに加え,術野をみやすくする一工夫も掲載され,手術前に読むだけで自信をもたらしてくれる一冊.
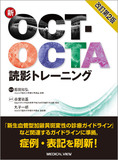
新OCT・OCTA読影トレーニング 改訂第2版
『新OCT・OCTA読影トレーニング』をアップデート。掲載項目・症例数は増加し,初版掲載症例よりも貴重な症例に差し替えた項目もある。また,最新の「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」など関連するガイドラインに準拠し刷新している。
この一冊にOCT, OCTAの画像を余すことなく載せているからこそ,読影力が自然と身につく必携書!

≪新篇眼科プラクティス 5≫
眼科救急治療
まったなし!急がば学べ
「新篇眼科プラクティス」シリーズの第5弾.本書では,「眼科手術レスキュー」「他科疾患にみる視機能障害」という従来とは異なる新たな切り口を追加.冷や汗必至の手術中の急変や,近年重要視される他科医師との連携も想定し対処法を解説した.時間的緊急性に加えて,様々な病態への対処が求められる救急疾患に対して,多数の写真やイラストを具体的な治療法と共に示した本書は,"待ったなし"の臨床現場で活躍する一冊である.

ポイントマスター!小児眼科・弱視斜視外来ノート
教科書には書かれていない小児眼科・弱視斜視外来のコツとポイントが、ぎゅっと凝縮 !
アジアでトップレベルの診療を行い、全国から眼科医が研修に訪れる浜松医科大学眼科学教室・小児眼科弱視斜視分野で、実際に使用されている外来診療マニュアルを書籍化 !
検査、眼鏡処方、弱視・斜視の診断治療のコツとポイントをスペシャリストがわかりやすく解説しています。
「寝転んで読みながらでも1週間以内に読めること」を目標にコンパクトにまとめ、小児眼科を専門としない眼科医、専門医を目指す若手眼科医、視能訓練士が“これだけは知っておきたいエッセンス”が効率良く身につきます。
付録として、浜松医科大学で用いている小児問診票やさまざまなリーフレット、斜視手術で使用している器具一覧を掲載。
眼科医・視能訓練士必携の一冊です !

眼科疾患最新の治療2025-2027
3年毎の改訂で,眼科疾患における治療指針と最新の情報を簡潔に提供.巻頭トピックスでは,話題のガイドライン,再生医療,AI診療,スマホ内斜視,萎縮型加齢黄斑変性の治療など,注目の10テーマをレビュー.各論では主要な眼疾患の治療を網羅し,コラムを豊富に掲載.日常診療のアップデートに欠かせない一冊.

眼底疾患パーフェクトアトラス
眼底疾患の診断で,何が診断の決め手となるかは千差万別であり,現在全盛のOCTといえども万能モダリティとは言えない.本書では,眼底に起こる疾患のほぼ全てを取り上げ,カラー眼底,FA,IA,OCT,ERG等眼科検査からCT,MRI,エコー,病理等他科の検査も含めた所見を掲載した.さらに画像には所見を矢印等で書き込み,初心者でもたやすく検査所見を把握できるよう工夫した.これ1冊で眼底疾患の診断をマスターできる決定版アトラス.

多発性硬化症・視神経脊髄炎診療のすべて
NCNP病院多発性硬化症センターの長年のノウハウを一挙公開.好評を博した前書『多発性硬化症(MS)診療のすべて』刊行以降,MS・NMO の病態研究や薬剤開発は加速度的な進歩を遂げた.
本書では「病態を踏まえた医療」「あきらめない医療」の実践を骨格とした精神を引継ぎつつ,最新知見から実践的治療戦略までを網羅した改訂を行った.日常診療から今後の展望まで,まさにMS・NMO診療の「すべて」を学べる1冊.

神経眼科診療のてびき 第3版
神経眼科は、眼を中心とした所見から原因となる神経疾患の診療を行う分野である。神経眼科疾患はそのすべてが理論的に説明でき、症状を正確に把握すればその病巣までも知ることができる。最新の診断機器や画像診断は必要ない。問診と身体所見のスキルで所見を捉え、神経解剖の知識から病巣局在に迫れ! 第3版では鑑別疾患のさらなるアップデートはもちろんのこと、治療についても詳細に記述。薬物治療ではその投与量や投与方法も具体的に解説した。診断から治療まで。神経眼科のすべてがここにある。

所見から考えるぶどう膜炎 第2版
圧倒的な質と量の症例写真で評価・鑑別のプロセスをわかりやすく解説
原因が多彩で鑑別診断が難しいぶどう膜炎をテーマに、“所見”をベースに評価・鑑別のプロセスと注意すべきポイントを示した好評書、待望の改訂版。初版の内容から写真を大幅に追加・変更しパワーアップ。「multiplex PCRの応用」「免疫チェックポイント阻害薬によるぶどう膜炎」など最新のトピックスもフォローするなど、臨床医が“今”知りたい内容へと生まれ変わった。

もう迷わない!眼内レンズの選び方
患者の満足度を高めるためのコツと方法
「いかにして患者に最適な眼内レンズを選択するか」──これこそ,白内障術後の患者満足度を左右する最重要ポイントといえる.本書は「最適な眼内レンズ選択」に特化した新しい書籍.問診・検査に始まり,得られた情報を分析し,最適な見え方を実現する眼内レンズの理論・テクニック,さらに,Vision Simulatorや現在国内で使用可能なIOLスペック一覧表など最新情報まで余すところなく掲載した.白内障診療に携わるすべての眼科医必携の一冊.

眼科診療の基本!
細隙灯顕微鏡スキルアップ
細隙灯顕微鏡を用いた診断は,眼科医にとって基本であり,必ずマスターしなければならない。角膜を観察するための検査というイメージが強いが,白内障診断,緑内障診断のための隅角や視神経乳頭の観察,網膜の観察など多種多様な疾患に対応する検査であり,そのためには各部位ごとに観察する際のポイント,所見のみかた等を身につけることが大切である。豊富な具体的所見に加えて類似や鑑別の所見も示し,迅速に正しく判断するコツを写真で理解し習得できる書籍。

ジェネラリストのための眼科診療ハンドブック 第2版
救急やプライマリ・ケアの現場で迷いがちな「眼科」のギモンに答えます! 「当直でも眼科医を呼ぶとき or 翌朝まで待てるとき」「通院できない高齢患者から眼症状を相談されたら」「点眼薬の継続処方はいつまで?」「内服薬の副作用による眼症状」「点眼薬・軟膏の正しい使い方」など、手元にあれば安心の1冊。第2版では、巻頭に診断フローチャート、本編に「眼に症状の出る全身疾患」、巻末に点眼薬の基本情報も加わりさらに充実。
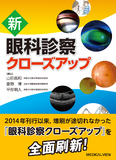
新 眼科診察クローズアップ
『眼科診察クローズアップ』(2014年)を,新しい検査や適応の拡大に対応してアップデートし,内容もブラッシュアップした新版。
診察の基本を十分にかみくだいた形で展開。イラストや写真には「医師から患者さんへの声かけ」を盛り込んだり,コツやポイントを矢印や引き出し文字で明確に記載。関連する本文は図表のそばに囲みで配置しわかりやすい紙面に工夫。
これから学ぶ若手にも,開業に向けて領域全体の知識をブラッシュアップしたい中堅にも役立つ1冊!

ベーチェット病診療ガイドライン2020
ベーチェット病は,全身に多様な症状が出現する難治性炎症性疾患で,特異的な検査所見がないために診断に苦慮することも少なくありません.本書では多臓器にわたる症状を横断的に理解できるよう,治療に限らず症状や所見に関するアルゴリズム・CQを豊富に収録し,ベーチェット病の多彩な症状・所見・治療すべてを網羅.ベーチェット病専門外の一般医にも使いやすい1冊です.
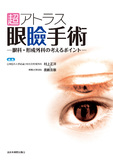
超アトラス眼瞼手術―眼科・形成外科の考えるポイント―
眼科・形成外科・美容外科各分野で大ヒット書籍が待望の電子化!!眼瞼手術の基本・準備から、部位別・疾患別の術式までを盛り込んだ充実の内容。
豊富な術中写真を用いたビジュアルな解説で、実際の手技がイメージしやすく、眼形成の初学者にも熟練者にも、必ず役立つ1冊です。
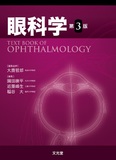
眼科学 第3版
“一冊で眼科専門医に必要十分な知識を学べる”教科書,『眼科学』の9年ぶりとなる改訂第3版.眼科研修医ガイドライン,眼科専門医認定試験出題基準に準拠し,疾患・診療から法律・歴史にいたるまで眼科のあらゆる領域を,最新知見を盛り込みつつ,当代一流の執筆陣272名が明瞭に解説.約3,000点の豊富な図版掲載で,臨床の現場でも活躍する一冊.
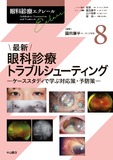
≪眼科診療エクレール 8≫
最新 眼科診療トラブルシューティング
ケーススタディで学ぶ対応策・予防策
眼科日常診療で遭遇するさまざまなトラブルを,救急外来,一般外来,病棟,手術室に分けて取り上げ,トラブルの背景,原因,対応策,そして予防策とフォローアップまでを,各領域のベテラン眼科医がわかりやすく解説.患者対応やレセプト業務に至るまで,280余りのケースについて,陥りやすい落とし穴と回避のポイントを示した珠玉の事例集.いざという時の心強い助けとなる一冊.

多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023
MS・NMOSD診療の心強い味方、6年ぶりの改訂
疾患概念の変化や診断基準の改訂、新薬の開発が日進月歩で進んでいくMS・NMOSD領域。前版発行からこれまでに生じた多くの変化を丁寧に整理し、わかりやすく解説する。第Ⅰ章は各疾患の特徴や診断アルゴリズム、治療薬を1つずつ取り上げ解説する総論的な内容。第Ⅱ章は専門医の中でも対応が分かれる「重要臨床課題」をCQ形式で取り上げる。第Ⅲ章はエキスパートの間では一定の了解が得られる事項をQ&A形式で紹介する。

眼科レジデントのためのベーシック手術 第2版 2
◆「基礎から学べるこんな手術書が欲しかった」を集約! 基本手術の手技とピットフォールをわかりやすく解説した「はじめての手術」書です。
◆多数ある眼科手術の中から、実際にレジデントが行う機会が多い術式や、手術件数が多く、携わる可能性が高い術式を厳選。
◆フルカラーで見やすい紙面とともに、術野写真やイラストに解説を充実させました。
◆まるで手術室を見学しているかのような動画はすべて字幕解説付き。本文と動画を相互に繰り返し参照することで、効率良く理解を深めることができます。
