
せん妄診療実践マニュアル 改訂新版
せん妄診療の定番書が,「ハイリスク患者ケア加算」に合わせて内容を刷新!現場に即した診療フローと豊富な図表を用いた解説で,効果的・効率的なせん妄対策のために「いま,何をすべきか?」がすぐわかる!

≪シリーズGノート≫
骨粗鬆症の薬の使いかたと治療の続けかた
患者さんに寄り添う、治療開始の判断から薬の選びかた・使いかた・注意すべき合併症、食事・運動療法まで
かかりつけ医の強みを生かして,患者さんに合わせた骨粗鬆症の診断・予防・治療を行うための必読書!高齢者の転倒・骨折を予防するための治療薬,食事療法,運動療法を網羅!

画像で究める認知症
年間1万例以上に及ぶ65歳以上高齢者の脳画像をみる神経放射線読影トップランナーが,汎用なCT・MRIから認知症の背景疾患の診断に迫る最前線のストラテジーを詳解。自験例を中心に認知症の背景疾患,注意すべき重畳的所見のなかでも特に優先すべき回復可能な疾患の鑑別から病期診断まで余すことなく徹底解説。新規治療薬で欠かせないARIAやピットフォールも豊富に示唆し,フォローアップ症例の病理画像やSPECT,解析データを交え,局所的診断と評価,根拠,放射線科医がチームとして共有すべき考え方を示す。認知症マネジメントに欠かせない日常診療の検査,高齢者診療にかかわるすべての人に伝える,放射線科医の視点からみた唯一無二のハイパーリファランス。

教えて!専門医の先生
疾患軌道図で学ぶ継続外来
悩みドコロを聞いておきました
診断がついていて,イベント発生から時間も経過し,比較的安定した状態にある患者さんを引き継ぐことってありますよね?でも,そんな慢性期の患者さんを診るうえでも,「現在の処方をいつまで続けていいの?」「これまでの経緯や治療内容が曖昧」「この検査値どこまで下がったら紹介しよう?」など,悩ましいことはいろいろあります.本書は,比較的長期の経過をたどることの多いコモンな疾患・症状について,引き継ぎの際に確認すべきこと,フォローの間隔や検査・薬の考え方,専門医との連携やコンサルトのタイミングといった,フォローする立場の医師が知りたいことを専門医に質問し,相談しながら一緒に作りました.また,各疾患がたどる長期的な経過を疾患軌道図で示し,いつどんな介入が必要になるかをビジュアルにまとめ,その患者さんが自分のところに来る前に何があって,今どの段階にいるのか,今後何が起こりうるのか,という視点がもてるように工夫しました.将来を予測しつつ患者さんの慢性期を支えていくことで,継続外来がぐっと面白く,やりがいのあるものになる一冊です.
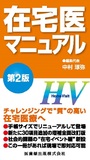
在宅医マニュアル 第2版
●これ1冊で在宅現場での対応がすぐわかる!ポケットサイズ化で増補全面改訂!
●在宅現場での即応に必須の実践書が,手帳サイズにリニューアルして登場!
●現場ニーズの高い30項目を追加して内容を充実させた,増補全面改訂版!
●「老老介護」など社会的課題への対応を記した“在宅イベント編”を新設!
●地域包括ケア時代の必携書! 在宅医ほか,訪問看護師,介護職にもおすすめ!

高齢者総合機能評価(CGA)に基づく診療・ケアガイドライン2024
超高齢社会を迎えたわが国では,CGAによる包括的・全人的な評価と,それに基づいた個別化された医療・ケアの提供が求められている.多職種協働により取り組む必要があり,CGAはその共通言語となる.本ガイドラインは,医師だけではなく高齢者に関わる医療介護福祉関係の多職種向けに作成した.診療やケアに幅広く活用いただきたい.

ポケジェリ
AGS高齢者診療マニュアル
あなたのポケットにジェリアトリクス-老年医学-を
老年医学領域における世界最大級の学会American Geriatrics Society(米国老年医学会)が誇る公式ハンドブック“Geriatrics At Your Fingertips”日本語版。ポケットサイズながら、実用性と網羅性の最適なバランスを追求。内科学、各専門領域を横断した総合診療の知識を根幹に、高齢者特有の問題や症状に対応するための最新の情報・幅広い知恵を凝縮。日本の医療現場に合わせ、1,000箇所に及ぶ訳注・薬剤監修、丁寧な翻訳による「日本化」を実現。高齢者診療の基本的な考え方が身につく。
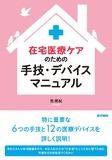
在宅医療ケアのための手技・デバイスマニュアル
その人らしい在宅療養を叶え、その人の人生の伴走者として、ともに戦う医療者のために
在宅医療ケアの手技やデバイスに特化したマニュアル。現場の感覚を盛り込んだ実践的な内容を特徴とし、多くのイラスト、図表を用いて直感的に理解しやすい書を目指す。今後、地域医療は「病院完結型」から「地域完結型」へ切り替わっていくはず。在宅医、訪問看護師はもちろん、在宅医療に興味のある研修医、専攻医、さらには薬剤師、介護職、そして患者・家族にも大いに参考にして頂きたい。よく聞かれる質問への回答も収載。
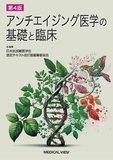
アンチエイジング医学の基礎と臨床 第4版
日本抗加齢医学会専門医・指導士認定のための研修用テキストが前版から8年ぶりの全面改訂。専門医・指導士を目指す医師・医療従事者のためのテキストとして,また超高齢化を迎えた社会のニーズに応える臨床医のための実用書としても必携の一冊。
項目の約半数が新規項目,旧版からの項目もすべて最新情報にアップデートされ,最新の知見に基づくアンチエイジング医学のすべてを網羅した内容となっている。
セルフアセスメント問題として第4版に関連する新たな問題のダウンロードサービス付!
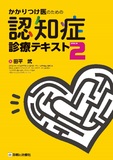
かかりつけ医のための認知症診療テキスト 改訂第2版
認知症1000万人時代の到来に伴い,今や認知症はまずかかりつけ医が診るべき疾患として定着してきている.本書はそうした先生方に向けて企画された入門書である.
認知症診療に関する臨床上のノウハウから社会資源の活用までを一挙網羅し,認知症を学びたい誰にとっても有益な書となっている.日々多忙な先生はまず「実践編」を,より詳しく知りたい事柄については「基礎編」を読むことで理解を深められるよう構成した.

一般病棟でよくある認知症患者さんの悩ましい言動の評価と対応をリエゾン精神科医がもれなく教えます
病棟の認知症患者さんが大声をあげる,食べない…そんなときには必ず理由がある! 医療者が対応に悩む14の言動について,その理由の考え方,対応方法を徹底的にまとめた1冊.思いがけないヒントが見つかる!

シンプルなロジックですぐできる
薬からの摂食嚥下臨床実践メソッド
●この1冊で誤嚥性肺炎の予防&治療、摂食嚥下リハ・薬物療法(認知症、パーキンソン病、COPD、気管支喘息、脳卒中、 etc.)・服薬管理のすべてがうまくいく!
●薬の視点からの摂食嚥下障害へのアプローチ方法を豊富な症例も含めて解説!
超高齢社会を迎えるわが国では、嚥下障害や誤嚥性肺炎患者が爆発的に増加しています。そのため、医療者は嚥下機能に影響を与える薬剤について評価し、嚥下機能の変化をチームでフォローしていく必要があります。
本書は、嚥下障害や食支援を薬剤の視点から実践的に解説しました。「嚥下や食を考慮した処方」という臨床的アドバンテージが身に付く1冊です。

高齢者診療で身体診察を強力な武器にするためのエビデンス 第2版
待望の改訂版!
○全編見直し。前版と比べて30%頁増量。
○「高齢者の定義は75歳以上説」「認知症の診かた」「敗血症の診かた」「超簡単な嚥下評価」について4つの章を追加。
エビデンスが「見てわかる」
○オールカラーページ。グラフや表が活用され、特に表はエビデンスの質に応じた色付けがされているので、高齢者の身体診察に関するエビデンスが「見える」ようになっています。
エビデンスに基づいた高齢者の身体診察3大メリット
○取りづらい病歴を補うことができる
○「早く、安く、痛くない」医療を提供できる
○検査を減らすことができる

高齢者ERレジデントマニュアル
「成人と高齢者は鑑別が異なる。マネジメントも異なる。高齢者は評価に時間がかかる」――。そんな悩みを抱える若手医師に向けて、本書は1)成人との比較論でない高齢者の特徴、2)診断できなくても結局どうするか、3)高齢者でも短時間で評価が可能なテクニックを解説した。救急搬送が年間1万台のERで研修医と日々奮闘している筆者が「高齢救急患者特有の診療・マネジメント」のコツを余すところなく注ぎ込んだマニュアル。

訪問診療の診かた,考えかた

誤嚥性肺炎の主治医力
卒後10年目の呼吸器内科医が綴る,誤嚥性肺炎診療の実践書.
誤嚥性肺炎は治りづらく,再発しやすい,よくわからないなど,難しい印象を持たれがちです.本書は筆者がこれまで学習をし,工夫・実践してきた誤嚥性肺炎の診療を余すところなく,書き綴っています.15名のエキスパートへのインタビュー,診療にも役立ち読み物としても面白いコラム,現場の医療者からの一言のコーナーなど,様々な角度から誤嚥性肺炎の診療が学べます.
誤嚥性肺炎の診療で悩んでいる方には,隣で一緒に考えてくれる,そして誤嚥性肺炎診療のやりがいを感じられるようになる,そんな書籍です.

認知症イメージングテキスト
画像と病理から見た疾患のメカニズム
アルツハイマー型認知症や血管性認知症、レビー小体型認知症など、認知症をきたす疾患の責任病変や症状の発症メカニズムなどをビジュアルに解説した1冊。MRIやCT、SPECTなどの画像所見、ミクロ・マクロの病理所見を豊富に用い、いまだ謎の多い認知症疾患の病態に迫る。細胞構築や機能に基づいて脳を定型的に区域分けする「パーセレーション」など、最新のトピックも収載。

在宅医療コア ガイドブック
在宅医療を担う医師は若手医師,家庭医,総合診療医,開業医など幅広く,今後ますます,需要が高まることが予想される.そこで本書は在宅医療を実践する上で重要なcommon diseaseである高血圧症,糖尿病,気管支喘息,COPD,CKD,慢性心不全,心房細動などの疾患の診療や管理について現場で求められるミニマルエッセンスを抽出して1冊にまとめた.

あめいろぐ高齢者医療
世界一の超高齢社会の日本.老年医学発祥の地・アメリカより,2人の日本人老年科医を招聘.認知症,多剤併用,緩和ケア,終末期の意思決定,ACP,お看取り,失禁,体重減少等,患者や家族の痛みと価値観に寄り添い,ともに「ベストなケアとは何か?」を考える書.

You Can Do it!誰でもサッとできる!
CDCガイドラインの使い方 感染対策
【エビデンスに基づいた感染対策ができる!】
「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使えばいいのかな?」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩までCDCガイドラインについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解説!知ってて当たり前のCDCガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載!
