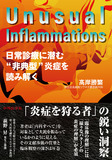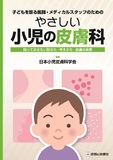医師・医療者が知っておきたい子ども虐待【電子版】
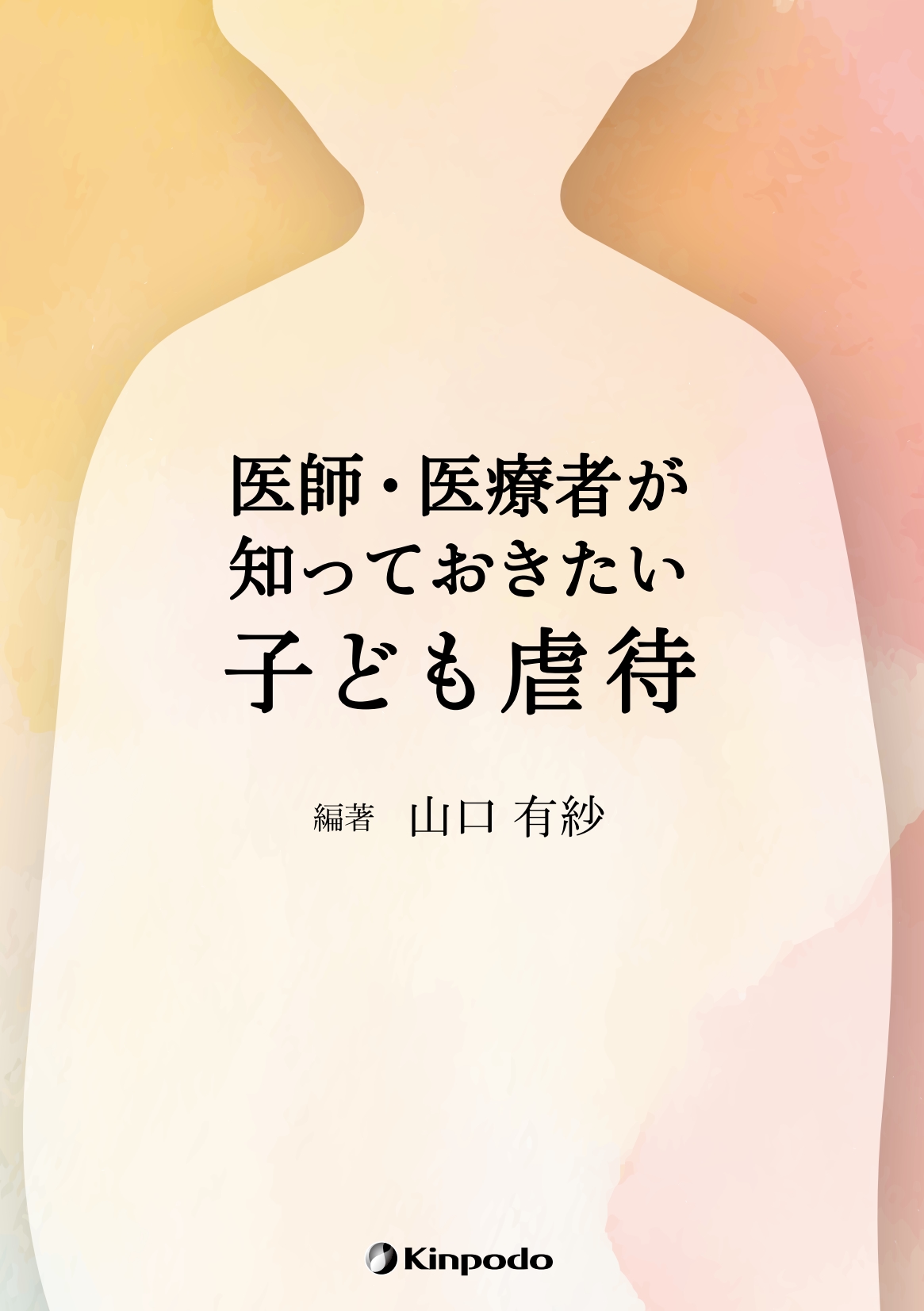
- 出版社
- 金芳堂
- 電子版ISBN
- 電子版発売日
- 2025/03/31
- ページ数
- 178ページ
- 判型
- A5
- フォーマット
- PDF(パソコンへのダウンロード不可)
電子版販売価格:¥3,960 (本体¥3,600+税10%)
- 印刷版ISBN
- 978-4-7653-2037-5
- 印刷版発行年月
- 2025/03
- ご利用方法
- ダウンロード型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 2
- 対応OS
-
iOS最新の2世代前まで / Android最新の2世代前まで
※コンテンツの使用にあたり、専用ビューアisho.jpが必要
※Androidは、Android2世代前の端末のうち、国内キャリア経由で販売されている端末(Xperia、GALAXY、AQUOS、ARROWS、Nexusなど)にて動作確認しています - 必要メモリ容量
- 462 MB以上
- ご利用方法
- アクセス型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 1
※インターネット経由でのWEBブラウザによるアクセス参照
※導入・利用方法の詳細はこちら
この商品を買った人は、こんな商品も買っています。
概要
目次
第1章 子ども虐待・ネグレクトについて、今わかっていること・行われていること
1 ウェルビーイングを形づくるもの ~子どもの権利の視点から
1 子どもの権利の視点
2 エコロジカルモデルの視点
3 子どもの発達に不可欠な要素の視点
2 子ども虐待とは何か
3 どのくらいの子どもが影響を受けているのか
4 子どもの虐待とネグレクトに関わる政策
1 子どもの発達に不可欠な要素の視点
2 対症療法の充実
3 子どもの権利と予防的アプローチの萌ばえ
4 子どもの最善の利益と子どもの声
5 こども家庭庁とこども基本法
第2章 なぜ子ども虐待・ネグレクトに医療者が関わるのか
1 子ども虐待に関わる要因
2 アタッチメントと発達
3 子ども虐待のライフコースへの影響 ~子ども時代の逆境的体験と保護的体験に関わる研究
1 子ども虐待の短期的な影響
2 子ども時代の逆境的体験がライフコースを通しておよぼす影響
3 傷つきの中で育つこと
4 社会全体へ経済的な影響
5 リスクからレジリエンスへ~子ども時代のポジティブな体験
4 医療と子ども虐待・ネグレクト ~なぜ医療者が子ども虐待に関わるのか
1 虐待とネグレクトの予防
2 虐待とネグレクトへの気づきとケア
3 虐待とネグレクトを受けた後の中長期的なケア
第3章 子ども虐待の診断と治療
1 子ども虐待の診断
1 通常の診断との相違
2 虐待を疑う
3 子ども虐待・ネグレクトを疑ったときの診察
4 疑わしきは行動を起こす
5 子ども虐待を疑ったときの検査等
6 医学的診察や検査が重要な虐待
2 虐待を受けた子どもと家族の治療
1 身体医学的治療
2 治療中の養育者への説明と、養育者と子どもの接触
3 養育者と子どもの関係の治療
3 地域連携と社会的処方
1 虐待相談の後に起こること
2 要保護児童対策地域協議会
3 社会的養護のいま
4 一時保護所の子どもたち
5 社会的養護のもとにある子どもと医療
6 社会的な処方
第4章 トラウマインフォームド・ケア
1 トラウマインフォームド・ケアとは何か
1 ストレス反応について知る
2 トラウマインフォームド・ケア
3 トラウマとは
4 トラウマによって起こること
5 ケアする人のケア
2 メディカル・トラウマ
第5章 医療者にできること
1 エビデンスに基づいた柔軟な対応:子ども虐待対応の手引き
1 子ども虐待を疑う
2 子ども虐待に対応する
3 子ども虐待を予防する
2 院内虐待対応チーム(Child Protection Team;CPT)
1 院内虐待対応チーム(Child Protection Team;CPT)とは
2 MDT(Multidisciplinary Team)の重要性
3 CAC(Children's Advocacy Center)とは
3 仲間を増やし、共に学ぶ
1 子ども虐待の卒前・卒後教育
2 医療機関向けの虐待対応啓発プログラムBEAMS(ビームス)
3 仲間を増やす
4 地域での保健師の役割
1 児童相談所で出会った子どもたち
2 保健師とは
3 妊娠期からの早期支援と長期的な視点を持った関わりの必要性
4 地域の保健部門の保健師の活動
5 児童相談所保健師の活動
6 医療機関と連携した事例
7 家庭の状況から見た各機関の役割
8 上流・下流の話
9 医療機関との連携
10 最後に
5 予防とケアのための一歩を踏み出す
1 虐待予防とは
2 子どもの育ちの基盤となる「安全で、安定した、あたたかい関係性と環境」とは
3 虐待予防のための親子関係性支援とは
4 虐待予防のための具体的支援策とは
5 まとめ
第6章 子どもの声からはじめる
1 子どもアドボカシーと医療
1 はじめに
2 子どものこえを聴くこと
3 すくい上げた声を社会につなげること
4 終わりに
2 子どもの声を聴く ~子どもアドボカシーとは何か
1 子どもの意見表明等支援とアドボカシー
2 子どもの声が聴かれない背景
3 独立/専門アドボカシーとは
4 「子ども抜きに子どものことを決めないで」を医療の世界にも
3 現場の声から
1 妊娠葛藤をつながる機会に
2 養育者のエンパワメント
3 言葉にならない「助けて」と共にあること
第7章 「病気の子どもの診断と治療」から「すべての子どもの尊厳とウェルビーイング」の医療へ
あとがき