ナースが知っておく 認知症“これだけ”ガイド 改訂第2版【電子版】
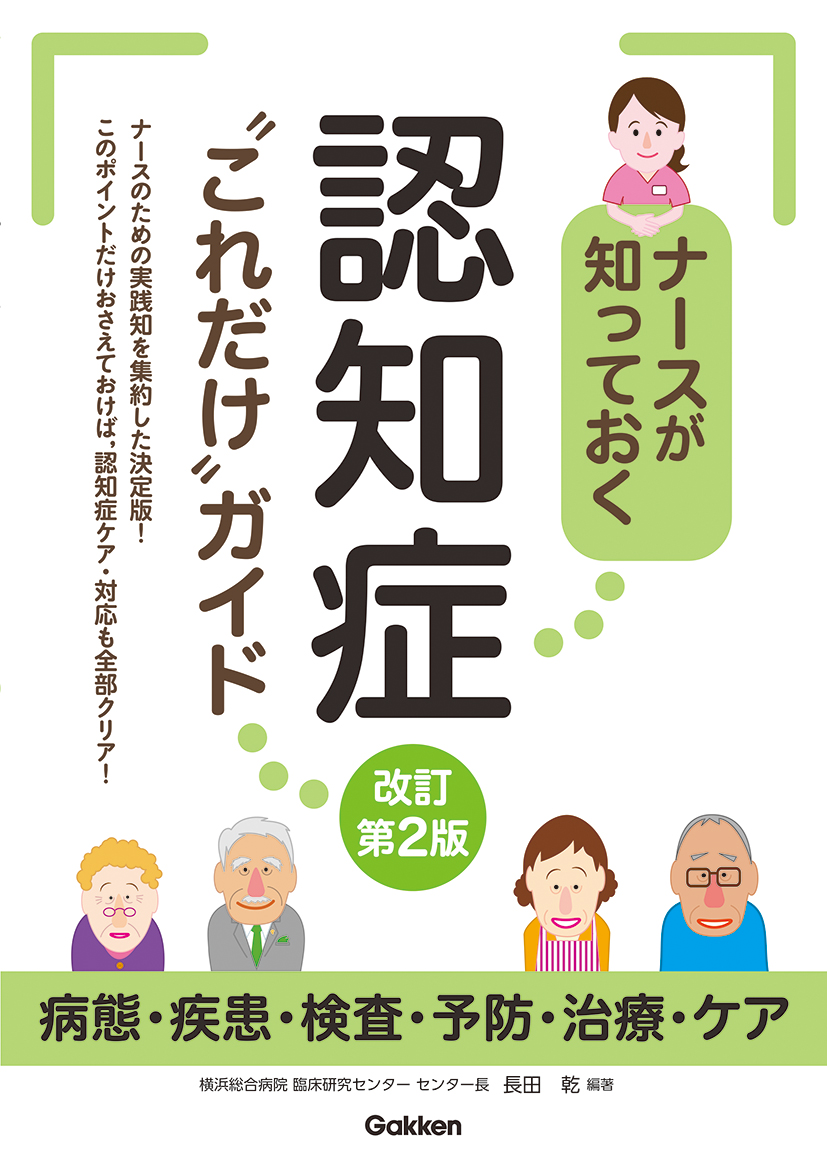
- 出版社
- Gakken(旧学研メディカル秀潤社)
- 電子版ISBN
- 978-4-05-988920-5
- 電子版発売日
- 2025/08/18
- ページ数
- 208ページ
- 判型
- B5
- フォーマット
- PDF(パソコンへのダウンロード不可)
電子版販売価格:¥3,520 (本体¥3,200+税10%)
- 印刷版ISBN
- 978-4-05-510081-6
- 印刷版発行年月
- 2025/06
- ご利用方法
- ダウンロード型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 2
- 対応OS
-
iOS最新の2世代前まで / Android最新の2世代前まで
※コンテンツの使用にあたり、専用ビューアisho.jpが必要
※Androidは、Android2世代前の端末のうち、国内キャリア経由で販売されている端末(Xperia、GALAXY、AQUOS、ARROWS、Nexusなど)にて動作確認しています - 必要メモリ容量
- 46 MB以上
- ご利用方法
- アクセス型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 1
※インターネット経由でのWEBブラウザによるアクセス参照
※導入・利用方法の詳細はこちら
この商品を買った人は、こんな商品も買っています。
概要
病態・疾患・検査・予防・治療・ケアに関する,必須,かつ最前線の知識が身につく1冊.
各テーマの冒頭にビジュアルポイント付き.豊富な図表も相まって,カラフル誌面で認知症の最新情報がやさしくわかる.
目次
Part1 病態を理解する
1 認知症は「症候群」である
認知症とは
認知機能と生活機能
軽度認知障害(MCI)
認知症の疫学
2 いわゆる「物忘れ」を掘り下げる
いわゆる「物忘れ」は奥が深い
認知症の臨床像
記憶障害
失見当識
実行機能障害(遂行機能障害)
注意障害
失語
3 認知症の臨床像と生活機能障害
認知症と生活機能
認知症の診断基準
国際生活機能分類(ICF)の考え方
認知症患者の生活を知る
意欲低下の問題
認知症の経過
慣れた環境は変えたくない
認知症を伴う入院患者
4 行動・心理症状(BPSD)と介護者教育
BPSDとは
BPSDの主な症状
BPSDの評価尺度
BPSDの原因
BPSDの治療
介護者教育
5 せん妄を理解する
そもそも「せん妄」とは
せん妄の分類
せん妄の原因
せん妄の評価の実際
認知症とせん妄の関係
せん妄の薬物治療
せん妄患者も増加する
Part2 疾患の理解を深める
1 アルツハイマー病
概念
名称
歴史
疫学・成因
遺伝・病理・生化学
危険因子
診断基準
臨床経過
症状と予後
治療
「まさにAD」の症状・「まさかAD」の症状
2 MCI(軽度認知障害)
MCI(軽度認知障害)とは?
MCIとよばれるまでの経緯
MCIと診断する臨床的意義について
MCIのさまざまなタイプ
MCIの現況について
臨床現場でのMCIの評価と診断の流れ
MCIの診断
MCIと診断されてから
MCIの早期認識が活かせる環境づくりを
3 レビー小体型認知症とパーキンソン病
レビー小体型認知症(DLB)とは?
DLBの臨床症状は?
DLBとパーキンソン病の違い
診断のための画像検査
DLBの精神症状:それは幻覚? 妄想?
パーキンソン病のOn-Offと,DLBの覚醒変動は区別できる?
どんな症状にどんな薬を使う?
転倒予防で注意することは?
高血圧,低血圧など血圧変動はDLBの症状?
精神症状への対応と家族指導のコツ
薬の副作用への対応
4 血管性認知症
血管性認知症(VaD)の定義
血管性認知症とアルツハイマー病
血管性認知症の臨床病型
血管性認知症の神経心理症状
診断にあたって
血管性認知症の治療
看護上の注意点
5 ピック病と意味性認知症
看護(ケア)の醍醐味を教えてくれるピック病
ピック病の基本知識
(行動異常型)前頭側頭型認知症(bvFTD)とは
意味性認知症(SD)とは
医療現場での気づき
看護(ケア)の視点
知識を知恵に変えていくことで道は開ける
Part3 検査を理解する
1 画像診断でどこまでわかるか?
認知症の正確な診断に画像検査は不可欠
脳の形態を見る画像検査:頭部CT・MRI
機能を見る画像検査:脳血流SPECTとFDG-PET,MIBG心筋シンチとDaTSCAN
異常タンパクの蓄積を見る画像検査:アミロイドPETとタウPET
画像検査の進歩と早期診断・早期介入をめざして
2 認知症の神経心理検査
認知症の臨床像と認知機能
神経心理検査の意義
神経心理検査の分類と位置づけ
認知症のスクリーニング検査
総合的認知機能検査
記憶障害の評価
実行機能の評価
認知症の全般的重症度の評価
円滑に検査を行うために
Part4 危険因子・予防を理解する
1 フレイルと認知症
フレイルの評価
認知症とフレイルの関係
フレイル:身体・認知機能低下への介入
身体的フレイルへの介入
精神心理的フレイルへの介入
社会的フレイルへの介入
2 生活習慣病と認知症
アルツハイマー病の診断
アルツハイマー病と血管性認知症の共通の危険因子
生活習慣病治療とアルツハイマー病
3 認知予備能とは
耄碌と認知症
アルツハイマー病の病理所見と臨床像の乖離
認知症の危険因子と防御因子
認知症の病態と認知予備能
認知予備能の本質は?
Part5 治療・ケアを理解する
1 非薬物療法①音楽療法
認知症の発症率は低下している!?
運動療法の有効性は確立
音楽療法はBPSDに対して有効
音楽療法はコスパに優れる
音楽体操の効果:御浜-紀宝プロジェクト
現場で音楽を活用する際の注意点
2 非薬物療法②認知作業療法
認知作業療法とは? 作業療法と理学療法の違い
認知作業療法が生まれたきっかけ
認知作業療法の手段と目的
認知症予防のための認知作業療法の位置づけ
認知症者への作業療法カウンセリング効果(事例)
3 認知症の病名告知をめぐって
患者の知る権利
日本における患者の知る権利
認知症と「患者の知る権利」
認知症の人に病名を告知する? しない?
患者の「知りたくない権利」
病名を伝える必要があるとき
4 抗認知症薬の使い方
コリンエステラーゼ阻害薬
NMDA受容体拮抗薬
アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症の薬物治療
疾患修飾薬
5 向精神薬の使い方
認知症の行動・心理症状
向精神薬の基礎知識
認知症で向精神薬が使用される場面は
向精神薬を使用する前に
BPSDに対する向精神薬の投与
Part6 認知症と社会支援
1 介護保険を活用する
介護保険と実施の背景
介護保険事業
要介護認定と介護サービス
申請から認定までの流れ
介護が必要となった主な原因
今後の課題
2 高齢者の運転免許更新と改正道路交通法
わが国における交通事故の状況
知っておきたい改正道路交通法
認知機能検査について知っておくこと
なぜ運転を継続したいのかの理由を見極める
高齢者ドライバーに自動車運転をやめさせるために行うこと
免許証の自主返納を勧める
3 認知症患者の社会参加
共生社会の実現を推進するための認知症基本法
認知機能と社会参加
認知症の人の社会参加
4 認知症ケア加算
病院での認知症対応 多職種チームについて
認知症ケア加算
索引





