
すべての診療科で役立つ免疫・炎症性疾患の薬ハンドブック
作用機序、薬の特徴と使い方、副作用がわかる
構造や仕組みが多岐にわたる免疫・炎症性疾患の薬を整理し,作用機序,特徴と使い方,副作用等を解説.各科専門医による現場目線の説明で,ガイドラインが教えてくれない疑問も解消.しかも,読みやすいQ&A形式!

失敗から学ぶ
小児神経診断エラー学
臨床医なら誰しもが経験する“診断の苦い失敗”.
でも,そこにこそ成長のヒントがあるとしたら?
本書の前半では小児神経を中心に多彩な領域で活躍する執筆者が,各自の視点で自由に論考を展開し,「診断エラー」を多角的に掘り下げています.後半では15の症例で診断エラーを真摯に振り返り,読者に貴重な教訓を提示します.
単なる「失敗談」ではなく,明日の臨床に活かせるリアルな学びが詰まっています.
ちょっと勇気を出して,自分の経験を見直してみたくなる一冊.
若手からベテランまで,すべての臨床医におすすめです.

看護展望 Vol.50 No.7
【特集】
コンピテンシー基盤型教育は臨地実習に何をもたらすのか?/編集協力・執筆=西村礼子
看護師の役割が拡大・複雑化するなか、卒業時に看護学生に求められる看護実践能力の水準は年々高まっています。この社会的な要請に応えるため、看護基礎教育には従来の知識伝達型教育からコンピテンシー基盤型教育(CBE)への転換が求められています。
本特集では、CBEの効果と課題に加え、教育と臨床をつなぐ鍵となる看護実践能力の共通認識と保証、「ケアリング」(相手の可能性を信じる姿勢)や「共育」(大学と臨床による共同育成)、さらにCBE実現に必要な臨床現場でのマネジメントについて報告します。

即戦力が身につく骨軟部の画像診断
3つの難易度レベルに分けて多岐にわたる骨軟部画像診断のエッセンスを実戦形式で解説!
「脳」「頭頸部」「肝胆膵」「胸部」に続くシリーズ第5弾!これで主要テーマが出揃う。はじめに現症を示したあと症例画像を提示して、所見を解説し、診断(疾患名)を明らかにするという実戦形式のテキスト。シリーズ最多となる155疾患を3段階の難易レベルに分け、各レベル内は診断名を類推できないようアトランダムに配置。後半では、当該疾患の解説に続いて、鑑別診断についても十分に補足。Q&A形式の設問も中に織り込み、専門医試験にも役立つよう配慮。放射線科のみならず、整形外科の研修医・専門医の実力アップに最適。

臨床画像 Vol.41 No.6
【特集】CT検査の指示出し:検査依頼に応える撮影プロトコル

医学のあゆみ293巻8号
レーザー医学の最前線――知られざる現状とその新展開
企画:中村哲也(獨協学園姫路先端医療研究センター長,特定非営利活動法人日本レーザー医学会前理事長・顧問)
・日本レーザー医学会が認定するレーザー専門医となるには,11の基本領域学会認定の専門医が安全教育講習会を受講し,試験に合格することが必要条件である.
・レーザー専門医は,レーザーとその生体作用,治療の原理,臨床現場における正しい管理法と使用法など,レーザーに関する十分な知識を持ち,より精度の高い安全なレーザー医療を提供することができる.
・本特集では,レーザー医療の安全対策や,各領域におけるレーザー治療など,日本におけるレーザー医学の知られざる現状とその新展開について,各領域のエキスパートが解説する.

薬局 Vol.76 No.7
生成AI×薬剤師
明日からのしごとに役立つ基本&活用術 近年,急速に普及している生成AI.薬剤師業務においても,生成AIは情報整理や資料作成など様々な場面での活用が期待できます.しかし,具体的な使用方法が分からない,または正確性やセキュリティへの不安などから,活用の一歩を踏み出せない方も多いです. そこで本特集は,”明日からのしごとに役立つ”を合言葉に,「生成AIとは?」という基本から,活用方法をまとめました.生成AIを使うために必須となる知識や臨床現場での活用方法のコツを解説しており,本特集を読めばすぐに生成AIを使いこなせる内容となっています.
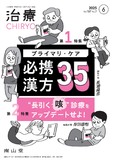
治療 Vol.107 No.7
【第1特集】プライマリ・ケア必携漢方35
【第2特集】“長引く咳”診療をアップデートせよ! 【第1特集】「患者に頼まれたから」や「何となく」で漢方診療をしていませんか?本特集では,プライマリ・ケアの現場でも実践可能な,使い方を覚えておくべき漢方薬を厳選して紹介します.日常診療で役立つ,真に患者の苦痛軽減につながる漢方処方の極意が満載!【第2特集】近年まれにみる大流行となったマイコプラズマや百日咳をはじめとする咳診療の最新の知見や診断法,とくにプライマリ・ケアにおけるアプローチを中心に,患者の身体的・精神的負担に直結する“長引く咳”への向き合い方をアップデートします.

精神療法 増刊第12号
アディクション支援のフロントライン 最近の四半世紀で登場したさまざまな治療法や支援実践、また各職種や当事者の試みなどを紹介し、新たな臨床上の課題を整理する。
