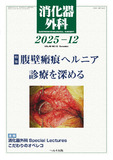
消化器外科2025年12月号
腹壁瘢痕ヘルニア診療を深める 診断・治療・再発予防などに,今なお多くの課題が残されている腹壁瘢痕ヘルニア。その診療に関する基礎的知識と,各種手術の具体的術式を解説することで腹壁瘢痕ヘルニア診療の“深化”をサポートする。

明日の足診療シリーズⅡ
足の腫瘍性病変・小児疾患の診かた
足の外科診療の最新をお送りする本シリーズの第2弾が早くも登場。「腫瘍性病変」と「小児疾患」を大ボリュームでまとめました。「腫瘍性病変」では整形外科だけでなく、放射線科、病理の観点から各疾患についてコンパクトにまとめ、各疾患の特徴的な所見を日常診療の場でもサッと確認できる構成とし、「小児疾患」では診療、検査をはじめ、各疾患を豊富な写真、イラストとともにエキスパート達が解説!豊富な文献サマリーがついて文献reviewとしても役立ちます。

臨床心理学 第25巻第3号
地域精神保健福祉の歩き方 地域精神保健福祉の現在から、多職種連携、様々な現場で活躍する援助者の苦難や支援の方法を掘り下げて解説する。

プチナース Vol.33 No.14
◆今のうちに病態生理を理解!じにの国試★頻出★16疾患
◆過去10年分の国試を分析 次ねらわれる一般問題

総合診療 Vol.33 No.8
特集 都市のプライマリ・ケア 「見えにくい」を「見えやすく」 ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読(医学生・初期研修医割引あり)が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。「総合診療専門医」関連企画も。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊
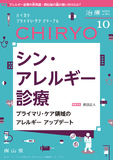
治療 Vol.104 No.10
シン・アレルギー診療 プライマリ・ケア領域のアレルギー アップデート アレルギー診療何が変わった?ここ数年で、診断法や新薬などアレルギー診療には進歩があり,それに伴って多くのガイドラインが改訂されました.そこで本特集では,ガイドラインをベースに,知識のアップデート目的にまとめました.とくに,現役世代が研修をされていた2000年ごろからの変化を中心としています.また,ガイドラインのみではどうしても基礎的な内容になってしまうため,専門の先生の臨床判断も加えております.例えば同種同効薬については使い分けの表を用いて整理しており,すぐに役立つ内容となっております.

検査値ベーシックレクチャー 第2版
何がわかるか どんな時に行うか 解釈と進め方
各種臨床検査のうち特に重要なものについて,「何がわかるか」「どんな時に行うか」「解釈と進め方」との要点に絞って解説した本書は,検査を行う理論的背景を理解しながら,進め方の実際を学ぶことができる.改訂版ではこれまでの16検査に加え「遺伝学的検査」の項目を追加.また,検査の「基準値」の概念を理解する上で必須となる「基準範囲」と「臨床判断値」の違いを明確にし,各検査項目の基準値(広義)を更新した.

摂食障害の認知行動療法
「摂食障害患者への認知行動療法」の実施やテクニックについて詳しく紹介。原因を問うよりも、病状を持続させているプロセスに注目し、まず摂食行動異常、そしてその背景にある精神病理についても扱っている。摂食障害患者にかかわる医師、臨床心理士にとって、日常臨床をより効果的に進めるための参考書。

血液内科 ただいま回診中!
血液内科病棟での感染管理や輸液テクニックなど患者管理の基本はもちろん,血液内科領域の疾患を病態の解説+指導医と研修医の会話形式でわかりやすく紹介.また本書最大の特長としてレジメンや抗がん剤の投与量,スケジュールを見える化した血液チャートを多数収載.臨床経過で出会うイベントと合併症に備えるためのノウハウを『血液内科 ただいま診断中!』の著者が書き下ろした血液内科病棟の必携書!

関節外科 基礎と臨床 Vol.39 No.5
【特集】アスレティックリハビリテーションの奥義
