
別冊整形外科 No.87 脊柱変形up-to-date
特に2000年以降に成人を含めた脊柱変形は自然経過,病態,診断,治療の各分野で発展してきた.扱うレベルは胸腰椎から頚椎や骨盤まで広がり,手術自体も内視鏡や腰椎椎体間固定術(LIF)などの小さな侵襲から前後合併のオープン手術まで,手技も多様になった.本号では、最新の診断・治療をはじめ、長期経過やアライメントの評価、首下がり症候群などについて幅広く論文を多く取り上げた.
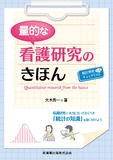
量的な看護研究のきほん
量的な看護研究の概要を実際にポイントになることを中心に解説!
●看護研究に慣れていない初心者が,臆せず第一歩を踏み出すことをサポートするような導入部とした.
●看護研究の初心者が行うことの多い,統計解析10題(アンケート集計から簡単な検定まで)を,実例を用いて具体的に解説.
●理想的な研究像ばかりを追うことなく,時間や予算など現実との兼ね合いをどのように考え,対処すればよいかについても解説.
●巻末には,量的研究の最終チェックに役立つ「統計解析チェックリスト」を綴じ込み!

理学療法39巻7号
小児理学療法におけるフィジカルアセスメントのポイント 本誌37巻1号で取り上げた「疾患別理学療法におけるフィジカルアセスメントのポイント」は成人を対象としたものであり,本号はその小児版とも言えるものです.
小児の理学療法におけるフィジカルアセスメントは,小児の年齢や成長・発達状況を考慮しつつ,態や障害構造の把握,臨床推論,リスク管理を行い,根拠に基づいた適切な理学療法を提供する上で欠かすことのできない基本的かつ重要な臨床能力です.
本特集では,小児の臨床において見逃されがちなフィジカルアセスメントの重要性を再確認すること,すなわち,小児の臨床において関わることが多い代表的疾患と障害を取り上げました.
また近年,在宅医療への移行が進む重症心身障害児の訪問理学療法におけるフィジカルアセスメントのポイントについても述べていただきます.

作業療法実践の仕組み 改訂第2版
作業療法の評価、実践、効果判断を一貫したプログラムとして進めるための知識、チェックと記録のための書式を網羅したガイドブック。

診断と治療 Vol.111 No.1
【特集】知っておきたい肝胆道疾患診療の最近の話題 肝胆道疾患に関するガイドラインのポイントや最近の話題など,一般内科医の先生もおさえておきたい最新の動向がわかる特集です.

精神看護 Vol.25 No.4
特集 精神科訪問看護の先人に、経営や看護のコツを聞く! 「地域」へ向けて、本格的な変革期に入る精神科領域。大きな時代の流れも見据えつつ、自分の仕事も楽しんでいきましょう。この雑誌にはワクワク情報がいっぱいです。 (ISSN 1343-2761)隔月刊(奇数月),年6冊

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.24 No.5
特集1 高齢者の「低栄養」 特集1:高齢者の「低栄養」
高齢者は、嚥下・咀嚼機能の低下や認知症の発症、心理・社会的要因などから低栄養状態に陥りやすく、その改善には介護上の問題や経済的な事情などにより難しいことが指摘されています。これらから、令和3年度介護報酬改定では、栄養改善・管理における取り組みの推進が挙げられました。
人は低栄養状態になると、体力や気力、筋力などが低下し、さらに骨折しやすくなったり褥瘡が発生しやすくなったりするなど、さまざまな問題を引き起こします。栄養状態が改善したことで、高齢者の表情が明るくなった、活動的になったという経験をした看護師も少なくないでしょう。栄養状態は、生活の質(QOL)に大きく関係しているのです。
本特集では、高齢者が低栄養状態に陥りやすい要因や低栄養状態のアセスメント方法、介入方法を解説するとともに、認知症・脳卒中・パーキンソン病・慢性心不全により低栄養状態にある高齢者への支援の実際を紹介します。
特集2:「訪問看護総合支援センター」地域における役割・機能とは
地域における訪問看護提供体制の強化のため、日本看護協会は、2019年度に「訪問看護師倍増策」を公表しました。そのための方策として、「訪問看護ステーションの拡充」「医療機関からの訪問看護の提供」「訪問看護師の採用・育成」を掲げ、これらを支援するための拠点として「訪問看護総合支援センター」の設置を推進しています。
同センターの役割は、地域の訪問看護提供体制整備の方向性を示し、都道府県看護協会・ナースセンター・訪問看護ステーション連絡協議会等の事業を支援するとともに、各団体が一体となった取り組みを推進することとしています。その実現に向けて、日本看護協会は2019年度より各都道府県での同センター設置をめざした試行事業を実施。本特集では、同センターの意義と試行事業の目的を解説した上で、試行事業に参加した機関(岡山県・山形県・静岡県)より、その経緯や活動内容、ステーションはどのように同センターを活用したらよいかなどについて示します。

J. of Clinical Rehabilitation 30巻7号
がんのリハビリテーション-成果と展望
がん治療の急速な進歩とがんサポーティブケアの充実に伴い,がん患者の生命予後の延伸と,がん患者のQOLの向上が図られ,がん対策基本法に掲げられた崇高な理念「がん患者がその居住する地域にかかわらず,科学的知見に基づく適切ながん医療を受けることができるようにすること」に着実に近づいていることは,国民の2人に1人ががんに罹患する時代の福音です.
2007年4月に施行されたがん対策基本法は,故山本孝史参議院議員が自らの体験を通して,がん対策の法制化の必要性を強く訴え続けた結果,議員立法として提出され成立した画期的な法律でした.がん対策基本法によって,わが国のがん診療が大きく変化し,進歩したことは誰もが認めるところでしょう.
2016年に改正されたがん対策基本法では,このような成果を踏まえて,次の段階へ内容を進化させ,医療の充実にとどまらず,がんサバイバーのQOL向上を目指す意思が強く表れています.2018年3月に策定された第3期がん対策推進基本計画には,がんゲノム医療,AYA世代がん対策,がんサバイバーシップ支援,支持療法の推進等,この10年間で新たに認識された課題が施策に加えられました.
がんのリハビリテーションは2010年にがん患者リハビリテーション料が保険収載され,がんのリハビリテーション研修会により,そのすそ野は確実に広がりました.また,がんリハビリテーションのTextbook,『CANCER REHABILITATION』が2019年に10年ぶりに改訂されたのと時期を同じくして,日本リハビリテーション医学会の「がんのリハビリテーション診療ガイドライン第2版」が発行されたように,リハビリテーション医学の中で臨床,研究レベルの成長が著しい分野です.一方で,がん治療の進歩は驚くほど速く,がんリハビリテーションの技術も当然進化しなければなりません.
そこで,これまでのがんリハビリテーションの成果を振り返り,最新のがん治療にふさわしいがんリハビリテーションの将来像を示すことをこの臨時増刊号の狙いとしました.第1章ではわが国のがん治療の最先端で活躍する第一人者により,リハビリテーション関連職種にとって必須ながん治療の知識がわかりやすく解説されているだけでなく,今後のがん治療の明るい未来が語られています.第2章ではがんリハビリテーションの各論について臨床経験豊富な筆者に,ご自身の実践と関連研究のReviewから成果をまとめていただき,望ましい未来について解説をしていただきました.さらにコラムでは,がん対策,がんリハビリテーションに関連する多くのトピックスを取り上げ,第一線で活躍されている方々に簡潔にまとめていただきました.
結果として,がんリハビリテーションに加えて現代がん治療とがん対策全体がupdateできる素晴らしい1冊が出来上がったと感動しています.
いまだ出口の見えないコロナ禍であり,日々の生活の閉塞感にとどまらず,診療における感染対策やTelemedicine対応,職員の健康管理にワクチン接種,研究活動の制約等,精神的にも物理的にもストレスの多い時期に執筆を快くお引き受けいただき,玉稿を賜った筆者の方々に心より御礼を申し上げます.(編者:水落和也)

臨床皮膚科 Vol.72 No.10
-
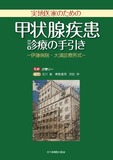
実地医家のための甲状腺疾患診療の手引き―伊藤病院・大須診療所式―
甲状腺疾患専門病院として本邦を代表する伊藤病院で活躍する執筆陣による実践書。診療の基本から実地診療でのポイント、専門病院との連携のあり方まで、幅広く解説。
