糖尿病のある人(person with diabetes)の診かた【電子版】
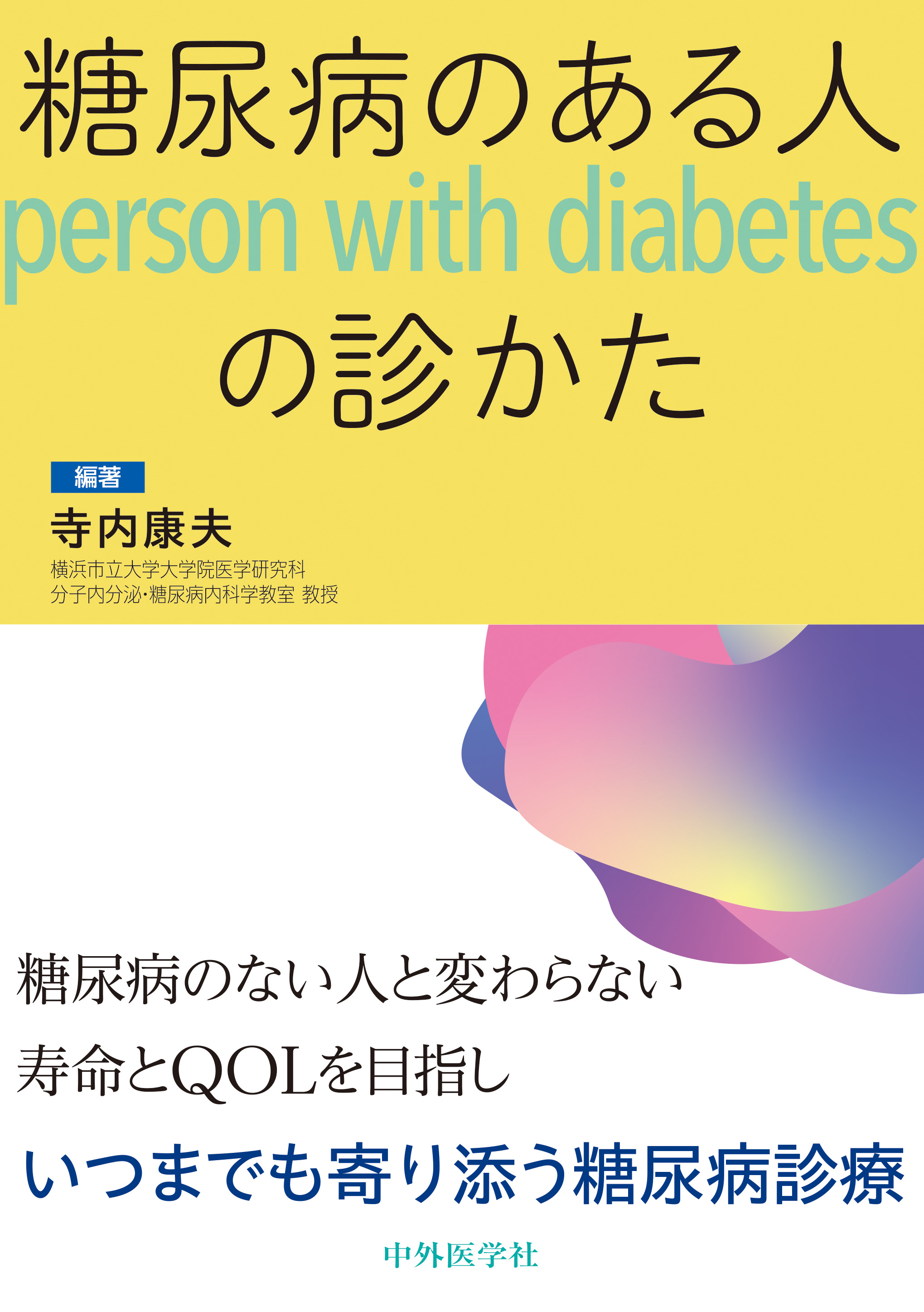
- 出版社
- 中外医学社
- 電子版ISBN
- 電子版発売日
- 2025/03/25
- ページ数
- 208ページ
- 判型
- A5判
- フォーマット
- PDF(パソコンへのダウンロード不可)
電子版販売価格:¥3,960 (本体¥3,600+税10%)
- 印刷版ISBN
- 978-4-498-22306-6
- 印刷版発行年月
- 2025/03
- ご利用方法
- ダウンロード型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 3
- 対応OS
-
iOS最新の2世代前まで / Android最新の2世代前まで
※コンテンツの使用にあたり、専用ビューアisho.jpが必要
※Androidは、Android2世代前の端末のうち、国内キャリア経由で販売されている端末(Xperia、GALAXY、AQUOS、ARROWS、Nexusなど)にて動作確認しています - 必要メモリ容量
- 16 MB以上
- ご利用方法
- アクセス型配信サービス(買切型)
- 同時使用端末数
- 1
※インターネット経由でのWEBブラウザによるアクセス参照
※導入・利用方法の詳細はこちら
この商品を買った人は、こんな商品も買っています。
概要
本書は,「糖尿病“患者”」という言葉を出来るだけ使わずにつくられています.糖尿病のある人(person with diabetes:PwD)の寿命が伸びてきている昨今,糖尿病との因果が確定している疾患:合併症(神経障害・網膜症・腎症,冠動脈疾患・脳血管障害・末梢神経障害など)の診療はもちろん重要です.一方で,糖尿病に起因しない(もしくは関与が少ない)加齢や環境要因によって生じる疾患:併存症・併存疾患について,糖尿病の延長線上で考えてはいないでしょうか.そのような考えでは,「糖尿病治療に際して真面目に取り組んでこなかったから合併症・併存症が起きた」という呪いの言葉が容易に生まれます.「患者」という言葉を捨て去ることで,それを当然とする世界から脱却できるかもしれません.PwDが糖尿病のない人と変わらない寿命とQOLを目指すために,エキスパートが何をどう実践しているか,ぜひご覧ください.
目次
企画趣旨~糖尿病のある人(person with diabetes:PwD)の診かた~〈寺内康夫〉
CHAPTER 0 糖尿病をもつ人の治療目標・目的としてのQOL〈石井 均〉
1 糖尿病をもつ人(person with diabetes)という呼び方がもたらす大きな意識改革
2 日本の医者の態度はどうだったのか,どう変わろうとしているのか ─革新性の理解のために
3 糖尿病をもつ人という立場から見た糖尿病治療の目標と目的
4 HRQOL(health related quality of life)とは具体的にどんな機能や状態を言うのか
1 医学的な概念としてのQOLが含む事象
2 QOL質問紙の種類
3 QOL測定(PROを含む)はなぜ重要なのか─HbA1c以外の何を伝えるか
5 糖尿病をもつ人の寿命とQOL ─糖尿病と治療の重要なアウトカム指標のエビデンス
1 寿命(生存年数)
2 QOL─それぞれの治療段階のアウトカム指標としてのQOL
2-1 日々の治療のアウトカム(第1段階)としてのQOL
2-2 中期的目標(第2段階):合併症がQOLに与える影響
2-3 長期的目標(第3段階):糖尿病のない人と変わらない寿命とQOL
3 QOLの全体像─QOLはアウトカムであると同時に予測因子である
6 医療者とPwDとの関係によってQOLが向上する ─ person centered care(collaborative care)につながる要因(PROも含めて)
1 「エンパワーメント」や「健康リテラシー」とQOL
2 治療への自信(self efficacy)とQOL ─自信を育てるような関わり方が重要である
3 医療者によるスティグマとQOL
4 医療者との関係─治療法について十分議論できているか(コミュニケーション)とQOL
5 まとめ─「糖尿病をもたない人と変わらないQOL」の維持は実現可能である
7 医師(医療者)の言葉と態度と共感
1 病をもつ人と関わっていくときの姿勢,態度,考え方:患者-医師関係(The Patient Physician Relationship)
2 言葉の重さ
8 合併症や併存症がある方にとっても(糖尿病をもつすべての人の)QOLが高くなるようなケアをしよう
1 合併症をもつ人への治療,身体障害をもつ人へのケア
9 まとめ 糖尿病医療学─糖尿病をもつすべての人へのケアとQOL
CHAPTER 1 糖尿病合併症・併存症を見つける〈山川 正〉
section 1 糖尿病のある人についての初期の初期
1 糖尿病と診断されて間もない患者を受け持ったら
1 糖尿病のさまざまなステージ
2 “糖尿病”の受け止めについて
2 診察のポイント
3 糖尿病合併症(細小血管症,大血管症)をどう説明するか
1 急性合併症について
2 慢性合併症について
4 糖尿病の併存症をどうやって説明するか
5 糖尿病の初期の治療戦略
section 2 糖尿病合併症の予兆・発症を見つけ出す〈南 太一〉
1 肝障害について
2 腎障害について
3 脂質異常症について
4 症例提示
section 3 糖尿病併存症の予兆・発症を見つけ出す〈田島一樹〉
1 症状別の想起・予防すべき併存症
2 その他,意識しておくべき疾患
CHAPTER 2 糖尿病合併症・併存症をコントロールする(糖尿病からの視点)
section 1 HbA1c高値が続くときの糖尿病診療〈北谷真子〉
1 血糖値が高い状態が続くのは,療養行動を「しない/できない」からではなく,「しない/できない理由,事情がある」からである
2 血糖高値の真の理由に迫りながら,患者さんとともに治療を進めるために ─糖尿病治療の2つのアプローチ,相互参加モデルとその盲点,困難さ
3 患者中心アプローチの実践 ─病棟での心理カンファレンス開催とそこから得られた学び
4 実際の症例へのかかわり─行き詰まったときの入院のススメ
5 Aさんと私たちの2週間を振り返る─行動変化ステージモデルの観点から
6 最後に 血糖値が高いままでも「患者中心」をあきらめない
section 2 合併症・併存症の新規発症に注意〈山?真裕〉
1 糖尿病と診断されたとき
2 合併症・併存症の早期発見のために
3 医療を行う場を作ること
4 チーム医療の役割
5 合併症・併存症の新規発症のそのあとに
CHAPTER 3 糖尿病合併症・併存症をコントロールする(合併症・併存症からの視点)
section 1 疾患別対応〈細井雅之,玉井杏奈,井坂吉宏〉
1 症例提示:腎機能障害をきたした肥満2型糖尿病男性
2 ギャップの理由 その1:バーチャルな病気
3 ギャップの理由 その2:現在バイアス
4 ギャップの理由 その3:つなぎの欠如
5 合併症・併存症の診かた その1:PwDと医療者のギャップ
6 合併症・併存症の診かた その2:関係性を保つ ─そこに糖尿病医療学が必要
7 合併症・併存症の診かた その3:糖尿病連携手帳の活用
1 糖尿病連携手帳について
2 糖尿病連携手帳のちから
3 便潜血のすすめ
8 合併症・併存症の診かた その4:チャート式糖尿病人生航路 ─「ゆるやかな法則からwell-beingへ」
section 2 マルチモビディティについての考え方〈?橋謙一郎〉
1 マルチモビディティとは?
2 糖尿病におけるマルチモビディティ
3 糖尿病診療でよく見られるマルチモビディティのパターン
4 マルチモビディティのエッセンス,診療のこつ
CHAPTER 4 糖尿病合併症・併存症と付き合う
section 1 総論〈皆川冬樹〉
1 これから起きる可能性のある合併症・併存症について
2 悪化してしまった状態を最初からPwDに意識させる必要性はあるのか?
section 2 各論 COVID-19を罹患した糖尿病のある人〈南 太一〉
1 COVID-19クラスター感染により災害医療を行わなければならない状況となる
2 COVID-19肺炎罹患時の糖尿病治療の困難さ
3 COVID-19肺炎罹患時の糖尿病治療の提案
1 目標血糖値について
2 COVID-19肺炎罹患時に推奨される糖尿病治療:インスリン療法
4 COVID-19肺炎に罹患する前の糖尿病治療
1 COVID-19肺炎は糖尿病のある人において重症化しやすい
2 COVID-19パンデミック下での糖尿病治療
5 糖尿病だったからCOVID-19が重症化したのだろうか
section 3 各論 悪性腫瘍ターミナル期の糖尿病をもつ人〈山?真裕〉
1 病をもつ人への医療者の態度
2 悪性腫瘍と糖尿病をもつこと
3 悪性腫瘍と血糖マネジメント
4 悪性腫瘍ターミナル期のスピリチュアル・ケアとしての血糖マネジメント
5 糖尿病だったから悪性腫瘍が治らずターミナル期となったのだろうか?
6 ターミナル期を診る糖尿病医療者の存在意味
section 4 各論 認知障害が進行した糖尿病のある人〈山田佳彦〉
1 認知症とは
2 進行した認知症の問題点
3 糖尿病と認知機能障害
4 認知機能が低下した高齢者の治療目標
5 認知機能障害が進行した糖尿病のある人へのかかわりと支援
CHAPTER 5 糖尿病のある人に対するコーチング〈松澤陽子〉
1 コーチングとは
2 コーチングの構造と基本スキル
3 コーチングサイクル
4 スキルを支えるコーチングマインド
5 コーチングの限界と糖尿病医療
CHAPTER 6 私はこう考える
section 1 糖尿病センターの掟〈八幡和明〉
1 病態の評価表
2 退院時の色紙
section 2 糖尿病のある人と向き合う医療者に求められること〈関根 理〉
1 自己中断のリスクがある糖尿病のある人へのかかわり
2 感情負担(スティグマに伴う)が強い糖尿病のある人へのかかわり
3 糖尿病のある人と向き合う医療者に求められるもの
section 3 患者さんの人生を支えるということ〈手納信一〉
●緒言 患者さんが医療に求めるもの
1 生きる意欲のない患者さんとの出会い
2 実践しようとしていること
1 Listen to the patient
2 語りの前提となる信頼関係を築く
3 聴くこと
4 共感(言葉や行動をジャッジしない)
5 自分の心と違ってはいけない
6 適切な返し
7 Informed choice
8 患者さんの人生は患者さんのもの
9 信じて待つ
10 患者さんをトータルに診る
●おわりに 施設全体で患者さんを支える姿勢
section 4 病院のなかの,糖尿病のある人とのお話の場である談話室(以前は診療室と呼んでいました)〈川地慎一〉
section 5 初診時の診察(熊倉医院の場合)〈熊倉 淳〉
共感力?
歴史・背景を知る(あなたはどういう人なのか知りたい),聴くこと,物語の準備
糖尿病についての情報を提供する(あなたは糖尿病についてどれだけ知っているのか知りたい)
今後の治療方針について相談する(待つこと)
定期受診の際に聴くこと
スタッフに感謝する
患者さんのことば
●さいごに─診療は愛だ!
索引





