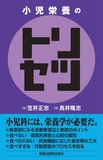
小児栄養のトリセツ
小児トリセツシリーズ第7弾。子どもは食べることで栄養を摂取し、成長していく。疾患によって栄養障害が起こった場合には、基礎疾患の治療とともに子どもの成長をサポートするための栄養管理が必要である。また、器質的な疾患によらない栄養障害も小児では問題になりやすい。乳幼児期や学童、思春期の「食べない・食べられない・食べすぎる」悩みは医学的なアプローチだけでなく、栄養学的な視点を加えることで解決に導けることも多い。
本書は小児医療に携わる人がはじめて栄養について学ぶための「トリセツ」である。
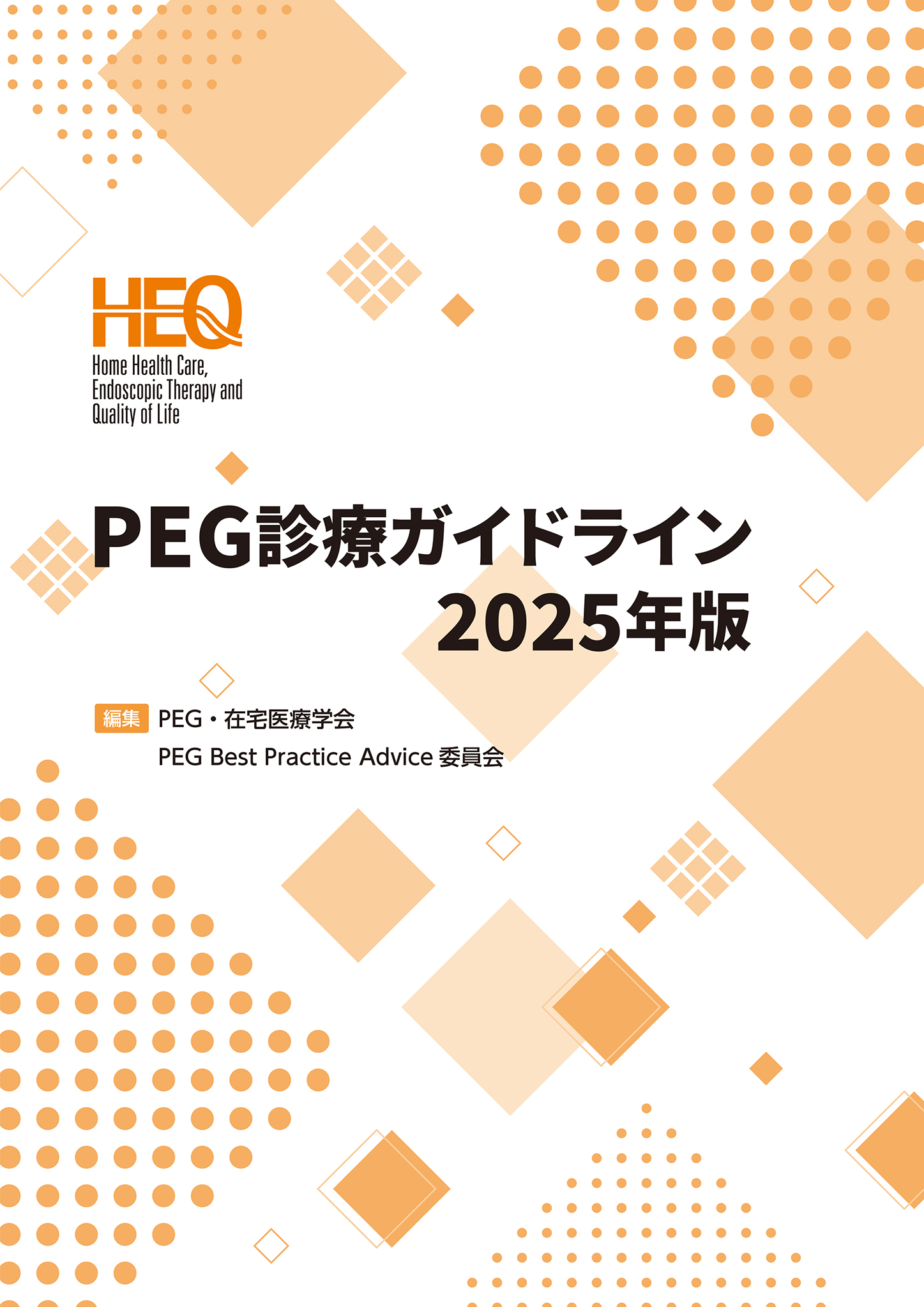
PEG診療ガイドライン 2025年版
●本書は,実臨床における真に必要なメッセージとしてPEGを冠する本学会の総力を挙げて作成されました。
<発刊に寄せてより>
今回刊行されたPEG診療ガイドラインの基本コンセプトは,実臨床において真に必要なメッセージを作成することで,そのためにエビデンスのみに縛られることなく,経験豊かな専門家の意見も柔軟に汲み入れられているはずです。海外の学会でも新定義の厳しい診療ガイドライン(PG)と区別してBest Practice Adviceという実臨床で役立つ支援ツールが開発されていますが,本ガイドラインは正にBest Practice Adviceとして,PEGに関連する診療に携わる方々を支援する有益な情報源となることを確信しています。(上野文昭)
<本書の刊行にあたってより>
胃瘻よりもCVポートの方を希望します,とか,誤嚥性肺炎の人には胃瘻がいいのでしょうか?とか,胃瘻からの栄養剤投与はどうしたらいいのですか?とか,胃瘻を造ったら口から食べられなくなるのですよね,といった声が近頃,医療従事者から私に届くようになりました。20年くらい前には想像がつかないような状況です。栄養投与には患者さんごとに最適の投与ルートがあることや,嚥下訓練には適切な栄養投与が必要なことや胃瘻の基本が理解されていないのだと痛感しました。(中略)
PEGは単なる「内視鏡を使って胃にカテーテルを留置することができ,胃内に栄養剤を注入することができる」投与ルート造設法です。胃瘻は造設することが目的ではなく,造ってからの栄養投与が目的なのです。胃瘻が出来てから医療が始まるのです。(中略)
このガイドラインはPEGと栄養に関する,現時点での標準的な扱い方が記されています。本書を読むことで,PEGを有する患者さんに真摯に向き合うようになってほしいと考えています。
多くのPEGに携わる方々に本書を読んでいただきたく思います。そして本書を手に取られた方々にとって,PEGの理解のために少しでも有用であれば望外の喜びです。(西口幸雄)

PICCの教科書
失敗しない!挿入から管理までのポイント
診療看護師による医師サイドにたった診療の補助(特定行為)の1つに「PICCの挿入」がある.PICCは安全性面で大きなメリットがあり,適切に管理すればカテーテルを長期間留置可能である.そのため,患者負担も軽減することになる.PICCは海外では広く普及しており,日本でもさらなる普及率増加が見込まれている.本書では、PICCの挿入から管理に至るまでの基本的知識、さらにスキルが身につくよう動画を交えて解説した.診療看護師をはじめ,診療看護師を目指す看護師,PICCを使用していきたいと考える医師にも十分に役立つ内容となっている.

≪ニュートリションケア2025年冬季増刊≫
最新版 消化・吸収・代謝と栄養素がまるっとわかるイラスト図鑑
【押さえておきたい栄養の基本が楽しく学べる】
栄養管理においては、栄養素の量やバランスを見きわめ、体の状態に応じて調整することが重要である。これらのバランスがくずれると、病気の原因となったり、症状が悪化したりする場合がある。本書は、栄養にかかわる臓器のしくみ、消化・吸収・代謝の流れ、栄養素のはたらきを、イラストを用いてわかりやすく紹介する。

輸液を学ぶ人のために 第3版
臨床現場に出るとすぐに必要なのは輸液の知識。その基本から応用までを、研修医・看護師向けに解説し、輸液の入門書として高い評価を得てきた本の第3版。とくに近年変化の著しい高カロリー輸液の部分を大幅に改訂。

≪ニュートリションケア 2024年秋季増刊≫
ひと目でなっとく! 水・電解質・酸塩基平衡
【水・電解質の基本と異常がスイスイわかる】人体の恒常性を保ち、さまざまな疾患に関係する水・電解質、酸塩基平衡の知識は、管理栄養士に必須である。本書では、むずかしいと思われがちな水・電解質、酸塩基平衡について、イラスト図解を交えて解説し、現場でよくみる電解質異常症例も取り上げる。
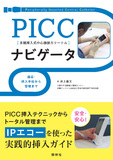
適応・挿入手技から管理まで
PICCナビゲータ
●PICCは、“末梢から挿入する”「中心静脈カテーテル」であるため、中心静脈栄養を行うための基本的な知識と技術を解説しました。
●カテーテル挿入を安全に行うために開発された機器である “IPエコー”を使用した挿入の具体的な手順を詳述しました。
●安全管理のポイントは、カテーテル関連血流感染症(CRBSI)の予防です。
挿入部・輸液ラインの管理方法についても解説しました。

≪ニュートリションケア2025年秋季増刊≫
栄養管理&栄養食事指導に活用できる検査値ガイド
【患者の状態を読みとり、伝える力が身につく】栄養ケアを行ううえで、検査値から患者の状態を読みとる力は重要である。本書では、覚えておきたい検査値の意味、推移の読み解き方や基準値・異常値、関連疾患に加え、栄養食事指導でのわかりやすい伝え方をコンパクトに解説する。ダウンロードしてそのまま渡せる「患者説明シート」つきで、日々の業務に役立つ一冊。
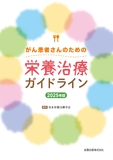
がん患者さんのための栄養治療ガイドライン 2025年版
さまざまな疾患において栄養障害が治療を受ける上で負の影響を与えることが明らかとなり、がんもその代表的な疾患のひとつです。栄養障害を改善するための栄養治療を並行して行うことで、治療効果を上げ、副作用や合併症を軽減し、生活の質を改善することもわかってきています。
栄養治療の重要性が再注目されていることから、患者向けガイドラインが刊行される運びとなりました。患者さんやご家族の疑問にQ&A形式で丁寧に答えます!

≪ニュートリションケア2023年秋季増刊≫
経腸栄養プランニング
【理論と根拠に基づいた経腸栄養管理ができる】経腸栄養管理は、管理栄養士に求められる重要なスキルである。本書では、経腸栄養法を行ううえで必須となる知識と、多様な疾患の症例を解説する。患者の病態を見きわめ、適切な経腸栄養剤の選択・投与・変更提案を含めたプランニングができる管理栄養士になるために欠かせない一冊。

開業医のための生活習慣病患者の療養計画書&指導シート
【療養計画書のラクラク策定で算定数UP!】令和6年度診療報酬改定で新設された「生活習慣病管理料(Ⅱ)」の算定時には、療養策定書を策定して患者の同意を得る必要がある。本書には、療養計画の策定から患者同意までをカバーできる患者説明シートを収載。ダウンロードして日々の診療に活用できる。

褥瘡治療・ケアトータルガイド
エビデンスに基づく確かな技術で「臨床力」アップ! 「褥瘡予防・管理ガイドライン(日本褥瘡学会編集)」に準拠! リスクアセスメントから予防、局所治療、ハイリスク患者への対応、在宅での予防・ケアまで、褥瘡診療に必要なテーマをトータルに解説!

≪ニュートリションケア2025年春季増刊≫
栄養ケア・マネジメントのギモンQ&A50
【介護保険施設の栄養管理を適切に&効率的に】令和6年度介護報酬改定では、地域包括ケアシステムの深化・推進や、リハビリテーション・栄養・口腔の一体的運用、医療・介護・障害の連携が求められている。管理栄養士は多職種の役割を理解して情報・方針を共有したうえで、専門性をもって栄養管理を行う必要がある。介護保険施設における食事・栄養の疑問にわかりやすく回答するQ&A集。

改訂7版 臨床栄養ディクショナリー
【臨床栄養指導に必要な最新情報と知識を解説】疾患・ライフステージ別の食事療法、栄養補給法、栄養素の解説を収録したディクショナリーで具体的な食品や献立例を挙げてわかりやすく解説している。日本人の食事摂取基準(2025年版)の内容に準拠。臨床栄養指導、管理栄養士国家試験対策、臨地実習など幅広い用途で活用できる!
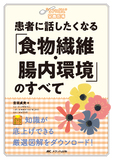
≪“ちょい足し”栄養指導≫
患者に話したくなる「食物繊維・腸内環境」のすべて
【ちまたで話題の栄養情報をスッキリ解説!】「体をととのえる」といわれる食物繊維と腸内環境について、知っているようで知らなかった基礎知識から、栄養ケアに活用できる最新情報まで紹介。「今」知りたいトレンドを“ちょい足し”した適切な栄養食事指導で、患者の心をつかむ。
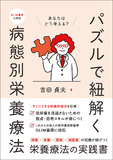
パズルで紐解く病態別栄養療法
●病態・栄養・薬剤・検査値の知識が結びつく栄養療法の実践書!
●すぐにできる栄養評価のコツや低栄養を見逃さないための視点・思考スキルを伝授!
●これからの成人の低栄養診断基準:GLIM基準に対応!
患者の栄養状態は、疾患の治療、回復、悪化防止と密接に関わっているため、その評価は適切な栄養療法を実施するうえで重要です。栄養療法を適切に行うためには、基本的な知識に加え、患者のさまざまな所見から問題点を抽出し、それぞれに対するアプローチを考えるトレーニングが求められます。
本書は、病棟で遭遇する栄養療法がカギを握る悩ましい疾患・病態について、質の高い実践的な症例を用いて問題点を抽出したのち、エキスパートとともにパズル形式で解決策を導きだす構成で、栄養評価や問題解決のための思考プロセスを惜しみなく解説します。さらに、非専門医・薬剤師もすぐに実践できるようGLIM基準を用いた栄養評価のコツも伝授。栄養療法を一通り学んだけれど、いま一つうまくいかない、いつもの栄養療法を見直したい医療者に手に取っていただきたい栄養療法の実践書です。

≪ニュートリションケア2024年冬季増刊≫
栄養評価と栄養療法のキホンQ&A
【ベッドサイド栄養管理の疑問を解消する一冊】令和6年度診療報酬改定における「栄養管理体制の基準」として、「栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること」が明確化された。医療チームの一員である管理栄養士が、栄養管理計画を立案するために迷いがちな栄養状態の評価、栄養補給方法、栄養管理上の課題をわかりやすく解説する。

京都御所南はらしま食堂
医師・栄養士・菜食研究家が考えた 野菜ピューレでつくる低塩・高栄養のおいしいレシピ
ここでは食材の力とうま味を濃縮した野菜ピューレを使い,日常では摂取しづらいビタミン類や食物繊維も豊富な,栄養豊かで塩分も控えたメニューをご提案します. 食事は,健康なこころと身体の源です.楽しくない・味気ない食生活や,栄養・エネルギーのバランスの崩れた食習慣は,私たちの生活の土台をゆるがしてしまいます.しかし,こころにも身体にも“おいしく”“たのしい”食事を両立するのは簡単ではありません. 例えば,入院中に提供される病院食の評価では,一般的に「味が薄くおいしくなかった」との声がよく聞かれます.また,高血圧や腎臓病などに配慮した低塩食・減塩食にも「おいしい」と評価されているものは多くありません.また,いざ栄養のバランスを考えて野菜を摂取しようとしたとしても,実際に目的の栄養素を十分にとるためには大量の野菜が必要であることに気づいてげんなりした人や,食材の管理や調理が容易ではないと感じた人も多いかもしれません.そのため,身体の健康のための食事を“味気ない”“手間がかかる”と考えて,「我慢して食べるもの」と受け止める人や,それらを生活に取り入れることに拒否感をもつ人もいるでしょう.さらに,こうした楽しみの少ない食生活を続ければ,ストレスがたまり,気持ちが落ち込んでしまいます. そこで本書では,野菜の味わいや彩りを活用した野菜ピューレをもとに,調味料として「食塩」をなるべく使用せずに“うま味”を楽しむ「低塩食」「高栄養」に特化したレシピを提案し,生活への取り入れかたをご紹介します.管理栄養士による栄養解析や,医師による栄養解説で,健康な食事のための知識もバッチリ. はらしま食堂のレシピでは,おいしさ,見た目の楽しさと,低塩・減塩および栄養バランスを両立していますので,高血圧や糖尿病などでお悩みの方も,ご家族や小さなお子さんと同じメニューで一緒に食卓を囲めます.身体にもこころにもおいしいレシピ,どうぞ召し上がれ!

NST栄養管理パーフェクトガイド(下)
Immunonutrition,抗酸化療法の最新情報や病態別経腸栄養剤の選択法のほか,診療報酬改定による減収対策についても記述.既刊(上)との併読でNSTスキルがパワーアップ出来る.

NST栄養管理パーフェクトガイド(上)
●(上)(下)2冊でNSTスキルパワーアップ! ●大学病院NSTを運営している著者がまとめた,NST栄養管理に必須の知識を収めた「1ランク高いレベル」の解説書. ●本書(上)は,消化管機能の基礎・臨床,栄養スクリーニング・アセスメント,静脈栄養・経腸栄養の特徴と投与の実際,問題点と対策などについて詳述. ●(下)は,Immunonutrition,抗酸化療法の最新情報や病態別経腸栄養剤の選択法のほか,診療報酬改定による減収対策についても記述.
