
心エコー 2026年3月号
弁膜症の未解決問題に挑む!~ガイドラインのスキマをしっかり解説 特集記事として,moderate ASは治療適応にならないのか?/mixed aortic valve disease(MAVD)とは?/複合弁膜症を考える─severe ASに合併するTR/ステージBのprogressive MRをどう診る?/ステージBのprogressive ARをどう診る?/Fallot四徴症術後遠隔期のPRをどう診る? 等を取り上げる.また,症例問題[Web動画連動企画]多発脳梗塞の原因検索に心エコーが有用であった1例,COLUMNとして,Echo Trend 2026,統計アレルギーのあなたに送る処方箋,伊藤 浩の3分で読める!イイ話等を掲載.

臨床スポーツ医学 2026年3月号
グロインペイン症候群とFAIの現在 特集記事として,グロインペイン症候群の歴史と診断/股関節鏡視下手術とFAIの歴史/股関節の関節包周囲筋の解剖/股関節のバイオメカニクス/股関節運動療法の筋電図/グロインペイン症候群に対する治療/FAIに対する治療/股関節鏡手術後のリハビリテーション/グロインペイン症候群診療の未来/FAI診療の未来 などを取り上げる.また連載では,「クイズに挑戦! 運動器エコーとスポーツ外傷・障害」「暑熱対策最前線」他を掲載.

Medical Practice 2026年3月号
大腸癌~実地医家が担う診療のフロントライン 特集記事として,[対談]“忙しい診療”の中でもできる大腸癌対策・予防,[総説]今さら聞けない大腸癌の疫学とリスク因子,わが国における大腸がん検診の現状と課題,[セミナー]症状から疑う大腸癌,[治療]進化する内視鏡切除術の適応と実際,免疫チェックポイント阻害薬の適応拡大 等.また連載では,[One Point Advice][今月の話題][知っておきたいこと ア・ラ・カルト][心電図がよめる,得意になるシリーズ]他を掲載.

病理と臨床 2026年3月号
血管炎 特集記事として,血管炎の診断と治療─近年の進歩を中心に─/大動脈を侵す血管炎─高安動脈炎を中心に─/結節性多発動脈炎を主体とする中型動脈を侵す血管炎/冠動脈を侵す血管炎─川崎病を中心に─/Buerger病を主体とする下肢動脈を侵す血管炎/腎生検における血管炎/皮膚生検における血管炎 等を取り上げる.また連載では,[マクロクイズ],[がん薬物治療選択に関わるバイオマーカー検査],[今月の話題] 他を掲載する.
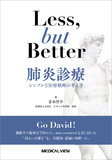
Less, but better 肺炎診療
シンプルな治療戦略の考え方
肺炎を疑うとき,数多くの病原菌と抗菌薬を前に,「どの薬剤を選ぶべきか」と迷う場面は少なくない。本書は,そうした臨床の実感を出発点に,“Less, but Better” をコンセプトとして肺炎診療を再整理した実践書である。
複雑に見える原因菌を,「気腔」「消化管」「環境」という3つの出どころに分類し(三群),現場で最低限押さえておくべき数種類のessential drugを明確に提示。それらを市中肺炎,院内肺炎,医療・介護関連肺炎といった各カテゴリーに正しく振り分けることで(三型),原因菌が特定できない状況でも,過不足のない抗菌薬選択へと導く考え方・選択の軸を解説する。
まず各論で肺炎診療に必要な知識の全体像を整理し,続く事例検討およびQ&A形式のREVIEWを通して,「三型・三群」の考え方を実践的に身につけられる構成となっている。
あえて「必須ではない部分(what is NOT essential)」を削ぎ落とし,診療の核となる「実践知」を身につけるための画期的な一冊。
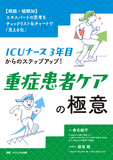
ICUナース3年目からのステップアップ! 重症患者ケアの極意
【先読み力&優先順位の見極め力が身につく!】
刻々と状況が変化するICUで「何を優先すべきか?」で迷うあなたへ。観察すべき項目・優先順位が“パッ”とわかるチェックリストとチャート、ICUでよく遭遇する15の患者像を網羅した解説で、現場で迷わず動けるようになる。ICUで現場力を高めるために必要な知識と実践をつなぐ1冊!

Clinical Engineering Vol.37 No.3(2026年3月号)
臨床工学ジャーナル[クリニカルエンジニアリング]
【特集】臨床工学技士が使用する薬剤の知識とピットフォール 臨床工学技士法の改正により、臨床工学技士が薬剤投与に関与する機会が増加している。本特集では、血液浄化・循環・呼吸などの領域で使用される薬剤の知識と投与時のピットフォールについて、薬剤師と臨床工学技士の視点からわかりやすく解説!

画像診断 Vol.46 No.3(2026年3月号)
【特集】診断に役立つ腹膜の解剖と疾患知識 腹膜・間膜を主役に、画像診断の視点から体系的に整理。解剖学的理解と病態生理を踏まえ、断層画像上でどのように描出されるのかをわかりやすく解説。腹膜を軸に読影する視点をもち、腹部画像診断の理解が一段深まる特集!

VisualDermatology Vol.25 No.3(2026年3月号)
【特集】脂腺系腫瘍およびその類縁疾患を考える ―脂腺癌を見逃すな! 脂腺系腫瘍の病理診断にかかわる基本的な知識、新しい分類などについて整理し解説。さらに日常診療で知っておくべき事項や新しい疾患概念も詳述!さらには、脂腺癌の診断と予後の最新情報、病理診断における問題点についても解説!

実験医学 Vol.44 No.4
特集1:疾患・生命の暗号を解き明かし、生成する ゲノム言語モデルを使う!/特集2:イノベーションを育む研究エコシステム
【特集1】AIを使ってゲノム配列から,疾患の原因予測や植物育種の新規デザインまでを実現する! Evo2,HyenaDNA,PlantCAD2など,最新のAIモデルを活用した実例をご紹介/【特集2】研究成果を社会につなぎ,次のイノベーションの資金を獲得する.サイエンスを加速させる産業との循環に踏み出そう!

外来処方ドリル
診察室でよく出合う症例を追体験、「なんとなくの対症療法・Do処方」から脱却する
「これから外来に出るのが不安」「これまでなんとか外来をこなしてきたけど,これでいいのだろうか」初心者からベテラン医師,看護師や薬剤師まで,外来にかかわるすべての医療者を助けます.一般外来でよく診る疾患が網羅できる,大好評のレジデントノート特集が大幅ボリュームアップで単行本化.薬物療法,食事・運動指導,薬の悩みまで解決する力が身に付く.

看護管理学習テキスト 第4版 第1巻 保健医療福祉制度・政策論 2026年版
社会保障制度や保健医療福祉制度の変遷のほか、新たにグローバルヘルス政策とその展望を詳述!
わが国の社会保障制度や保健医療福祉制度の変遷、政策の動向をふまえ、地域のヘルスケアサービスに貢献するために必要な自施設の機能・役割と多組織との連携、看護管理者の役割等のほか、グローバルヘルス政策とその展望等について詳述しています。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫

看護管理学習テキスト 第4版 第2巻 看護サービスの質管理 2026年版
質の高い看護を支えるマネジメントのあり方を学びます
近年、注目される組織論や社会ビジョンの紹介を通じて、現代のマネジメントの多様な考え方を示します。
また、目標管理やBSCといった経営視点から、患者安全や看護管理における研究の推進まで体系的に解説。さらに、第三者評価やデータを活用した看護の質改善といった現場で不可欠な視点も盛り込み、看護管理者に求められる知識と判断力を養います。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫

プライマリケアで診る慢性心不全 改訂2版
心不全パンデミックを食い止めるための実践バイブル
「心不全パンデミック」が現実となった今,生活習慣病を診るプライマリケア医こそが心不全診療の最前線です .本書は最新ガイドラインや臨床試験結果を踏まえ,「日常診療での使いこなし」に焦点を当てて内容を刷新しました .無症候な「前心不全」を捉えるBNP活用の勘所から,リスク群として位置づけられた慢性腎臓病(CKD)の管理,増悪を防ぐ初期対応まで網羅 .より良い診療の根幹となる実践的な知恵が詰まった,かかりつけ医必携の最新版です .

看護管理学習テキスト 第4版 第3巻 人材管理論 2026年版
人材育成・活用の理論と実践および労務管理に必須の法制度を体系的に解説します
専門職としてのキャリア発達・開発をふまえて、人材育成や教育に関する諸理論をわかりやすく紹介しながら、マネジメントの実際につなげていきます。
現役の看護管理者と研究者による、今の時代に求められる実践的な管理論です。また、人事システムや賃金制度・賃金体系の基本的な知識を押さえたうえで、現場での体制整備や労務管理に必須の法律について学べる構成です。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫

看護管理学習テキスト 第4版 第4巻 組織管理論 2026年版
経営学の諸理論や考え方を用い、また法律の解釈や経験知を通じて、看護職が所属する組織を多面的にとらえる
看護や医療の現場の例を挙げながら、主要理論に基づいて、組織の成り立ち・構造、組織分析・組織開発、組織文化、組織変革、組織倫理を詳述します。
また、地域のヘルスケアニーズに貢献する多様なサービス提供のあり方について、行政・病院・施設・起業など幅広く学べる構成です。地域における危機管理として、新興感染症を含む災害マネジメントについても解説します。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫

看護管理学習テキスト 第4版 第5巻 経営資源管理論 2026年版
看護と経済・経営を結びつける視点や、看護管理者に必須な「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の知識が幅広く学べます
限られた資源を活用し、効果的かつ効率的なケアを実践するために必須の経済・経営およびサービス、マーケティングの基本的知識について解説しています。
また、組織の管理に必要不可欠な4つの資源である「ヒト(人的資源)」「モノ(物的資源)」「カネ(資金的資源)」「情報(情報資源)」を軸に章を構成し、看護管理者が押さえておくべき知識を幅広く学べます。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫

看護管理学習テキスト 第4版 別巻 看護管理基本資料集 2026年版
看護に関する基本文書と、看護管理に欠かせない重要法令・公的文書をもれなく収録しています
看護管理者が、日常の業務を無用な迷いにとらわれずに行ううえで必要となる情報をセットしました。
看護に関する基本文書と、看護管理に欠かせない重要法令・公的文書を満載したアーカイブです。
第1部は、看護の理念をつむぐための土台となる思想や原理が、文書として収載されています。第2部は、専門職としての実践が法令によってどう規定され、守られているのかを知るために欠かせない文書が示されています。
≪本書は第4版(2026年版)第1刷の電子版です≫
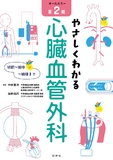
術前~術中~術後まで
やさしくわかる心臓血管外科 第2版
2018年に出版した初版を、さらにわかりやすくリニューアルしました。
編著の千葉西総合病院では、国内最速で最新機器「ダヴィンチ5」を取り入れ、低侵襲手術を行っています。
最先端の現場だからこそわかる、ロボット支援下手術でおさえるべきポイントをしっかり掲載しています。
また、術式別の項目を設けたことで、術前~術中~術後にどんな看護をすべきか、患者さんが今どんな状況なのかをパッと見て理解しやすくなりました。
解剖や検査・薬などの基礎知識から、周術期管理、補助循環やリハビリテーションまで、これ1冊で心臓血管外科看護のことがやさしくわかります。
心臓血管外科について知りたいとき、まずは本書をご覧ください。
心臓血管外科に初めてかかわる方にも、学び直したい方にも、後輩に指導したい方にもオススメです。
<本書の特徴>
・最新のロボット支援下手術について、写真つきで解説
・心臓の解剖や疾患、検査や薬などの基礎知識を網羅
・術前~術中~術後まで、周術期管理が1冊でわかる
・補助循環・リハビリテーションのポイントが押さえられる
・手術の流れと看護が、フロー形式でパッとわかる
<おもな内容>
心臓血管外科看護に必要な基礎知識
PART1 心臓血管外科看護のポイント 術前
PART2 心臓血管外科看護のポイント 術中
PART3 心臓血管外科看護のポイント 術後
PART4 補助循環の看護
PART5 心臓血管外科手術後のリハビリテーション
PART6 術式別の看護

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
造血器腫瘍 第2版
腫瘍病理鑑別診断シリーズ「造血器腫瘍」,WHO分類第5版に対応した待望の第2版.初版刊行(2013)から13年.造血器系のWHO分類も第5版(2024)となり,分子分類がより重要視され,分類自体も細かく,複雑になった.また,2025年には造血器腫瘍の遺伝子パネル検査が保険収載されるなど,造血器腫瘍の診断を取り巻く環境は変化の只中にある.そうした状況を踏まえ,今改訂では,最新知見を盛り込み,精選した病理写真とともに病理診断の要点,鑑別ポイントを解説した.
