
社会保険旬報 №2969
外来医療からリハ 入退院支援、食事 働き方までを議論 ̶中医協・入院医療等分科会̶
中医協の入院・外来医療等の調査・評価分科会(尾形裕也分科会長)は6月19・26日、令和8年度診療報酬改定に向けて、「外来医療」、「データ提出加算」、「情報通信機器を用いた診療」、「働き方・タスクシフト/シェア」、「病棟における多職種でのケア」、「入退院支援」、「リハビリテーション」、「食事療養」をテーマに議論を行った。外来医療ではかかりつけ医機能の制度整備が本格化することを踏まえた対応、オンライン診療では適切な推進を図る論点、入退院支援では入院料や患者像により異なる対応、リハビリテーションでは各段階の役割に応じた切れ目のないリハビリテーションの観点などからさまざまな資料が示され、議論が行われた。

プチナース Vol.34 No.9
◆ナースの視点でコツを伝授 急性期実習マスターになる
◆異常波形をかげさんと簡単攻略! 心電図の覚えかた

≪診療報酬・完全攻略マニュアル≫
ビジュアル速解 診療報酬・完全攻略マニュアル 2025年4月補訂版
診療報酬点数表全一覧&レセプト請求の要点解説
2024年10・12月の一部改定,追加告示・通知等もすべて取り込んだ2025年4月現在の最新版!! 診療報酬点数表のあらゆる規定を一覧表にわかりやすく総まとめ!!
■2024年10月・12月の初診・再診・外来診療料の一部改定(「医療情報取得加算」「医療DX推進体制加算」の改定),6月の診療報酬改定後に発出された多数の追加告示・通知等もすべて収録した2025年4月現在の最新版!!
■請求・点検業務ですぐ調べたいときに便利な必携マニュアル。点数検索が飛躍的にスピードアップする画期的な1冊。
■各部の冒頭で「算定の決まり事」「計算手順」「レセプトの書き方」を具体的事例で解説。基礎的な臨床の図解も多数収録した,初心者にもわかりやすい絶好の入門書。診療報酬請求事務能力認定試験等の参考書としても非常に有効です。

アニメ・映画で学ぶ 子どもの発達と家族のかたち
理論からみえる看護のヒント
発達理論は,小児看護を実践するうえで,子どもや家族を理解するために欠かすことのできないものです.しかし,普段看護の現場ではあまり使われていない表現や文脈からなる内容を読み解かなければならないため,理論への抵抗感をもってしまう人も少なくありません.そこで,本書では,漫画やアニメ・映画作品のストーリーを通して,そこで描かれる子どもたちの成長発達,学びの過程をもとに発達理論をわかりやすく解説します.漫画やアニメ・映画好きな方,子ども好きな方はもちろん,子どもは苦手・接したことがないからわからないという方にもおすすめの一冊です.

NICUマニュアル 第6版
NICUの座右の書が11年振りの改訂。1989年初版発行以来、世界最高水準と名高い日本の新生児医療の発展とともに、その歴史を刻んできた。緊急時にすばやく参照でき、実践的かつ具体的な対処法が簡潔にわかる。
これまで通り実臨床における経験知に重きを置ながら、現在確立しているエビデンスを融合させ、より一層臨床に役に立つマニュアルとしてアップデートされた。122名の執筆陣による新生児医療の最前線がここにある。

胆と膵 2025年6月号
特集:胆道癌の早期発見をめざして

月刊/保険診療 2025年6月号
特集 虐待・DVを見逃さない~医療現場での見極め方と対応事例集~ 特集 虐待・DVを見逃さない~医療現場での見極め方と対応事例集~
Part1 虐待・DVの現状と対応マニュアル/森田展彰
Part2【鼎談】虐待・DVの問題をどう考えるか/石倉亜矢子,川﨑二三彦,古屋智子
Part3【ケーススタディ】医療・介護現場の虐待・DV対応/紫藤直美,松本葉子,山中京子
Part4 虐待・DVが増える社会病理とは何か
1 子ども虐待を見逃さない体制づくりはどうあるべきか/柏女霊峰
2 社会病理としてのDV・子ども虐待の特徴と加害者への対応/中村正
視点 美容医療と保険診療 /武田啓
連載
厚生関連資料/審査機関統計資料
月間NEWSダイジェスト
介護保険/医学・臨床/医療事故NEWS
めーるBOX
■エッセイ・評論
プロの先読み・深読み・裏読みの技術/工藤高
こうして医療機関を変えてきた!/長堀薫
NEWS縦断「薬機法改正」/武藤正樹
TREND/大江和郎
■医事・法制度・経営管理
医療機関のDATA分析“特別捜査官”シーズン2「リハ栄養口腔連携加算を検証せよ! PARTⅡ」/流石学
病院&クリニック経営100問100答「病院における地域活動の意義と実践」/小松大介
かがやく!事務部門/東京ベイ・浦安市川医療センター
■臨床知識
カルテ・レセプトの原風景【腎癌末期】病状の進行を認めたくない末期癌患者と家族への支援/小澤竹俊,武田匤弘
教えて! 川上先生 新型コロナウイルスのホントのこと/案:川上浩一,画:ぼうごなつこ
■請求事務
実践DPC請求Navi/須貝和則
点数算定実践講座/圓山研介(協力:市川静夫)
レセプト点検の“名探偵”/野中義哲
保険診療オールラウンドQA
読者相談室/杉本恵申
休載:日本の元気な病院&クリニック,医療事務Openフォーラム
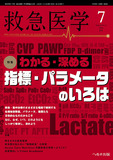
救急医学2025年7月号
わかる・深める 指標・パラメータのいろは いつも臨床でお世話になる検査数値、パラメータ、指標たち。身近な存在だからこそ、振り返る機会はあまりないかも。頻用パラメータの、なぜ・なに・いつ・どのように、を基礎から学んで深めよう。
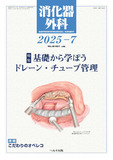
消化器外科2025年7月号
基礎から学ぼう ドレーン・チューブ管理 消化器外科領域の術中・術後、管理・評価・治療に欠かせないドレーン・チューブの留置。その意義や分類、適応といった基礎知識から、各手術での適切な留置法・管理法といったノウハウまで、この1冊で網羅する。

臨床心理学 第25巻第4号
トラウマインフォームドケア TIC(トラウマインフォームドケア)に第一線で取り組む臨床家・支援者が、各領域での必要性や実践内容、困難点、組織づくりの工夫を初学者向けに紹介する。

J-IDEO (ジェイ・イデオ) Vol.9 No.4
【Special Topic】抗菌薬の持続投与を再考する Special Topic「抗菌薬の持続投与を再考する」
今号では,抗菌薬の「持続投与」について,薬物動態・薬力学(PK/PD)の視点から松元一明先生にご解説いただきました.持続投与により治療効果向上が見込まれる抗菌薬もあれば,理論上は有効でありながらエビデンスが蓄積されていない抗菌薬もあり,各薬剤について現時点の知見がわかりやすくまとまっています.OPAT(外来静注抗菌薬療法)についても取り上げていただき,今後の実臨床応用を見据えた内容になっています.最新の知見と実践的な示唆が詰まったSpecial Topic,是非ご一読ください.
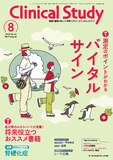
クリニカルスタディ Vol.46 No.9
【特集1】
測定のポイントがわかる
バイタルサイン
〔執筆〕渡邉 惠
実習で行う機会の多いバイタルサイン測定。手順や測定値に迷わず対応できる自信はありますか? 本特集では、バイタルサインの基礎知識と測定時に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。自信をもって実習に臨めるよう準備しましょう!
【特集2】
各分野のエキスパートが推薦!
将来役立つおススメ書籍
〔執筆〕山本 健人、飯田 恵子、谷原 弘之、鶴屋 邦江、今西 洋介
もうすぐ夏休み。いつもよりゆとりができるこの機会に、読書で視野を広げてみませんか? 今回は、医療・看護界で活躍するエキスパートが、将来役立つ書籍を紹介します。今のうちに読めば、「あのとき読んでよかった!」と思える日が来るはずです。

看護学生 Vol.73 No.5
【特集1】
夏休みに遅れを取り戻そう! 復習まるごとガイド
夏休みは前期に学んだ内容の復習をするいい機会です。この特集では,先輩が夏休みに作成した復習ノート,具体的な学習内容,勉強スケジュールの立て方などに ついて紹介します。夏休みを有効に使って後期に向けて準備しましょう。
【特集2】
進学コースを知ろう
准看護師が看護師になるための看護師学校 養成所2年課程は,通称“進学コース”とよばれています。その種類,授業時間,授業内容,受験科目,費用などのほか,全国にある進学コースを紹介します。

救急・ICUで「終末期ケアを実践する」ということ
“どう対応したらいいかわからないから、ベッドサイドに行くのがつらい・・・”
正解がないからこそ知りたい「エキスパートによる実践知」をひたすら具体的に
終末期ケアは、予後が比較的長いがん領域を中心に発展してきました。
しかし、救急・ICUでは時間的余裕がなく、本人の意思がわからないまま終末期を迎えることや、家族が患者さんの生命にかかわる決断をせざるを得ないことが多く、かかわるすべての人たちにとって、大きな心理的負担となります。
ガイドラインやプラクティスガイドもありますが、どうしても“それを、どう実践におとしこんだらいいのか”がわかりづらいのが実情です。
加えて、個別性も大きく、絶対的な正解がないからこその悩ましさもあります。
エキスパートが自らの実践をもとに生きたスキル・実践的なヒントをあますところなくまとめた充実の1冊です。

トラウマと解離の文脈
ピエール・ジャネの再発見
フロイトに先駆けて解離とヒステリーの研究と臨床に携わったピエール・ジャネの業績を解き明かし,現代のトラウマ臨床に甦らせる試み。

Heart View Vol.29 No.8
【特集】ALL about 心房細動

臨牀透析 Vol.41 No.7
■特集:透析患者の心臓病のすべて-インターベンションを中心に
診断:従来の心エコーや心筋シンチグラフィーに加え,FFR-CT や心臓MRI などの先進的画像技術により,透析患者特有の高度石灰化やびまん性病変,無症候性虚血の評価を示して頂いた.
治療:「ISCHEMIA 試験」以降,薬物療法と血行再建の適応が見直され,PCIとCABG の選択における透析患者特有の課題についても詳細に論じられている. TAVI やTEER といった低侵襲治療が高齢・ハイリスク透析患者にも適応されるようになりつつある.さらに,心不全や不整脈への対応,心臓リハビリ,看護,周術期管理など,多面的アプローチの重要性も示した.

がん看護 Vol.30 No.4
エビデンスに基づく 看取り期のケア 高齢者機能評価(GA・CGA)を活かした高齢がん患者のケア がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

乳腺腫瘍学 第5版
「乳癌取扱い規約(第19版)」「乳癌診療ガイドライン2022年版」に準拠し、乳腺診療の最新情報を反映するとともに、治療分野では高齢者乳癌の記載を充実させた。
前版からの治療法別の構成や多角的な視点からのアプローチはそのままに、知識の整理・アップデートにさらに役立つ内容とした。
乳腺専門医を目指す医師だけでなく、専門医や認定医となった医師、メディカルスタッフや医学生にも必携の一冊。
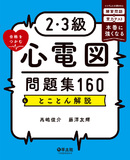
2・3級合格をつかむ心電図問題集160&とことん解説
ランダムに出題される練習問題と実力テストで本番に強くなる
心電図検定2級・3級対策の決定版!問題を系統的に並べるのではなく,本番と同様にランダムに出題しているため真の判読力が身につく!実力テスト1回分を含めて全160問を収録.合格するための知識・コツを,人気著者が豊富なイラストを用いて手厚く解説.とことん解いて,とことん理解できる問題集!
