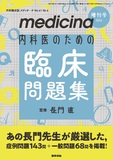
medicina Vol.61 No.4
2024年 04月号 増刊号
内科医のための臨床問題集
内科医のための臨床問題集 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

医師・PT・柔整・あはき師のための手技療法学
あらゆるセラピストに役立つ一冊
本書は,医師・理学療法士・柔道整復師・あはき師が,臨床現場で手技療法を「考えて使う」ための基本について,豊富な写真を交えながら解説した実践書です.評価編では,問診や触診から状態を見立て,治療へつなげる思考の流れを症例とともに提示し,施術編では,施術者と患者の姿勢,力の使い方,アプローチの選択などを具体的に示します.何から始めればよいかわからない初学者から,日々の施術を見直したい臨床家まで,幅広いレベル・職域の方に役立つ一冊です.
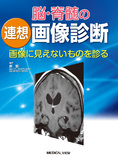
脳・脊髄の連想画像診断
画像に見えないものを診る
読影に臨む2人の研修医と指導医の軽妙でユーモアあふれる問答により,中枢神経,脊髄疾患の画像診断についてわかりやすく解説。絵合わせだけでなく,診断に至る論理を問答形式で解明する。
疾患の診断はもとより,CT・MRIとは何か,画像診断報告書の機微と落とし穴,そもそも画像診断とは何なのかを言語学や行動経済学を交えて解き明かす。画像診断に臨む際の心理にも踏み込んだ意欲作。症例画像に見える所見から,別のスライス画像に隠れた所見を連想し,さらに画像の向こう側の病態,患者さんの症状まで思いをはせる...。そんな放射線科医の診断の醍醐味を軽快にそして奥深く追求した書籍。

脳性麻痺 運動器治療マニュアル
脳性麻痺による運動障害は,小児神経科・整形外科・脳神経外科・リハビリテーション科が治療に当たり,症状に合わせたオーダーメイド治療が求められる。そのために合同カンファレンスを毎月開催している沖縄県立南部医療センターのノウハウを一挙公開!
児の5年後,10年後を見据えた継続的かつ包括的な治療を行うために必要な脳性麻痺の基礎知識から内科治療・外科治療,リハビリテーション,装具治療まで,臨床で使える実践的な内容を厳選してタイプ別の治療の使い分けを具体的に記載,また原因不明骨折を予防するためのチーム活動についても紹介。
徒手検査の仕方や児の観察の仕方,術前・術後の比較などの動画も付いた充実の1冊!

精神看護 Vol.24 No.3
2021年5月発行
「身体拘束最小化」をしていきたいが、どうしてもできない部分。それこそを話し合おう/特集2 看護学生、臨地実習体験のリアル
「身体拘束最小化」をしていきたいが、どうしてもできない部分。それこそを話し合おう/特集2 看護学生、臨地実習体験のリアル 2020年11月に『「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開』が発行され、身体拘束最小化のためのさまざまな考え方、方法が提示されました。しかしこの本を読んでもなお、現場では「それでもできない」事情や理由が残っています。
そこでこの座談会は、さらに身体拘束最小化に踏み出していきたいという意欲をお持ちの一般科病院と精神科病院の方々に声をかけ、「現場の状況や困りごとを率直に出し合い、話し合う中で、身体拘束最小化のためにできることを見つけていこう」という趣旨で開催させていただきました。
なお、貝田博之さんには身体拘束最小化に取り組む一歩先行く先輩として、アドバイザー的立場でご参加いただきました。『精神看護』2020年3月号の特集「松蔭病院の身体合併症病棟が身体拘束をやめることができた理由」で、貝田さんが所属する病棟が身体拘束最小化に挑戦し、結果を出すことができた経緯を解説していただいたことがあるからです。

超実践型 リアルワールドデータビジネスの教科書
「リアルワールドデータ(RWD)」という概念は、医療・ヘルスケア分野が先駆けですが、近年、ビジネス分野でも、この概念が広がりつつあります。そのため、ビジネスマンは、リアルワールドデータを学ぶために、医学書コーナーで本を探している状況です。そこで本書では、最近のニーズを踏まえ、ビジネスマンのために、リアルワールドデータの活用方法を詳しく掲載しています。リアルワールドデータについて、何も知らないという読者でも理解しやすい内容です。なお、mMEDICI株式会社の行うウェビナー先生の経験などを踏まえ、実践的です。本書を読んで、リアルワールドデータの可能性を広げ、企業ニーズも広げたい著者の思いが詰まっています。

看護のための臨床病態学 第5版
臨床看護師に必要な知識を過不足なく学ぶことができ,看護師国家試験にも対応できるコンパクトにまとまった病態学の教科書です.臓器別の解剖生理から始まり,各種疾患の病態を分かりやすく解説し,正しく学ぶことができます.また,理解を補うためのカラー図表や写真を数多く使用し,看護師国家試験出題基準に示された疾患については網羅しています.また,各種疾患の解説では,冒頭に「必修ポイント」として病態図とともに要点を簡潔にまとめ,復習しやすいよう工夫しています.さらには,3種のコラムを所々に設けており,看護師が必要とする知識や姿勢は「ナースの視点」,臨床医からの役立つ豆知識は「ドクターから一言」,専門性は高いが注目されている疾患などは「もうちょっと勉強」と多面的に興味を持てるように構成しました.改訂5版では,図表や本文の見直し,急速に進歩する治療に関しても最新情報を取り上げ,一層の記載の充実を図りました.

コメディカルのための専門基礎分野テキスト
医学概論 改訂8版
コメディカルにとって必要十分な医学の知識を分かり易く解説したテキスト.
コメディカルの方々にとって必要な医学についての知識を余すところなく,且つわかりやすく解説した入門書.医学とは何か,その歴史と現況についてから,人体の構造と機能,主要症状とその原因,主な疾患の解説と対応法,医療に関わる各種制度・法律・保険医療対策,疾病状況,医療従事者,介護保険など,医療とその周辺の事柄を網羅している.適宜図表を用いて平易に解説し,最新データを反映させた改訂第8版.

改訂5版 看護研究サポートブック
【計画書がうまくいけば看護研究はほぼ完成!】苦手意識をもつ人も少なくない看護研究。本書は、オリジナルワークシートを用いることで、そうした人も自然と看護研究のプロセスを踏みながら、看護計画計画書が作れるよう構成されている。また、看護研究の具体例も豊富に掲載し、書き方などがイメージできるよう工夫されている。

訪問看護が支える 在宅ターミナルケア 第2版
最期まで「その人らしさ」を支えるターミナル期のケアを実践するために、必要な知識・技術・心構えを知る
待望の改訂版!
好評書「訪問看護が支える 在宅ターミナルケア」の初版を全面的に見直しました。
令和6年度診療報酬・介護報酬改定を踏まえた加算情報をアップデート。さらに、非がん疾患も含めた症状緩和や、意思決定支援(ACP)と本人意思の推定、薬剤関連の情報などを更新・追加し、さらに充実させました。
在宅ターミナルケアの考え方と、訪問看護の役割をわかりやすくまとめています。
≪本書は第2版第1刷の電子版です。≫
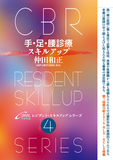
≪レジデント・スキルアップ シリーズ 4≫
手・足・腰診療スキルアップ
本レジデント・スキルアップシリーズ中の超ベストセラー。専門医の方から「あのころこれがあれば骨折患者を他科に紹介しなくてもよかった」としばしばいわれるほど、本書はレジデントだけでなく、救急、総合診療、内科、整形外科の専門医にとっても格好の外来診療の手引書。増刷のたびごとに常にアップデートされている、JPTEC,JATEC、ACLSの項目は医師のかたから救急救命士、看護師の方々にまで広く愛読されている。さらに、何よりの本書の特長は長年に渡って磨き上げられた、かゆいところに手が届く骨・関節の解剖イラストと著者の哲学に裏打ちされた、深い内容が平易ななじみやすい表現で分かりやすく解説されていること。どの診療科に進まれる人にも基礎知識として是非お勧めいたしたい1冊。

≪医学統計学シリーズ 5≫
新版 無作為化比較試験
―デザインと統計解析―
好評の旧版に加筆・改訂。
〔内容〕原理/無作為割り付け/目標症例数/群内・群間変動に係わるデザイン/経時的繰り返し測定/臨床的同等性・非劣性/グループ逐次デザイン/複数のエンドポイント/ブリッジング試験/欠測データ

臨床泌尿器科 Vol.79 No.10
2025年 09月号
特集 ラインナップ! 小児泌尿器科の手術,余さずお見せします〈特別付録Web動画〉
特集 ラインナップ! 小児泌尿器科の手術,余さずお見せします〈特別付録Web動画〉 泌尿器科診療にすぐに使えるヒントを集めた「特集」、話題のテーマを掘り下げる「綜説」、そして、全国から寄せられた投稿論文を厳選して紹介する。春に発行する書籍規模の増刊号は、「外来」「処方」「検査」「手術」などを網羅的に解説しており、好評を博している。 (ISSN 0385-2393)
月刊、増刊号を含む年13冊

≪Emer-Log2025年春季増刊≫
救急外来・ERの重要疾患 スピードマスター
【あるある訴えから緊急・重症疾患を見抜く!】診断がついていない患者が受診する救急外来で、「主訴」から、どう「疾患」を見抜けばよいのか、どんな検査・初療が必要なのか、さらにそれぞれの場面での動き方まで、疾患別に重要なポイントに絞って解説。救急の重要疾患を網羅した、困った時にサッとチェックでき、パッとわかる、救急ナース・研修医・若手医師必読の1冊!
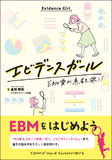
エビデンスガール
EBM愛が患者を救う!
●PICOからコホート研究、RCT、システマティックレビューまで、論文の読み方をやさしく解き明かす!
●医師、薬剤師、看護師問わず学べるEBMのレクチャー本
●小説のストーリーに沿って楽しくEBMを学べる!
EBMという言葉を知らない医療者はまずいないと思います。では、EBMを実践するとはどういうことでしょうか? そもそもエビデンスとは何でしょうか?
本書は「論文を自由自在に読めるようになりたい」「自分で解釈できる力を身につけたい」という医療者に向けて、数えきれないほどのEBMワークショップを開いてきた医師が語る、EBMのイロハや論文の読み方のレクチャー本です。大学生が主人公の小説形式で解説が進むので、サッと読めてわかりやすい構成です。本書を通じて学ぶことの楽しさを味わうことができます。

看護学生の勉強と生活まるごとナビ
自律的に過ごすための23のレッスン
看護学生に求められる「勉強」と「生活」を網羅!
看護学生に求められる「勉強」と「生活」について、イラストを交えてわかりやすく紹介するガイドブック。
学生生活をイメージできるよう、「看護とは」「看護師に必要な力」などを整理したうえで、講義・演習・実習それぞれの学びと面白さ、教科書の読み方やノートの取り方、定期テストや国家試験に向けた取り組みなどを具体的に示しています。
対人関係やコミュニケーションのアドバイスも、ぜひご活用ください。
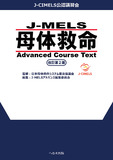
J-MELS 母体救命 Advanced Course Text 改訂第2版
J-CIMELS公認講習会
母体救命の集大成
重症化した母体に対応する医療従事者に向けた、母体救命のバイブル、改訂第2版。日本母体救命システム普及協議会(J-CIMELS)の公認講習会「J-MELS Advanced Course」 のオフィシャルテキスト。
産婦人科医に限らず、周産期に関わる麻酔科医、救急搬送に対応する救急医、産科危機的出血に対応するIVR医、重症化した母体に遭遇する助産師・看護師など、妊産婦に関わるすべてのメディカルスタッフへ。母体救命に必要な多領域のスキル(S)、どんな重症母体にも対応できる普遍的な診療アプローチ(A)、医療チームとして最大のパフォーマンスを発揮するためのマネジメント(M)を網羅し、各種ガイドラインに基づいた各分野エキスパートにより構成された「母体救命」のための必携の一冊。

脳血管内治療トラブルシューティング 脳動脈瘤編 改訂第2版
年々増加している低侵襲の脳血管内治療では,術中の出血や血栓症などの合併症対策に習熟することが求められる.本書は脳動脈瘤治療のエキスパートによる,様々な場面で使える手術のトラブル解決法を紹介.ケースを通じ,145点のイラストと229点の写真による臨場感あふれる貴重なテクニックが学べます.
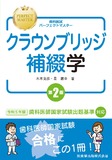
歯科国試パーフェクトマスター クラウンブリッジ補綴学 第2版
歯科医師国家試験合格にグッと近づくパーフェクトマスターシリーズ
出題基準改定(令和5年)に対応した改訂版,登場
歯科医師国家試験対策のために愛用されてきた『歯科国試パーフェクトマスター』シリーズが,国試の出題基準改定(令和5年)に対応して新しくなりました.最新の出題基準に対応した本書を活用して大切なポイントをしっかり抑え,歯科医師への道に進みましょう!
・直近の試験問題を精査して対策が記載されているので,各科目の大まかな出題傾向がつかめます!
・図や写真を多く用いているので,わかりやすく,覚えやすい!
・国試対策のほか,CBT対策や定期試験,各科目の授業の予習 ・復習にも活用できます!

施設基準等の事務手引 令和6年6月版
令和6年6月診療報酬改定に対応し新版を発刊。
診療報酬点数表で別に定められている人員や設備・施設などの基準をまとめました。
施設基準と定められた疾患等を網羅しています。
●診療報酬には、一定の基準(施設基準)を満たし、届け出ることによって、はじめて点数が算定できる項目があります。
本書は、この施設基準の全内容(医科・歯科・調剤の施設基準)を収載しました。
●基本診療料、特掲診療料それぞれの施設基準を項目別に収載。
関係する告示・通知・届出様式を整理して、関連する疑義解釈や診療報酬などの情報とあわせてまとめました。
●あわせて、診療報酬上、別に定める扱いになっている疾患や注射薬等も同様にすべて収載しています。
●医科のみならず、歯科と調剤に定められた施設基準についても収載、これ一冊で施設基準がすべてわかります。
●告示・通知の改正部分や新設の施設基準がわかるよう編集するとともに、主な改正のポイントをまとめています。
●自院の最適な診療報酬算定のための施設基準を知るために、ぜひご活用ください。
