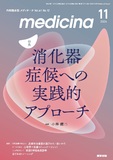
medicina Vol.61 No.12
2024年 11月号
特集 消化器症候への実践的アプローチ
特集 消化器症候への実践的アプローチ 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

健康運動指導士試験パーフェクト予想問題集
健康・体力づくり事業財団が認定する「健康運動指導士」の試験対策のための問題集.2024年度版の健康運動指導士養成講習会テキストの改訂内容に対応.試験本番を想定した4択問題を400問と,全科目からなる模擬問題を2つ収載.本書シリーズ『健康運動指導士試験 要点整理と実践問題 第4版』と合わせて使うことでさらなる学習効果が期待できる.

整形外科 術後理学療法プログラム 第3版
リハスタッフに向けに「理学療法に必要な解剖・疾患の知識」,「手術の知識」を整形外科医が丁寧に解説。それに沿ってPT,OTが「術後理学療法プログラム」,「理学療法の進め方」を解説したものを1セットとし,疾患ごとにまとめた。「解剖,疾患,手術の知識」を読み,術式や術後の禁忌の知識を得ることで各疾患に対してより的確にアプローチできるように構成されている。各疾患の術後プログラムの流れが図で示されているので,一目で全体を把握できる。
改訂にあたって術式などの記載内容は最新の情報に改め,さらに,近年増加している高齢者に対する手術の術式などを追加した。

Heart View Vol.29 No.1
2025年1月号
【特集】12誘導心電図徹底攻略:治療はもう始まっている!
【特集】12誘導心電図徹底攻略:治療はもう始まっている!

Dr.浅井の本当にやさしい
ねころんで読める医療統計
【ぜったいに挫折させない統計の基礎と選び方】統計を理解しようと努力しても挫折していた人、これから学ぶ人にぜひ読んでもらいたい一冊。統計用語、考え方の基本が身近な例ですんなり理解でき、数多くある統計法のなかから、自分の研究内容にあわせた統計が選択できるようになる。各章に練習問題つき。

借金なし・コンサルなし・多店舗展開
女医の非常識なクリニック経営
コンサルなし,借金なし,開業初日から週3日外来,30代で2院目開業,合理的なミニマム経営,プライベート重視……常識に囚われない発想でそれら全てを実現してきた人気女医の経営ノウハウを詰め込みました.女性医師はもちろんのこと,多店舗展開したい開業医,女性医師や女性スタッフを採用したい男性医師,ずっと勤務医でいたい医師にも多くの共感や気づきがきっと得られる一冊です.

アセスメントができる検査値の読み方
【本書の特徴】
☑検査値の変化と疾患・病態の関連をふまえた検査値の読み方を解説しているから、検査値のアセスメントができるようになる!
☑日々の報告に検査値の根拠がもてるようになる!
☑呼吸機能・心機能など、高齢者特有の加齢に伴う検査値の変化を解説しているから、検査値のアセスメントに迷ったときに参考にできる!
【異常な検査値の読み方の例】
●感染症で、CRPとWBCが上がるのはなぜ?
●炎症で、Albが下がるのはなぜ?
●心不全で、BNPが上がるのはなぜ?
●肝障害で、ASTとALTが上がるのはなぜ?
●脱水で、BUN/Cre比が上がるのはなぜ?

初学者にも、ベテランにも役立つ音楽療法 効果・やり方・エビデンスを知る(第4版)
2006年の発行以来、改訂を重ねていた『補完・代替医療 音楽療法』。本書は、音楽療法の生み出す心理学的・生理学的効果について様々な研究結果をもとに解説し、また具体的な実践方法や成功のポイントまで、音楽療法の流れをまとめたものであった。
『補完・代替医療 音楽療法』の初版発行からこれまでの間、医療・看護における音楽への関心は高まり、音楽療法は、高齢者や障害児、精神疾患を抱える患者などをはじめ、幅広い分野で取り入れられるようになってきた。それに伴い、音楽療法士の国家資格化・音楽療法の保険点数化の声も生まれ、需要は高まってきている。
この度、新たな執筆者を迎え、書名も新たに『初学者にも、ベテランにも役立つ音楽療法 効果・やり方・エビデンスを知る』(第4版)としてリニューアルした。音楽療法の需要が高まるなか、音楽療法士だけでなく、看護学生、看護師、医療従事者にも知ってほしい音楽療法の知識をここに集約した。音楽療法のやり方や効果、エビデンスをまとめ、実際の臨床に役立つ1冊となっている。また、ホスピス・緩和ケアにおける音楽療法セッションの映像付き。
本書は、人工呼吸管理に苦手意識をもっている医師や医療従事者向けに、日本呼吸ケア教育研究会が行っている好評な人工呼吸管理のワークショップを書籍化しました。人工呼吸管理を基礎からしっかりと体系的に伝えた内容で、また、そのワークショップで伝えている内容もWEB動画で学べるようにしました。本書を読み、WEB動画をあわせて見ると、独学で、人工呼吸管理がしっかり学べる1冊になっています。
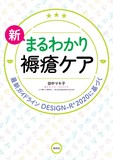
最新ガイドライン、DESIGN-R2020に基づく
新 まるわかり褥瘡ケア
褥瘡予防・治療・ケアの全体がぐるっと見渡せる1冊。
初心者からベテランまで、すべてのナースに必要な褥瘡ケアのup to dateを網羅しました。
スキン-テア、MDRPU(医療関連機器圧迫創傷)、IAD(失禁関連皮膚炎)、Wound Hygiene(創傷衛生)なども詳述しており、新しくなった「DESIGN-R2020」「褥瘡予防・管理ガイドライン」第4版・第5版にも準拠しています。
豊富な褥瘡の症例写真で、アセスメントのポイントもよくわかります。

社会保険旬報 №2954
2025年2月11日
《レコーダ》 『日本在宅療養支援病院連絡協議会が研究会 在支病が地域医療の中心に地メディの理念が重要』
《レコーダ》 『日本在宅療養支援病院連絡協議会が研究会 在支病が地域医療の中心に地メディの理念が重要』
日本在宅療養支援病院連絡協議会(鈴木邦彦会長)は昨年12月22日、東京都内で有識者らによる講演や意見交換などで構成する研究会を開催した。基調講演では厚労省の高宮裕介大臣官房参事官が登壇し、今後の地域医療における在宅療養支援病院(在支病)の重要性を強調。「地域包括医療病棟の開設に向けて」と題したシンポジウムでは、厚労省保険局医療課の林修一郎課長が講演したほか、いち早く地域包括医療病棟(地メディ)の入院基本料を算定する体制を整えた病院のトップが事例を紹介した。シンポジウム「介護施設との連携:現状と課題」では、厚労省老健局老人保健課の堀裕行課長が登壇したほか、それぞれの地域で、医療・介護連携などに関する取り組み事例を共有した。同研究会の要旨を掲載する。

三尖弁治療スタートガイド[Web動画付]
カテーテルインターベンション時代の道しるべ
TriClip,PASCALなど新たなカテーテル治療を中心に,重症度分類,心エコーなどによる画像診断・評価,治療法の選択,外科治療など,三尖弁閉鎖不全症治療を成功させるためのTipsを豊富なカラー画像(動画付き)とともに解説。循環器診療にかかわる医師必携の実践的入門書。

社会保険旬報 №2953
2025年2月1日
《インタビュー》 『不断の改革を通じて、持続可能な医療提供体制と皆保険制度を確保』厚生労働大臣 福岡資麿
《インタビュー》 『不断の改革を通じて、持続可能な医療提供体制と皆保険制度を確保』厚生労働大臣 福岡資麿
団塊世代がすべて75歳を超える2025年を迎え、今年は社会保障制度にとって節目の年となる。昨今の物価・賃金上昇や人手不足など経済社会環境の変化もあり、医療・介護の課題は山積している。医療提供体制の改革では、医師偏在是正や新たな地域医療構想の実現に向けた議論が進んでおり、今年はその具体化が期待される。超高齢社会を乗り切るには医療DXが不可欠だがそのカギとなるマイナ保険証の普及は道半ばで利用促進が望まれる。そして、これらの前提となるのは、国民皆保険制度の持続可能性の確保だ。こうした重要課題の陣頭指揮をとる福岡資麿厚生労働大臣に対応策をきいた(取材日は2024年12月25日)。

胆と膵 2025年6月号
2025年6月号
特集:胆道癌の早期発見をめざして
特集:胆道癌の早期発見をめざして
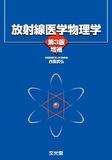
放射線医学物理学 第3版増補
放射線医学の進歩,それを支援する放射線医療技術学の進歩は目覚ましく,医療人として,その基礎となる放射線医学物理学を理解することは重要である.本書では放射線の性質,放射線と物質との相互作用など,放射線医学物理学の基礎領域を中心に記述.診療放射線技師養成校のカリキュラムに則った編集により大好評を博した本書第3版に,約70頁もの問題・解答集を添えた増補版.診療放射線技師を目指す学生必携テキスト最新版.

臨牀消化器内科Vol.30 No.07
2015年6月増刊号
【特集】胃癌の診療
【特集】胃癌の診療 臨牀消化器内科 Vol.30 No.7 増刊号は『胃癌の診療』
まず胃癌診療に必要な基礎知識として罹患率,死亡率,胃癌の危険因子,Helicobacter pyloriとの関係,EB ウイルス,遺伝子変異,エピジェネティクス,萎縮性胃炎,腸上皮化生などを取り上げている.
胃癌の診断に関しては,腫瘍マーカー,画像診断としてX 線造影,CT,MRI,PET 検査を取り上げ,内視鏡診断,生検診断,切除標本診断などを取り上げている.
胃癌の治療では,治療ガイドライン・ESD/EMR ガイドラインの概要,早期胃癌に対する内視鏡治療,外科標準手術,腹腔鏡下手術,術前・術後補助化学療法,化学療法,緩和治療,肝転移に対するアプローチ,腹腔内化学療法,放射線療法,免疫治療,さらには漢方の役割まで取り上げ,胃癌類縁疾患についても述べており,まさに現在の『胃癌の診療』のすべてを取り上げている.

臨牀消化器内科Vol.32 No.07
2017年6月増刊号
【特集】大腸癌の診療
【特集】大腸癌の診療 臨牀消化器内科 Vol.32 No.7 増刊号は『大腸癌の診療』
「胃癌死亡数の減少が達成されているにもかかわらず,大腸癌はどうかというと,道半ばであり,未だに罹患数および死亡数は右肩上がりである.大腸癌をいかに克服していくかという視点に方向転換をはかりながら,診療,研究を遂行していく必要があり,まだまだやるべきことは山積している」と序文でも述べられています.

≪ジェネラリストBOOKS≫
薬の上手な出し方&やめ方
なんとなく出し続けていたこの薬、他科でもらっているあの薬、必要? やめる? 続ける? 薬を入り口に、総合医と薬剤師であれこれ話し合ってみました。「やめる根拠」と「続ける根拠」、「上手な処方」や「減薬」のヒント、そして薬の話にとどまらず「診療のコツ」がそこここに。専門医による「上手な処方指南」もあります。答えは1つではない。正しい答えがあるとも限らない。けれど、考え続ける先に道はある。

誰でもわかるNPPV
近年増えてきたNPPV(非侵襲的陽圧換気)について、適応の判断、機器の操作とトラブル対応、合併症の予防、緊急対応、退院後の生活支援と指導など、最新の知識・技術と管理のポイントをビジュアルかつコンパクトにまとめました。

理学療法ジャーナル Vol.55 No.3
2021年3月発行
特集 重症化予防
特集 重症化予防 -

イラストで学ぶ系統的肺区域切除術 区切アトラス
切除実質と手術創の縮小という低侵襲手術は昨今の潮流となっている.その流れに乗って肺区域切除術は注目の術式である.肺区域切除術は結核の外科治療として発達したが,現在は,肺癌治療のトピックスとなっている.術後の肺機能をできるだけ温存しつつ,再発の抑制を追求した本術式のスタンダードがここにまとめられている.
