
INFECTION CONTROL(インフェクションコントロール)2025年5月号
2025年5月号
特集:清潔・不潔を交差させない!ベッドサイドにおける感染対策テキスト
特集:清潔・不潔を交差させない!ベッドサイドにおける感染対策テキスト
医療関連感染対策の総合専門誌『INFECTION CONTROL』は、すべての感染対策活動を全力で応援します。
「整理された最新情報が欲しい」というあなたのために、ピンチを乗り切る最新情報&指導ツールとともに、現場ですぐに生かせるトピックや領域で話題のテーマを分かりやすく解説します。
現場で活躍する執筆陣による、専門誌ならではの解説はICT・ASTメンバー必読!そのまま使えるイラストやパワーポイントなど、豊富なダウンロードサービスも充実です。

INFECTION CONTROL(インフェクションコントロール)2024年5月号
2024年5月号
特集:新人研修のためのベッドサイド感染対策マニュアル
特集:新人研修のためのベッドサイド感染対策マニュアル
医療関連感染対策の総合専門誌『INFECTION CONTROL』は、すべての感染対策活動を全力で応援します。
「整理された最新情報が欲しい」というあなたのために、ピンチを乗り切る最新情報&指導ツールとともに、現場ですぐに生かせるトピックや領域で話題のテーマを分かりやすく解説します。
現場で活躍する執筆陣による、専門誌ならではの解説はICT・ASTメンバー必読!そのまま使えるイラストやパワーポイントなど、豊富なダウンロードサービスも充実です。

Medical Technology 52巻6号
血液培養検査の基本と精度管理
血液培養検査の基本と精度管理
●血液培養検査は血流感染症診療において必要不可欠ともいえる検査だが,適切に実施されなければ,汚染菌の検出などにより不要な検査・抗菌薬治療を招くことがあり,これらは臨床現場や医療経済の面からも悩ましい問題となる.
●本特集では血液培養検査の精度管理にフォーカスし,適切な診断・治療につなげるための考え方や手法を,基本から解説いただいた.また,リソースが限られる夜間・休日の対応についても,意義や注意点,運用上のポイントなどを含め,実例を交えながら紹介している.

医療職のためのバランスト・スコアカード実践マニュアル 1版2刷
BSCを理解し,納得し,実行し,成果を上げる
・BSCを病院経営に役立てるためのノウハウが満載!
・医療BSCの第一人者が医療機関への正しい導入・運用法を詳述!

周産期医学52巻11号
成育基本法と医療的ケア児等支援法に基づく育児支援
成育基本法と医療的ケア児等支援法に基づく育児支援

小児の静脈栄養マニュアル
小児の静脈栄養の特徴は,現状を維持するだけでなく,児の成長も促すことにある。また,栄養剤の投与にあたっては,小児ゆえの各器官の未熟さ,栄養投与血管の細さ,また血管確保後の児の体動など注意すべきことが多くある。
本書は,まず1章で「小児の静脈栄養の基本を知る」として,栄養必要量,静脈栄養剤の種類・特徴,栄養評価,デバイスの選択・手技や,合併症対策・予防などを解説している。特に,静脈栄養剤は依然として小児用に特化した輸液製剤は少なく,各施設で作製されているものも多いため,栄養剤の作製時や成人用の栄養剤使用時の注意点などについて詳しく述べている。さらに,近年日本でも普及してきているNST(nutrition support team)についても,具体的なチーム活動や他チームとの連携などを紹介している。
2章では「小児医療の臨床で静脈栄養を上手に運用する」とし,臓器別の疾患に対して,どのように静脈栄養を行っていくかを具体的症例を交えながら解説している。さらに,低出生体重児や炎症性腸疾患,化学療法時や周術期などの特殊な病態に対する静脈栄養法も取り上げた。また,退院後の在宅での静脈栄養療法も掲載している。
本書は,小児の静脈栄養を余すところなく紹介し,即座に臨床で役立つ,小児医療に携わるすべてのスタッフ必携の1冊である。

レジデントのための画像診断アトラス
必ず理解しておくべき全身200疾患
画像診断の知識は,臨床研修修了後に専門研修を放射線科で行う場合はもちろん,全ての診療科・領域で研修を行う際にも不可欠なものである.
研修医にとって重要な全身の疾患を取り上げ,その症例画像(X線,CT,MRI,PET,超音波,内視鏡など)をまとめた1冊.
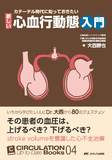
≪CIRCULATION Up-to-Date Books 04≫
カテーテル時代に知っておきたい 新しい心血行動態入門
いちから学びたい人にDr.大西から80のクエスチョン
【治療戦略を立てるための心血行動態の入門書】
カテーテル治療が全盛のいま、臨床で増える拡張不全あるいは重症心不全などの診断・治療には心血行動態の知識が欠かせない。これまで心血行動態を学んでこなかった若い医師には、80のクエスチョンから今後の治療戦略のヒントが得られる入門書である。

精神医学 Vol.66 No.10
2024年 10月号
特集 不登校の理解と支援
特集 不登校の理解と支援 精神医学領域のさまざまなテーマを毎号特集形式で取り上げ、第一線の執筆陣による解説をお届けする。5月号は増大号として領域横断的なテーマや、1つのテーマを幅広い視点から掘り下げる充実の内容。日々の臨床から生まれた「研究と報告」「短報」など原著論文も掲載している。 (ISSN 0488-1281)
月刊、増大号を含む年12冊

臨床雑誌外科 Vol.78 No.12
2016年11月増刊号
イラストで学ぶ消化器外科再建法のすべて
イラストで学ぶ消化器外科再建法のすべて 1938年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

高次脳機能障害の理解と診察
理学療法士や作業療法士などのメディカルスタッフに必要な神経内科学の知識をわかりやすく解説したテキスト.学校教育における専門基礎分野のテキストとして使用するにあたって反映せるべき2006年の初版以降の新しい知見や進歩,医学的見地などを盛り込むとともに,現状のガイドラインや教育カリキュラムなどを踏まえ,国試にも役立つよう内容を更新した待望の改訂2版

臨床画像 Vol.41 No.14
2025年10月増刊号
【特集】まとめておさえておきたい感染症の画像診断
【特集】まとめておさえておきたい感染症の画像診断

手術 Vol.78 No.2
2024年2月号
外科医のための臨床研究入門
外科医のための臨床研究入門
Academic surgeonを目指すのであれば,医学の3本柱である「臨床・教育・研究」に励む必要がある。本誌は言うまでもなく手術手技の解説を得意とする臨床雑誌であり,手術教育など,若手外科医向けの論文収載にも努めてきたが,研究を主テーマとする特集は今回が初である。日常の臨床に追われ,dutyの処理に埋没しがちな若手外科医が,どのように「臨床研究」を進めればよいか……。超一流の執筆陣が指南する。

2ページで理解する
標準薬物治療ファイル 第4版
本書は臨床で遭遇する主要70疾患について,ガイドラインに基づき標準的な薬物治療およびその管理をコンパクトに整理したチェック・リストである.SOAP形式で患者情報を記録し処方設計・管理を行う際,医師・薬剤師が何を確認し治療を進めていくかを箇条書き形式で2ページにまとめた.病棟業務や薬学教育における実務実習に必携の1冊.

手・肘の外科 診断と治療のすべて
近年,目覚ましい発展を遂げた手・肘の外科のすべてを集約。
解剖,画像診断,症候学といった基本的知識から,各疾患の病態,診断,治療まで,豊富な解剖イラストや症例画像とともに詳細に解説。診断から治療まで,日々の診療はもちろん,領域全体を俯瞰する系統的知識の整理にも役立つ一冊。

臨床外科 Vol.72 No.7
2017年7月号
特集 イラストでわかる!消化器手術における最適な剥離層〔特別付録Web動画付き〕
特集 イラストでわかる!消化器手術における最適な剥離層〔特別付録Web動画付き〕 消化器の手術は適切な剥離層の選択の技術であるといえる.当然のように,良性疾患における剥離層と悪性疾患における剥離層とでは,同じ臓器の切除においてもまったく違うものになるであろう.本特集では,根治性と機能温存を両立させた適切な剥離層の選択を主体として消化器手術を紐解いていく.

≪jmedmook 96≫
jmedmook96 もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ
◆ 忙しい外科系専攻医が避けて通れない「外科系当直」。本書は、そのストレスを解消し、救急外来での診療に自信を持って臨むための実践的ガイドです。
◆ 外科当直で見逃してはならない「レッドフラッグ」を示す疾患や、外因性に見える症状に潜む緊急性の高い内因性疾患への対応方法を徹底解説。初期診療において何を見逃さず、どこで専門医に相談すべきかを明確に示します。
◆ 肘内障や鼻出血の処置といった、自身で比較的安全に実施できる手技のコツも紹介しており、実践的なスキルアップが期待できます。
◆ 本書は、思考回路を繰り返し学ぶことで型を確立し、診療時間の短縮にも繋がる内容となっています。読めば一生役立つ知識とスキルを身につけられます。
◆ 新進気鋭のヒットメーカー三谷雄己先生、髙場章宏先生、看護師でイラストレーターの角野ふち氏のチームが贈る1冊です!
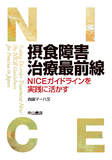
摂食障害治療最前線−NICEガイドラインを実践に活かす
わが国初のNICEガイドラインを活用した摂食障害治療の実践書。
エビデンス豊富なNICEガイドラインを、わが国の摂食障害治療に活かすべく、症例とともに詳細、かつ平易に解説。
プライマリケア医から専門医まで、摂食障害に関わる人、必読の1冊。

臨床外科 Vol.72 No.11
2017年10月号 (増刊号)
手術ステップごとに理解する 標準術式アトラス
手術ステップごとに理解する 標準術式アトラス 本特集では,外科医が扱う各領域において術式を細かく分類し,それぞれエキスパートの先生に術式ごとの手技上のコツを解説していただいた.各術式においてキーとなるステップのアトラスが呈示されているので,それぞれの手順を着実に理解できるものと大いに期待している.本邦の手術成績は世界トップクラスにあり,それを支えてきたのは標準術式の正確な理解と習熟であるといっても過言ではない.解説とアトラスを通じて,ぜひ各術式の根拠・理念をも会得していただき,本書を手に取った各人がこれからの手術診療での実践に活用されることを願ってやまない.

手術 Vol.79 No.5
2025年4月号
消化器外科における周術期栄養療法
消化器外科における周術期栄養療法
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集テーマは周術期栄養療法。総論3本・各論9本の2章構成で,消化器外科医にとって必要な栄養療法に係る基本的知識を概説し,領域別の実践例を収載した。いまだ十分なエビデンスがないテーマであるが,今後の発展が期待される「いま学んでおくべき特集」といえる。
