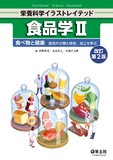
≪栄養科学イラストレイテッド≫
食品学Ⅱ 改訂第2版
食べ物と健康 食品の分類と特性、加工を学ぶ
食品そのものについて,正しい知識が身につく!日本食品標準成分表2020年版(八訂)に準拠し,食品ごとに種類や性質,成分などを解説.写真・図表はフルカラーで豊富に掲載,より深い理解に役立ちます.

≪栄養科学イラストレイテッド≫
食品学Ⅰ 改訂第2版
食べ物と健康 食品の成分と機能を学ぶ
食品の基礎知識がしっかり身につく!国家試験出題基準に対応した章立てで,栄養素など食品成分の種類や性質,加熱等による変化,人体でのはたらきなどをバランスよく解説.フルカラーの図表は見やすいと好評です.

≪栄養科学イラストレイテッド[演習版]≫
解剖生理学ノート 人体の構造と機能 第3版
覚えることの多い解剖生理学を効率よく学習できる書き込み式ノートがリニューアル!穴埋め問題を解くことで要点を整理できるから,管理栄養士国試対策,講義の予習・復習に最適です.姉妹版テキストとの併用が効果的

≪できる!画像診断入門シリーズ≫
頭部画像診断のここが鑑別ポイント改訂版
改訂で新たに疾患を追加し,132の頭部疾患を網羅!各疾患の典型例と,その鑑別疾患を見開きで解説.CT(単純・造影),MRI(T1・T2・FLAIR・造影)等,モダリティによる所見の違いもよくわかる!

CTGモニタリングテキスト 改訂版

≪看護学テキストNiCE≫
看護学テキストNiCE
小児看護学Ⅱ 小児看護支援論 改訂第5版
病気・障害のある子どもと家族への看護
主な小児疾患を網羅しながら事例を通して小児看護を学べる実践的テキスト.各疾患の一般的な子どもと家族の課題をまとめた経過図や,事例の情報をまとめた情報関連図を用いて看護の全体像をとらえ,看護過程をたどり看護実践について学べる.今改訂では,発達段階別から器官・系統別の構成に再編し,疾患と看護をより体系的に学びやすくしたほか,各章で扱う主要疾患および看護の全体像を概説する節を新設した.

根拠と事故防止からみた
老年看護技術 第4版
数多くの写真・イラスト・動画・付録で老年看護技術がわかる、みえる!
豊富な写真・イラスト・動画・付録で老年看護技術の手順を詳しく解説。高齢者のケアでは、高齢者の社会的背景や身体的・心理的特徴を的確にふまえたうえでの看護技術実践が求められる。本書は、全技術項目について(1)高齢者の特徴とアセスメント、(2)看護技術手順という構成で解説。手順には「根拠」「コツ」「注意」「事故防止のポイント」「緊急時対応」を豊富に記載。高齢者の看護に役立つ1冊。

看護研究 Vol.58 No.6
2025年 12月号
特集 未来型デジタル健康活躍社会の到来と日本版看護診断
特集 未来型デジタル健康活躍社会の到来と日本版看護診断 研究の充実がますます欠かせない時代。看護とは? 研究とは? という原点を見つめながら、変わらない知を再発見し、変わりゆく知を先取りしながら、すべての研究者に必要な情報をお届けします。誌面を通して、看護学の知と未来をともに築きたいと考えています。 (ISSN 0022-8370)
隔月刊(偶数月)、年6冊

病院 Vol.84 No.12
2025年 12月号
特集 赤字経営脱却 危機的状況からの経営改善
特集 赤字経営脱却 危機的状況からの経営改善 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

検査と技術 Vol.54 No.1
2026年 01月号
若手臨床検査技師、臨床検査技師をめざす学生を対象に、臨床検査技師の「知りたい!」にこたえる総合誌。日常検査業務のスキルアップや知識の向上に役立つ情報が満載! 国試問題、解答と解説を年1回掲載。増大号は年2冊(2・8月号)に発行。 (ISSN 0301-2611)
月刊、増大号2冊(2月・8月)を含む年12冊

脳神経外科 Vol.53 No.6
2025年 11月号
特集 小児脳腫瘍に向き合う 診断・治療から長期フォローアップまで
特集 小児脳腫瘍に向き合う 診断・治療から長期フォローアップまで 「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、横断テーマも広く特集する。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説する。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得できる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載している。掲載論文はPubMedで検索が可能。 (ISSN 0301-2603)
隔月刊(奇数月)、年6冊

生体の科学 Vol.76 No.6
2025年 12月号
特集 新組織学シリーズVI:心臓
特集 新組織学シリーズVI:心臓 生命科学・生物科学領域における最先端の研究を、毎号特集形式により紹介。神経科学はもとより分子生物学・酵素科学・栄養科学にいたる領域も含め、注目されるトピックテーマの最新情報を提供する。 (ISSN 0370-9531)
隔月刊(偶数月)、増大号を含む年6冊

医学のあゆみ295巻12・13号
脱毛症――研究と診療の進歩
脱毛症――研究と診療の進歩
企画:伊藤泰介(浜松医科大学医学部皮膚科)
・毛包は人の体の中でも極めてユニークな組織であり,組織幹細胞を有し,自律的に毛周期を繰り返すなど,他の組織にはみられない特徴を備えている.
・近年では,発生学,再生医療,幹細胞生物学,遺伝学,毛包免疫学,臨床医学,植毛学など,幅広い学問領域が毛包を中心に融合しながら進展し,心身の健康に至る広い生命現象を理解する糸口を与えている.
・本特集では,一見ニッチながらも奥深い研究領域である“毛包組織”をテーマに,基礎から臨床に至る最新の進歩を取り上げる.

皮膚科の臨床 Vol.67 No. 13
2025年12月号
悪性上皮系腫瘍
悪性上皮系腫瘍
日常診療でも遭遇する機会の多い“悪性上皮系腫瘍”の症例報告を多数収載。臨床写真はもちろん,診断に役立つ病理組織所見・各種画像検査所見を豊富に掲載しています。エッセイ『憧鉄雑感』も好評連載中!

眼科 Vol.67 No.13
2025年12月号
ぶどう膜網膜炎の画像診断検査―基本から最新の知識まで―
ぶどう膜網膜炎の画像診断検査―基本から最新の知識まで―
今月はぶどう膜網膜炎の画像診断検査の特集です。眼底造影検査から光干渉断層計(OCT)、そして自発蛍光やOCT angiographyまで、マルチな手法を駆使して後眼部の炎症を高精度で鑑別診断するために必要な基礎知識と最新情報が満載です。サイトメガロウイルスによる眼内炎症の綜説と併せて是非ご覧ください。ほかに老視矯正眼内レンズの動向やアフリベルセプト8 mg製剤の情報、投稿論文3篇など、来年の準備をしつつご一読いただければ幸いです。

臨牀消化器内科 Vol.40 No.13
2025年12月号
■特集:咽頭・喉頭病変の内視鏡診断と治療&■休刊記念:臨牀消化器内科40 年の歩み
■特集:咽頭・喉頭病変の内視鏡診断と治療&■休刊記念:臨牀消化器内科40 年の歩み
これまでの上部消化管内視鏡検査は胃癌の発見が主たる目的であり,咽頭・喉頭領域はただ通過するだけの臓器であった.しかしながら,咽頭表在癌が見つかるようになり,かつその発見頻度は経年的に増加が見られ,種々の内視鏡を用いた治療技術の進歩により高い確率で治癒切除が得られ,全体の予後向上に貢献している.こうした状況を多くの医師と共有し,多くの内視鏡医や消化器内科医に最新の知見を得てもらうことで,一人でも多くの方の咽頭・喉頭癌治療に貢献することが必要である.
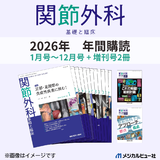
『関節外科』2026年 年間購読(1月号~12月号+増刊号2冊含む計14冊)
月刊誌『関節外科』の2026年の年間購読(電子版)です。
第一線の整形外科医が注目する関節を中心とした最新の研究・治療法を特集として取り上げ,各分野のエキスパートが臨床に直結した鋭い視点から解説しています。
年2回(3月・9月発売)増刊号を発行。

スポーツ運動医学
スポーツ運動医学は、アスリートや愛好家が安全にスポーツや運動を行い,健康維持・増進を図るための総合的な知識を育む学問です.機能解剖学や運動生理学から,競技力向上、疾病・外傷・障害の治療・リハビリテーションまでを扱います.本書はその多岐にわたる情報を分かりやすく解説した学生・初学者に最適な教科書です.

つながる薬学 臨床検査
―患者さんの検査値,薬学管理に活かせていますか?
臨床検査値がわかると,患者さんの体内で起こっている見えない変化も予測でき,処方監査や処方提案,副作用の早期発見などにつながります.本書は,解剖や生理の知識をもとに,検査値が示すこと,異常値が出たときに考えられる病態や検査値に影響を及ぼす薬について解説.検査値に関連した症例も充実させました.
病態の理解や薬物治療に欠かせない,臨床検査値の知識が学べる一冊です.

≪看護学テキストNiCE≫
看護学テキストNiCE
小児看護学Ⅲ 小児看護技術[Web動画付] 改訂第5版
子どもと家族の力を引き出す技
子どもの力を引き出し,処置やケアへの主体的参加に向けた看護を学べるテキスト.前版『NiCE小児看護学Ⅰ 小児看護学概論・小児看護技術』を分冊化し,本書は「小児看護技術」の巻として再編.各技術項目につき,Skill表を掲載.「アセスメント」「実施」「副作用・合併症と対応」「記録・報告」の各工程において,根拠やポイント,注意点を示した.今改訂では,「子どもと家族のセルフマネジメントを促す技術」の章を新設したほか,新たに12本の動画を収載.
