
疼痛治療における貼付剤の過去・現在・未来
整形外科医であったフランス王室公式外科医のAmbroise Paréは、16世紀に医師の心得として「to cure sometimes(時々治療する)、to relieve often(しばしば和らげる)、to comfort always(いつも癒す)」という言葉を残している。彼の言葉から痛みの治療について考えてみると、「侵襲的な治療は時々、薬物療法はしばしば、患者の痛みの訴えへの傾聴はいつも」と捉えることができる。要するに痛み治療における薬物療法の重要性が理解できる。
痛み治療での薬物療法において、重要な選択肢が貼付剤である。日本薬学会では貼付剤を「布やプラスチックフィルムに有効成分と基剤の混合物を薄く延ばし、皮膚表面の患部または皮膚を通して局所患部へ有効成分を到達させる、皮膚に粘着させて用いる製剤」と解説している。貼付剤の歴史は古く、皮膚を介して薬が体内に吸収される経皮吸収システムの概念が確立され、痛み治療では内服以外の薬の投与経路としての重要性が増している。
近年の経皮薬物送達システム(貼って皮膚から薬を送りこむ投薬方法、transdermal drug delivery system:TDDS)の開発は目まぐるしく、貼付剤には「経皮吸収型局所作用製剤(従来より湿布とよばれている製剤)」のみならず、「経皮吸収型全身作用製剤(パッチ、テープなどとよばれている製剤)」が広く臨床使用されるようになった。
経皮吸収型局所作用製剤は、皮膚から組織中に薬物が移行することで貼った部位周辺に効果を発揮することから、患部への直接効果が期待できる、使用が簡便、全身性の副作用が起こりにくいなどのことが期待され、痛みの治療の第一歩といっても過言でない。経皮吸収型全身作用製剤は、薬物が皮膚組織の毛細血管に移行し、全身血流を循環することで、経口摂取せずに効果を発揮、製剤の投与や中断が簡便に行える、投与の有無を確認しやすい、比較的作用時間が長いなどの利点があり、その存在感は増している。
『疼痛治療における貼付剤の過去・現在・未来』と題した本書では、疼痛治療における貼付剤の歴史と基礎、がん疼痛と慢性疼痛における臨床について、痛みの専門医が長年の経験をもとにわかりやすく解説した。是非、本書を痛みという身近な訴えにかかわるすべての医療者に、貼付剤という身近な存在による痛み治療の可能性を再考するための参考書としていただきたい。
(山口 重樹「序」より)

手術 Vol.79 No.10
2025年9月号
ロボット支援膵切除術をマスターする
ロボット支援膵切除術をマスターする
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集テーマはロボット支援膵切除術。同手術は,手術支援ロボットで行うメリットの大きい高難度手術であるが,その導入成果を最大化するためには従来手術と異なる独自のノウハウが求められる。先進施設で執刀するエキスパートの創意工夫や手技のコツを解説いただいた。

臨牀透析 Vol.41 No.10
2025年9月号
■特集「透析患者の呼吸器感染症」■特集「テナパノル症例集―使い方,副作用への対処」
■特集「透析患者の呼吸器感染症」■特集「テナパノル症例集―使い方,副作用への対処」
■特集「透析患者の呼吸器感染症」
本特集では呼吸器感染症の原因(一般細菌,結核・非定型抗酸菌症,真菌,ウイルス)に加え,呼吸器感染時における透析看護,誤嚥性肺炎に対する栄養リハビリテーション,標準的感染予防策と環境対策,ワクチン接種法などを取り上げています.また,最近注目されている呼吸サルコペニアの疾患概念,肺炎に伴う胸水の鑑別法についても,コラムとして執筆いただきました.
■特集「テナパノル症例集―使い方,副作用への対処」
本特集ではテナパノル塩酸塩の特性と至適投与法を明らかにする目的で,CKD―MBD 領域のエキスパートの先生方にお願いし,使用経験に基づく症例集をまとめることにしました.

J-IDEO (ジェイ・イデオ) Vol.9 No.5
2025年9月号
【Special Topic】狂犬病の経験から
【Special Topic】狂犬病の経験から
Special Topic「狂犬病の経験から」
今号のSpecial Topicでは,日本国内では遭遇することが稀な狂犬病症例を実際に経験された3名の先生方にご登場いただきます.個々の症状や経過を提示していただくとともに,3名の鼎談では初期症状の非特異性や恐水・恐風といった特徴的な症状,診断に至るまでの葛藤を語っていただきました.また,「グラム染色」をテーマに開催した特別座談会も収載します.

看護学生 Vol.73 No.7
2025年10月号
【特集1】
認知症のある患者さんとのかかわり
多くの人は,認知症のある患者さんに対して「かかわるのが難しい」というイメージをもっているのではないでしょうか。この特集では,認知症でみられる症状に ついて解説し,患者さんとのかかわり方につ いてQ&A方式で答えていきます。
【特集2】
実習記録8つのルール
実習中,「実習記録をどうやって書いていいかわからない」と悩む学生を多く見かけます。実習記録を“指導者に見てもらうためのもの”ではなく,“自分が看護について考え学ぶもの”にするためのポイントを紹介します。

クリニカルスタディ Vol.46 No.11
2025年10月号
【特集1】
キャラクターで楽しく理解!
内分泌のはたらき
〔執筆〕増田 敦子
解剖生理学のなかでも、内分泌系は特にはたらきをイメージしにくく、覚えるのが難しい分野ですよね。本特集では、ホルモンをキャラクター化してわかりやすく楽しく解説します。
【特集2】
“ 困った” を解決!お悩み別テスト勉強法
〔執筆〕ななえる
「何から手をつければいいかわからない……」そんなテスト勉強の“困った”を解決するヒントを、お悩み別に紹介します。本特集で、自分に合った勉強法を見つけて、自信をもってテストに臨めるようにしましょう!

消化器外科2025年9月号
集学的アプローチで挑む 胆道癌診療
集学的アプローチで挑む 胆道癌診療 さらなる予後の改善が望まれる胆道癌。治療成績向上を目指した集学的治療、すなわち、適切な外科手術とその適応判断、術前・術後の薬物療法と放射線療法、そしてconversion surgeryの最先端がここにある。

麻酔 Vol.74 No.09
2025年9月号
周術期のアレルギーに関する諸問題
周術期のアレルギーに関する諸問題 周術期アレルギーの最前線を網羅した実践特集です!アナフィラキシーの最新知見から、麻酔薬・筋弛緩薬・ラテックス・抗菌薬・輸血製剤・食物アレルギーまで、各分野の第一人者が臨床で役立つ知識と対応策を徹底解説。喘息発作への備えも含め、明日からの麻酔管理に直結する実用情報が満載の1冊です。

形成外科 Vol.68 No.09
2025年9月号
形成外科におけるQOL評価と心理社会支援
形成外科におけるQOL評価と心理社会支援 形成外科医が患者のQOLを支えるためには、どのような考え方とアプローチがあるのか。患者の幸せとは何か。形と機能の改善を目指す形成外科医は、何のために治療を行うのか。患者報告アウトカムを特集の軸に、医療者が抱く「患者のQOL」にまつわるさまざまな問いに真正面から向き合った1冊です。
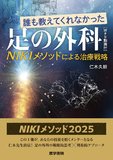
誰も教えてくれなかった足の外科[Web動画付]
NIKIメソッドによる治療戦略
足の外科手術で起こる「こんなときどうしたらいいのか」に答える
この1冊が足の外科を学ぶ人のメンターになる! 解剖学と病態の詳細な観察から本領域を開拓してきた著者直伝の「NIKIメソッド」による手術戦略を、100本を超える動画と豊富な画像を交えて惜しみなく解説。多様な症例をベースに、足の外科手術で起こる「こんなときどうしたらいいのか」という疑問に、エキスパートの視点から答える。ワンランク上を目指す足の専門医必読のテキスト。

尾内流 悪質口コミ対策実例集
医療機関ができること
インターネットでの口コミサイトで、一方的な誹謗中傷、虚偽のコメントに悩む施設が多い。近年は訴訟にまで発展しているケースも増えている。このような悪質な書き込みをされた医療機関も多く、口コミサイト管理者に内容の修正あるいは削除を求めても「単なる患者の感想」として、まともには対応されない。実際には、事実誤認、悪意ある虚偽の書き込みも多く、それが医療者を苦しめている。保険医協会に所属していた著者は、業務の一環としてこのような悪質口コミ被害に苦しむ医療者の相談を受け、これまで数多くのケースに対応してきた。“なにわのトラブルバスター”としても著名な著者は多くの経験から、投稿者自身と口コミ内容をよく見据えてサイトのガイドライン等と照会して反証をまとめ、投稿者あるいはサイト管理者に冷静に訴えることで、結果を得てきた。本書はこのような悪質口コミにどう対応し、どうアプローチし、どう働きかけるとよいかという著者の対応実例集をまとめたものである

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
協奏する看護組織をつくる
地域と病院と現場が自律して響き合うために
自ら考え、実践し、自律した組織づくりを目指す すべての看護管理者へ
医療・介護を取り巻く環境が大きく変化する今、一人ひとりが専門性を発揮し自律しながら協働する「協奏する看護組織」づくりが求められています。本書では、急性期病院でトップマネジャーを務めてきた筆者が、「協奏」を軸として目指してきた地域に根差した組織づくりの実践と、その考え方を紹介。実際のプロジェクトとプロセスを言語化し、しなやかで自律した組織の育て方を示します。自組織を振り返り、次の一歩を考えるために。

医学のあゆみ294巻10号
第1土曜特集
分子基盤に基づくメカノバイオロジーの臨床応用最前線
分子基盤に基づくメカノバイオロジーの臨床応用最前線
企画:曽我部正博(金沢工業大学人間情報システム研究所)
・「メカノバイオロジー」は2015年に「AMED-CREST/PRIME メカノバイオ(略称)」が発足して以降,研究者数が急速に増加し,現在はまさに成長期にある.
・日本のメカノバイオロジーは医系研究者の層が厚く,そのさらなる発展には分子・細胞レベルの基礎研究との連携が鍵となる.基礎と応用の隔たりはまだ大きいが,それは今後の発展の余地ともいえる.
・本特集では,分子センサーと疾患の連関,組織レベルでのメカノ応答,メカノバイオロジーの臨床応用やウェアラブルデバイスによる疾患の診断・予防・治療の役割など,各著者の成果を中心とした基礎研究と臨床研究に関して,鮮度の高い情報を5章にわたってまとめる.
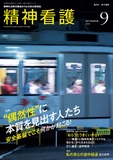
精神看護 Vol.28 No.5
2025年 09月号
特集 “偶然性”に本質を見出す人たち 安全基盤でこそ何かが起こる!
特集 “偶然性”に本質を見出す人たち 安全基盤でこそ何かが起こる! 変革の流れを見据えながら、精神科医療福祉に従事する皆さんにとって役に立つ情報をお届けします。
病や障害をもつ人の“心も身体も”ケアする方法をご紹介していきます。また、あらゆる年代・疾患のニーズに応えながら、社会課題に向き合う記事も取り扱います。挑戦する実践家、変革期を支える臨床家、やさしい環境をつくる人たちに注目します。 (ISSN 1343-2761)
隔月刊(奇数月)、年6冊

訪問看護と介護 Vol.30 No.5
2025年 09月号
特集 訪問看護のカスハラ、どうする? どうしてる!
特集 訪問看護のカスハラ、どうする? どうしてる! 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。
ケアに関わる情報はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を皆さんに代わって編集室が取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)
隔月刊(奇数月)、年6冊

病院 Vol.84 No.9
2025年 09月号
特集 転換点を迎えた医療介護連携
特集 転換点を迎えた医療介護連携 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.97 No.10
2025年 09月号
特集 なかなか治らない厄介な痛みと痺れ
特集 なかなか治らない厄介な痛みと痺れ 目のつけ処が一味違う耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門誌。「こんなときどうする!?」などの臨床的なコツの紹介から、最新の疾患概念を解説した本格特集まで、硬軟とり混ぜた多彩な企画をお届けする。特集2本立ての号も。「Review Article」欄では研究の最前線の話題をわかりやすく解説。読み応えのある原著論文も多数掲載。 (ISSN 0914-3491)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床婦人科産科 Vol.79 No.9
2025年 09月号
今月の臨床 産科・婦人科のメンタルヘルスケア 周産期から生殖,婦人科腫瘍まで
今月の臨床 産科・婦人科のメンタルヘルスケア 周産期から生殖,婦人科腫瘍まで 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、Web動画を用いて解説する記事もある。毎春に刊行する増刊号は必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊

臨床外科 Vol.80 No.9
2025年 09月号
特集 いざ談義! 噴門側胃切除後の再建法
特集 いざ談義! 噴門側胃切除後の再建法 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

月刊/保険診療 2025年8月号
特集 病医院の建築・設備・アメニティの現在~SDGs・感染・災害・経営の視点から~
特集 病医院の建築・設備・アメニティの現在~SDGs・感染・災害・経営の視点から~ 特集 病医院の建築・設備・アメニティの現在~SDGs・感染・災害・経営の視点から~
Part1 医療機関の建築・設備・アメニティの実事例10選
1 災害や感染症に強い設備の導入
2 最先端の技術で病院機能を強化
3 レイアウトの工夫でコミュニケーションを活性化
4 省エネ・CO2削減・廃棄物減量などの環境対策でSDGs
5 地域の気候の特徴を捉え,省エネルギー化を実現
6 患者にわかりやすく,連携しやすい構造の新病院
7 病院初の意匠登録,動線をゼロにした病室配置
8 院内の建築士が設計したユニバーサルデザイン
9 カラーユニバーサルデザインで色覚の多様性に対応
10 参加型のホスピタルアートで医療を身近なものに
Part2【鼎談】いかに建築・設備・アメニティを見直したか/伊関友伸,川崎淳一,小前貴志
Part3 プロフェッショナルに聞く
1 建設費の高騰と病院建築の未来/中山茂樹
2 病院の建替え・改修における施設整備の課題/筧淳夫
視点 緊急事態条項が招く未来/飯島滋明
第62回診療報酬請求事務能力認定試験(医科):問題と解説
厚生関連資料/審査機関統計資料
月間NEWSダイジェスト
介護保険/医学・臨床/医療事故NEWS
■エッセイ・評論
TREND/田渕典之
NEWS縦断「どうする病院経営危機」/武藤正樹
こうして医療機関を変えてきた!/吉澤徹
プロの先読み・深読み・裏読みの技術/工藤高
■医事・法制度・経営管理
医療機関のDATA分析“特別捜査官”シーズン2「”フォーミュラリ”の現状を把握せよ!」/流石学
病院&クリニック経営100問100答「医療機関におけるスマートフォン導入の進め方」/八木貴裕
かがやく!事務部門/武蔵野赤十字病院
■臨床知識
知らないじゃ済まない!~感染症・寄生虫の最新事情~「春~秋の野外活動はマダニによる日本紅斑熱に注意!」/岡田晴恵
カルテ・レセプトの原風景【腸閉塞】腸閉塞の種類,対応と留意点/木村圭一,武田匤弘
教えて! 川上先生 新型コロナウイルスのホントのこと/案:川上浩一,画:ぼうごなつこ
■請求事務
実践DPC請求Navi/須貝和則
レセプト点検の“名探偵”/秋山貴志
保険診療オールラウンドQA
読者相談室/杉本恵申
休載:日本の元気な病院&クリニック,医療事務Openフォーラム,点数算定実践講座,めーるBOX
