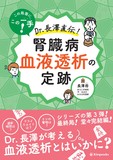
この局面にこの一手! Dr.長澤直伝! 腎臓病 血液透析の定跡
Dr.長澤の定跡シリーズ「腎臓病薬物療法の定跡」・「腎臓病患者マネジメントの定跡」に続く第3弾完結編.血液透析をはじめとした「腎代替療法」をテーマとして,末期腎不全患者に対する腹膜透析,腎移植などのトピックスを含めた基礎知識と患者管理に必要なノウハウについてまとめました.既に知っていると思っていたことも,研修医・専攻医目線の会話から何か新しい視点でヒントを得ることができるかもしれません.

この局面にこの一手! Dr.長澤直伝! 腎臓病薬物療法の定跡
どうしてその薬を使うの? 腎臓病に対する薬物療法の選択がこの1冊でわかる!
日本には多くの慢性腎臓病(CKD)の患者さんがおり、どの科に進んでも、CKDを合併している人を診療することになるでしょう。そのため、本書を用いて勉強すると普段よく診る疾患に対して、よりうまく対処できるようになります。
腎臓病薬物療法といえば、真っ先に、「どの薬を使うのがいいのかな?」に目が行きがちです。ただ実際は、どの病態にどのような薬を使うか、その副作用、患者さんへの説明など、腎臓内科において知っておくべき大切なことが他にもたくさんあります。本書を繰り返し読み、腎臓病の薬物療法の理解を深めていきましょう。

救急・ICU重要薬クイックノート
ポケットサイズで使いやすいと大好評の『ICU看護クイックノート』の姉妹本です。
「使用方法を誤ると効果が出ない」「使用方法を誤ると危険」「判断にスピードが要求される」など、救急・集中治療領域の薬物治療は、複雑で難しいという声をよく聞きます。
そこで、臨床でよく使う臓器別99薬について看護師に知っておいてもらいたいことを薬剤師がわかりやすくまとめました。薬理作用、禁忌・相互作用、用法用量、配合変化、副作用、観察項目など薬のポイントをすばやく確認できます。
現場でわからないこと、疑問に感じることがあったとき、薬剤師に質問する感覚で使ってみてください。

骨折・脱臼 第5版
本書は整形外科領域の代表的疾患である“骨折”と“脱臼”のすべてを各部位の治療スペシャリストにより解説した2000年の発刊より好評を得ている国内屈指の外傷学成書.改訂5版では全面的に記載内容を見直し,高齢者骨折の充実をはじめ各部位における最新の知見・治療法などを幅広くアップデートした.

臨床整形外科 Vol.61 No.2
2026年 02月号
特集 エビデンスと実践知から探る 腰部脊柱管狭窄症診療の最適解
特集 エビデンスと実践知から探る 腰部脊柱管狭窄症診療の最適解 よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

小児麻酔のエッセンス 安全な麻酔をすべての子どもたちへ
本書は「安全」をテーマに、小児麻酔における導入・気道確保・維持管理・覚醒といった一連のプロセスから、頻度の高い症例の対応、さらには危機的状況への対処法までを、具体的かつ実践的に解説しています。単なるマニュアルではなく、麻酔科医が自信を持って小児麻酔に臨めるよう、詳細な手順と“安全に行うためのポイント”を明確に提示した一冊です。
編者は、世界標準の教育プログラムであるSAFE(Safer Anaesthesia From Education)小児麻酔コースの日本代表としても活躍。小児麻酔に取り組むうえで多くの医師が抱える「不安」や「つまずき」に焦点を当て、それらを解消・共有できるような内容に仕上がっています。
実臨床で役立つコラムも多数収録し、普段は小児麻酔を専門としない麻酔科医にとっても、日常診療のヒントが得られる一冊となっています。
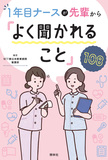
1年目ナースが
先輩から「よく聞かれること」108
先輩からの質問、どこまで答えられますか?
「今日1日、どんなスケジュールで回る?」
「この点滴は、どこから投与する?」
「はじめて受け持つ患者さん。カルテからどんな情報をとる?」
「頓用の鎮痛薬と時間指定の抗菌薬、どの順番で投与する?」
「術後の水分バランスは、なぜみるの?」
など、臨床で先輩から聞かれる質問内容は、多岐にわたります。
何も答えられずに無言で固まらないように、それぞれの質問に対して、おさえておきたいポイントだけを厳選しました。
「せめてここまで答えたい」「ここまで答えられたらすごい!」と段階的に回答例を提示しているので自分にあわせて学べます。また、「なぜ先輩はこの質問をするのか」「この回答の根拠は何か」「あわせて覚えたい知識」も解説されているので、しっかりと身につけることができます。

先生!先輩!ペースメーカ・ICD・CRT植込み後の対応、教えてください!
心電図の解釈、設定・合併症・フォローアップなど心臓デバイスの悩みをすっきり解消
「とことん本」の大好評タッグ再び!心臓デバイスの心電図は,設定や合併症の評価など,理解すべきポイントが独特です.本書では現場で必要な植込み後管理の“考え方”を,医師・研修医・看護師の会話形式で体系的に整理します.トラブルへの気づき方・フォローアップのしかたなど,「どこを見て」「どう考え」「どう判断するか」が身につき,心臓デバイス植込み患者さんを自信をもってみられます.

症例で学ぶ肺非結核性抗酸菌症
『呼吸器ジャーナル』誌の好評連載「症例で学ぶ非結核性抗酸菌症」をアップデートして書籍化。近年、著しい増加傾向にある肺非結核性抗酸菌症。患者の拾い上げが進む一方、不明点も多く「いつからいつまで、どのように治療すべきか」、臨床上の課題が多く残されている。本書では具体的な症例を元に、これまでにわかっているエビデンスと、臨床現場ではこのように対応すべきというエキスパートオピニオンとを交えて解説する。

子宮体癌取扱い規約 病理編 第5版
WHO組織分類(2020年)に基づき病理学的な取扱いを一新。これまでの組織学的予後因子に加えて分子遺伝学的予後因子が登場し、治療効果判定(ホルモン療法)、リンパ節転移の扱いや術中迅速組織診断についても適宜アップデートされた。巻末には精選された110枚の組織図譜や、付録として免疫組織化学に用いる抗体/マーカーの一覧表が収載されている。

≪jmedmook 96≫
jmedmook96 もう困らない外科系当直 歩いてくるレッドフラッグ
◆ 忙しい外科系専攻医が避けて通れない「外科系当直」。本書は、そのストレスを解消し、救急外来での診療に自信を持って臨むための実践的ガイドです。
◆ 外科当直で見逃してはならない「レッドフラッグ」を示す疾患や、外因性に見える症状に潜む緊急性の高い内因性疾患への対応方法を徹底解説。初期診療において何を見逃さず、どこで専門医に相談すべきかを明確に示します。
◆ 肘内障や鼻出血の処置といった、自身で比較的安全に実施できる手技のコツも紹介しており、実践的なスキルアップが期待できます。
◆ 本書は、思考回路を繰り返し学ぶことで型を確立し、診療時間の短縮にも繋がる内容となっています。読めば一生役立つ知識とスキルを身につけられます。
◆ 新進気鋭のヒットメーカー三谷雄己先生、髙場章宏先生、看護師でイラストレーターの角野ふち氏のチームが贈る1冊です!

≪シリーズGノート≫
まずはこれだけ! 内科外来で必要な薬剤
自信をもって処方ができる、自家薬籠中のリスト
内科外来で使う薬を厳選しました.多くの類似薬の中から患者背景に合わせて使いこなせるようにするための,自家薬籠リストです.自分で自家薬籠リストを作成する際の拠り所にもなる1冊!(電子書籍版では、書籍版と一部異なっている箇所があります)

変形性股関節症診療ガイドライン2024 改訂第3版
変形性股関節症は関節軟骨の変性や摩耗による関節の変形,骨棘形成などの骨増殖を特徴とする.股関節部の疼痛と可動域制限や跛行などの歩行障害を呈し,多くは進行性で長い時間をかけて病期は悪化していく.変形性股関節症の「疫学・自然経過」「病態」「診断」に関して,最新の知見とガイドライン作成指針に基づいて解説.また「保存療法」「関節温存術」「人工股関節全置換術(THA)」および「大腿骨寛骨臼インピンジメント」の各章では多様なclinical question(CQ)を設定し推奨度を示した.
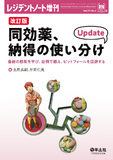
レジデントノート増刊 Vol.27 No.2
【特集】改訂版 同効薬、納得の使い分け Update
【特集】改訂版 同効薬、納得の使い分け Update
『なぜその処方を選ぶのか?』各分野のエキスパートが若手の視点に立って「同効薬の使い分けで研修医が知っておくべき基本や,1人で診療する際の処方の考え方」を概説!選択の根拠をしっかり学び,症例とピットフォールを通して上級医の思考プロセスを理解することで,現場での判断力を鍛えられる!薬剤情報を最新アップデート&新規項目の追加で,初版よりますます充実.どの診療科でも現場で即役立つ知識をこの一冊で!

外科レジデントのための下部消化管のベーシック手術
「外科レジデントのための肝胆膵のベーシック手術」に続き,若手医師にとって最高の下部消化管のベーシック手術スキル本ができました!
・外科レジデントにマスターして欲しい「基本的な解剖・検査・画像診断」「手術器具の使い方,基本操作」「基本手術」がコンパクトにまとまっています。
・先輩医師の情熱やこだわりの詰まった解説と手技動画で学べば,手術の理解が格段にアップすること間違いなし!

外科レジデントのための上部消化管のベーシック手術
「外科レジデントのためのベーシック手術」シリーズ第4弾!
・若手医師にとって最高の上部消化管のベーシック手術スキル本ができました。
・外科レジデントにマスターしてほしい食道・胃の発生と外科解剖,がんの手術における郭清や再建のポイント,良性疾患に対する手術のコツがコンパクトにまとまっています。
・現在最前線で活躍する先輩医師の解説と手技動画で学べば,手術の理解が格段にアップすること間違いなし!

中心静脈ポートの使い方 改訂第2版
安全挿入・留置・管理のために
ポートシステムを安全に使いこなすために必要な知識をコンパクトにまとめた好評書の改訂版.ポートの概念・種類から,留置の基本,各社製品の特徴や注意点,トラブルシューティング,さらには不具合の取扱いまでを解説.巻末には,製品一覧,造影CTに関する添付文書記載内容,ポート関連手技料保険関連資料を収録.ポートに携わる医師・メディカルスタッフ必携の一冊.

「その」手術室外での鎮静・鎮痛 安全ですか
検査・処置や救急・集中治療の現場で欠かせない「鎮静と鎮痛」。適切な管理は患者の苦痛を和らげる一方、薬剤反応の差により重篤な合併症を招く危険を伴う。
本書は鎮静の基本概念から安全に行うための体制・機器・人員までを体系的に解説。さらに、各領域での安全な実践を専門家が解説するとともに、臨床で役立つチェックリストも巻末に収載した。
手術室外における鎮静の質と安全性を高めたい全ての医療者に必携の一冊!

小児心臓麻酔事始め
LiSA連載まとめ買い(2022年8月号~2023年12月号)

極論で語る腎臓内科 第2版
臨床における腎臓疾患という現象を考えに考えた末のいぶし銀の視点が「極論」。シリーズの中でもよりロジカル、基礎医学領域に依拠した腎臓内科編は、この科目を苦手とする若手医師も多い中、とりわけ人気があります。「尿所見の見方」「高血圧」「尿路結石」の章を新設し、全章見直してさらに「極論」を推し進めた大改訂2版をご期待ください。
