
しみじみわかる血栓止血 Vol.1 DIC・血液凝固検査編
人気ブログがついに書籍化!血栓止血関連領域の情報をわかりやすく解説する人気ブログ「金沢大学 血液内科・呼吸器内科/血液・呼吸器内科のお役立ち情報」が多くの読者の声に応え待望の書籍化! 「寝ころびながらでも読めて、血栓止血学がしみじみ分かる」をモットーに、vol.1の本書ではDICと血液凝固検査の基本を丁寧に解説します。血栓止血領域の臨床について知りたい方に最適な一冊です。

臨床婦人科産科 Vol.73 No.1
2019年01月発行 (合併増大号)
今月の臨床 エキスパートに学ぶ 女性骨盤底疾患のすべて
今月の臨床 エキスパートに学ぶ 女性骨盤底疾患のすべて -

やさしい抗菌薬入門書
ねころんで読める抗菌薬
【100分で読める身につく抗菌薬のキホン。】
ねころんで読めるからアタマに入る、Dr.矢野が伝授する抗菌薬処方のエッセンス。基本的な17の心得をマスターし、敵(病原体)の性格を理解し、おもな抗菌薬の特徴をつかむ。ややこしいけど知っておかなければならない、明日から使える抗菌薬のキホン知識が100分でスラスラ読めて自然と体得できる!
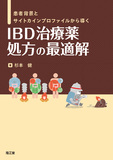
患者背景とサイトカインプロファイルから導く
IBD治療薬 処方の最適解
多様な選択肢がある炎症性腸疾患(IBD)の治療薬について,重症度だけでなく病態(サイトカインプロファイル)の類推と,患者背景の2点に着目するという著者独自の観点から患者ごとの“IBD治療薬の最適解”の考え方を提供.診断や重症度分類などの基本的知識から,薬剤選択の考え方,各薬剤の特徴,IBD治療がなぜ難しいのかを解説し,“皆が知りたいが誰にもわからない”IBD治療薬の使い分けに対する疑問に答える.消化器内科医はもちろんIBD診療に携わるプライマリ・ケア医にも必携の一冊.

よくわかる 質的研究の進め方・まとめ方 第2版 看護研究のエキスパートをめざして
●初学者もよくわかる好評書に待望の改訂版登場!
●看護研究でよく用いる「質的研究」をわかりやすく解説した好評書に第2版が登場.
●基礎知識から各研究手法まで,最新情報などを盛り込んでバージョンアップされた役立つテキスト.

外傷エコー診療のすすめ【Web動画付】
エコーが「あると便利」から「診療に必須」へ!
外傷×エコーの有用性、可能性について、120本の動画と豊富な図写真で徹底解説しました!
プローブの持ち方は?何が見えて、どう診断するの?伝達麻酔は? 治療への応用は?
エコーを使いこなすための様々なノウハウを、エコーの達人から学べます!
「外傷」に焦点を当てているからこそ、
臨床家が知りたい情報だけが網羅され、これからの診療に必ず役立つ一冊に仕上がりました!
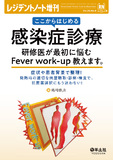
レジデントノート増刊 Vol.26 No.8
【特集】ここからはじめる感染症診療 研修医が最初に悩むFever work-up教えます。
【特集】ここからはじめる感染症診療 研修医が最初に悩むFever work-up教えます。 急性の発熱の原因で最多なのは感染症.この1冊で,よく出合う感染症を症状別にスッキリ整理し,原因微生物の推定・抗菌薬の選択までできるようになる!さあ,感染症診療はここからはじめよう!

スタートアップ!脳卒中診療
国立循環器病研究センター副院長 豊田一則先生推薦!
「若手医師が脳卒中の何を知りたがり、脳卒中診療の何に困っているのか」について的確にツボを押さえた1冊(推薦文より)
脳卒中診療におけるファンダメンタル(=基本項目)について、初期研修医と指導医との会話形式でまとめました。
多くの症例や画像を元に、実臨床に即した構成となっています。
豊富なエビデンスと著者の経験を詰め込んだ、「脳卒中診療の先輩が気軽に相談に乗るように脳卒中診療の基本やポイントを伝える」1冊です。

≪オペナーシング2024年春季増刊≫
完全保存版! 手術室の器械・器具210
【“器械の多さ”を乗り越える新人の味方!】内視鏡下・ロボット支援下手術の器械を含む新人が押さえたい手術室の基本の器械を網羅! 渡し方・組み立て方・点検の仕方が学べる動画50本つき! 予習・復習&後輩指導にすぐに活用できる! 全オペナースが苦労する“器械の多さ”を乗り越える完全保存版!

≪非腫瘍性疾患病理アトラス≫
肺
非腫瘍性肺疾患には,感染症,間質性肺疾患,肺高血圧症等々,多岐にわたる疾患が含まれ,肺の構成要素を複合的に侵す.これらの疾患を理解するために「肺の解剖学的・組織学的所見に照らした病変分布」を意識しながら平易に解説.組織写真とともに,必要に応じてX線画像,肉眼写真やシェーマも用いる.総論では胎齢期の組織像が提示され,各論には剖検でしかみることがない疾患や,病理像から病因に迫るユニークな考察もある.

東洋療法学校協会編教科書 解剖学 第2版【2025年1月10日 第2版第20刷】
本商品は2025年1月10日発行の「第20刷」となります.ご購入の際は刷りに間違いがないか再度ご確認いただきますようお願い申し上げます.
◎図や表を2色刷りにして読みやすくした改訂第2版!
・細胞・組織,内臓などの人体の基本を分かり易く解説したテキスト.理解を容易にするために,項目ごとに小見出しをつけ,簡潔明解に記述している.改訂第2版では図と表を2色刷りにしたほか,一部にカラーの図も収載して理解が深まるように編集.

学生や新人が「発達障害かもしれない」と感じたら
それぞれの困りごとから考え、ともに成長する学習者支援
なぜ、教育者は学習者が発達障害かもしれない、と感じるのか。教育者のあり方を問う
18歳人口の減少、医療の多忙化など、医療者教育は新たな展開を迎えています。社会においても、発達障害への関心が高まる中、これまでの方法が通じなくなったとき、つい、学習者が発達障害かもしれない、と感じるようです。本書では、発達障害への理解を深めるとともに、よりよい支援を実現するための考え方、あり方をお伝えします。教育者、医療従事者、職場の管理者必携の一冊です。

レジデントノート Vol.27 No.13
2025年12月号
【特集】皮膚疾患 所見の診かた・鑑別、コンサルト、薬の使い分けがわかる!できる!
【特集】皮膚疾患 所見の診かた・鑑別、コンサルト、薬の使い分けがわかる!できる!
「自分だけでどこまで対応できる?」「皮膚科に相談すべき?」「相談時に伝えるべき情報は?」といった皮膚疾患の疑問にエキスパートが応えます.適切な評価・鑑別・対応・専門科へのコンサルトができるようになるための知識を,現場の共通用語や伝わりやすい所見の表現を含めて解説します.病棟・救急でよく出合う疾患への初期対応が身につく1冊です.

はじめてのがんゲノム医療
臨床のための基礎知識
がんゲノム医療を学ぶ 「最初の 1 冊」として最適な,初学者必携の入門書. 第一人者による,わかりやすさに徹した丁寧な語り口で, 実臨床に必要な情報からがんゲノム医療の全体像までを一挙に解説した.事前知識がなくても,自分に必要な部分を選んで読み進められる構成.SNSで大人気のDr.ぺぺぺによる表紙・扉のイラストも必見!

腹腔鏡下胃切除術公式テキスト
日本内視鏡外科学会教育委員会による,腹腔鏡下胃切除術における技術認定取得のための公式テキスト.幽門側胃切除,胃全摘,噴門側胃切除におけるリンパ節郭清から再建まで,ビデオ審査における評価ポイントを押さえた「推奨される術式」を豊富な写真で明快に解説.さらに,「陥りやすい悪い例」として改善・克服すべきポイントも強調しており,術者・助手をはじめとする手術チームの共通理解を深められる.円滑に腹腔鏡下手術を完遂する力を身につけるために最適の指南書である.

3DCTで解剖から学ぶ腹部エコーの基本とコツ
血管を指標にした走査法と超音波所見をマスターする
腹部エコーで重要な解剖を3DCTを用いて解説!豊富な画像と,プローブ操作・エコー像が連動した動画で腹部を思い通りに描出できる!プローブの持ち方,検査のコツや描出困難例への対策も解説した初学者必読の1冊

多発性骨髄腫の診療指針2024 第6版
CAR-T細胞療法や二重特異性抗体(BsAb)など,新たな薬剤や併用療法の進歩が著しい多発性骨髄腫.本書では,骨髄腫の定義から臨床所見,診断基準,治療,類縁疾患の診断と治療に至るまで,最新の知見を踏まえて解説する.“臨床現場で気軽に手に取り,参照できるガイドライン”を目指し,診療に関する膨大な情報を図表で整理しつつ,治療アルゴリズムや開発中の薬剤など,最新の動向も取り入れた.
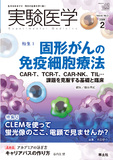
実験医学 Vol.44 No.3
2026年2月号
特集1:固形がんの免疫細胞療法 CAR-T、TCR-T、CAR-NK、TIL…課題を克服する基礎と臨床/特集2:CLEMを使って蛍光像のここ、電顕で見ませんか? 標的部位を精密に狙い超微構造を見る
特集1:固形がんの免疫細胞療法 CAR-T、TCR-T、CAR-NK、TIL…課題を克服する基礎と臨床/特集2:CLEMを使って蛍光像のここ、電顕で見ませんか? 標的部位を精密に狙い超微構造を見る
特集1:固形がんの壁を打ち破る! CAR-T細胞やTCR-T細胞,NK細胞,iPS技術など,多角的アプローチで弱点を克服し治療の限界を押し広げる「免疫細胞療法」の最前線に迫る/特集2:蛍光顕微鏡で捉えた現象を,電子顕微鏡の解像度でもう一度見る.研究の説得力を高める「光-電子相関顕微鏡法」への誘い

内科医のための
認知症のBPSD(行動・心理症状)への向精神薬の使い方
認知症の患者には,もの忘れ,注意障害といった中核症状に加えて,人によっては,拒絶,不穏,興奮,暴言,暴力,徘徊,性的逸脱行動などの行動症状と,不安,焦燥,抑うつ,幻覚,妄想,誤認などの心理症状がみられる.本書では,こうした多彩な行動・心理症状(BPSD)について,認知症を診察する機会のある医師向けにエビデンスやガイドラインの推奨を示しながら,使用されることの多い向精神薬について情報を整理・紹介した.
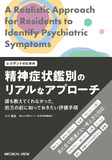
レジデントのための精神症状鑑別のリアルなアプローチ
誰も教えてくれなかった,処方の前に知っておきたい評価手順
これまで語られることのなかった精神症状の評価と鑑別手順について,研修医向けのレッスン形式でわかりやすく解説。
精神科に限らず臨床で遭遇する典型例を基に評価方法を示し,不安、怒り,眠れない,指示に従わない,「死にたい」と言う,といった
実践的なテーマごとに鑑別と対応を学ぶ。疾患や病態により重なりあう症状,見た目でだまされないための評価の根幹を凝縮した一冊。
