
≪栄養科学イラストレイテッド≫
食品衛生学 第3版
改正食品衛生法の完全施行,そしてHACCPの実施に伴い改訂!現場で役立つ食品衛生の基礎を,わかりやすく解説!食品衛生関連の法律・制度から,食中毒の科学的な知識まで,幅広く網羅したオールカラーの1冊!
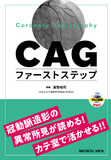
CAGファーストステップ[Web動画付]
冠動脈造影の異常所見に気付き,カテ室で活かすTips
心臓カテーテル検査のエキスパートが伝授する,カテ室スタッフのための読影テキスト。
冠動脈造影(CAG)の異常所見の読み方や評価,読影後のカテ室での動き方(管理での活かし方)に焦点を当て,豊富な画像や動画,最新の評価法,トレーニング問題によって,一人前になるための必須知識をゼロから学べ,わからないことがあったときにもすぐに読んで理解できる実践的入門書!
トレーニング問題・動画付き。

理学療法38巻9号
2021年9月号
成長期のスポーツ障害と理学療法
成長期のスポーツ障害と理学療法 「成長期の身体は,大人の身体とは異なる」と言われるように,成長期の骨には成長軟骨板(骨端線)が存在し,特に男子では13歳頃,女子では11歳頃に成長軟骨の代謝が活発になり急速に成長します.
軟骨や筋,靱帯などにも成長期特有の生体力学的特性があるため,成長期のスポーツ活動による過剰な運動負荷(オーバーユース)は障害発生を招き,それに伴う不適切な処置や治療はさらに障害を助長するなどのリスクとなりえます.
そのため成長期のスポーツ障害に対する理学療法を進めるには,成長期の運動器および心身機能の特性,スポーツ障害の特徴について正確に理解することが必要です.また,特有の傾向性もある点も踏まえ治療に取り組むとともに,スポーツ障害発生予防も含めたスポーツ指導に取り組むことが重要です.
本特集は,成長期のスポーツ外傷と障害のうち「障害」に絞った内容を述べていただきます.

OCP・OFP・OBPで学ぶ 作業療法実践の教科書
面接,観察,スクリーニングなどの場面で,「なぜそのような思考に至ったのか?」「どのようなときにこの会話を行うのか?」など,作業を中心とした実践において大切なことや考慮すべきことについて,事例を紹介しながら丁寧に解説。これらをお手本にアプローチすれば,クライエントに対して効果的な実践が身につきます。
ベストセラー『5W1Hでわかりやすく学べる 作業療法理論の教科書』,『5つの臨床推論で整理して学ぶ 作業療法リーズニングの教科書』に続く第3弾登場!

理学療法38巻7号
2021年7月号
エビデンスを参照した呼吸器疾患に対する理学療法の考え方と進め方
エビデンスを参照した呼吸器疾患に対する理学療法の考え方と進め方 好評の「エビデンスシリーズ」の呼吸器疾患編です.
「根拠に基づく実践(Evidence-based Practice:EBP)」
における臨床判断要素としては,臨床研究の実証結果である狭義のエビデンスだけでなく,臨床家の臨床能力,施設の設備や環境,そして,患者の意向や価値観を含めた広義のエビデンスを踏まえた,患者中心型の総合的な判断が重要となります.
したがって,担当患者に関連したエビデンスがヒットしても,患者の意向や価値観との折り合いがつかなかったり,施設の設備・環境の関係で対応できない等,場合によっては他の選択肢を選択するという臨床判断を行うことも必要となります.
本特集では,エビデンス “を” 判断の中心に置くのではなく,エビデンス “も” 含めた患者中心型の包括的な臨床判断を行う考え方を「エビデンスを参照した」と記すこととし,このような実際的なEBPの概念と行動様式に基づいた呼吸器疾患患者に対する理学療法の考え方と進め方に焦点を当てるべく述べていただきます.

理学療法38巻8号
2021年8月号
骨粗鬆症予防と理学療法の取り組み
骨粗鬆症予防と理学療法の取り組み 「2015年度版骨粗鬆症ガイドライン」によると,国内の患者数は,女性980万人,男性300万人と報告されています.
加齢に伴い骨が脆くなり骨粗鬆症が進行することが知られており,特に女性では閉経後に骨粗鬆症が急速に進行し,腰椎や大腿骨の骨折をもたらし,それが腰痛や寝たきりを招き,廃用症候群につながります.
そのため骨粗鬆症に対して予防的観点から取り組むことが重要な課題となっています.
そこで本特集では,骨粗鬆症に対し理学療法がどのような取り組みを展開することができるかを述べていただきます.

病理と臨床 2024年3月号
皮膚付属器腫瘍update~WHO分類第5版からの最新知見
皮膚付属器腫瘍update~WHO分類第5版からの最新知見 特集テーマは「皮膚付属器腫瘍update~WHO分類第5版からの最新知見」.Poroma, porocarcinoma and NUT(adnexal)carcinoma/Hidradenoma/hidradenocarcinoma/Spiradenoma/cylindroma/malignant neoplasms arising from spiradenoma, cylindroma, or spiradenocylindroma/ Syringocystadenoma papilliferum/tubular adenoma/apocrine gland cyst/Digital papillary adenocarcinoma/Microcystic adnexal carcinoma/Trichoblastoma/basal cell carcinoma/Sebaceous carcinoma を取り上げる.連載記事として[マクロクイズ],[鑑別の森],[AIと病理―これまでの5年,これからの5年] 臓器別病理AI(1)肺癌とAI,また,[今月の話題]キナーゼ融合遺伝子陽性間葉系腫瘍─emerging entityがもたらす混乱と新たな診断・治療への期待─,[ひろば]等を掲載する.

Medical Practice 2024年3月号
頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践
頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践 特集テーマは「頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践」.記事として,[座談会]頭痛難民はどのようにしたら減るのか:実地医家の役割とは,[総説]頭痛の診療ガイドライン2021を紐解く,[セミナー]あらためて学ぶ片頭痛の病態,[治療]薬剤の使用過多による頭痛への対処.連載では,[One Point Advice]障害者の健康管理,[今月の話題]「肥満症診療ガイドライン2022」改訂のポイント,[知っておきたいこと ア・ラ・カルト] 他を掲載.

臨床スポーツ医学 2024年3月号
一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること
一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること 「一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること」特集として,一流のサッカー選手になるためには何が必要か?/一流の野球選手になるためには何が必要か?/一流の水泳選手になるためには何が必要か?/筋肉づくりとたんぱく質補給/柔軟性獲得の基本/心肺機能を鍛える/メンタルを鍛える/一流の女性アスリートになるために などを取り上げる.また,[スポーツ関連脳振盪-アムステルダム声明-]他を掲載.

心エコー 2024年3月号
シン・エコーで冠動脈疾患に迫る
シン・エコーで冠動脈疾患に迫る 特集は「シン・エコーで冠動脈疾患に迫る」.動脈硬化リスクに迫る─subclinical atherosclerosisを診断する/胸痛患者のトリアージとしての心エコーを活用する/診断に負荷心エコーを活用する/INOCAに心エコーで迫る/心筋viabilityに迫る/陳旧性心筋梗塞患者の予後を予測する/心筋梗塞に合併する虚血性僧帽弁逆流に迫る/あえて問う,冠動脈血流速を計測する意義/preclinical heart failureに心エコーで迫る 他を取り上げる.連載として症例問題[Web動画連動企画],[COLUMN]を掲載.

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
脳腫瘍 第2版
分類の理解の上で欠かせない遺伝学的な異常をわかりやすく解説しつつ,診断現場の実際を考慮して形態学的診断にも重きを置き,精選された写真とともにその組織像を解説した.さらには分子分類に即した免疫染色の応用や腫瘍と鑑別を要する非腫瘍性病変も取り上げている.そして,臨床との連携を目指して,治療に伴う病理所見の解釈と報告書の記載法についても解説した.難しいとされる脳腫瘍の病理診断もまずはこの1冊から.

看護の約束
本書は、社会に向かって「看護のことをわかってください」と訴えるのではなく、「看護はこういうことができるのです」と言明しています。それこそが看護職の責務であると著者は言います。「看護とは、自然が患者に働きかけるのに最も良い状態に患者を置くこと」というナイチンゲール看護論に始まり、看護師・看護教育者としての実体験から生まれたエピソードを盛り込んで、「看護とは何か」を明らかにしていきます。
※本書は発行元がライフサポート社から照林社へ変更しました。
ISBN9784904084236『看護の約束』2020年7月10日発行(初版第6刷)と同一の内容です。

改正感染症法ガイドブック
改正のポイント&施行日別条文
令和4年12月の感染症法等の改正の全体像がわかるガイドブック。条文は施行日別に改正箇所を明記し、委任事項がある箇所は対応する政省令の条文も収載。重要な改正には「改正のポイント」として改正要旨を明記した。新型コロナ5類移行にも対応した感染症対策業務の必携書。

コメディカルのための専門基礎分野テキスト
内科学 改訂8版
必要にして十分な内科学の知識を箇条書きと図表を中心にまとめた,最新のテキスト.
本書は著者らがコメディカルの教育に携わった経験をもとにこれらの学生・卒業者のために必要にして十分な内科学の知識を箇条書きと図表を中心にコンパクトにまとめたものである.ミニマムでありながら分かりやすい解説はそのままに,近年の変化やトピックスを加えた.基本を補強するとともに,最新の知識を学べる改訂8版.コメディカルスタッフ.

ICUとCCU 2024年2月号
2024年2月号
特集:重症患者の腸内細菌叢は制御できるか?:腸管内治療の現況と展望
特集:重症患者の腸内細菌叢は制御できるか?:腸管内治療の現況と展望

重症心身障害/医療的ケア児者 診療・看護実践マニュアル 改訂第2版
重症心身障害児者や医療的ケア児者の診療や看護にあたるスタッフの基本的知識や具体的手技をまとめた実践的マニュアルの改訂版.最新の進歩や知見を取り入れ,内容が拡充されている.
満載の図表・イラストだけでなく,補足解説としてのコラムを掲載し,さらに理解を深めることができるようになった.医師・看護師・リハビリテーションスタッフなど,重症児者にかかわるすべての方に役立てていただける一冊.
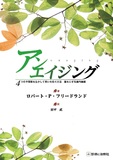
アンエイジング
4つの予備能を生かして老いを防ぐ方法
「老化は避けられないものではなく,むしろチャンス」――ケンブリッジ大学出版局の造語「アンエイジング」のテーマで,健康で長生きする方法を紹介.
脳神経内科医の筆者が老化のプロセスを説明し,「4つの予備能」を生かすことで,認知症などの加齢に伴う神経変性疾患や機能低下などへ対応する方法を示す.古今の名言や映画などの話題も交え,知的読み物として読むことができる一書.

≪透析ケア別冊≫
血液透析のキホンがわかるQ&A厳選30
【患者&ナースの血液透析の小さな疑問が解決】血液透析について「知っているけれど、患者に説明しようとするとうまくできない」「なんとなく理解しているけれど、人に教えられるほどではない」という透析ナースに贈る透析看護の入門書。患者にそのまま伝えることができる簡単な回答と、くわしく学べる解説で、血液透析と透析患者への理解が深まる。

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.26 No.3
2024年3月号
特集:支援ニーズの高い利用者に応える 精神科訪問看護の体制整備
特集:支援ニーズの高い利用者に応える 精神科訪問看護の体制整備
精神科訪問看護の利用者数が増え続けています。
さらに治療を中断した人、身体合併症のある人、ひきこもりの人、他害・迷惑行為がある人、子育て期の人など、精神科支援ニーズの高い人が増加していることも、各種の実態調査から判明しています。一方、多くの訪問看護ステーションでは、精神科訪問看護の経験が少ない看護師が実践を行っていることが推察されます。
この状況に際して、訪問看護ステーションはどのような体制を整備すべきでしょうか。
本特集では、人材教育と連携が鍵になると考えました。
そこで、まずは精神科訪問看護の現状を読み解き、ニーズと訪問看護ステーションに求められる支援を明らかにします。さらに、精神科に特化していないステーションにおいて、限られた予算や時間の中でもできる教育の工夫を紹介し、支援ニーズの高い利用者の事例を5つ報告します。
いずれも行政や複数の専門職がかかわっており、連携のあり方を具体的に示しています。
1つのステーションだけですべての支援ニーズに対応することは困難です。
この現実を踏まえた上で何ができるか、何をしていくべきかを感じ取っていただけたら幸いです。

触れるケア
「触れるケア」とは、相手の状態に合わせて“手”を使ってからだに働きかける行為全般を言います。「触れることは人にとってどんな意味を持つのだろうか」という問いかけが、本書の底にずっと流れています。看護の原点ともいえる「触れる」行為を、“からだ”のしくみや“手”の機能から説き起こし、触れる前の準備、触れる技術、触れた後の相手への配慮に至るまで解説します。わかりやすいイラストと簡潔な文章が「触れる」行為のイメージを鮮明にしてくれます。
※本書は発行元がライフサポート社から照林社へ変更しました。
ISBN9784904084175『触れるケア』2014年6月25日発行(初版第4刷)と同一の内容です。
