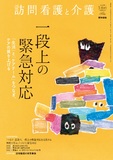
訪問看護と介護 Vol.28 No.3
2023年 05月号
特集 一段上の緊急対応 「生活」と「ケアチーム」をつなぎ、ケアの質を上げる
特集 一段上の緊急対応 「生活」と「ケアチーム」をつなぎ、ケアの質を上げる 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。制度改定の情報やケア技術はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)隔月刊(奇数月)、年6冊通常号定価:1,650円 (税込)

病院 Vol.82 No.5
2023年 05月号
特集 生き残りをかけた病院の事業連携・統合 多様化する手法
特集 生き残りをかけた病院の事業連携・統合 多様化する手法 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.95 No.6
2023年 05月号
特集 神経の扱い方をマスターする 術中の確実な温存と再建
特集 神経の扱い方をマスターする 術中の確実な温存と再建 目のつけ処が一味違う耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門誌。「こんなときどうする!?」などの臨床的なコツの紹介から、最新の疾患概念を解説した本格特集まで、硬軟とり混ぜた多彩な企画をお届けする。特集2本立ての号も。「Review Article」欄では研究の最前線の話題をわかりやすく解説。読み応えのある原著論文も多数掲載。 (ISSN 0914-3491)
月刊、増刊号を含む年13冊
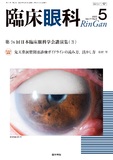
臨床眼科 Vol.77 No.5
2023年 05月号
特集 第76回 日本臨床眼科学会講演集[3]
特集 第76回 日本臨床眼科学会講演集[3] 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床外科 Vol.78 No.5
2023年 05月号
特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法
特集 術後QOLを重視した胃癌手術と再建法 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊
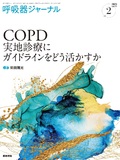
呼吸器ジャーナル Vol.71 No.2
2023年 05月号
特集 COPD 実地診療にガイドラインをどう活かすか
特集 COPD 実地診療にガイドラインをどう活かすか 2017年1号から「呼吸と循環」誌を全面的にリニューアルし、呼吸器領域に特化した季刊誌として刊行。呼吸器専門医、および専門医を目指す呼吸器科医・研修医を対象に、臨床の現場で必要とされている情報を的確に提供する。特集では、呼吸器領域の重要なテーマを最新の知見に基づいてプラクティカルに解説。 (ISSN 2432-3268)
年4冊刊(2月・5月・8月・11月)
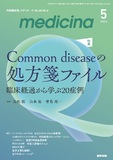
medicina Vol.60 No.6
2023年 05月号
特集 Common diseaseの処方箋ファイル 臨床経過から学ぶ20症例
特集 Common diseaseの処方箋ファイル 臨床経過から学ぶ20症例 「いかに診るか」をコンセプトに、内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。プラクティカルにまとめた特集に加え、知識のアップデートと技術のブラッシュアップに直結する連載も充実。幅広い診療に活かせる知識・技術が満載の増刊号も発行。 (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

公衆衛生 Vol.87 No.5
2023年 05月号
特集 これからの結核対策 ポストCOVID-19における結核低まん延下の結核対策を考える
特集 これからの結核対策 ポストCOVID-19における結核低まん延下の結核対策を考える 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。 (ISSN 0368-5187)
月刊、年12冊

医学のあゆみ285巻5号
第5土曜特集
mRNAワクチンやゲノム編集で注目が集まる遺伝子治療
mRNAワクチンやゲノム編集で注目が集まる遺伝子治療
企画:中神啓徳(大阪大学大学院医学系研究科健康発達医学寄附講座)
森下竜一(大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学寄附講座)
・COVID-19の世界的な感染拡大により,新興感染症の脅威と対峙するなかで遺伝子治療技術を用いたワクチンが迅速に開発されたことは,これからこの分野の研究をさらに加速させる大きな転機となると予感させる.
・本特集では,遺伝子治療の新技術,実用化に向けた挑戦,疾患治療の観点から,それぞれの分野のわが国の最先端の先生に執筆をお願いする.
・遺伝子治療製品開発の規制,企業の視点での課題,アメリカでの現状との比較に関しても取り上げることで,研究で育まれた技術をいかして,どのように社会実装へと発展させるのか,そのためのヒントになればと思う.
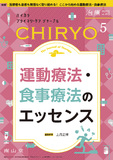
治療 Vol.105 No.5
2023年5月号
運動療法・食事療法のエッセンス
運動療法・食事療法のエッセンス さまざまな患者さんが訪れる外来診療において,限られた時間内で運動・食事について細やかな指導をするのは容易ではありません.また,理想論や一般論による指導では生活習慣の改善に取り組めない患者さんも多いです.本特集では,医師が忙しい外来診療のなかでも実践でき,患者さんも日常生活に無理なく取り入れられる,運動療法・食事療法のエッセンスをまとめました.評価や治療の進め方はもちろんのこと,患者さんをやる気にさせる秘訣も多数紹介しており,明日からの診療で実践したくなること請け合いです!

Clinical Engineering Vol.34 No.5(2023年5月号)
臨床工学ジャーナル[クリニカルエンジニアリング]
【特集】標準治療としてのオンラインHDF─実践に活かせる最新知見─
【特集】標準治療としてのオンラインHDF─実践に活かせる最新知見─ HDFを受ける患者数は年々増加しており、透析療法の標準治療となった。オンラインHDFの基本を改めて確認するとともに、高齢患者へのHDF、I-HDFの長期成績など最新の知見を交え、HDFの特徴について再確認する。

画像診断 Vol.43 No.6(2023年5月号)
【特集】唾液腺・甲状腺をきわめる
【特集】唾液腺・甲状腺をきわめる 頭頸部領域においてある意味寡黙な臓器である「唾液腺」「甲状腺」について,基本的な知識から最新情報まで余すところなく解説.大唾液腺,耳下腺,顎下腺,舌下腺,小唾液腺,甲状腺のCT・MRIおよび核医学検査の他,外科医の視点からの要望にもふれる.

VisualDermatology Vol.22 No.5(2023年5月号)
【特集】The 酒皶 reloaded. 酒皶・赤ら顔の治療 ─私はこうしている
【特集】The 酒皶 reloaded. 酒皶・赤ら顔の治療 ─私はこうしている 酒皶・赤ら顔の治療は、まだまだ標準的治療方法が確立されているとは言いがたい。また、ここ数年「マスク皮膚炎」による顔面の赤ら顔の問題なども増えている。これらの酒皶・赤ら顔・マスク皮膚炎の診断から治療までのアプローチについて解説する。

整形・災害外科 Vol.66 No.5
2023年4月臨時増刊号
脊椎脊髄領域の画像診断―最新の知識と進歩
脊椎脊髄領域の画像診断―最新の知識と進歩
脊椎脊髄領域の画像診断技術は急速に進歩している。本特集では,総論でEOSやPET/CT,MRI,トモシンセシス,脊磁図,エコー,有限要素解析など最新の画像診断技術を紹介。各論では成人,小児の画像診断の章を設け,整形外科にとどまらず放射線科や脳神経内科などスペシャリストが解説。また,近年注目の人工知能(AI)の総論や深層学習を用いた自動診断システムについての章も設けた。外来診療における脊椎脊髄疾患の診断に役立つ最新の技術と知識が満載。

月刊/保険診療 2023年1月号
特集 1095日の“失敗”のメカニズム~可視化されない最悪の365日~
特集 1095日の“失敗”のメカニズム~可視化されない最悪の365日~ 特集 1095日の“失敗”のメカニズム~可視化されない最悪の365日~
Part1 新型コロナ“34”の失敗/編集部
Part2 【鼎談】新型コロナ“失敗”のメカニズム/上昌広,木村知,倉持仁
【論述】新型コロナ“失敗”のメカニズム/渡辺晋一
【論述】日本のコロナ対策の失敗と行政・専門家のあり方/米村滋人
Part3 【対談】日本社会の“失敗”のメカニズム/古賀茂明,白井聡
【論述】日本社会の“失敗”のメカニズム/山崎雅弘
視点 世界に例を見ない高齢者福祉の削減と過重負担の現実/唐鎌直義
第57回診療報酬請求事務能力認定試験(医科):問題と解説
連載
厚生関連資料/審査機関統計資料
月間NEWSダイジェスト
介護保険/医学・臨床/医療事故NEWS
めーるBOX
■エッセイ・評論
プロの先読み・深読み・裏読みの技術/工藤高
組織をつくる6枚の設計図~人を育て,続く組織をつくる~/原麻衣子
NEWS縦断「医療機関サイバー攻撃とその対応」/武藤正樹
BSCを最大活用する12メソッド/竹内将
■医事・法制度・経営管理
病院&クリニック経営100問100答「職員を不正から『守る』ための内部統制(預金編)」/三枝康成
かがやく!事務部門/島根県立中央病院
■臨床知識
カルテ・レセプトの原風景【偽痛風】多方面からの鑑別による診断/鹿島健,武田匤弘
■請求事務
実践DPC請求Navi/須貝和則
パーフェクト・レセプトの探求/株式会社ソラスト・大港優太
レセプト点検の“名探偵”/駒井三千典
保険診療オールラウンドQA
読者相談室/杉本恵申
休載:日本の元気な病院&クリニック,医療事務Openフォーラム,こうして医療機関を変えてきた,医療事務View,点数算定実践講座

大原アトラス4皮膚外科手術アトラス
珠玉の大原アトラス第4弾.
「皮膚外科学」の草分け的存在である,大原國章先生の初の手術アトラス!
術式選択のポイントとその後の経過がひとめでわかる!
手術に対する大原先生の考え方を1冊にまとめた書.
皮膚科医・形成外科医必携!

病理と臨床 2023年5月号
前立腺癌~病理と臨床のクロストーク
前立腺癌~病理と臨床のクロストーク 特集テーマは「前立腺癌~病理と臨床のクロストーク」.前立腺癌の診断・治療手技と泌尿器科医からのメッセージ/泌尿器科医が求めている前立腺病理診断報告書/前立腺癌取扱い規約第5版 病理学的事項の改訂点/前立腺導管に関連した病変/前立腺癌のがん遺伝子パネル検査 他を取り上げる.連載記事として,[マクロクイズ],[鑑別の森],[若手病理医のためのキャリアパス講座],また,[今月の話題],[Review/Opinion]を掲載.
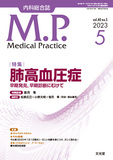
Medical Practice 2023年5月号
肺高血圧症~早期発見,早期診断にむけて
肺高血圧症~早期発見,早期診断にむけて 特集テーマは「肺高血圧症~早期発見,早期診断にむけて」.記事として,[座談会]肺高血圧症─血行動態の改善からQOLの改善にむけて,[総説]肺高血圧症の歩み─歴史から最新の分類,病態まで─,[セミナー]肺疾患に伴う肺高血圧症,[トピックス]精神疾患に潜む肺高血圧症,[One Point Advice]肺炎像は必ずしも感染ではない./ベストな体重はどのくらいでしたか?,[知っておきたいこと ア・ラ・カルト]慢性疲労症候群.

心エコー 2023年5月号
はじめての救急当直 心エコー虎の巻
はじめての救急当直 心エコー虎の巻 特集は「はじめての救急当直 心エコー虎の巻」. POCUSの基本/症候編:ショック・胸痛/症候編:息切れ・呼吸困難/疾患編:急性冠症候群/疾患編:大動脈解離/疾患編:肺血栓塞栓症/疾患編:心不全/疾患編:心タンポナーデ/疾患編:心筋炎・心膜炎 などを取り上げる.連載はWeb動画連動企画「若年男性に発症した急性心不全の1例」,COLUMNとして[Echo Trend 2023]learn from AHA 2022/[Something new, Something special]エコー動画を見つめることの大切さ を掲載.

泌尿器外科 Vol.36特別号
Vol.36特別号
特集:後期研修医がおさえておきたい泌尿器手術 TOP30 2023
特集:後期研修医がおさえておきたい泌尿器手術 TOP30 2023
