
Medical Technology 51巻3号
ここまできた 血栓止血検査の標準化
ここまできた 血栓止血検査の標準化
血栓止血検査は①原理が異なる,②測定機器の差により検査結果が乖離しやすい,③絶対的な標準物質がない,④検査前プロセスがもっとも重要である一方で脆弱である,などの理由から,標準化が難しい検査の一つです.しかし,今日ではどの施設で測定しても正確で信頼できる検査結果を得ることが求められ,そのためには検査法の標準化が必要です.
そこで本特集では,現時点でどこまで標準化が進んでいるかや,解決すべき課題,今後の展望などをご解説いただきます.血栓止血検査の精度を考えるきっかけになれば幸いです. (編集部)

J. of Clinical Rehabilitation 32巻3号
リハのデジタル情報とデータサイエンス
リハのデジタル情報とデータサイエンス
デジタル化とそれを基盤にしたビッグデータ解析,そして人工知能(AI)の分野で,わが国は出遅れたといわれる.この遅れを取り戻すためには,教育をはじめ,さまざまな領域での変革が求められている.その皮切りに2016年に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」があるが,日本が目指すべき未来社会として「Society 5.0」創生が掲げられている.その基礎を成すのがビッグデータ解析を社会に役立てるAI技術,そしてヒト・物とコンピュータを直接つなぐIoT技術といわれる.これに向けて文科省は新学習指導要領を策定し,小学校から順次導入され,間もなく大学入試科目の一部にも取り入れられる.また,文系理系を問わず多くの大学の授業には「数理・データサイエンス(DS)・AI」の科目が設けられるようになった.2021年にはデジタル庁が設置され,広く国民へのアプローチが始まったことで,いよいよその本気度を感じるに至った.
こういった教育変革が背景なのかもしれないが,最近,PCプログラミングを操る若者が増えている.プログラム言語が目的ごとにブロック・モジュールを用意し,数学が不得意な文系の若者にも容易に使えるようになったことが理由であろう.中身はブラックボックスで理解していなくても何かのパラメータを入力すると,何か役に立ちそうな結果が出力される.これを利用するのは文系理系も関係ないわけである.インターネットの中には膨大なデータが収められており,それが自分の興味対象であれば,何かを知りたいという欲求が生じるのは不思議ではない.それが若者をドライブしているように思われる.
DS技術が身近な存在となりつつあるがゆえに,リハビリテーション(以下リハ)の世界では何が起こっているのか,また将来何ができるかを知りたいと思う読者も多いと思う.実際,リハ関連の学会・研究会でDSを用いる発表が見られるようになってきた.こういった状況を背景に本特集では一般の読者にも理解できるリハ関連のDSやAIを概説いただき,また実例提示を通して,その将来性に触れてもらうことにした.
兵庫医科大学医学部の井桁正尭先生らには基本的な知識として,DS,AIとその中心要素を成す機械学習・深層学習を概説,さらにプログラム言語や身近な実例にも触れていただいた.産業医科大学医学部の松垣竜太郎先生らには医療データ源としてDPCを概説していただき,そこから得られた急性期リハの課題を示していただいた.一方,回復期リハについては森ノ宮病院の宮井一郎先生にアウトカムを志向した解析をご紹介いただいた.AI技術はリハ帰結予測解析にも多用されるが,藤田医科大学医学部の岡崎英人先生には従来の多変量解析との使い分けについてわかりやすくご説明いただいた.また,産業技術総合研究所の多田充徳先生らにはリハが扱う時系列データの解析として慣性計測器を使った応用例をご紹介いただいた.そして,最後に杏林大学保健学部の藤澤祐基先生に動作画像データそのものの解析について,現状と将来をお示しいただいた次第である.(編集委員会)

検査と技術 Vol.51 No.4
2023年 04月号
若手臨床検査技師、臨床検査技師をめざす学生を対象に、臨床検査技師の「知りたい!」にこたえる総合誌。日常検査業務のスキルアップや知識の向上に役立つ情報が満載! 国試問題、解答と解説を年1回掲載。年10冊の通常号に加え増大号を年2回(3月・9月)発行。 (ISSN 0301-2611)
月刊、増大号2冊(3月・9月)を含む年12冊

総合リハビリテーション Vol.51 No.3
2023年 03月号
特集 遠隔リハビリテーション治療・支援のさらなる展開
特集 遠隔リハビリテーション治療・支援のさらなる展開 リハビリテーション領域をリードする総合誌。リハビリテーションに携わるあらゆる職種に向け特集形式で注目の話題を解説。充実した連載ではリハビリテーションをめぐる最新知識や技術を簡潔に紹介。投稿論文の審査、掲載にも力を入れている。5年に一度の増大号は手元に置いて活用したい保存版。
雑誌電子版(MedicalFinder)は創刊号から閲覧できる。 (ISSN 0386-9822)
月刊、年12冊

医学のあゆみ284巻11号
生体内リプログラミングによる個体生命機能の制御
生体内リプログラミングによる個体生命機能の制御
企画:山田泰広(東京大学大学院医学系研究科病因・病理学専攻分子病理学分野)
・iPS細胞の樹立成功に代表されるように,一過性の転写因子の発現誘導により転写ネットワークの書き換えが可能であり,さまざまな細胞種において細胞アイデンティティの転換,すなわちリプログラミングが実証されている.
・生体内リプログラミング技術の進歩により,細胞運命転換を介した個体生命機能への人為的な介入が可能であることが示され,再生医療の開発のみならず,さまざまな疾患に対する治療戦略開発にも適用されつつある.
・本特集では,生体内リプログラミングによる生命機能制御の可能性やその疾患研究への応用,さらにはリプログラミング技術により解明された臓器機能の恒常性維持機構の知見について,最新の研究成果を解説いただく.

精神医学 Vol.65 No.3
2023年 03月号
特集 災害精神医学 自然災害,人為災害,感染症パンデミックとこころのケア
特集 災害精神医学 自然災害,人為災害,感染症パンデミックとこころのケア 時宜にかなった特集、オピニオンを中心に掲載。また、臨床に密着した「研究と報告」「短報」など原著を掲載している。「展望」では、重要なトピックスを第一人者がわかりやすく解説。 (ISSN 0488-1281)
月刊、増大号を含む年12冊

胃と腸 Vol.58 No.3
2023年 03月号
主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療
主題 食道ESD瘢痕近傍病変の診断と治療 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。 (ISSN 0536-2180)月刊、増大号2冊を含む年12冊
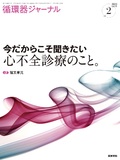
循環器ジャーナル Vol.71 No.2
2023年 04月号
特集 今だからこそ聞きたい心不全診療のこと。
特集 今だからこそ聞きたい心不全診療のこと。 -

≪看護管理まなびラボBOOKS≫
看護師・医師を育てる経験学習支援
認知的徒弟制による6ステップアプローチ
認知的徒弟制の6ステップで経験から学ぶ力を引き出す!
「自ら考え、学び、動く人材」を育てるために、後輩や部下の経験からの学びをどのように支援すべきか悩むあなたへ──経験学習サイクルを適切に回す手助けとなる認知的徒弟制の6ステップ(①モデル提示、②観察と助言、③足場づくり、④言語化サポート、⑤内省サポート、⑥挑戦サポート)を解説。新人看護師・新任副看護師長・医師(心臓血管外科医)については、6ステップの優れた指導例とそのポイントを示す。

わかりやすい省察的実践
実践・学び・研究をつなぐために
すべての悩める実践家に。待望の入門書
看護、教育、福祉などの対人関係専門職にとって、実践・学び・研究はどのように位置づけられるのか。現場の知を探求していくために必要な考え方を、省察的実践や成人学習理論の成書を多数翻訳してきた第一人者がわかりやすく解説。実践に悩む人はもちろん、教育・研修担当者、大学院進学に興味のある方へもおすすめ。学び続けるあなたを応援する1冊。

トップジャーナルへの掲載を叶える ケースレポート執筆法
アクセプトの鍵は、ロジックと記憶に残るストーリーにある
アクセプトされる症例報告を書くポイントは? この症例は報告に値するだろうか? どのようなスケジュールで進めればいい? 臨床で出合った症例を紙面に残して報告するのは、臨床医としての大切な役割だ。初学者向けの基礎から熟練者による指導方法まで、効果的な執筆プロセスを解説。臨床医の多忙な業務の合間にも執筆を進められる「考え方」や「方法論」を提示する。

関節外科 基礎と臨床 Vol.42 No.4
2023年4月号
【特集】側弯症の治療アップデート
【特集】側弯症の治療アップデート

家族看護を基盤とした
地域・在宅看護論 第6版
2022年4月入学者から適用される新カリキュラムに対応
読者と同じ看護学生の物語を主軸として、くらしや家族、地域の理解が深まる
本書では、地域・在宅看護の実践を、「くらしにくさを感じている人々が自分たちでどうにかしていくプロセスを、看護師という専門家が支援すること」と捉え、人々のくらしを支える看護の実践について詳述しました。本書の特徴は主に以下の4つです。①読者と同じ看護学生である「桜」に起こった家族の物語を軸に展開 ②くらしを支えるために欠かせない「家族看護」の学びが深まる ③くらしを支える看護技術について詳述 ④多くの事例により確かな学びが得られる
≪本商品は初版の電子版です≫

屈折異常とその矯正 第7版
30年以上にわたり、版を重ね続けた視機能のスタンダード・テキスト。屈折・調整の測定と検査法、矯正法などの理論をイチから詳しく解説。新しい知見も取り入れたカコミ記事も充実でわかりやすい。
付録として「主要な数式」と身体障害者福祉法「身体障害認定基準」を掲載。眼光学・屈折・調節関係の復習に役立つ「視能訓練士国家試験の問題と解説」は過去5年分もダウンロードできる。

理解を深めよう視野検査 第1版補訂版
10年以上にわたって好評を博してきた「理解を深めよう視野検査」が、視野検査の基礎知識と臨床力がきちんと身につく、豊富な図版と症例を呈示したわかりやすい記述はそのままに、視野検査が重要な役目を担う身体障害認定要領における視覚障害認定基準の改正に対応するため、当該項目を全面的に書き下ろし補訂版となりました。
初学者の履修にも、臨床現場での対応にも、専門家の復習にも役立つ、視野検査の解説書の決定版です!

障害別 運動療法学の基礎と臨床実践 第1版
理学療法の治療体系の中でも核となる運動療法は「疾患別」と「障害別」の2階層に区分されるが、本書は「障害別運動療法」に焦点を当て、系統的にわかりやすくまとめたものである。
各障害の運動療法に対し9つの共通項目を立てて網羅的に解説し、一部は動画で実際の動きを確認できるようにした。
著名な執筆陣により、理論や経験則、さらに最新のエビデンスを交えた実践方法を紹介。これから臨床現場に出る学生や新人理学療法士必読の書。

ここがポイント!脳卒中の理学療法 第1版
筆者らの臨床経験に基づき、実習先や現場ですぐに役立つ知識と技術を豊富な写真とともに紹介。気楽に読めるコラムを多用しながら「誰もができる片麻痺評価・治療書」をめざした。初学者でも自信と興味をもって脳卒中片麻痺へのアプローチを学べる。
解剖学、神経内科学の各専門家に加え、作業療法士、言語聴覚士、義肢装具士による理学療法に役立つ知識・見るべきポイントの解説ページも見逃せない。これまでの書籍とは違った味わいを堪能できる一冊。

消化器クリニカルアップデート Vol.4 No.2
2023年(Vol.4 No.2)
特集:この領域のランドマーク論文はこう読むべき!
特集:この領域のランドマーク論文はこう読むべき!

未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術100のテクニック
各部位のコイル塞栓術におけるエキスパートのテクニックを伝授!
脳動脈瘤コイル塞栓について,手技や方法,治療現場で実際に行っている工夫をすべて教えます.これから治療しようとしている症例に似たケースに対し,エキスパートはどのように挿入しているのか,同じ部位でも術者によって異なるアプローチを知ることで自分に合うテクニックを習得できる1冊!

臨牀消化器内科 Vol.38 No.4
2023年4月号
あなたの知らないIBD 診療の世界
あなたの知らないIBD 診療の世界
「あなたの知らないIBD 診療の世界」という特集名をつけたけれども,いまだに「だれも知らないIBD 診療の世界」というのがあることも各著者の先生方の原稿から読み取ることができた.新規薬剤やモニタリング法の使い分けやUCでの手術のタイミング,CAP 維持療法の適切なやり方など,これからも解決していかなければならない問題はたくさんある.
