
眼科 Vol.65 No.3
2023年3月号
超高齢化社会における緑内障マネージメント
超高齢化社会における緑内障マネージメント
トピックス、診療のコツ、症例報告、どこから読んでもすぐ診療に役立つ、気軽な眼科の専門誌です。本号の特集は眼科医にとって極めて身近な課題である「超高齢化社会における緑内障マネージメント」につき4つの話題を4人の先生方に解説していただきました。その他、眼窩骨折と視神経管骨折の画像検査やコホート研究の意義という抑えておきたい話題の綜説、各種連載企画、投稿論文2本も掲載されております。是非ご一読ください。

VisualDermatology Vol.22 No.3(2023年3月号)
【特集】JAK阻害薬を上手に使おう
【特集】JAK阻害薬を上手に使おう JAK阻害薬は外用薬と内服薬の両方でアトピー性皮膚炎に対して使われるなど高い有効性が示されている一方、長期的な安全性への懸念も存在するJAK阻害内服薬について、JAK阻害薬を上手に使うための情報をお示しする。

小児科診療 Vol.86 No.4
2023年4月号
【特集】知っておきたい小児炎症性腸疾患(IBD)
【特集】知っておきたい小児炎症性腸疾患(IBD) 指定難病疾患で最も患者数の多いIBDは小児領域でも患者数が増加しています.
小児IBDの徴候から検査,診断,治療までを網羅的に学び,腹部症状の日常診療にお役立ていただければ幸いです
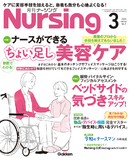
月刊ナーシング Vol.43 No.3(2023年3月号)
【特集】【1】ナースができるちょい足し美容ケア【2】観察・バイタルサイン・フィジカルアセスメント ベッドサイドの気づき スキルアップ!
【特集】【1】ナースができるちょい足し美容ケア【2】観察・バイタルサイン・フィジカルアセスメント ベッドサイドの気づき スキルアップ! 「臨床実践に強くなれるプロの看護総合情報誌」として、斬新で実践に役立つテーマを特集し、多忙な業務で見失いがちな看護ケアや技術などの最新情報をビジュアル豊富な誌面で深く掘り下げタイムリーにご紹介。

Clinical Engineering Vol.34 No.3(2023年3月号)
臨床工学ジャーナル[クリニカルエンジニアリング]
【特集】新型コロナウイルス感染拡大から医療が学んだこと
【特集】新型コロナウイルス感染拡大から医療が学んだこと 新型コロナウイルス感染症対策について、今日までの教訓や課題(啓発・医療資源・病床の不足や、一般医療へ及ぼす影響など)について、様々な領域や職種の視点で解説!

実践! 心不全療養指導
心不全療養指導をうまく実践していくために必要な知識をやさしく解説。
わかりにくくつまずきやすい知識を,症例を基に豊富な図版と簡潔な文章でビジュアル的に理解できる。
「この項目で押さえたいこと」で必須知識が一目でわかり,CHECK POINT(○×問題)を解くことで理解できたか確認できる。さらに「練習問題」で力試しができる。
“必須知識”や“ワンポイントアドバイス”などすぐに使える知識も満載。
心不全療養指導士をこれから目指す初学者も,すでに資格を取得したメディカルスタッフにも,質の高い療養指導を実現するために長く役立つ実践書!

看護 Vol.75 No.3
2023年3月号
特集1 コロナ禍における看護職のメンタルヘルスケア
特集1 コロナ禍における看護職のメンタルヘルスケア
2020年以降、新型コロナウイルス感染症がまん延し、医療現場や保健所ではその対応に追われてきました。コロナ禍の長期化に伴い、看護職はもちろん、職員を支え続けた管理職もメンタルヘルスへの影響がより深刻さを増し、慢性疲労やバーンアウトが懸念されています。そこで、日本看護協会は2022年1月に「看護職のためのメンタルヘルス相談窓口」を開設。看護職のメンタルヘルスの不調に関して多くの相談が寄せられています。
本特集では、相談窓口などに寄せられた相談内容の推移と現状を明らかにした上で、看護職自身へのケアと、医療機関・保健所における組織的なケアの方法について、管理者への支援を含めて解説します。さらに、日本看護協会が実施している精神看護専門看護師による看護管理者への相談支援の内容についても紹介します。
特集2:変化する社会で求められる看護 キーワードは「深化」と「拡張」
「2022年度日本看護学会学術集会」において、神奈川県立保健福祉大学 理事長・大谷泰夫さんが行った特別講演「未来に向けた看護のパラダイムシフト~深化と拡張~」は、今後の“看護”の方向性を、「未病」という健康観、「治す」から「維持・改善」への発想転換、ヘルスイノベーションにおける看護の立ち位置などに着目して論じた興味深い内容でした。本特集では、大谷さん自身が『看護』読者に向けて論考として再構成し、特に看護職の能力・活動領域の「拡張」について展望試案を述べます。
そして、大谷さんの論考を読んだ、立場の異なる4人の看護管理者らが、自らの所属組織での看護と照らし合わして現状を振り返るとともに、看護のパラダイムシフトについて思うこと、今後の取り組みへの反映などについて語ります。

トータルアスリートサポート
院内リハビリテーションから現場でのコンディショニングまで
7種のスポーツ競技(野球/サッカー/バスケットボール/陸上/競泳/テニス/ラグビー)について,国内トップレベルの現場スタッフが執筆!
ドクター&コーチのニーズを踏まえ,理学療法士とトレーナーがいま何をすればよいか,また異なる現場でそれぞれ何をしているかをタイムラインで提示し,身体機能,体力要素ごとに解説。アウトフィールドからオンフィールドまでの競技復帰+トータルコンディショニングについて,スポーツ現場でアスリートのサポートに関わる方の道標となる1冊。

行動医学テキスト 第2版
待望の第2版.日本行動医学会,策定のコア・カリキュラムに準拠した学会公認テキスト.
日本行動医学会公認のテキストとして「行動医学」や「行動科学」の歴史や概念,臨床における実践などをわかり易く解説する初学者向けの入門書.精神医学,心身医学,心理学,公衆衛生学,看護学などの教育場面におけるテキストとして,また医療現場でスタッフが臨床に活用できる実践的な内容を網羅的に解説した実践的な標準教科書.2015年に刊行された初版に最新の知見やデータを反映して加筆修正された第2版.

シンプル理学療法学シリーズ
理学療法概論テキスト 改訂第4版
初学者が理学療法と理学療法士の全体像を理解しやすいように平易な言葉や具体例を用いて解説.医療・福祉・保健の現場の様子など理学療法士を目指す学生に必要な情報をコンパクトにまとめた.補足資料はQRコードを本文の対応箇所に付けることでスマートフォンなどを用いて閲覧可能とした.「理学療法士作業療法士国家試験出題基準令和6年版」に対応し、理学療法(士)を取り巻く最新の状況をつかめる内容となっている.

看護学テキストNiCE
薬理学
看護師が必要とする薬物治療学の視点を取り入れた薬理学の教科書。「人」をイメージできるよう、疾患の病態、薬物療法の方針、薬理作用の解説という流れで構成。「副作用」「禁忌」については、薬理作用と結びつけて記載し、なぜ起こるのかが理解できる。また、患者観察や看護のポイントを盛り込み、臨床とのつながりを意識した学習が可能。薬剤の特徴をまとめた一覧表を網羅。

麻酔Vol.72 No.3
2023年3月号
慢性疼痛の現況と課題
慢性疼痛の現況と課題 慢性疼痛患者への治療と対処という特集を企画したのは15年前のことになる。その間、社会の高齢化とともに慢性疼痛患者数の増加が見られ、対策が重要となり疼痛への関心も増加した。今回、あらためて慢性痛を取り上げ、痛みの概念とともに薬物療法、光線療法、介入療法、理学療法、集学的療法などについて分かりやすく説明した本特集を企画した。

形成外科 Vol.66 No.3
2023年3月号
創傷外科医が「歩行」を診るために
創傷外科医が「歩行」を診るために 創傷外科医は下肢・足の創傷治癒に取り組んできたが,必ずしも歩行を念頭に置いた治療を行ってきたわけではなく,日本の医学教育では歩行を学ぶ機会がない。また歩行機能回復は,理学療法士や看護師など,多職種協同が必要な分野でもある。創傷外科医が歩行機能に熟知し,集学的治療の一端を担うことができるよう,多職種からの報告を集めた。

緩和ケア Vol.31 6月増刊号
2021年増刊号
【特集】緩和ケアに活かすICT(Information and Communication Technology)
【特集】緩和ケアに活かすICT(Information and Communication Technology)
2020年に世界を襲ったCOVID-19の影響を受け,緩和ケアの現場も大きく様変わりした。その最も大きな変化は,「情報通信技術(ICT)をどのように利用していくか」ということではないだろうか。緩和ケアに求められる「人と人とのつながり」が,感染リスクを背景に歪められてしまうなか,現場では患者,家族,医療者とも大きなストレスにさらされてきた。一方で,この災厄を乗り切るためにインターネットを用いて人とつながっていくことが一気に加速した社会のなかで,緩和ケアの分野もその領域の活用が強く求められるようになってきている。今回の企画を通じて,緩和ケア×ICTの未来の可能性について,考えていきたい。

緩和ケア Vol.29 6月増刊号
2019年増刊号
【特集】どこでもやっているわけではない治療ー先進・先端治療から補完代替医療まで
【特集】どこでもやっているわけではない治療ー先進・先端治療から補完代替医療まで
情報や価値観の多様化している今日、がん治療の臨床において、患者・家族からしばしば「〇〇はできませんか?」と質問されることが増えてきた。〇〇には、「新しい技術を使った治療(いまならちょうどゲノム医療のまっさかりである)」や、あるいは、「そこでしかやってない治療、他の施設ではやっていない治療」が入ることが多い。
さて、臨床家として、質問にどう対応するのがいいのだろうか。この課題の土台となることを目的として企画されたのが本特集である。特集の意図は、〇〇を手放しで称賛したり、否定したり、是非を判断することではない。「〇〇はどうなんでしょう?」と思っている患者と家族の立場になって考えるには、まず、〇〇(または、〇〇を実施している施設の考え方)についてそれなりに知っていなければ、患者・家族をサポートすることができないと筆者は考える。
本特集を組むことには、編集委員のなかでも賛否の意見があったし、また、執筆の依頼をしている間にも賛否の(どちらかといえば否が多かったが)意見をいただいた。筆者は、〇〇がいいか、悪いか、という視点ではなく、「〇〇はどうなのか」と昼も夜も気になってねむれない患者・家族をサポートするために、〇〇のこと、〇〇を実施している施設の考え方をすこしでも知りたいと思う。
そんな願いをこめて、本書が、「どこでもやっているわけでもない治療」を幅広く知るきっかけとなり、是非の彼岸をこえて患者・患者の助けになることを願いたい。

公認心理師カリキュラム準拠 臨床統計学[心理学統計法・心理学研究法]
公認心理師カリキュラムに準拠した新テキスト!
「臨床にいきる統計学」として,論理的な考え方から問題解決につながる研究・統計法をまとめた画期的な一冊!
○研究法を理解しながら統計法を学ぶことで、相互の関連性をより深く学ぶことができる構成。
○実際の研究例に基づいたわかりやすい解説。
○各章の「INTRO」では学生の疑問に先生が答える対話形式で、読者が研究を身近に捉えることを促す工夫がなされている。
≪シリーズコンセプト≫
◎公認心理師をめざす学生が興味をもって学び、臨床での問題解決能力・技能が身に付くように工夫された新テキスト。
◎授業コマ数に応じた、学びやすい全15章構成。
◎各章には学習の指標となる【到達目標】【key word】を掲載し、章末には知識の整理に役立つ【Q&A】を掲載!
◎より深く理解するための、関連コラムや注釈も充実。

現代医学概論 第3版
医療専門職をめざす人たちから広く支持を得ている好評書!
各種データをアップデートした最新版!
●医療専門職をめざす人たちから広く支持されている,好評テキストの改訂版!
●看護師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,診療放射線技師,臨床工学技士,管理栄養士・栄養士など,各種医療職を目指す人のための基礎教育テキスト.
●医学全般にわたり現代の状況を理解でき,学習の基本となるリベラルアーツとしても役立つ一冊.
●改訂版では,各種データを最新にアップデート. 医師の働き方改革を中心とした新しい法律についての記述を追加するなど,全編にわたり内容を更新.
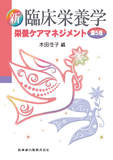
新臨床栄養学 第5版 栄養ケアマネジメント
栄養ケアマネジメントにウエイトを置いた好評テキスト第5版!
●医療ニーズを実践する管理栄養士の育成を目指すテキストが,より学びやすくバージョンアップ!
●症候と疾患への処置など治療レベルに応答する,今日的な栄養ケアマネジメントのスキルの習得を目的とした内容.
●本書の主軸となる「第V章 治療となる栄養ケア」は,疾患の概要,病因,疫学,症状,診断基準,治療,栄養生理,栄養食事療法とし,栄養ケアマネジメントの実践のステップで解説.

臨床整形外科 Vol.58 No.3
2023年 03月号
特集 二次骨折予防に向けた治療管理
特集 二次骨折予防に向けた治療管理 整形外科医の臨床の質を高める情報を発信。一流の査読陣による厳正な審査を経た原著論文「論述」「臨床経験」「症例報告」などを収載。「特集」では話題のテーマを多面的に解説する。好評連載も。2020年から増大号がスタート! 運動器診療でいま知りたいことにフォーカスし、困った時の1冊、を目指します。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

看護研究 Vol.56 No.1
2023年 02月号
特集 RCTのその先へ──現実世界に応える介入研究デザインの探求 Dr. Ivo Abraham特別講演を中心に
特集 RCTのその先へ──現実世界に応える介入研究デザインの探求 Dr. Ivo Abraham特別講演を中心に 研究の充実がますます欠かせない時代。看護とは? 研究とは? という原点を見つめながら、変わらない知を再発見し、変わりゆく知を先取りしながら、すべての研究者に必要な情報をお届けします。誌面を通して、看護学の知と未来をともに築きたいと考えています。 (ISSN 0022-8370)
隔月刊(偶数月)、年6冊
