
臨床雑誌『外科』バックナンバー(2023年セット )
南江堂発行の臨床雑誌『外科』の2023年の年間購読(電子版)になります。臨床雑誌『外科』の内容は下記をご覧ください。
1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。
毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。
一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
通常号:100頁・増刊号:約200頁

Heart View Vol.27 No.2
2023年2月号
【特集】Point of care ultrasoundを循環器診療に活かす
【特集】Point of care ultrasoundを循環器診療に活かす

医学のあゆみ284巻1号
第1土曜特集
疾病予防・健康寿命延伸に資する栄養・食生活とは?
疾病予防・健康寿命延伸に資する栄養・食生活とは?
企画:津金昌一郎(医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所)
・栄養・食生活と健康との関係については,がん,循環器疾患,糖尿病など特定の疾病や肥満,血圧,脂質,血糖値,腎機能,肝機能などの中間マーカーなどの関連について,疫学研究からのエビデンスが蓄積されている.
・本特集では,主要な疾患の重症化予防の観点から,栄養・食生活との関係について,また疾患横断的に多くの疾病を予防し,健康寿命延伸に帰結する栄養・食生活を明らかにする試みなどについて紹介していただく.
・さらに,ライフステージごとの栄養・食生活のあり方,健康的な食事とされている和食や食糧の持続可能性を考慮にいれた人と地球の双方にとって健康的な食事についてもレビューしていただく.
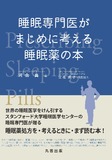
睡眠専門医がまじめに考える睡眠薬の本
(電子書籍版)
睡眠薬で不眠症が治らないのならどうすればいいのか? 多くの医師は不眠症の治療において睡眠薬しか選択肢を知らずに見よう見まねで処方をしている。スタンフォード大学睡眠医学センターで不眠症を治療してきた睡眠専門医の河合真医師が睡眠医学の知識と不眠症の特性をひも解き、「不眠症の治癒(=睡眠薬の中止)」に至るまでの考え方を解説する。
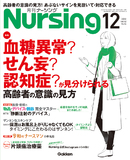
月刊ナーシング Vol.42 No.14(2022年12月号)
【特集】血糖異常? せん妄? 認知症が見分けられる 高齢者の意識の見方
【特集】血糖異常? せん妄? 認知症が見分けられる 高齢者の意識の見方 「臨床実践に強くなれるプロの看護総合情報誌」として、斬新で実践に役立つテーマを特集し、多忙な業務で見失いがちな看護ケアや技術などの最新情報をビジュアル豊富な誌面で深く掘り下げタイムリーにご紹介。
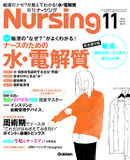
月刊ナーシング Vol.42 No.13(2022年11月号)
【特集】輸液の“なぜ?”がよくわかる! ナースのための水・電解質
【特集】輸液の“なぜ?”がよくわかる! ナースのための水・電解質 「臨床実践に強くなれるプロの看護総合情報誌」として、斬新で実践に役立つテーマを特集し、多忙な業務で見失いがちな看護ケアや技術などの最新情報をビジュアル豊富な誌面で深く掘り下げタイムリーにご紹介。

骨盤臨床解剖に基づく
婦人科手術のキーポイント
安全・確実な手術をめざして
骨盤臨床解剖に基く子宮周囲の6カ所の組織間隙を開放することにより,安全・確実に子宮を摘出できる。婦人科手術の神髄を説く,初心者から手術指導医まで必携の書。

講座 スポーツ整形外科学 セット
講座 スポーツ整形外科学のセット(全4冊)です。
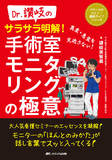
≪メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ≫
Dr.讃岐のサラサラ明解! 手術室モニタリングの極意
【モニターから次を予測するコツが学べる!】
メディカの人気セミナー1日分のエッセンスを、サクッと読める内容にまとめた一冊。モニターは装着するだけでは、意味がなく、「なんのために」装着してるのかを考えて使うことが大切。使いかたや見かたから、麻酔科医のアタマの中まで、新人さんにもわかるやさしい言葉で説明している。

ヤバいを絶対見逃さない! ゴロで診分ける消化器症状
【危険サインを知れば鑑別スキルがアップする】
消化器症状は多様な疾患で見られ、その鑑別に苦労することも多い。重篤な経過をたどることもあるが、初期にその徴候を見逃されることもある。消化器症状を全身疾患から鑑別するポイント、消化器症状に対する診察の各所に潜む危険サインを、楽しく学べる一冊。
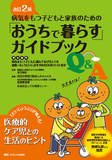
改訂2版 病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A
【先輩家族・専門家からのヒントが満載の1冊】
医療的ケア児が病院を退院後、家で暮らすために準備すること、地域にどんな支援サービスがあるかを紹介。外出や食事の工夫、教育といった日常生活の疑問や不安に対して、先輩家族や各専門家がさまざまな立場からヒントや答えを示してくれる1冊。

≪透析ケア2022年冬季増刊≫
透析ナースが答えに困った患者の疑問・質問・悩み事
【リアルな50症例で問題解決能力を磨ける!】
本書は全国の透析室スタッフから集まった、透析の知識・患者の症状・DW・食塩や水分管理・食事管理・患者や家族の気持ち・感染対策などにまつわる患者からの質問や悩み、訴えへの回答・介入方法を収載している。執筆陣が経験知とエビデンスを交えて解説する、渾身の一冊。

薬局 Vol.74 No.1
2023年1月号
おくすり比べてみました 知っておきたい!同種・同効薬の使いどころ
おくすり比べてみました 知っておきたい!同種・同効薬の使いどころ 治療に不可欠な薬。その種類は数多あり、同じ効能・効果をもっていたり、似たような場面で使われるけれど機序や特徴が異なっていたり…など、使い分けはさまざまです。活躍する場面に違いがあるのか、その違いの源は何なのか、今回の特集ではそれらをひと思いに比較してみました。各薬剤を作用機序、エビデンスに加え、患者の使用感、臨床・経験上の使い心地など、さまざまな視点より比較しながら、ご専門の先生方にご解説いただいております。薬の使い分けや位置づけ、エビデンスを学びたい方にぴったりの一冊です。

生理学実習NAVI 第3版
生理学実習の準備から記録・レポートまで,これ一冊で完結できる!
●さまざまな医療職をめざす学生から,広く支持されてきた好評実習書をリニューアル!
●改訂版では,高価な機器を用いなくても,ちょっとした工夫で人体の機能に関して実践的な考え方を学べるように,身近なものを使って身体の仕組みを理解する方法を紹介.
●機器や試薬を使用する際の注意事項をよりくわしく示すことで,実習を安全に実施できるよう留意した内容へアップデート.

高次脳機能障害マエストロシリーズ(4)リハビリテーション介入
高次脳機能障害リハビリテーションに必要な基礎知識と臨床ポイントを具体的に収載した好評書!
●豊富な症例を通して,自ら考え,実践し,臨床力を身につけることを目指しています.
●各障害において,現段階で示しうる訓練法のモデルとその理論を提示しています.
●長期的なフォローを捉え,職場復帰,施設・地域での支援のありかたまで紹介しています.

高次脳機能障害マエストロシリーズ(3)リハビリテーション評価
豊富な症例を通して,自ら考え,実践し,臨床力を身につけるための新シリーズ!
●評価のkey である「患者さんの観察と生活評価」に重点をおき,これまでにない“泥臭い臨床”をとらえています.
●単なる検査法の羅列ではなく,評価のプロセスを図解しながら,介入に向けた情報の読みとり方,評価の解釈を示しています.
●15の障害を取り上げ,概説および実例を通した評価の実際をまとめています.

Medical Technology 50巻13号
臨時増刊号
今日から役立つ 形態学的検査,がんゲノム検査の検体取り扱い
今日から役立つ 形態学的検査,がんゲノム検査の検体取り扱い
正確な臨床検査データを出すためには,検査技術とともに検査を行うまでの検体取り扱いが大切である.近年,検査技術の熟成とともに,検体検査の正確度・精密度を確保するために,検査前の検体取り扱いに注目が集まっている.臨床検査技師にとって,検査検体の保存,外注に出すまでの検体処理は必須であり,当直時などは一人でいろいろな検体に対応しなくてはならない.また,臨床側に検体取り扱いの説明を求められることも想定される.がんゲノム検査はまだ発展途上であるが,抽出した核酸のクオリティーが検査結果に影響するとの考察をよく耳にする.
以上の状況から,現在,形態学的検査とがんゲノム検査の検体取り扱いについて,広く解説した技術書はなく,本書はそうしたニーズに応えることを目的としている.具体的には,形態学的検査における染色までの技術に加え,がんゲノム検査のための検体取り扱いについても詳説している.対象読者は,病院や登録衛生検査所の臨床検査技師をはじめ,研究室,大学教員なども想定しているが,学生や企業の方々にも有用と思われるので,ご活用いただきたい.
本書の構成は病理,細胞診,がんゲノム(組織,血液),血液検査(塗抹,固定,他),尿沈渣,寄生虫検査および染色体検査であり,それぞれ独立した章とした.また,論文内で解説しきれなかった箇所についてはコラムに記載しているので,ぜひそちらも合わせて読んでいただきたい.
「1章 病理」では固定,包埋,薄切,伸展,未染色標本の保存を解説した.ホルマリン固定・パラフィン包埋(FFPE)組織も加え,組織凍結,特に筋生検組織の凍結技術,さらに電子顕微鏡の検体取り扱いについても解説した.「2章 細胞診」では,従来法の剥離細胞診の他,FNA(fine needle aspiration)やLBC(liquid-based cytology)も盛り込んだ.「3章 がんゲノム」では,ホルマリン固定・パラフィン切片,血液検体からの核酸抽出検体取り扱い,およびがんゲノム検査を目的とした組織の取り扱いと組織保存法を解説した.「4章 血液検査」では塗抹技術と目的に応じた細胞固定法にも言及し,5章は尿沈渣検査を目的とした検体の取り扱いを紹介した.6章では,寄生虫学検査における糞便を主体とした検体取り扱いに加え,直接塗抹,浮遊法などの標本作製についても解説した.そして7章は染色体検査である.実際に行う機会は少ないと想定されるが,採取された血液細胞の培養から染色体標本作製技術の知識を身につけることは有用である.
本増刊号が,『染色法のすべて』(水口國雄 編集代表,医歯薬出版,2021年)とあわせ,形態学的検査およびがんゲノム検査に役立ち,読者の皆様に永きにわたりご愛読いただけることを願っている.
2022年12月
月刊『Medical Technology』編集委員会
順天堂大学 医療科学部 臨床検査学科 教授
廣井禎之

看護管理 Vol.33 No.1
2023年 01月号
特集 いま,改めて考える「組織倫理」 新型コロナウイルス感染症対応で,看護管理者に問われたものとは
特集 いま,改めて考える「組織倫理」 新型コロナウイルス感染症対応で,看護管理者に問われたものとは 社会の変化を的確にとらえながら、看護管理者として直面するさまざまな問題について解決策を探る月刊誌。看護師長を中心に主任から部長まで幅広い読者層に役立つ情報をお届けします。 (ISSN 0917-1355)
月刊、年12冊
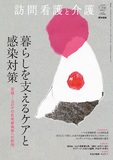
訪問看護と介護 Vol.28 No.1
2023年 01月号
特集 暮らしを支えるケアと感染対策 実践! コロナの自宅療養者への訪問
特集 暮らしを支えるケアと感染対策 実践! コロナの自宅療養者への訪問 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。制度改定の情報やケア技術はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)隔月刊(奇数月)、年6冊

病院 Vol.82 No.1
2023年 01月号
特集 社会保障制度の未来から読む病院経営
特集 社会保障制度の未来から読む病院経営 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
