
臨床雑誌外科 Vol.74 No.9
2012年9月号
消化器癌に対するneo-adjuvant therapyの最新情報
消化器癌に対するneo-adjuvant therapyの最新情報 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.74 No.10
2012年10月号
消化器癌併存症──周術期の対処法
消化器癌併存症──周術期の対処法 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.74 No.11
2012年11月号
肝内胆管癌と細胆管細胞癌
肝内胆管癌と細胆管細胞癌 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
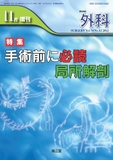
臨床雑誌外科 Vol.74 No.12
2012年11月増刊号
手術前に必読 局所解剖
手術前に必読 局所解剖 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.74 No.13
2012年12月号
大腸肛門病外科──最新のトピックス
大腸肛門病外科──最新のトピックス 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.1
2013年1月号
癌治療の選択──治療効果と治療費
癌治療の選択──治療効果と治療費 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.2
2013年2月号
外科医必読 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)のすべて
外科医必読 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)のすべて 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.3
2013年3月号
局所高度進行直腸癌のすべて
局所高度進行直腸癌のすべて 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.4
2013年4月号
外科医が知っておくべき緩和ケア
外科医が知っておくべき緩和ケア 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.5
2013年5月号
肝門部胆管癌の治療戦略2013
肝門部胆管癌の治療戦略2013 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.6
2013年6月号
必見!アッペのすべて
必見!アッペのすべて 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.7
2013年7月号
リンパ節転移と郭清
リンパ節転移と郭清 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.8
2013年8月号
大腸癌肝転移up to date
大腸癌肝転移up to date 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.9
2013年9月号
各種デバイスを応用した私の手術
各種デバイスを応用した私の手術 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.10
2013年10月号
消化器癌術後フォローアップ
消化器癌術後フォローアップ 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.11
2013年11月号
肝切除をめぐる最近の話題
肝切除をめぐる最近の話題 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.12
2013年11月増刊号
外科医が知っておくべき癌治療の薬物療法
外科医が知っておくべき癌治療の薬物療法 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.75 No.13
2013年12月号
直腸癌側方リンパ節転移のすべて
直腸癌側方リンパ節転移のすべて 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.76 No.1
2014年1月号
消化器外科術後合併症の治療
消化器外科術後合併症の治療 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床雑誌外科 Vol.76 No.2
2014年2月号
膵切除をめぐる最近の話題
膵切除をめぐる最近の話題 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
