
手術 Vol.76 No.12
2022年11月号
形成外科医に学ぶ手術手技─消化器・一般外科医が知りたいコツと工夫
形成外科医に学ぶ手術手技─消化器・一般外科医が知りたいコツと工夫
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。本号の特集テーマは“形成外科”。体表治療や再建手術のプロフェッショナルである形成外科医が,基本知識と基本手技の観点から本領域のupdateな情報を消化器・一般外科医のためにわかりやすく解説。初学者からベテランまで,見逃せない情報を満載した特集となっている。

整形・災害外科 Vol.65 No.12
2022年11月号
女性アスリートのサポートを考える
女性アスリートのサポートを考える
近年,女性アスリートへの医学的サポートの重要性が認知され,女性アスリート外来が全国的に増えつつある中で,多職種連携により多角的な視点でサポートを行うことがますます重要になっている。本特集では整形外科医,産婦人科医,内科医,小児科医,精神科医,リハビリテーション科医,栄養士,理学療法士,スポーツファーマシスト,アスレティックトレーナー,運動生理学者により最新の知見と女性アスリート特有の問題に対する指導・サポートの留意点を解説している。

関節外科 基礎と臨床 Vol.41 No.12
2022年12月号
【特集】上肢のスポーツ外傷・障害Up to date
【特集】上肢のスポーツ外傷・障害Up to date

エキスパートナース Vol.38 No.15
2022年12月号
◆「『DESIGN-RⓇ2020』は難しい」から「わかる!」に変わる 褥瘡状態の評価
◆二次性骨折予防のためのQ&A
◆「『DESIGN-RⓇ2020』は難しい」から「わかる!」に変わる 褥瘡状態の評価
◆二次性骨折予防のためのQ&A

生殖医療フロントラインMOOK(1)EBMから考える生殖医療
生殖医療の最前線の知識と技術を伝えるシリーズ第一弾.令和4年,一般不妊治療と生殖補助医療が保険適用となり,生殖医療の需要はますます高まっている.同時に,ARTは日進月歩で発展し,携わる医療者のスキルアップも重要な課題だ.そんな現状を鑑みて,本シリーズでは生殖医療に携わるチーム全体での向上を叶えるべく,必要な情報を精査.第一弾では,最新のエビデンスを踏まえて重要なトピックスについて解説している.
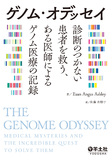
ゲノム・オデッセイ 診断のつかない患者を救う、ある医師によるゲノム医療の記録
ゲノム医療の先駆者のアシュリー博士が綴る,奮闘と革新的進歩の軌跡,そして未来.解析に挑んだチームの挑戦や患者の苦悩,大学の垣根を越えた起業の過程などを,臨場感あふれる筆致で描く.研究者,医師にお勧め!

麻酔Vol.71 No.10
2022年10月号
投稿論文特集号
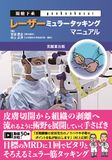
眼瞼下垂レーザーミュラータッキングマニュアル
皮膚切開から組織の剥離へ流れるように術野を展開していく手さばき! 目標のMRDに1回でピタリとそろえるミュラー筋タッキング! 百戦錬磨の宮田信之DRのCO2レーザーを用いた「Extended Müller Tucking」。その手術の詳細を動画50編を交えて紹介します。「眼瞼形成手術に携わる医師に極めて有益なコツの『宝箱』になりました!」(共著:村上正洋)。

形成外科 Vol.65 No.10
2022年10月号
新規創傷治療材料をいかに活かすか
新規創傷治療材料をいかに活かすか 新規創傷治療材料では,創傷被覆材,人工真皮製材のほか,生物学的製材も取り扱われるようになった。これらは,すべての創傷に適応があるわけではなく,急性創傷,慢性創傷,感染性創傷などさまざまである。形成外科(創傷外科)医は,創傷に対応する機会が他科に比べ圧倒的に多く,素材,特徴,くせ,取り扱い方を熟知していなければならない。

石井先生にもっと聞いてみよう患者の気持ち
糖尿病こころのよろづ相談
2010年に刊行された「糖尿病診療よろづ相談」では,糖尿病診療において一般的に遭遇する問題(低血糖,合併症,血糖自己測定,インスリン導入など)についての患者さんのこころを解説した。本書では,具体的な治療における問題に限定せず,糖尿病患者さんが抱えているこころの問題について解説した。「糖尿病診療よろづ相談」を読んで「もっと石井先生に聞いてみたい」と感じた読者の先生方にお答えできる,また本書を読んで「糖尿病診療よろづ相談」も読んでみたいと思っていただける一冊である。

臨牀消化器内科 Vol.37 No.13
2022年12月号
肝の超音波を知り尽くす-肝腫瘍の診断と治療支援
肝の超音波を知り尽くす-肝腫瘍の診断と治療支援
びまん性肝疾患同様,肝腫瘍の画像の成り立ちを考えると忠実に血流や組織を反映した画像を得ることができる.肝腫瘍の画像と病理診断はわが国が世界のトップリーダーといっても過言ではない.
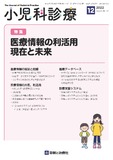
小児科診療 Vol.85 No.12
2022年12月号
【特集】医療情報の利活用 現在と未来
【特集】医療情報の利活用 現在と未来 電子カルテシステムの情報は十分に利活用できているでしょうか.小児科医に必須の医療情報収集・利活用方法を,遠隔診療,データベース,法律のスペシャリストが解説します!

心エコーエキスパート完全レシピ
心エコー領域は日々著しい進歩を遂げ,「心エコーなくして循環器診療は行えない」といわれるほど,中核を担う検査となっている。
心エコーの各種セミナーは「エキスパートになるための」と銘打っているものが多く,ステップアップしたいと願う先生や技師の多さを裏付けていると考えられる。さらに,このエキスパートになるために必要な知識や技術こそが,実臨床で欠かせない内容であることを多くの心エコーのスペシャリストの先生方が論じている。
しかし,現在出版されている刊行物の多くは初心者にターゲットを絞った内容が多いのが現状であり,上記に記したエキスパートになりたいと願う先生方の需要に応えていない。多くのエコー術者が自身のスキルアップを考えており,各種セミナーに参加し,それらの内容を収載した書籍を欲している状況である。
本書は循環器内科にとどまらず,外科を含めたエキスパートの先生方にご執筆いただき,教科書には載っていないより具体的な生の声を入れて構成している。基礎的な内容は成書にゆだね,「心エコーエキスパート」になるために身につけておくべきこと,方法をレシピ(手順書)として紹介する。

消化器クリニカルアップデート Vol.4 No.1
2022年(Vol.4 No.1)
特集:診療ガイドラインに基づいた胆膵疾患の診断
特集:診療ガイドラインに基づいた胆膵疾患の診断
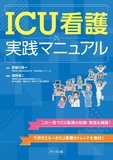
ICU看護実践マニュアル 第1版
本書は救急・ICU 部門で現在も第一線で働いている青梅市立総合病院救命救急センターの看護スタッフが中心となり、さらに一緒に診療にあたっている医師の協力によってまとめられたICU看護の知識・実践を網羅したマニュアルである。今押さえるべき「ICU看護のトレンド」を集約したベッドサイドで生かせる実践書である。ICUの現場で新人への指導や自身の知識の再構築にも役立つとともに、ICU看護の標準化・手順の見直しも使える。

月刊/保険診療 2022年10月号
特集 ”施設基準”のリフォーム事例集~変遷の文脈をどう捉え,いかに再構築するか~
特集 ”施設基準”のリフォーム事例集~変遷の文脈をどう捉え,いかに再構築するか~
Part1 【座談会】”施設基準”のリフォーム技術/小林竜弥,竹田和行,橋本敦,藤井大輔
Part2 ”施設基準”のリフォーム事例×7
1 施設基準の管理体制を4つのポイントでリフォーム /金城悠貴
2 今後の医療界の動向を見据えた施設基準管理のために/松浦裕樹
3 地ケアの病棟再編と施設基準管理の体制づくり/堀健太郎
4 施設基準対応に向けた病院全体の体制づくり/中嶋理恵
5 クリニックにおける施設基準の見直しと戦略会議の実施/松本忠幸,橋本,菅原,大口
6 クラウドサービス施設基準管理システム「iMedy」/只友裕也
7 “新たな発見に繋がる”施設基準クラウドシステム「施設基準@INX」/舛賀康祐
連載
厚生関連資料/審査機関統計資料
月間NEWSダイジェスト
介護保険/医学・臨床/医療事故NEWS
めーるBOX
■エッセイ・評論
プロの先読み・深読み・裏読みの技術/工藤高
こうして医療機関を変えてきた!/一戸和成
NEWS縦断「看護師の処遇改善」/武藤正樹
TREND /塩田祥大,田中大地
BSCを最大活用する12メソッド/金田昌之
組織をつくる6枚の設計図~人を育て,続く組織をつくる~/原麻衣子
■医事・法制度・経営管理
医療事務View/江口達也
病院&クリニック経営100問100答「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の進め方」/平川伸之,金野楽
かがやく!事務部門/佐久医療センター
■臨床知識
カルテ・レセプトの原風景【腰椎圧迫骨折】腰椎圧迫骨折の治療例/名月諭,武田匤弘
■請求事務
実践DPC請求Navi/須貝和則
パーフェクト・レセプトの探求/株式会社ソラスト・高塚康弘
レセプト点検の“名探偵”/大下裕矢
点数算定実践講座/大西正利(協力:田中優衣)
保険診療オールラウンドQA
読者相談室/長面川さより
休載:日本の元気な病院&クリニック,医療事務Openフォーラム

≪ナイチンゲールの越境 4・時代≫
ナイチンゲールが生きたヴィクトリア朝という時代
ナイチンゲール、光と闇の大英帝国に生きる
産業革命により経済、科学技術、工学、自然科学等々が大きく発展した一方で、富める上流階級と貧しい労働者階級という〈二つの国民〉の分断が著しい格差社会でもあったヴィクトリア朝。
これまでのナイチンゲール研究ではあまり取り上げられてこなかった〈時代〉にフォーカスをあて、ナイチンゲールに及ぼした影響について、歴史、文化・社会史、西洋文学、人類学、看護学の研究者らが考察しました。

≪ナイチンゲールの越境 5・宗教≫
ナイチンゲール、神の僕となり行動する
神の召命を受けたナイチンゲールがとった行動とは
ナイチンゲールにとって〈神〉とは、「祈り」の対象ではなく、貧しい人びとを救済する善意に基づく「行為」の内に存在するものでした。「神の僕として、貧しい人びとの救済のために行動する」──これこそ、17歳のときに〈神〉の声を聞いた彼女が人生を捧げたものだったのです。
特定の宗派に属さず「善きサマリア人」派だったナイチンゲールの宗教観に迫ります。

病院覚え書き
第3版
『看護覚え書き』と並ぶナイティンゲールの代表的著作『病院覚え書き』の決定版(第3版)、本邦初の完全翻訳!
「病気が同じであれば、自宅で療養する病人よりも病院に入っている病人のほうが死亡率が高い」という事実を見出したナイティンゲールは、本書の冒頭に「病院が備えるべき真に第一の必要条件は、病院は病人に害を与えないことである」という有名な一文を記しました。
戦地クリミアで英国軍病院の恐るべき実態を目のあたりにした経験から、病院とはどうあるべきか、いかに管理されるべきかを示した、『看護覚え書き』と並ぶナイティンゲールの代表的著作、本邦初の完全翻訳版です。

知っておきたい がんの日常診療
あなたならどう対応しますか?
本書で解説するのは化学療法のレジメンや手術の手順ではない。患者が医師に訴えるがんにまつわるさまざまな疑問・不安にどう応えるかを,具体例をあげながら解説している。「患者の訴え」「NG/Good対応例」「ポイント」「知っておきたい基本的知識」「患者のその後」「take-home message」で構成され,見開き2頁の簡潔な紙面の本書を読めば,医療者として知っておくべきがんの知識が幅広く得られるようになっている。
