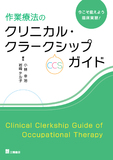
今こそ変えよう臨床実習 ! 作業療法のクリニカル・クラークシップ(CCS)ガイド
本邦初、作業療法のためのクリニカル・クラークシップ(CCS)ガイド誕生 !
2005年、正式に医学教育に導入されたクリニカル・クラークシップ(臨床参加型実習、CCS)は、現在、多くの職種の実習の手引きに取り入れられるようになり、作業療法の世界においても、その導入がまったなしになっている。従来型実習からCCS方式臨床実習へ移行する実習施設や養成校も確実に増えている。
本書では、そのような流れを踏まえ、CCS方式とは何か、従来型実習とどのように違うのか、そのメリットは何かなど、たいへんわかりやすく解説。また実際の導入に際し、どのような手順・段階を踏んでいけばスムーズに導入することができるのか、養成校教員・臨床教育者の双方からの視点・実践を豊富に掲載し、具体的な導入・実践方法を提示した。作業療法の各領域における実践も掲載され、日本作業療法士協会が進める生活行為向上マネジメントについても、CCS方式による実践法を取り上げている。
養成校教員、臨床教育者のためのCCS方式の実践ガイドブックである。

小児内科53巻5号
【特集】不定愁訴―漠然とした訴えにどう応えるか
【特集】不定愁訴―漠然とした訴えにどう応えるか

小児外科53巻5号
【特集】シミュレーションとナビゲーション
【特集】シミュレーションとナビゲーション

手の運動を学ぶ
手の役割と手の機能解剖との関係から運動を紐解き、臨床に活かす
間違った手指訓練で、患者の手の機能回復を妨げないために、知っておくべき手の臨床的知識
患者が“自然(無意識)”に使ってくれる手の再構築を目指して
◎日常生活における手の役割とはなんだろう ?
◎手の役割を支える手の機能解剖はどうなっているんだろう ?
◎整形外科疾患や脳血管疾患により、手がその役割を果たすのが難しくなった時、再び手の役割を再構築するための機能的治療訓練とはどのようなものだろうか ?
これらの疑問に、数多くの文献と臨床知から深く答える1冊

理学療法MOOK21 がんの理学療法
本邦初、理学療法士が知っておくべきがんの知識がこの一冊でわかる !
1981年以降、がんはわが国における死亡原因の1位を占めており、現在では、男性の2人に1人、女性の2.5人に1人ががんに罹患すると推計されている。一方、近年の診断技術や治療方法の進歩によりがん患者の生存率は向上し、長期生存者も大幅に増える中、患者のADL・QOLをいかに高めていくかについては非常に重要な問題であるといえる。
本書では理学療法士が理解しておくべきがん患者の病態理解、診断・治療・管理方法、リスク管理、理学療法評価法、理学療法治療法など、基本的な知識や技術をわかりやすく解説。
さらにがんのリハビリテーションについての最新トピックスを紹介し、国内にとどまらず米国における現状についても提示した。
がん患者に対して理学療法を行う際、がんの種類や部位、進行度を考慮し、原疾患の進行にともなう機能障害の増悪、二次障害を予測しながら適切に対応することが必要とされる。
本書を是非手の届くところに置き、何度でも見返し活用してほしい。

現場に学ぶ 訪問リハセラピストのフィジカルアセスメント
押さえておくべきフィジカルアセスメントのポイントをピックアップ !
訪問リハセラピストにとって、施設リハとは異なるスキルや知識が求められる場面に遭遇することは少なくない。特にフィジカルアセスメントはリスク管理の視点から、訪問リハセラピストにとって切り離せないものであり、利用者のちょっとした変化やトラブルに出会ったときに戸惑ったり、専門性の高い事項なのか、医療従事者として押さえておくべき事項なのか迷うこともあるだろう。本書は、訪問リハセラピストが押さえておきたいフィジカルアセスメントをピックアップ、事例を用いてわかりやすく対応を述べている。訪問リハセラピストが、自らも現場において思考し、医療従事者としての知識を高め、行動できるようになることを目指した1冊。

周産期医学51巻5号
【特集】これからの出生前遺伝学的検査を考える
【特集】これからの出生前遺伝学的検査を考える

JOHNS37巻5号
【特集】口腔癌診療の最前線
【特集】口腔癌診療の最前線

産科と婦人科 Vol.88 No.12
2021年12月号
【特集】少子化時代における就労女性の不妊治療
【特集】少子化時代における就労女性の不妊治療 支援が進む不妊治療ですが仕事との両立はまだまだ難しい状況です.気軽に治療に臨める環境作りのために産婦人科医が心得たい治療の工夫やコツを解説いただきました.

イラストで解る
救急救命士国家試験直前ドリル 第4版
救急救命士国家試験対策の好評書の第4版.最新の救急救命士国家試験出題基準に沿って,また改訂10版救急救命士標準テキストに準拠しつつ,より試験対策に役立つように記述内容・イラストの加筆・修正を行った.救急救命士国家試験の頻出問題について,図表を多用し項目別に要点を整理.各項目には,重要キーワード・キーポイント,暗記のためのゴロ合わせ,国家試験既出問題などを掲載! 暗記に役立つ赤色チェックシートも添付.

高次脳機能障害に対する理学療法
■脳の構造・機能,脳画像のみかたがわかる
高次脳機能障害に対して適切な理学療法介入を行うためには脳画像から得られる情報が必須.明日からの臨床に役立つ,脳の解剖と画像のみかたを詳細に解説.
■理学療法介入に必要な知識を網羅
理学療法による直接的な介入効果がある高次脳機能障害:pusher症候群,半側空間無視,失行,認知障害について,その病態や疫学,メカニズムや責任病巣,実際の治療を膨大な知見に基づいて徹底的に解説.

≪教科書にはない敏腕PTのテクニック≫
臨床実践 変形性膝関節症の理学療法
本書は,前半で,理学療法評価と治療アプローチに関する臨床上の工夫を記載し,後半で,クリティカルパス通りに進まない場合のアプローチ,歩行(歩容)の改善など,臨床で遭遇する症例への対応,さらに,対象者を取り巻く心血管疾患を中心とした内科的問題を併発する場合の運動療法の進め方,荷重関節疾患との関連がある肥満に関する考慮のポイント,日常生活を含めた患者教育の実践と工夫などを,豊富な図表とともに詳解する.
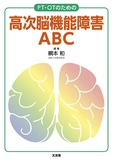
PT・OTのための
高次脳機能障害ABC
リハビリテーション関連職種を目指す学生・臨床経験の浅い初学者を基本的な対象と想定しているが,指導的立場にある経験者にも知識・情報を整理して新たな展望を拓くことにも役立つ,臨床家(professional)のための実践書である.障害の定義・概要,なぜその障害が出現するのか,評価とアプローチとその流れ,症例提示,理論的背景や臨床におけるさらに一歩進んだ解説に加え,画像診断についても解説している.
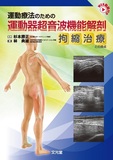
運動療法のための
運動器超音波機能解剖 拘縮治療との接点
理学療法士が拘縮治療を行う際,有用と思われる運動器超音波機能解剖を解説しつつ,それらの所見を踏まえた技術的なクリニカルヒントについて,豊富な超音波画像,解りやすい解剖イラスト,そして動きをリアルタイムでとらえることの出来る実際の動画(WEB動画)を観ながら理解することが出来る.運動器を扱う全てのセラピストにとって必読の内容がぎっしり詰まった一冊.

一歩進んだ
腹部エコーの使い方
エコーが役立つとき・役立たないとき
いまや臨床医にとって必須のスキルとなった腹部エコーだが,再現性に乏しく苦手意識をもつ医師は多い.そこで本書は,診断を下すときにエコーが役に立つ状況,あるいは逆に役立たない状況をとりあげ,臨床医のニーズに応える内容とした.さらに,意外と知らない知識,見落としがちな所見を紹介し,エコーの思わぬ落とし穴についても解説を加え,“一歩進んだ”エコーの知識を存分に披露した内容となっている.

≪皮膚科サブスペシャリティーシリーズ≫
1冊でわかる皮膚アレルギー
皮膚科医,内科医を対象に,皮膚アレルギーの基礎知識から,診療のポイント,検査のしかた,最新の治療まで,各項目を第一線の専門家が解説.図表が多く,ガイドラインなどの最新情報を紹介し,実地診療にすぐ役立つ内容.皮膚科専門医をめざす若手医師にも,さらなるステップアップをめざすベテラン医師にも,これまで実地診療で感じていた「なぜ?」「どうして?」を解決するヒントが満載で,考える楽しさを与えてくれる1冊.

臨床検査 Vol.65 No.12
2021年12月発行
特集 移植医療と臨床検査
特集 移植医療と臨床検査 「検査で医学をリードする」をキャッチフレーズに、特集形式で多領域をカバー。臨床検査にかかわる今知っておきたい知識・情報をわかりやすく解説する。「Essencial RCPC」など連載企画も充実。年2回(4月・10月)、時宜を得たテーマで増刊号を発行。 (ISSN 0485-1420)

精神医学 Vol.63 No.11
2021年11月発行
特集 「実感と納得」に向けた病気と治療の伝え方
特集 「実感と納得」に向けた病気と治療の伝え方 時宜にかなった特集、オピニオンを中心に掲載。また、臨床に密着した「研究と報告」「短報」など原著を掲載している。「展望」では、重要なトピックスを第一人者がわかりやすく解説。 (ISSN 0488-1281)
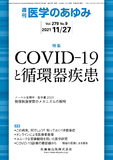
医学のあゆみ279巻9号
COVID-19と循環器疾患
COVID-19と循環器疾患
企画:竹内一郎(横浜市立大学医学部救急医学)
・新型コロナウイルス感染症(COVIDー19)はまたたく間に世界へと広がり,人々の生活を大きく変革させたが,疾患はCOVIDー19だけではなく,常にCOVIDー19とそれ以外の疾患との両立が求められる.
・全国各地で新たな医療システムも動き出している.体外式膜型人工肺(ECMO)が必要な重症患者の集約化,そのための患者搬送,経口治療薬の開発,自宅療養患者のモニタリングと容態変化を早期に把握できるシステムなどである.
・本特集では多岐にわたるCOVIDー19での課題に対して第一線で闘ってきた研究者,臨床家に解説いただく.今後も新興感染症によるパンデミックが発生するであろう.本特集がその体制作りに少しでも役立つことを期待する.

心理学からひも解く認知症の症候学
記憶障害,判断力の低下,帰宅願望,暴力や暴言,人物誤認など,認知症患者が示す不可解な行動や言動は多岐にわたる.こういった認知症患者によくみられる症候について,本書では心理学的視点を用いて解説した.認知症の症候の発現機序や心理機制はもちろんのこと,心理学用語への理解も深まる1冊である.
