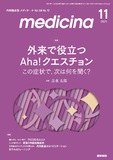
medicina Vol.58 No.12
2021年11月発行
特集 外来で役立つAha!クエスチョン――この症状で、次は何を聞く?
特集 外来で役立つAha!クエスチョン――この症状で、次は何を聞く? 「いかに診るか」をコンセプトに、内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。プラクティカルにまとめた特集に加え、知識のアップデートと技術のブラッシュアップに直結する連載も充実。幅広い診療に活かせる知識・技術が満載の増刊号も発行。 (ISSN 0025-7699)

公衆衛生 Vol.85 No.11
2021年11月発行
特集 感染症対策の変化と進化――コロナがもたらしたもの
特集 感染症対策の変化と進化――コロナがもたらしたもの 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。特集に加えて、連載企画「世界に届け! Boshi-Techo(母子手帳)」「列島ランナー」ほかを掲載し、現場に密着した話題を提供する。 (ISSN 0368-5187)

実験医学増刊 Vol.39 No.17
【特集】核酸医薬 本領を発揮する創薬モダリティ
【特集】核酸医薬 本領を発揮する創薬モダリティ 基盤技術の発展により,近年新薬承認がつづく核酸医薬.その迅速な新薬開発を可能にする作用機序から,薬物を標的分子へ安定して届ける核酸修飾と薬物輸送技術,注目集まる新たな治療薬開発の最先端まで解説します.

超生物学―次のX
私たちがいま手にしている細胞工学
実験医学誌の好評連載を単行本化.ゲノム編集を嚆矢とする革新的バイオテクノロジーと,1細胞技術・情報工学が融合し,今何が起きているのか.研究者たちの大胆なビジョンが変えてしまう新時代の細胞工学を知る.

聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍の手術とマネージメント
四半世紀にも渡り,聴神経腫瘍・小脳橋角部腫瘍手術の研鑽を積んできた著者の経験と技術が詰まった類のない1冊.本書は,知識の整理の部分と技術の部分をそれぞれ形式にこだわらずふんだんに盛り込んで解説している点が特徴的であり,他分野を目指す若手脳神経外科医にとっても,剥離や止血法など参考になる内容となっている.また,80本を超える著者の手術動画も収載し,DVDとオンラインでの視聴が可能だ.頭蓋底外科の匠の技を学べる決定版と言える.

≪新戦略に基づく麻酔・周術期医学≫
麻酔科医のためのリスクを有する患者の周術期管理
さまざまな疾患や症状などのリスクを有する患者においては,適確な術前評価と麻酔計画が重要となる.
本書では,日常診療で遭遇する頻度が比較的高いリスクを有する患者を取り上げ, 各種麻酔法の選び方や使い方,周術期管理の実際を分かりやすく解説した.また,十分な術前コントロール・評価のできない緊急手術における対応についても実践的な解説を加えた.

≪新戦略に基づく麻酔・周術期医学≫
麻酔科医のための周術期危機管理と合併症への対応
周術期における安全対策・危機管理は,麻酔科医が日常臨床で常に直面する問題であり,現在の医療現場では最も基本となる重要事項として熟知していなければならない.本書では,災害時での対応にも言及して,安全を確保するための基本を簡潔にまとめ,さらに,危機的状態が予想される重篤な合併症・偶発症について,実臨床での対応を具体的に解説した.麻酔科医必携の一冊.

≪新戦略に基づく麻酔・周術期医学≫
麻酔科医のための周術期の診療ガイドライン活用術
麻酔科医が周術期において根拠に基づいた医療を実施するために必要となる主な診療ガイドラインを術前管理,術中管理,術後管理に分けて取りあげ,その活用法について想定症例をあげて具体的に解説した.
最善の医療を求められる実際の診療でガイドラインを適切に活用できるよう,活用のポイントを実践的にまとめた.最後に,研究倫理と終末期医療に関する指針についても示した.

≪新戦略に基づく麻酔・周術期医学≫
麻酔科医のための周術期のモニタリング
周術期のモニタリングの目的は,患者のバイタルサインをチェックすることによって適切な全身管理を行い,危険兆候を早期に発見して,迅速な治療および対処を可能にすることである.本書では,神経,呼吸,循環,筋弛緩などに関する各種モニターの測定原理や特性,臨床使用の実際,問題点およびコツについて詳細に解説した. 麻酔科医が各種モニターを有効に使いこなすための必携書.

スタンダード病理学 第4版
4年制課程での医学・医療技術科学における病理学教科書のスタンダード,改訂第4版.臓器・組織の正常構造・機能に触れつつ,医療技術系の学生に必須の生体の病的変化をまとめた.病理各論では疾患の臨床症状,臨床検査所見等も盛り込み,基礎と臨床の橋渡しとなる内容である.学生は元より,医師や各医療従事者の生涯学習にも応える1冊.

管理栄養士を目指す学生のための
生化学テキスト
管理栄養士養成校の学生向けの好評の生化学教科書.文章と図版は見開きで理解できるようにし,文章はすべて箇条書きにした.図版はフルカラーとしたので,目で見て理解しやすい.重要な事項は赤い文字で強調し,管理栄養士として知っておくと便利な知識は「メモ」として随所に挿入.管理栄養士をめざす学生にはおすすめの1冊.
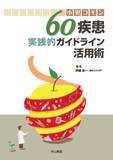
小児コモン60疾患実践的ガイドライン活用術
小児科領域の診療ガイドラインは約100にも及ぶ.定期的に改訂される内容を熟知し,診療で使いこなすのは容易なことでない.
小児科医の日常診療をサポートするため,ガイドラインを知悉した専門医により,臨床で遭遇するcommon diseaseへの活用術をダイジェスティブかつ実践的に紹介.典型例,非典型例,難治例,特異例,症例ごとに展開されるガイドラインの使い方は,まるでリアルな追体験.

消化器画像診断アトラス
東北大学消化器内科を中心として,上部・下部消化管はもとより,肝胆膵まで含んだ消化器全般にわたる疾患をとりあげ,迫力ある美しい画像を多数提示して,疾患の「概要」「典型的な画像所見とその成り立ち」「確定診断へのプロセス」「治療」の要点を画像所見と関連づけながら簡潔に解説.
一般の消化器医にも疾患の全体像と診療のポイントがよく理解できる,これまでにない画像診断アトラス.
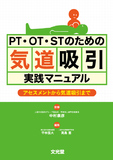
PT・OT・STのための
気道吸引実践マニュアル
アセスメントから気道吸引まで
気道吸引を業務の一部として実施できるようになったリハビリテーション関連職種のためにケースを元にした基本的知識・手順の確認および技術の習得を目的とした実践書.実際のケース紹介,問題解決への道筋の立て方とポイント,対象者の評価,手技,と順に理解できるわかりやすい構成.内容は全9章からなり,1章で紹介するケースを基に各章で必要事項を解説し,最終章でプログラム立案を行い,対象者の問題解決を図る.

大動脈弁形成術のすべて
メカニズムを識る・弁温存を目指す
本邦ではまだまだ普及していない大動脈弁形成術について,その理解を深め,手術成績向上のため,心臓血管外科医はもちろん,循環器内科医,心臓麻酔医,臨床工学技士,手術室看護師にも読んでいただけるよう,大動脈弁の解剖や病態生理から実際の方法や成績までを解説.また,実臨床で苦慮すると考えられる症例を徹底解説し,より理解を深められるよう工夫した.“負担を減らす”という大きな福音を患者さんにもたらすための1冊.
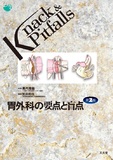
Knack & Pitfalls
胃外科の要点と盲点 第2版
外科手術の第一線で活躍する執筆陣の経験と叡知を,サイエンスに裏づけられたアートとして伝達するKnack & Pitfallsシリーズ.手術の際に知っておきたいコツ,陥りやすい落とし穴を,カラー写真と美しいシェーマで解説.手術手技に限らず,診断から術後管理に至るまで,実際的知識を満載.本第2版では,初版以来6年の間の胃外科の変化「拡大手術至上主義から化学療法併用への転換」「腹腔鏡手術の普及」の2点を取り入れアップデートした.

リウマチ・膠原病内科クリニカルスタンダード
必携 ベッドサイドで必ず役立つリウマチ・膠原病学のエッセンス
膠原病・リウマチ学領域における臨床・研究の最前線で活躍中のトップリーダーを執筆陣に迎え,若手スタッフ,研修医に向けて,臨床に必要なエッセンスを一歩踏み込んで,かつコンパクトにまとめたマニュアル.本文は箇条書きで手順のみを示し,一目でわかる図表や処方例を多用したデータブック的な要素を併せ持つ.また,詳細に突っ込んだ説明をメモ書きにまとめ,多忙な現場での使いやすさ・読みやすさを追求した充実の1冊.

幕内肝臓外科学
1980年代から30年余にわたり肝臓手術で世界の頂点に立つ幕内博士が,自身の手術のサイエンスとアートを余すことなく披瀝した記念碑とも言える歴史的1冊.肝癌切除手術,肝移植手術については,術式ごとに鮮明なカラー写真で詳細に手術手順やコツを記載し,将に幕内肝臓外科の真髄に触れることができる.図版30点,表組6点,カラー写真543点,モノクロ写真48点.

心臓の機能と力学
苦手意識を持つ人が多い心機能.そんな“心機能アレルギー”の方々へ送る,アレルギー克服のための入門書.ひとつひとつ,喩えも使ってわかりやすく解説することで,心機能・心力学が正しく分かる構成となっている.心エコー,MRI,CTなどの画像診断または心カテで心機能を評価したい人,血行動態や心機能を理論的に理解して心不全の診断・治療を行いたい人など,心機能をこれから学ぶ人や自信がない人はまず手に取ってほしい1冊.

心房細動のトータルマネジメント
治療の常識が変わる!
心房細動は最もありふれた不整脈である.従来,不整脈をどう治療するかに関心が向けられていたが,決して心房細動患者の生命予後は良くないことがわかってきた.昨今,新しい抗凝固薬が出され,心原性脳塞栓症を予防し,生命予後改善の基盤が整いつつある.本書では,抗不整脈薬を漫然と使うことを避け,「脈のコントロールから生命予後の改善へ」を治療姿勢とし,心房細動のトータルマネジメントのための考え方と方法をまとめる.
