
糖尿病プラクティス
プラクティス 36巻2号
糖尿病と時間生物学-生活習慣病としての糖尿病と体内時計との関連-
糖尿病と時間生物学-生活習慣病としての糖尿病と体内時計との関連-
病気には時間と関係の深いものがあり,朝方に多いのは心筋梗塞や脳梗塞,夜にかけて多いのはリウマチなど関節の痛みや心不全,ぜんそく発作などである.24 時間の時間周期は地球の自転によるところであるが,明暗の周期や月と地球のあいだに起こる潮汐力など時間とともに移り変わる地球上の現象の影響を受けて,生物の活動も変化する.この“時間とともに変化する生命活動”と疾病の関係については,昨年のノーベル医学賞で時計遺伝子の研究が受賞したことから,今後この領域の研究が発展していくものと期待される.糖尿病も2010 年に時計遺伝子と膵 β 細胞の関わりが明らかになってから(Nature,466:627~631,2010),糖尿病が時間との深い関わりをもつこともわかってきた.今回の特集は,こうした糖尿病と時間,あるいは明暗の周期による睡眠・覚醒といった生理的な活動と糖尿病がいかに関連しているか,その理解の一助になればと願い,国内におけるこの分野の研究に造詣の深い方々にご執筆いただいた.
本特集の最初には概日リズム(サーカディアンリズム)と睡眠に関わる科学について基礎医学の立場から,名古屋大学の小野大輔先生にご解説をいただいている.山口大学の太田康晴先生からは概日リズムとインスリン分泌,インスリン抵抗性といった糖尿病に関わる内容についてご解説いただいた.富山大学の笹岡利安先生方からは睡眠と覚醒に関わるオレキシンの観点から,糖尿病の治療戦略を解説いただいた.糖尿病の栄養学的な視点から,時間栄養学について早稲田大学の柴田重信先生から詳しくご解説をいただいた.メタボリックシンドローム・糖尿病・肥満など代謝制御について,臨床的な観点から時間栄養学の解説を,名古屋大学の小田裕昭先生方よりいただいた.
最後に,どのような時間に運動をすればよいかなど,24 時間のエネルギー代謝の観点から基礎的な解説をいただいたのは,筑波大学の田中喜晃先生方である.そして,まさに糖尿病の血糖変動を24 時間のエネルギー代謝から臨床的な視点でご解説いただいたのは国際医療福祉大学塩谷病院の山内恵史先生方である.これらの専門の先生方からまさに時間と睡眠・栄養・糖尿病との関わりのエッセンスについて論文をいただいており,読者諸兄の忌憚のないご意見をいただければ幸いである.
(NTT東日本札幌病院 黒瀬 健・中之島クリニック 吉岡成人)

糖尿病プラクティス
プラクティス 36巻1号
低血糖はなぜいけないか-臨床・疫学・社会からのアプローチ-
低血糖はなぜいけないか-臨床・疫学・社会からのアプローチ-
現代の糖尿病治療で低血糖がよくないということに異論を唱える人はだれもいないと考えられる.
しかしながら,30 年程前には著名な糖尿病の教科書に「グリコヘモグロビンを低下させるためには多少の低血糖もしかたない」という記載があった.グリコヘモグロビンと糖尿病合併症の関係が次々と明らかになり,数値を改善させることが糖尿病の治療の目標であり,SU 薬とインスリンしかなかった時代を反映していたと考えられる.
その後,なんとなく低血糖が臨床上悪いような印象があったのであるが,低血糖をきたさない糖尿病治療薬が次々と登場し,ACCORD 試験の結果から糖尿病治療における低血糖と死亡リスクに対する関心が一気に高まった.
本特集では,低血糖の臨床・疫学・社会からのアプローチとして,各分野のエキスパートに執筆をお願いした.麻生好正先生には低血糖の定義と,臨床的に問題となっている高齢者や夜間の無自覚性低血糖の病態・診断・治療について詳細に解説していただいた.辻本哲郎先生には重症低血糖では何が起き,どのような危険が潜んでいるかについて豊富な自験データを交え執筆いただいた.さらに,そのなかで特に問題となる,心疾患,認知機能に関して,それぞれ,後藤 温先生,鈴木 亮先生に病態と疫学について解説していただいた.低血糖はほとんどが糖尿病治療に伴うものであるが,それ以外の原因による低血糖も日常臨床では看過できない.恒川 新先生には内分泌疾患や薬物などによって生じる低血糖について概説いただいた.低血糖による交通事故は,被害者はもとより,加害者・主治医にとっても痛ましいことである.わたしどもが気をつけておかなくてはならない,低血糖や薬物療法中の交通事故の法的解釈について,医師であり弁護士でもある田邉 昇先生に判例を交えて寄稿いただいた.
本特集によって読者の皆様の低血糖に対する理解が深まり,糖尿病患者のQOL 向上につながれば幸いである.(みうら内科クリニック 三浦義孝)

新型コロナウイルス感染症と血管内皮
循環器予防医学の視点から探る重症化予防策のヒント
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では,基礎疾患を有する患者の死亡率が高いことが報告されており,高齢者や喫煙者では重症化しやすいことも明らかになっている.本書では,循環器予防医学の視点からCOVID-19の病態生理について解説し,重症化の予防や診断・治療に関して新たな戦略となりうる概念をまとめた.
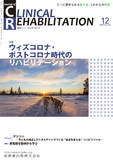
J. of Clinical Rehabilitation 29巻13号
ウィズコロナ・ポストコロナ時代のリハビリテーション
ウィズコロナ・ポストコロナ時代のリハビリテーション
2020年は東京オリンピック・パラリンピックをはじめとして,だれもが華やかな年になることを想像していたのではないだろうか.しかし,年明けから新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中で猛威をふるい残念な結果を迎えた.2020年11月1日現在,世界中で4,594万2,902名の感染者が報告されており,死者は1,192,644名に達している.感染者数は国別に,米国8,952,086名,インド8,184,082名,ブラジル5,516,658名と続いている.わが国では感染者102,062名(クルーズ船712名を除く),死者1,775名(クルーズ船13名を除く),と報告されている.第2波も到来し,状況は深刻さを増しており,事態の長期化は避けられず,医療界のみならず社会全体での対応が否応なしに求められている.また,リハビリテーションの主な対象者である高齢者や重症患者がCOVID-19で重篤になりやすく,その治療の困難さや感染の蔓延化に悩まされている現状がある.
これまでのリハビリテーションは,患者に寄り添うため「3密状態」で行うのが当然のことであった.しかし,COVID-19患者に際してはリハビリテーション医療関係者の厳格な感染予防管理が必須となり,可能な限り「3密回避」が必要となって,状況が一変した.さらに,第2波への対応,再感染予防,第3波の防止,後遺症にどう対応するか,地域医療構想にどう反映させるか,感染対策と医療経済・国民経済の両立をどうするか等,多くの国民的課題への対応が求められ,テレビ,新聞,インターネット等,マスコミでもCOVID-19の話題を聞かない日は皆無である.
本特集では,このようなウィズコロナ時代ならびに将来のポストコロナ時代において,リハビリテーション医療全体にどのような影響が生じるのか,医学史的にはどうか,病院・施設での感染予防対策や感染者のリハビリテーションをどのように行うべきか,といったテーマを取り上げた.執筆者は,COVID-19対応経験のある先生を中心に,極めて充実した内容になっている.すなわち,上月先生らからは,総論としてCOVID-19がリハビリテーションにもたらす影響を,佐々木先生らからは急性期病院での重症COVID-19患者へのリハビリテーションの実際を,土岐先生らからは急性期病院でのCOVID-19院内感染対策を,岡本先生らからは回復期・生活期リハビリテーション病院でのCOVID-19院内感染対策を解説していただいた.また,海老原先生からはウィズコロナ・ポストコロナ時代のフレイル対策とリハビリテーションを,江藤先生からは医学史からみた感染症パンデミックとリハビリテーションを解説していただき,共通課題としてのフレイル対策や医学史からみたCOVID-19の位置づけ等を俯瞰していただいた.
本特集は,ウイズコロナ・ポストコロナ時代において,読者がリハビリテーション医療職として,患者や社会に対してどのような役割を果たせるのか,どのように「変化」していかねばならないのかを考えるのに役立つものと期待している.(編集委員会)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻12号
サルコペニアの診断,治療,予防
サルコペニアの診断,治療,予防
サルコペニアがRosenbergにより世界で初めて1989年に提唱されて約30年が経過した.その後,病態,診断等の研究が進み,骨格筋量の低下と筋力/身体機能低下をもつ病態としてサルコペニアが定義されるようになった.さらに,サルコペニアは高齢者においてその健康寿命を脅かすだけではなく,さまざまな疾患に関連し,その予後に影響を与えることが明らかとなってきた.これらの研究の進展を受けて,欧州やアジアの各地より専門職によるワーキンググループが立ち上がり,操作的定義や予防,治療の提言がなされるようになった.日本を含むアジアの各国ではAWGSを用いたサルコペニアの診断が多くなされるようになり,サルコペニアの研究が飛躍的に進歩した.さらに2016年にはサルコペニアがICD-10のコード(M62.84)を取得し,国際的にサルコペニアが独立した疾患として認識されるに至った.わが国でも2018年よりサルコペニアがレセプト病名となった.
リハビリテーションにおけるサルコペニアの有病率は比較的高く,約50%である.さらに,サルコペニアはリハビリテーションにおける日常生活動作(ADL)や嚥下障害の改善,自宅退院率等の重要なアウトカムと負の関連がある.健康面では,サルコペニアは,転倒と骨折のリスクを増加させ,ADLの低下,心疾患,呼吸器疾患および認知機能障害に関連する.また,運動障害を引き起こし,生活の質(QOL)の低下,自立性の喪失や長期にわたる介護の必要性,あるいは死亡のリスクとなる.また,サルコペニアに対する治療的介入は運動療法と栄養療法の併用が原則である.しかし,リハビリテーションの領域で適切にサルコペニアがスクリーニング,診断され,治療が行われているとは言い難い.機能障害に対するリハビリテーションの標準的プログラムに加えて,レジスタンストレーニングの処方や,高たんぱく質高エネルギーの栄養サポート,口腔や嚥下管理,薬剤管理等,多職種の連携が重要である.
本特集では,リハビリテーションの医療者が知っておくべき筋疾患としてのサルコペニアの診断,治療,予防について最新の知見をまとめた.いずれの項目も最新情報が掲載されており,いずれの執筆者もこの領域におけるオピニオンリーダーである.多忙の中で執筆していただいた各先生方に心より御礼を申し上げる.サルコペニアはリハビリテーション医療の対象疾患のひとつである.リハビリテーション医療の日常診療でサルコペニアを診断・治療し,医原性サルコペニアを予防することが当たり前になり,高齢者の機能・活動・参加が最大化されることを期待する.本特集がこの領域におけるスプリングボードになれば幸いである.(編集委員会)
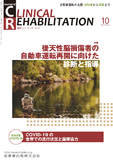
J. of Clinical Rehabilitation 29巻11号
後天性脳損傷者の自動車運転再開に向けた診断と指導
後天性脳損傷者の自動車運転再開に向けた診断と指導
近年,高齢者,認知症者の運転による交通事故,さらに,脳卒中や脳外傷等の後天性脳損傷に起因する症候性てんかんによる自動車事故に関する多くの報道から,脳損傷者の運転能力の有無,運転免許所持の是非を問う社会的関心が極めて高くなった.しかし一方で,自動車運転は,社会参加,社会復帰のためには必須となる地域が数多く存在することから,運転能力評価にかかわる多職種間で,安全運転に必要とされる一定の基準を共有することが求められている.この傾向は,車社会先進国といわれる欧米において顕著にみられる.
英国では,政府が運転免許庁(Driver and Vehicle Licensing Agency;DVLA)を設置し,医療専門職向けに140 ページにわたり,各種疾患に起因する障害者の運転の適否を示したガイドラインを作成している.また米国では,米国医師会が,300 ページ以上にわたって,“Clinician’s guide to Assessing and Counseling Older Drivers” と題する高齢ドライバーの運転基準を,運転リハビリテーション専門師協会が運転能力にかかわる各障害に関するチェックポイントを52 ページにわたりガイドラインとして公表している.また,カナダ医師会は医師に対し,「患者の運転能力を適切に判断するべきである」とし,判断材料の一助として,“Determining Medical Fitness to operating Motor Vehicles” と題する冊子を公表している.さらに,欧州連合(EU 運転免許制度)でも,一般運転手と職業運転手を分けて運転再開基準を提示している.このように欧米の先進諸国では,統一した運転再開基準が公表されている.
しかし,わが国ではいまだこのようなガイドラインは作成されていない.そこで,本特集では,第一線で自動車運転支援に精力的に取り組んでおられる先生方に,わが国に即した運転再開の基準について,minimum requirement として,その要点をまとめていただいた.
本特集は,まずはじめに,運転再開支援を行ううえで必要な各種制度について,森口真吾先生,一杉正仁先生に,わが国の道路交通法,運転再開の手順,事故時の医療者および事故当事者の法的責任等を解説していただいた.次いで,武原 格先生に,自動車運転に必須な身体機能を,四肢体幹,視覚,聴覚機能,高齢者に分けて解説いただき,あわせて身体障害を補うべく自動車改造についても触れていただいた.加藤徳明先生には,自動車運転に必須な高次脳機能について,その内容,検査方法のご説明をいただいた.さらに高齢者の運転についてのチェックポイントも示していただいた.そして,後天性脳損傷者に合併しやすい循環器疾患,糖尿病,睡眠時無呼吸,そして薬剤に関する考え方を,渡邉 修先生にまとめていただいた.最後に,地域における自動車運転支援の実際を,富山県の指導方法を例に,影近謙治先生にご提示いただいた.
以上,5 項目の内容は,自動車運転を再開する後天性脳損傷者を指導する専門職にとって,minimum requirement の知識である.運転再開を支援する専門職の皆様にとって,少しでもお役に立てていただければ幸いである.(編集委員会)
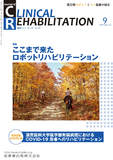
J. of Clinical Rehabilitation 29巻10号
ここまで来た ロボットリハビリテーション
ここまで来た ロボットリハビリテーション
最近はリハビリテーション(以下リハ)医学,医療の分野でロボットを目にする機会が急増している.大規模な国際学会,国内学会では当然のようにリハロボットの展示が行われ,国際的にも熾烈な開発競争が行われており,わが国においても多くのリハロボットが開発されている.ロボットリハの最大の長所は多様な課題を同じ条件で多数回行えることである.しかし,単にロボットを使えば効果があるわけではなく,ロボットリハを行うためにはこれまでのリハ医療で培われた多くの概念,特に運動学習の知識と応用が重要である.運動学習による行動変化のためには訓練量,フィードバック,適切な難易度の調整が特に重要である.訓練量はロボットを用いたリハ医療では比較的獲得しやすいので,フィードバック方法と難易度の設定が鍵となり,既にそれらを組み込み済みのロボットも出現している.さらに2020年4月の診療報酬改定により運動量増加機器加算が新設されたことも追い風となっている.
一口にリハロボットといっても多くの違いがあり,本特集では5つのロボットについて各先生から解説いただいた.内山侑紀先生(兵庫医科大学リハビリテーション科)からはイスラエル製のロボットを日本人の体型に合わせて改良した上肢用ロボット型運動訓練装置ReoGo®-J について,中島 孝先生(国立病院機構新潟病院脳神経内科)からは既に神経筋疾患に対して医療機器としての承認を受けているHAL医療用下肢タイプについて,平野 哲先生(藤田医科大学医学部リハビリテーション医学I講座)からは片側下肢麻痺患者の歩行練習支援に特化したウェルウォークについて,松下信郎先生(西広島リハビリテーション病院)からは軽度から中等度の歩行障害を対象としたHonda歩行アシスト®について,上野 真先生(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科リハビリテーション医学)からはリーチング動作の実現を目的とした上肢用ロボットCoCoroe AR2についてそれぞれ解説いただいた.ロボットによっては使用前に講習が義務づけられているものもあり,価格もさまざまである.今後もリハロボットはさらなる発展を遂げる分野であるが,ロボットは決して療法士の代わりにリハ治療を行う存在ではなく,リハ医療全体の中でどのようにリハロボットを使っていくかが問われる.state-of-the-artに触れることで,リハ医学の進歩を味わって欲しい.(編集委員会)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻9号
摂食嚥下障害に対する電気・磁気刺激療法
摂食嚥下障害に対する電気・磁気刺激療法
摂食嚥下障害は特に高齢者にとっては最後の楽しみともいわれる「食べる楽しみ」を奪う原因となり,リハビリテーション(以下リハ)医学,医療においては日常生活活動の中でも極めて重要な分野である.摂食嚥下障害に対しては多くのリハ治療法が用いられているが,残念ながらエビデンスのあるものはまだ少ない.一方,電気刺激療法はかなり古い歴史があり,20世紀後半からは電気刺激療法,磁気刺激療法がリハ医療においても積極的に使用されるようになってきている.最も普及しているのが末梢神経に対する電気刺激療法であり,わが国においても日常のリハ診療で広範に用いられている.また,最近は一部の施設においては経頭蓋直流電気刺激,経頭蓋磁気刺激も積極的に行われている.しかし,摂食嚥下障害に対する電気・磁気刺激療法は比較的最近行われるようになったことからその普及はまだ十分ではない.
本特集では,5人の専門家から執筆いただいた.藤田医科大学医学部リハビリテーション医学I講座の加賀谷 斉先生からは,オーバービューとして電気・磁気刺激療法を解説いただいた.電気・磁気刺激療法にはそれぞれ中枢神経刺激,末梢神経刺激が存在することから,その後に各論として,経頭蓋直流電気刺激療法について聖隷淡路病院の重松 孝先生,神経筋電気刺激療法について日本医科大学大学院医学研究科リハビリテーション学分野の松元秀次先生,反復経頭蓋磁気刺激療法について三重大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学分野の百崎 良先生,末梢神経磁気刺激療法について藤田医科大学医学部リハビリテーション医学I講座の戸田芙美先生から執筆いただいた.特に神経筋電気刺激療法については現在市販されている製品も多いことから,各製品についても触れていただいた.Q&Aでは,「摂食嚥下障害に対する適用はいつからどのように始まったか?」「適応と禁忌,使用方法は?」「どのような効果が得られるか?」「今後の展望は?」等各治療法のポイントについてまとめてもらっている.
摂食嚥下障害に対する電気・磁気刺激療法は歴史が浅いこともありまだ十分に広まっているとは言い難いが,近年はそのエビデンスが蓄積されつつある.特に電気刺激療法はリハ関係者にとってなじみ深い治療法であり,エビデンスのある治療法が少ない摂食嚥下障害に対しての電気・磁気刺激療法は注目すべき治療法と思われる.今後の発展も期待され,必要に応じて積極的に活用いただきたいと願っている.(編集委員会)
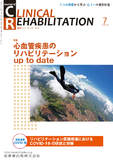
J. of Clinical Rehabilitation 29巻8号
心血管疾患のリハビリテーションup to date
心血管疾患のリハビリテーションup to date
わが国における身体障害者手帳所持者数の中で内部障害は肢体不自由に次いで多く,内部障害の過半数が心臓機能障害である.そして,心血管疾患のリハビリテーション(以下リハ)については質の高いエビデンスも既に得られている.しかしながら,わが国において心血管疾患のリハは普及が最も遅れている分野の一つではないだろうか.その原因としては,他の分野のリハに比してリスク管理が難しい,循環器内科医や心臓血管外科医の十分な協力が得られないと行いにくい等が考えられる.けれども,心血管疾患のリハは急性期のみならず,回復期,生活期と生涯継続されるべきものである.特に,急性期病院では在院日数短縮のため十分なリハを受けられないまま退院せざるを得ないケースも多いと思われるが,その後のリハについても不十分であるのが実状である.
本特集では,特に5つの病態についてそれぞれのエキスパートからup to dateな情報を執筆いただいた.埼玉医科大学国際医療センターの牧田 茂先生からは心筋梗塞,藤田医科大学病院の河野裕治先生からは心不全,順天堂大学保健医療学部の高橋哲也先生からは心臓外科手術後,聖隷浜松病院心臓血管外科の立石 実先生からは小児心疾患,東北大学大学院医学系研究科の三浦平寛先生からは心臓移植後をテーマとして,それぞれ,急性期,回復期,生活期のリハはどのように行うか? さらにはリハ専門職に望むことについて述べていただいた.心筋梗塞,心不全,心臓外科手術後は特に急性期病院ではよく出合う疾患や病態であるが,たとえ自分の専門領域でも常に最新の情報を把握するのは決して容易ではない.本特集が皆さんの知識の上書きに役立てることを期待している.また,小児心疾患,心臓移植後については,経験したことのないリハ専門職も多いと思われるが,臨床の場面においては待ったなしであり,急に対応を求められたときに本特集が有益な情報になることは間違いないと思われる.
本特集においては特に各テーマ内の“リハ専門職に望むこと”をぜひ読んで欲しい.心血管疾患のリハにおいてもリハ専門職は多くのことを期待されているのである.残念ながら,期待に十分応えられていないのが現状ではあるが,いつまでもそれが許されるわけではない.本特集を契機に多くのリハ専門職が心血管疾患のリハに興味をもち,心臓機能障害をもつ多くの患者さんに役立てることを期待する.(編集委員会)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻7号
臨時増刊号
脊髄損傷のリハビリテーション医学・医療―最前線と未来への展望
脊髄損傷のリハビリテーション医学・医療―最前線と未来への展望
この臨時増刊号の企画を構想していた昨年の秋頃は,2020年夏に開催される東京パラリンピックを世界中のパラアスリート,そして私も含め多くの人々が待ち望み,楽しみにしていた.しかし,2020年になり新型コロナウイルスの感染拡大により世界の状況は一変し,3月にはWHO がパンデミックを宣言し,4月には日本でも緊急事態宣言が発令された.そして,残念ながら東京オリンピック・パラリンピック開催の1年間の延期が決まった.ただ,今はこの難局を世界中の人々が協力し知恵を出し合い乗り越えていくことが大切である.この難局を乗り越えた先に,世界中の人々の団結の証として新しい時代に向けた象徴的な大会として東京オリンピック・パラリンピックが開催されることを願う.
日本では,1964年にパラリンピックが,今回と同じ東京でオリンピックとともに開催されている.56年前に開催された東京パラリンピックは,中村裕先生の尽力により実現した.中村裕先生は,1960年にグッドマン博士が英国のストークマンデビル病院で脊髄損傷者の治療にスポーツを取り入れていることに感銘を受け,わが国においても脊髄損傷者のスポーツ参加を積極的に進めた.そして,現代の障がい者スポーツの基礎を築くと同時に,脊髄障害者に積極的にスポーツをさせて社会参加させるという考えは,脊髄損傷者のリハビリテーション医療に大きく貢献した.このときから約50 年間が過ぎ,脊髄損傷者のリハビリテーション医学・医療は大きく発展した.電気刺激やロボット技術を利用した機能再建,ボトックスやITB による痙縮治療等さまざまな新しい治療が開発され,そして,再生医療も現実のものとなり脊髄損傷者のリハビリテーション医学・医療にも大きな変革が起きようとしている.さらに,脊髄損傷者の治療として始まった障がい者スポーツも,今や非常に高レベルの競技スポーツに発展している.
50年以上の歴史を経て,再び東京でパラリンピックが開催される.脊髄損傷者を含むわが国の障がい者スポーツを未来に向けて発展させる大会になることは間違いない.本臨時増刊号も,障がい者スポーツを含め脊髄損傷者のリハビリテーション医学・医療の新しい未来への発展に寄与できる内容にしたいと考え企画した.そこで,テーマを「最前線と未来への展望」とし,脊髄損傷者の障がい者スポーツも含めたリハビリテーション医学・医療の最新の知見と未来への展望について,それぞれの分野の第一線で活躍されている先生方にご執筆いただいた.さらに,巻頭の座談会では,東京パラリンピックに向けた障がい者スポーツの現状と未来について,東京パラリンピック開催に向けて第一線で活躍されている陶山哲夫先生,三井利仁先生,安岡由恵先生にお話を伺った.また,コラムではトピックス的な内容も含め,脊髄損傷者のリハビリテーション医療や障がい者スポーツにかかわるすべての方々に,ぜひ知っていただき実践で役立ててもらいたい項目を選び執筆いただいた.本臨時増刊号が脊髄損傷のリハビリテーション医学・医療の新しい未来への発展に少しでも寄与できれば幸いである. (編者:中村 健)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻6号
小児のリハビリテーション
小児のリハビリテーション
わが国では少子高齢化の進行が止まらない.厚生労働省の発表によれば,2019年の日本人の国内出生数は86万4千人となり,1899年の統計開始以降初めて年間出生数が90万人を下回った.第1次ベビーブーム期の約270万人,第2次ベビーブーム期の約210万人という数に比べれば少子化がいかに進んだかがわかる.この小児人口の減少は,医療の現場にもさまざまな変化をもたらしている.臨床現場全体では,経験する小児疾患の頻度が少なくなり,分野によっては小児患者への対応に苦慮することが多くなっている.一方で,小児疾患の診断や治療の進歩は著しく,小児の成長を取り巻く環境も変化している.その結果,リハビリテーション医として知っておくべき新しい疾患概念や治療法が登場している.そこで本特集では最近の小児リハビリテーション医療のトピックを取り上げ,以下のように解説いただいた.
オーバービューでは井之上寿美先生ら(島田療育センターはちおうじ)に小児におけるリハビリテーションの特徴と最近の課題を示していただいた.近年,児童・生徒の運動器検診が推進されている.帖佐悦男先生(宮崎大学)には膨大なご自身の調査結果から小児の運動器の機能不全を早期に見い出し,将来のロコモティブシンドロームを予防することの重要性を提示していただいた.小児を対象としたロボットリハビリテーションに関する最近の話題を上野友之先生(筑波大学整形外科)に執筆いただき,脳性麻痺児に対する歩行練習・歩行補助具としてのロボット,装着型歩行訓練ロボットの最新の話題を紹介いただいた.また,小児の心疾患術後のリハビリテーションについて,鈴木孝明先生(埼玉医科大学国際医療センター)に疾患の特徴と術式を詳説していただいた.NICUを有する施設では超未熟児に対する理学療法や言語聴覚療法の依頼が多いため,欅 篤先生(高槻病院リハビリテーション科)にNICUで必要なポジショニング,呼吸理学療法,哺乳指導,発達支援について解説いただいた.半澤直美先生(よこはま港南地域療育センター)にはリハビリテーション医が知っておくべき発達障害の診断や支援のあり方等を解説いただいた.
小児に対するリハビリテーション医療は長い期間にわたることが多く,その中で最適な治療を実施することが求められる.本人へのアプローチと同時に,両親や家族に対する対応も必要で,リハビリテーション医が最新の知識を確認しておくべき分野である.本特集が小児リハビリテーション医療の現場に貢献できれば幸いである.(編集委員会)
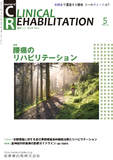
J. of Clinical Rehabilitation 29巻5号
腰痛のリハビリテーション
腰痛のリハビリテーション
日本人での腰痛有訴率は40~50%とされ,頻度の高い疾患である.腰痛は短期間に改善する例がある一方で,原因が不明で治療に難渋する症例も多い.スポーツに起因する腰痛や小児での腰痛は病態の把握や治療が困難な場合が多く,臨床現場で問題となる.超高齢社会を迎えたわが国では,ロコモティブシンドローム(ロコモ)やサルコペニアが注目され,その腰痛とのかかわりが指摘されている.また,最近では腰痛を器質的異常としてのみではなく,心理的・社会的疼痛症候群としてとらえることの重要性が認識されるようになった.運動療法は腰痛の多くの例に対して中心的な治療法である.そこで本特集では腰痛に関するこれらの最近のトピックを取り上げ,運動療法をはじめとしたリハビリテーション医療でのポイントを解説いただいた.
スポーツ障害で生じる腰痛は頻度が高く,保存治療が選択されることが多い.金岡恒治先生(早稲田大学)に腰痛の誘発動作による分類をお示しいただき,病態と具体的な運動指導を詳述いただいた.アスレチックリハビリテーションの現場で直ちに役立つ内容である.小児での腰痛は頻度が低いものの,種々の原因疾患のスクリーニングと的確な病態の把握が重要である.後藤 強先生(徳島大学)には小児の腰痛の病態に応じた具体的な治療プログラムをご提示いただいた.サルコペニアは高齢者の増加にともなって腰痛の原因として重要な位置を占めるようになった.診断基準が確立されているが,その病態は多彩で治療法も確立していない.そのなかで運動療法は最も推奨される治療で改善効果が期待される.酒井義人先生(国立長寿医療研究センター)には腰痛とサルコペニアに関する現時点での最新の知見を解説いただいた.ロコモは加齢にともなって運動器が障害され移動機能が低下している状態と定義される.ロコモに占める脊椎疾患の割合は高く,腰痛を有する例が多い.粕川雄司先生(秋田大学)にはロコモと腰痛の関連を説明いただき,具体的な運動療法を示していただいた.腰痛には心理社会的因子が影響することは古くから知られていて,その評価の重要性が強調されている.そこで最近は画像所見のみによらず,多面的評価が求められている.中楚友一朗先生(愛知医科大学)には実際の評価方法とその結果に基づくリハビリテーションの実際を解説いただいた.
『腰痛診療ガイドライン2019』(日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,腰痛診療ガイドライン策定委員会)では,運動療法について急性腰痛,亜急性腰痛,慢性腰痛のそれぞれについて評価された.そのうち急性腰痛と亜急性腰痛に対してはエビデンスが不明であるとされるものの,慢性腰痛に対しては,「運動療法は有用である」ことが強く推奨(推奨度1,エビデンスの強さB)されている.本特集がリハビリテーション医療の現場で,腰痛に対する病態に応じた最適な運動療法実施に貢献するものと期待している.(編集委員会)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻4号
内部疾患の運動療法のエビデンスと実践
内部疾患の運動療法のエビデンスと実践
運動療法は理学療法,作業療法を含めたリハビリテーション(以下リハ)の一部という認識であったが,リハとは切り離されて1 つの独立したものとして扱われていると感じたことがある.かなり前のことであるが,コメディカルのリハの教科書編集に携わった際に,医学全集を多く手掛けていらっしゃる監修者から,本のタイトルを「リハビリテーション・運動療法」にして心疾患等に対する運動療法を強調してほしいと言われた.運動療法はリハに含まれ,また運動療法には筋力増強や関節可動域訓練もあることから,タイトルとして違和感があると反論した.ところが,医療全体からみると運動療法は食事療法と並び予防医学の見地からも語られるべきものであると言われ,リハとは別扱いしたほうがわかりやすいとのことであった.リハというと障害の三次予防に位置付けられるが,一般の医療従事者からみると健常者の一次予防,発症後の疾病の二次予防への運動療法の役割のほうが重要というわけである.
本特集で扱う運動療法の対象は循環器,代謝疾患等のいわゆる内部疾患である.特に心疾患,末梢動脈疾患の運動療法には多くのエビデンスが蓄積されている.臨床的な効果の実証のみならず,分子レベルでのメカニズムが解明されつつある病態も少なくない.有酸素運動というシンプルなモデルが研究しやすいのかもしれないが,運動器,脳血管障害のリハのエビデンスを一歩リードしていることは確かである.しかし,決して有酸素運動だけではなく,最近では筋力増強,さらには多職種が関与する包括的リハも唱えられていて,リハにおける内部疾患,運動療法の重要性は増している.
リハ従事者の運動療法への関心はかつて大きいとはいえなかった.運動学習を一大命題として掲げるリハ医にとっても,スキルを志向する療法士にとっても,シンプルな運動療法をリハの使命と考えていなかったのかもしれない.しかし,急性期病院でのリハが医療の中で重視され,リハ従事者に心疾患を主とするリスク管理の知識とスキルが求められるようになり状況は変わった.内科医が専門的にリハ医療に携わるようになったことも転機だったと思う.また,認定あるいは専門理学療法の1 つの領域,つまり心リハを中心とした内部障害理学療法としてまとめられたことも方向性を示した.加えて,自転車エルゴメータ等を用いて行う運動負荷試験に療法士が直接関与するようになり,身近な存在になっていることも重要な要素である.
内部疾患の定義は曖昧で,本来は呼吸器や腎疾患も含むと思うが,本特集では運動療法のエビデンスの視点で循環器疾患と糖尿病に焦点をあてて,各々の領域の専門家に実践的見地に立って執筆いただいた次第である.(編集委員会)

J. of Clinical Rehabilitation 29巻3号
社会的行動障害へのアプローチ
社会的行動障害へのアプローチ
高次脳機能障害へのリハビリテーション(以下リハ)医療の取り組みとして,2001年より開始されたモデル事業時代の実態調査でも,社会的行動障害は高次脳機能障害の症状として頻度の多い4大症状の一つとして挙げられた.社会的行動障害と一言で表されるが,その状態は多岐にわたり,固執性,易怒性,意欲低下,病識欠如等多くの病態を含む「社会参加の制限につながる行動障害」の総称である.リハ医療がどのようにこの障害に取り組んでいけばよいのか,現場では日々苦慮している状況にある.
高次脳機能障害の支援が全国的に事業化され,10年余り経過する中で支援のうまくいかない困難事例の大部分が社会的行動障害の強い事例であると考えられ,2016年~2018年に厚生労働科学研究で社会的行動障害の実態調査が実施された.その詳細な報告およびその成果物として「社会的行動障害への対応と支援」というマニュアルが昨年7月に公開された.そのような動きの中,本誌で社会的行動障害にスポットライトを当てる特集を企画した次第である.
本特集では,まず社会的行動障害についての概説,さらに2016年度より実施された実態調査の結果について,高次脳機能障害支援事業の開始当初から中心的にご活躍された中島八十一先生に解説していただいた.次に,多くの精神症状・行動障害の中で頻度の多い「易怒性,感情コントロール障害」「意欲・発動性低下」にターゲットを絞り,それぞれ京都大学の上田敬太先生,埼玉総合リハビリテーションセンターの先崎 章先生に執筆いただいた.これらの精神科医療との狭間にある症状に対する薬物治療の実際と,リハ医療でも実践可能な非薬物的治療(心理療法,環境調整等)にも言及していただいている.また社会的行動障害は当事者の社会参加を制限するにとどまらず,介護者,特に家族に大きな負担感を与える障害であることから,家族支援をテーマに東京慈恵会医科大学の渡邉 修先生に執筆いただいた.最後に,社会的行動障害の一端ではあるが,起きてしまうと大きな問題となる「触法行為」を取り上げ,触法行為と精神障害の関係,鑑定書・意見書を求められたときの留意点等を弁護士の中井克洋先生に解説いただいた.
本特集では,「明日からの診療に役に立つ情報をお届けする」をテーマに企画したが,それぞれの領域の第一人者の先生方にご執筆いただくことができ,大変充実した内容になったと考えている.本特集が高次脳機能障害患者の社会的行動障害の対応に日々苦慮する先生方の診療の一助となればと期待している.(編集委員会)
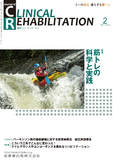
J. of Clinical Rehabilitation 29巻2号
筋トレの科学と実践
筋トレの科学と実践
近年,筋萎縮・筋力低下の問題は高齢者のサルコペニアに焦点が当てられるなか,栄養学を含めた学際的な領域へと発展してきている.単に食事を十分とって運動するというだけでは解決できない問題のようだ.先日,サルコペニア肥満の症例を診る機会があったが,外見では筋萎縮はわからないということを実感した.そもそも脂肪と筋組織が違うのは当然で,栄養補給もその視点で考えるのは同じく当然のことである.しかし,普通の食事をとって普通のsedentaryな生活を送っている高齢者のなかにもサルコペニアは存在するわけで,改めて筋萎縮の問題の深淵さを感じる.
リハビリテーション(以下リハ)以外の領域でサルコペニアやフレイル(frailty)が取り上げられる機会が増える一方,リハではどう対応するのかを問われることも増えている.筋トレはリハの原点の1つでもある.いろいろ要件はあるものの,この問いに対しては筋トレと答えるわけであるが,踏み込んだ話になると答えられないことも多い.そもそも筋肥大はどういうメカニズムで起こるのか,どうすれば効率的に筋肥大が起こるのか,筋肥大は筋力増強と同義なのか等,リハ従事者としては生化学,そして生理学的な基礎に立ち返って答えなければならないと考える.
高齢者のサルコペニアの話題から離れて,若い層の中でも筋トレがブーム化している.体育系の学問を修めた専門家が下支えして,スポーツジム文化が育っている.ボディビルとまでいかないまでも,ダイエットを意識した筋トレ人口は相当数あるのではないだろうか.その延長線上では電気刺激や加圧トレーニングといった技術を取り入れたものまで用意されている.治療としての電気刺激についてはリハ領域でも長い歴史があるが,商業ベースで使われる電気刺激装置に関する知識は乏しく,果たして効果はどの程度なのかと質問されても答えに窮する.一方,リハでは筋トレと電気刺激を組み合わせた新技術が研究され,既にシステム化されており,無重力での廃用性筋萎縮に学問的に取り組んだ報告もある.加圧トレーニングも医療界で取り組む例が出てきており,高齢者,種々の基礎疾患をもった患者にも安全に適用できることが報告されている.
本特集ではこのような社会背景に対して,筋トレを正面から扱い,生化学,生理学,栄養学,理学療法学,そして医学における当該領域の第一人者から執筆いただくことにした.高齢者,患者のためだけのテーマでなく,広く一般の筋トレブーマーにも役立つ内容になっているので,リハに携わる読者には自身の専門領域の知識の補充として役立てられたい.(編集委員会)
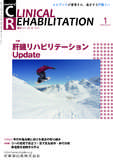
J. of Clinical Rehabilitation 29巻1号
肝臓リハビリテーション Update
肝臓リハビリテーション Update
肝臓は代謝中枢機能を持ち,また消化吸収に重要な胆汁分泌や生体に不要な物質を排泄する胆汁色素代謝・解毒等,身体のホメオスターシスや健康を維持するための多くの重要な役割を果たしている.しかし,肝臓は「沈黙の臓器」といわれるように,病気になっても当初は自覚症状に乏しく,肝硬変や肝がんといった重篤な事態になって初めて気づかれる場合も少なくない.重度の肝臓機能障害では,脱力感,掻痒感,筋肉痛,体重減少,腹水による腹部の膨満感,浮腫,消化管の静脈瘤の破綻による吐下血,脳症による意識障害・昏睡,食思不振・悪心・嘔吐等の症状により日常生活活動が制限される.
肝臓機能障害は2010年4月に新たに追加された内部障害である.CRでは2011年4月号で「見えない障害,肝臓のリハビリテーション」というわが国初の肝臓リハビリテーションの特集を組んだ.それから,8年が経過した.この間に,肝臓機能障害の身体障害認定基準が緩和され,肝臓リハビリテーションの運動療法のエビデンスが大きく進歩を遂げた.
そこで,本特集号では,肝臓機能障害の基礎疾患,身体障害認定基準の変更内容,障害の特徴,ADLや運動耐容能をレビューするとともに,慢性肝炎,肝硬変,肝がん,肝移植後の肝臓リハビリテーションの方法と効果について最新知見やエビデンスを交えながら解説いただくこととした.
執筆者はこの領域でトップランナーとしてご活躍されている先生方であり,極めて充実した内容にしていただいた.すなわち,上月正博先生からは総論として肝臓リハビリテーションの考え方を明快に示していただいた.また,NAFLD/NASH患者のリハビリテーションを小田耕平先生らに,肝硬変患者のリハビリテーションを筆保健一先生らに,肝がん患者のリハビリテーションを西田佳弘先生らに,小児の肝移植後患者のリハビリテーションを峯 耕太郎先生らに,肝移植術後患者に対する微弱電気刺激療法を花田匡利先生らに,それぞれ,病態,運動耐容能やADL,運動療法の効果,食事療法・薬物療法の効果,リハビリテーション普及の阻害因子と解決法等に関してわかりやすく解説していただいた.
肝臓機能障害は腎臓機能障害と並ぶリハビリテーション医学・医療のこれからの大きなターゲットである.本特集により肝臓機能障害を正しく理解するスタッフが増え,自信を持ってそのリハビリテーションの普及にますます貢献されることを期待する.(編集委員会)
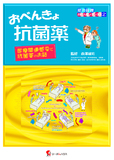
おべんきょ抗菌薬
医療関連感染と抗菌薬のお話
薬剤耐性菌(AMR)対策が世界的に深刻な問題となり,医師,看護師など職種を問わず,抗菌薬の知識が求められる昨今,本書は,医療関連感染と抗菌薬の関係性を中心に講義形式で読みやすく解説した抗菌薬入門書です!感染管理おべんきょブックスシリーズの第2弾。
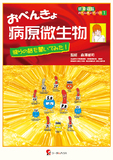
おべんきょ病原微生物
彼らの話も聞いてみた!
「感染」や「感染症」,「免疫」,「耐性菌」,「消毒」などについて病原微生物が微生物目線で語るスタイルの異色のテキスト。病原微生物の勉強が苦手な方々にも読みやすい内容です。感染管理おべんきょブックスシリーズの第1弾。

医療従事者のための 感染対策ルールブック
感染対策は感染防止のために必要なルールの集積です。本書は,エビデンスに基づいた227のルールを感染対策の第一人者である矢野邦夫先生がカテゴリー別に厳選し,ハンディーな新書判にまとめています。現場で感染対策を実践する医療従事者の方々,とりわけ研修医や新人看護師のみなさんにとって有益な情報を満載した手軽に使える実務重視のポケットルール集です。

皮膚病診療 Vol.42 No.13
2020年増刊号
【特集】形からみる皮膚疾患
【特集】形からみる皮膚疾患
皮膚症状の形に注目して7項目(線状、帯状、環状、網状、地図状、斑状、結節性)に分類し,その特徴から考えられる疾患をまとめた症例集です。
