
がん看護 Vol.25. No.8
2020年11-12月号
ゲノム医療とがん看護
ゲノム医療とがん看護 がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

精神看護 Vol.23 No.6
2020年11月発行
特集 この人いいですよ!あなたが仕事に関連してオススメしたいSNSの人、教えてください
特集 この人いいですよ!あなたが仕事に関連してオススメしたいSNSの人、教えてください 皆さんは普段、SNSとどのようにつきあっていますか。他の人のSNS事情を知ることってなかなかできませんが、実は気になるところですよね?というわけで、この特集では、医療界で働く12人の方々に、以下の質問を投げて答えてもらいました。なお、今回はネット検索した際に簡単にヒットするものについてはURLを省き、ヒットしにくいと思われるものにだけURLを付けました。例えば今回ご紹介した方々のTwitterを見る場合は、「(Twitter:@○○○○)」の@マーク以下(ユーザー名)をTwitterの検索欄に入れていただくと、その人のページに行くことができます。この特集をぜひ、「目的を持って有効にSNSとつき合っていく」ための情報源の1つにしてください。
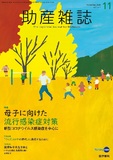
助産雑誌 Vol.74 No.11
2020年11月発行
特集 母子に向けた流行感染症対策 新型コロナウイルス感染症を中心に
特集 母子に向けた流行感染症対策 新型コロナウイルス感染症を中心に 2020年,新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な流行が始まりました。世界各国が緊急対策に乗り出す中,日本では4月に緊急事態宣言が発令されました。そこから今もなお,周産期医療機関では妊産褥婦や児への感染対策が課題となっているかと思います。そして暑い時期を乗り越えた今,いよいよ感染症が蔓延しやすい季節が迫ってきています。新型コロナウイルス感染症などの流行感染症から母子を守るためには,どのような対策を打てば良いでしょうか? 本特集では「注意するべき流行感染症」「感染症治療薬の母子への影響」「感染症罹患・または罹患疑いのある妊婦さんへの対処・管理法」といったテーマを取り上げました。これからの感染症流行への備えとして,お使いいただけますと幸いです。

訪問看護と介護 Vol.25 No.11
2020年11月発行
特集 在宅浮腫マネジメントのための新常識 利尿薬だけの対応になっていませんか?
特集 在宅浮腫マネジメントのための新常識 利尿薬だけの対応になっていませんか? 訪問看護現場で多く遭遇する「むくみ」。実は、原因も対処法もさまざまです。QOLを大きく左右するこの困り事について、私たちはどう応え、ケアしたらよいのでしょうか。治療とケアの新常識を分かりやすく学ぶとともに、在宅ならではの「浮腫のみならず全身を看る」アセスメント&マネジメントのコツを特集します。

保健師ジャーナル Vol.76 No.11
2020年11月発行
特集 統括保健師 憧れのポストになるために
特集 統括保健師 憧れのポストになるために 新型コロナウイルス感染症への対応において,統括的な役割を担う保健師による組織全体を見渡した人材・業務の調整や他組織との連携の重要性が再認識された。本特集では,統括保健師の現状や課題とともに,望まれている姿や統括保健師としてやりがいをもって活動した事例を紹介し,統括保健師の意義や魅力をあらためて捉える。
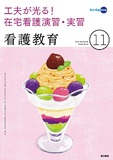
看護教育 Vol.61 No.11
2020年11月発行
特集 工夫が光る! 在宅看護演習・実習
特集 工夫が光る! 在宅看護演習・実習 指定規則の改正により、「在宅看護論」は「地域・在宅看護論」へと科目名が変更されました。これは、医療構造の変化を反映したものであり、今後、看護基礎教育において地域・在宅の学びはさらに重視されることになるでしょう。期せずして新型コロナウイルス感染症が看護教育機関にも大きな影響を及ぼし、看護教育の根幹ともいえる実習の実施などが難しい状況となりました。特に在宅看護領域においては、学生や教員が多くの施設に分かれて行う形式が主流であること、病院と比べ感染管理などが困難であることから、実習の実施がさらに難しい状況であると予測されます。そこで本特集では、コロナ禍において実施された、在宅看護分野における、工夫が光る学内演習やオンライン実習を紹介し、時代をみすえた教育方法をご提案します。

臨床泌尿器科 Vol.74 No.12
2020年11月発行
特集 泌尿器科医のためのクリニカル・パール いま伝えたい箴言・格言・アフォリズム〈下部尿路機能障害/小児・女性・アンドロロジー/結石・感染症/腎不全編〉
特集 泌尿器科医のためのクリニカル・パール いま伝えたい箴言・格言・アフォリズム〈下部尿路機能障害/小児・女性・アンドロロジー/結石・感染症/腎不全編〉 -

臨床外科 Vol.75 No.12
2020年11月発行
特集 消化器外科手術 助手の極意 開腹からロボット手術まで〔特別付録Web動画付き〕
特集 消化器外科手術 助手の極意 開腹からロボット手術まで〔特別付録Web動画付き〕 各領域における手術術式は,手技の進歩やデバイスの進化に伴い,より解剖に則った精緻な手術が要求されるようになってきました.また,開腹や腹腔鏡下手術,ロボット手術など,アプローチもさまざまあります.適切な手術を遂行させるには,アプローチの違いによらず,助手による視野展開やカメラワークが非常に大事になってきます.手術を円滑かつ安全に進めるための手術手順,視野展開の方法などを助手の目から熟知することは,手術の理解と若手外科医の術者への道の第一歩として重要なことと考えられます. 本特集では,各領域について,助手からみた手技の重要なポイントに焦点をあてて,具体的にご解説いただきました.
編集室より:本号では関連する動画を配信しています。ぜひご覧ください。
※ 配信・閲覧期限:発行後3年間
※ ファイルは予告なしに変更・修正,または配信を停止する場合もございます。あらかじめご了承ください。

病院 Vol.79 No.11
2020年11月発行
特集 医療経済からみた病院経営
特集 医療経済からみた病院経営 病院は地域経済を支えている一方で、高齢者人口の急増から国の医療財源は逼迫することが想定される。加えて、新型コロナウイルス感染症による財政支出や景気の冷え込みにより、医療を取り巻く経済環境は相当厳しくなるだろう。本特集では、病院はどのように医療経済と向き合って経営していけばよいのかを探る。

臨床泌尿器科 Vol.74 No.11
2020年10月発行
特集 泌尿器科医のためのクリニカル・パール いま伝えたい箴言・格言・アフォリズム〈腫瘍/処置・救急・当直編〉
特集 泌尿器科医のためのクリニカル・パール いま伝えたい箴言・格言・アフォリズム〈腫瘍/処置・救急・当直編〉 -

臨床皮膚科 Vol.74 No.12
2020年11月発行
-

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.92 No.12
2020年11月発行
特集 漢方医学入門 耳鼻咽喉科で漢方薬を使いこなす
特集 漢方医学入門 耳鼻咽喉科で漢方薬を使いこなす -

臨床眼科 Vol.74 No.11
2020年11月発行増刊号
特集 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル
特集 すべて見せます! 患者説明・同意書マニュアル -

臨床整形外科 Vol.55 No.11
2020年11月発行
特集 足部・足関節の画像解析 画像から病態を探る
特集 足部・足関節の画像解析 画像から病態を探る -

呼吸器ジャーナル Vol.68 No.4
2020年11月発行
特集 失敗できない若手のための呼吸器診療実践ガイド
特集 失敗できない若手のための呼吸器診療実践ガイド -

総合診療 Vol.30 No.11
2020年11月発行
特集 診断に役立つ!教育で使える!フィジカル・エポニム!身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
特集 診断に役立つ!教育で使える!フィジカル・エポニム!身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考 「エポニム(eponym)」とは、人名に因んで命名された言葉のこと。今に名を残すメディカル・エポニムは、歴史的風化に抗して、脈々と継承されてきたものです。本特集では、なかでも「フィジカル(身体所見)」に絞って取り上げ、その身体所見や診察技術の由来と臨床的意義を深堀りしました。より診察技術を深め、次世代へと伝えるために!

medicina Vol.57 No.12
2020年11月発行
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する
特集 膠原病・自己免疫疾患を「見える化」する -

公衆衛生 Vol.84 No.11
2020年11月発行
特集 日本型MPH教育の軌跡と展望 公衆衛生専門職を目指す!生かす!
特集 日本型MPH教育の軌跡と展望 公衆衛生専門職を目指す!生かす! -
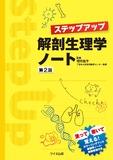
ステップアップ解剖生理学ノート 第2版
人体の仕組みや働きを理解するため必要な要点をまとめた簡潔な文章により、自己学習用の解剖生理学ノートとして、解剖生理学の授業の予習復習に、試験前の要点チェックに活用できる。今回、問題や図版を新しくした、待望の改訂第2版!

口腔粘膜・皮膚症状から「見抜く」全身疾患
オラドローム,デルマドローム
口腔粘膜と皮膚に現れる局所症状は、潜在的な全身疾患を見抜く重要な手がかりとなる。特に口腔粘膜所見を全身疾患と結び付け診断を導くための知識は、皮膚科医の診断力を向上させる。本書は、統一的な記載形式で、口腔粘膜症状および皮膚症状から奥に潜む全身疾患を特定する流れを分かりやすく解説。隠れた真実を「見抜く」力を身に付けられる実践書。
