
CPXポケットマニュアル
●知って安全!心肺運動負荷試験実施の基礎知識
●CPX(心肺運動負荷試験)は心エコーと並んで生理機能検査の中核をなしており,心臓・呼吸・腎臓リハビリテーションの運動処方には必須の検査となっている.
●実施には運動生理学的知識,安全を担保するための知識が必要で,医師,臨床検査技師はもとより理学療法士,看護師等にも,実施法や検査結果の見方を含めた知識が求められている.
●運動負荷試験の実施に迷った際にすぐに求める知識が得られるよう,図表や箇条書きを多用してコンパクトな紙面にまとめた,現場への携帯に便利なポケットマニュアル.

続・楽しく学んで好きになる! 心電図トレーニングクイズ2
●クイズ形式で楽しくわかりやすく心電図を学べる好評書に,待望の第2弾が刊行!
●月刊『Medical Technology』の好評連載「楽しく解いて好きになる!不整脈心電図トレーニングクイズ」の内容に,新たに11問を書き下ろした待望の書籍化!
●25問のクイズ形式で,苦手とする人の多い「不整脈」を中心に,さまざまなケースの心電図を掲載.楽しくわかりやすく解説しつつ,各心電図のポイントがしっかりと学べる一冊.
●心電図判読の手順・方法だけでなく,豊富な類似波形によって各疾患の鑑別ポイントも理解できる!
●好評姉妹書『楽しく学んで好きになる!心電図トレーニングクイズ』に続く第2弾!

別冊「医学のあゆみ」 診療ガイドラインの作成方法と活用方法――公平で偏りない作成方法と患者のための活用に向けて
●臨床家と患者の意思決定を支える存在である診療ガイドライン.ガイドラインの作成者・利用者双方に役立つ情報が満載!
●診療ガイドラインは作成して終わりではなく,臨床導入したのちに課題を再検討し,さらなる進化をめざして改訂していく継続的な作業が重要である.
●本書では,診療ガイドラインの歴史・定義などの基本知識にはじまり,システマティックレビューや評価など具体的な作成方法や,活用に向けた実際の工夫のほか,医療訴訟への対応やビッグデータの活用などの話題まで幅広く解説!

匠が伝える低侵襲脊椎外科の奥義
低侵襲化が急速に進んでいる脊椎手術の最前線がこの1冊に凝縮!
最先端手技のFED(全内視鏡手技),MISt(脊椎最少侵襲手術)に加えて,最先端治療である人工椎間板やVR/AR(仮想現実/拡張現実)を使用した手術法なども紹介。さらに理学療法士任せになりがちな運動療法についても,脊椎外科医が知っておくべき内容を解説。「匠のポイント伝授!」や「匠の奥義」など,重要ポイント解説も充実!

診察室の対話から思いを引き出すヒント
認知症のある人と向き合う
徘徊、嫉妬妄想、物盗られ妄想=認知症と決めつけていませんか? 私たちは認知症という病気をよく耳にするようになりましたが、理解は十分とはいえません。じつは認知症のある人が安心して暮らすために本当に大切なものは薬でなく、日々の温かい関わりです。気鋭の認知症の専門医が、診察室で、街中で、家庭で、認知症のある人に関わるすべての人に伝えたい21の言葉を収めました。

薬剤師・販売登録者専用!
フローチャート薬局漢方薬
薬局で買える漢方薬は、葛根湯だけでも100種類! 正直何から勉強すればよいのかわかりませんという皆さま。いろいろ本を買ったけどマスターできなかったという皆さま。本書なら確実にわかります。新型コロナウイルスで病院に行きにくいという患者さん。なんとか自分で予防したいという皆さま。何を飲めば良いのか、症状から自分で探せる便利なフローチャートです。

医療にできること
性暴力救援マニュアル
もしも身近な人から性被害の相談を受けたら、正しい対応できますか?
魂の殺人といわれる性暴力の被害者にとって正しい対応と必要な支援を実践に即してまとめたポケットブック。医療者のみならず、当事者、家族、学校関係者、職場関係者、保健関係者など、幅広い読者を対象にわかりやすく解説。性暴力支援に真摯に取り組む、医療者、弁護士、支援者など、それぞれの領域におけるリーダーが集結して執筆した力強い参考書。

新訂版 クイックマスター薬理学 第3版
分かりやすい解説とイラストで難解な薬理学を十分理解することができる。待望の改訂第3版発行。
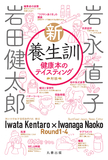
新・養生訓
健康本のテイスティング
巷に溢れる医療情報の「何が真実・何がデマか」を知るには,目利き力の涵養が必要だ.感染症医の岩田健太郎医師と医療ジャーナリストの岩永直子氏が対談を行い,11冊の本をcritique(批評).健康本の吟味の仕方,受動喫煙やHPVワクチン問題,働き方改革,事故報道の在り方,編集者の姿勢,健康をめぐる諸問題もテイスティングした!

新訂版 ニューワークブック基礎看護
准看護学生用の基礎看護参考書のベストセラー。

新訂版 ニューワークブック解剖生理
准看護学校のサブテキストの決定版。各章とも練習問題があり、授業の予習や復習に、知識の再確認に使える。理解を深めるために、新たにイラストを付け加えた。
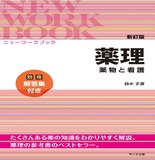
新訂版 ニューワークブック薬理
たくさんある薬の知識をわかりやすく解説。薬理が苦手な多くの学生から、長年にわたり支持されてきた薬理参考書のベストセラー。

検査と技術 Vol.48 No.11
2020年10月発行
-

総合リハビリテーション Vol.48 No.10
2020年10月発行
特集 認知症ケアのプラットフォーム
特集 認知症ケアのプラットフォーム 認知症ケアは,認知症リハビリテーションを実施するうえでも必要不可欠なツールの一つとなっています.さる2019年6月に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられ,医療・介護・福祉の分野において認知症リハビリテーションとともに認知症ケアのより一層の充実が求められています.そこで,本特集では,「認知症ケアのプラットフォーム」として,パーソン・センタード・ケア,バリデーション,STrAtegies for RelaTives(START)プログラム,認知症カフェ,さらには Dementia Friendly Community を取り上げ,それぞれ第一線でご活躍されている先生方に解説していただきました.
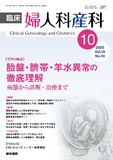
臨床婦人科産科 Vol.74 No.10
2020年10月発行
今月の臨床 胎盤・臍帯・羊水異常の徹底理解 病態から診断・治療まで
今月の臨床 胎盤・臍帯・羊水異常の徹底理解 病態から診断・治療まで -
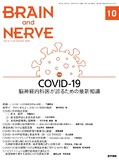
BRAIN and NERVE Vol.72 No.10
2020年10月発行
特集 COVID-19 神経内科医が診るための最新知識
特集 COVID-19 神経内科医が診るための最新知識 2020年4月7日の緊急事態宣言発令から半年が経ち,新型コロナウイルス感 染症(COVID-19)による神経症候も少しずつ明らかになってきた。まだ先の見通しが立たない中ではあるが,疫学データや神経症候の特徴,治療方針, COVID-19で明らかになった課題や実際に最前線で重症患者の診療を行った経験など,これまでの知見を集積し,脳神経領域において知っておくべき現時点 での最新知識としてまとめた。日々変化するCOVID-19に神経学の専門家としてどのように対応していくか,その足掛かりとなれば幸いである。

生体の科学 Vol.71 No.5
2020年10月発行 (増大号)
増大特集 難病研究の進歩
増大特集 難病研究の進歩 -

臨床医のための医学からみた認知症診療 医療からみる認知症診療―治療編
「診断編」に続く第2弾.認知症診療について,エビデンスに基づいた医学的知識と臨床経験に基づく知識の2つの視点からディベート形式で平易に解説.患者さんそれぞれが持つ背景や家族の考え方など多くの要因が影響を及ぼす認知症治療において,個々の患者さんに最適な治療の提供を目指すために、両者の視点を学ぶことは、治療スキル向上に役立つこと間違いなしだ.
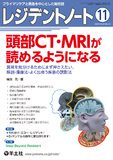
レジデントノート Vol.22 No.12
【特集】頭部CT・MRIが読めるようになる
【特集】頭部CT・MRIが読めるようになる 頭部画像の読影に苦手意識のある方,必見!画像オーダーの基本や解剖,よく出会う疾患でのCT・MRIそれぞれの特性をふまえた読影など,異常所見を見分けるために知っておきたい,専門家の読み方を教えます!

臨牀透析 Vol.36 No.11
2020年10月号
高齢透析患者の療養生活支援-事例を通して見えてくるもの
高齢透析患者の療養生活支援-事例を通して見えてくるもの
いつ頃からだろうか,透析室の様子が変わってきたのは.気がつけばベッドの1/3 を75 歳以上の高齢者が占めるようになっていた.(中略)いずれにしても,認知症やサルコペニア・フレイルの先頭を切っているのは高齢患者である.
