
患者の声を医療に生かす
新しい「患者の声」は、対立型でもお客様型でもない。医療者とともに良き医療をめざす《パートナーシップ型》だった――。患者が講師、医療者が学生というマスコミ注目の「でんぐりがえしプロジェクト」を、テーマごとに徹底編集。ナマの患者の声を知る「生きた教材」として、医学・看護教育に最適。

認知行動療法事典
◆広範な治療法をもつ認知行動療法を網羅的に学ぶための全329項目:見開き(2p/4p)完結の中項目事典◆基礎理論、基礎研究から公認心理師主要5分野の解説までを網羅◆公認心理師の国家資格化を踏まえ、「認知行動療法」のスタンダードを知ることができる決定版

専門医が教える 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)診療の手引き
病因・病態の解明に向けた臨床研究が進む筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)。本書では厚生労働省・日本医療研究開発機構(Japan Agency for Medical Research and Development;AMED)研究班での病因・病態の解明,治療法の開発に携わってきた専門家が筆を執り,同疾患の最新知見を開陳しています。

1人でイチから始めたい先生のための
訪問診療マネジメントガイド
──人材確保、モノ、マーケティング、業務、財務、組織、労務。
在宅医療未経験の先生が、訪問診療を専門とするクリニックを開業しようと決意する。そこにはさまざまな“マネジメント”が大きな壁として立ちはだかり、先生を悩ませます。医師1人で“マネージングプレイヤー”にならざるを得ない院長先生がこれらのマネジメントから距離をおけば、出口のない負のスパイラルに陥ること必至です。
本書は姜琪鎬先生を中心とする経験豊富な執筆陣が、訪問診療専門クリニックの開設・運営に必要なノウハウを詳述。数々の辛酸をなめ,成功を勝ち取ってきた先駆者だからこそ語れる、本当に貴重な情報が満載です。

イラストとQ&Aでわかる 患者・家族説明にそのまま使える
ヘルスケアプロバイダーのためのがん・生殖医療
【若年がん患者のサバイバーシップを支える】
がん治療が生殖機能に及ぼす影響、生殖補助医療の基本と妊孕性温存治療など、がん・生殖医療に携わる医療者に必須の知識をビジュアル解説。さらに、妊孕性温存に至るまでのチーム医療を事例で紹介するとともに、多様で個別的な支援に役立つ視点をQ&Aで提供。患者・家族説明にも役立つ一冊。
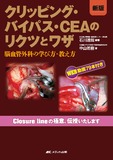
新版 クリッピング・バイパス・CEAのリクツとワザ
脳血管外科の学び方・教え方/WEB動画79本付き
【脳血管外科手術の最終回答はこれだ!】
脳動脈瘤手術、脳血行再建術のエキスパートによる、実践的手術指南書の改訂版。手術における「リクツ」と「ワザ」をやさしく味わい深い独特の筆致で記述。昨今話題になることの多い、著者が提唱したclosure lineについても詳しく解説。

You Can Do it!誰でもサッとできる!
CDCガイドラインの使い方 感染対策
【エビデンスに基づいた感染対策ができる!】
「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使えばいいのかな?」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩までCDCガイドラインについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解説!知ってて当たり前のCDCガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載!

臨床検査 Vol.63 No.11
2018年11月号
今月の特集1 腎臓を測る/今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策
今月の特集1 腎臓を測る/今月の特集2 大規模自然災害後の感染症対策 -

臨床眼科 Vol.73 No.12
2019年11月発行
特集 感染性角膜炎 もうガイドラインだけでは足りない!
特集 感染性角膜炎 もうガイドラインだけでは足りない! -

精神医学 Vol.61 No.10
2019年10月発行
特集 トラウマインフォームドケアと小児期逆境体験
特集 トラウマインフォームドケアと小児期逆境体験 -

公衆衛生 Vol.83 No.11
2019年11月発行
特集 歯科口腔保健をどう進めるか
特集 歯科口腔保健をどう進めるか -

胃と腸 Vol.54 No.11
2019年10月発行
主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望
主題 大腸腫瘍の病理診断の課題と将来展望 -

臨床心理アセスメント 新訂版
臨床心理士や認定カウンセラー、教育カウンセラーなどの資格取得にとって必修科目とされている「臨床心理アセスメント(診断)」に関して噛み砕いて平易に解説する標準テキストです。 現場のカウンセラーは、悩みをもって来談した患者さんに対して、まず、面接・行動観察を行いますが、さらに詳細な診断を行うためには、問題内容や症状に合わせて、いくつかの心理テストを実施し、その結果に基づいて、どうようなカウンセリングを行うかを決める必要があります。 本書「臨床心理アセスメント 新訂版」では、種類も多く習得も大変な様々な「心理テスト全般」についてわかりすく解説するとともに、臨床心理アセスメントの実施法についても具体的に紹介していきます。
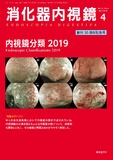
消化器内視鏡31巻4号
【特集】内視鏡分類2019
【特集】内視鏡分類2019

JOHNS35巻4号
【特集】耳管のすべて
【特集】耳管のすべて
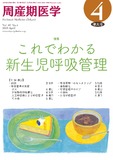
周産期医学49巻4号(増大号)
【特集】これでわかる,新生児呼吸管理
【特集】これでわかる,新生児呼吸管理

小児外科51巻4号
【特集】技術認定取得医が解説する高難度内視鏡外科手術
【特集】技術認定取得医が解説する高難度内視鏡外科手術
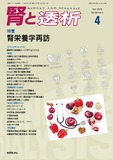
腎と透析86巻4号
【特集】腎栄養学再訪
【特集】腎栄養学再訪

外国人診療で困るコトバとおカネの問題
突然,外国人患者が来院したらどうする? 外国人の外来・入院に備えて何を準備すべき? そんな悩みをもつ医師や医療事務員,病院管理者におすすめ!外国人医療の場で必ず起こる問題とその解決方法をすべて記載!

決定版 阻害剤・活性化剤ハンドブック
作用点、生理機能を理解して目的の薬剤が選べる実践的データ集
ラボにあれば頼れる1冊!あらゆる実験の基本となる阻害剤・活性化剤を500+種類,厳選して紹介.ウェブには無い,実際の使用経験豊富な達人たちのノウハウやTipsも散りばめられています.
