
保健師ジャーナル Vol.74 No.11
2018年11月号
特集 地域包括ケアにおける難病保健活動
特集 地域包括ケアにおける難病保健活動 2015年の難病法の施行以降,地域包括的に難病患者や家族を支援する体制や事業の構築が求められている。本特集では,その進展や現状を整理するとともに,各地の難病保健活動の取り組みを紹介し,地域包括ケアにおける難病保健活動の在り方や保健師の役割を考える。
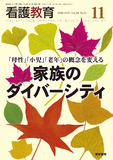
看護教育 Vol.59 No.11
2018年11月号
特集 「母性」「小児」「老年」の概念を変える 家族のダイバーシティ
特集 「母性」「小児」「老年」の概念を変える 家族のダイバーシティ 「お父さんとお母さんと子ども1,2人で全員同戸籍」というのが家族の標準とする見方があります。しかし,上記の構成員のいずれかがいない家族は珍しくありませんし,戸籍を基準とした形態ばかりが家族でもありません。“標準”という考え方は,そこに準じないものを意識的にあるいは無意識に排除しがちですから,注意する必要があります。さて,看護師は「患者の多様性に注目して対応する」ことを求められます。このことは,入学直後の段階から繰り返し語られるものですが,実際,患者を含む家族の多様性にどこまで踏み込んだ教育を受けているでしょうか。教員はその多様性を十分意識して学生に接しているでしょうか。今回の特集は,患者はもちろん,学生自身そして教員自身の家族が多様性(ダイバーシティ)をもつことを前提として教育にあたっていただくための,呼び水になればと願って組みました。家族の多様化で概念に変化が生まれるであろう「母性」「小児」「老年」に注目して,提言をいただきましたが,もちろんすべての領域にかかわるテーマです。今までの家族の“標準”にとらわれない柔軟な思考をもつ教員が増えることを期待しています。
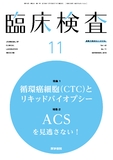
臨床検査 Vol.62 No.11
2018年11月号
今月の特集1 循環癌細胞(CTC)とリキッドバイオプシー/今月の特集2 ACSを見逃さない!
今月の特集1 循環癌細胞(CTC)とリキッドバイオプシー/今月の特集2 ACSを見逃さない! -
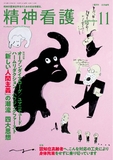
精神看護 Vol.21 No.6
2018年11月号
特集 認知症高齢者へ、こんな対応の工夫により身体拘束をせずに乗り切っています
特集 認知症高齢者へ、こんな対応の工夫により身体拘束をせずに乗り切っています 病院での身体拘束がデータ上増加しています。これは今まであやふやだったものも身体拘束として報告するようになったためという説もあり、増えているのではなく、もともと多かったし、実際の身体拘束はもっと多いだろうとも言われています。ただ、身体拘束が減っていない理由として確実に言えるのは、認知症患者の入院が増えたことです。スタッフは誰も、やりたくて自由を奪っているわけではありません。「縛るしかない」と思い込み、“必要悪”として“仕方なく”行っているのだと思います。しかしそれにより自らの自尊感情も下がり、患者さんへのケアが逆に増え、患者さんからの悪感情を受け……という悪循環に陥っています。そこでこの特集では、認知症高齢者が入院してきた場合でも、身体拘束をせずに治療と看護を実践できるようになった病院に、そのやり方、発想の転換、実現できた経緯、試行錯誤などを教えていただきました。

臨床・病理
脳腫瘍取扱い規約 第4版
2016年にWHO中枢神経系腫瘍分類が改訂され、従来の病理診断に加え、分子診断による遺伝子異常の検討が必須となり、大きなパラダイムシフトが起きた。今回の改訂では、より正確で客観性の高い脳腫瘍診断を実現することに重点が置かれ、病理診断に軸足を置きつつ、分子診断を大幅に取り入れた。統合診断に基づき、層別化・個別化医療を発展させ、治療の選択性や予後予測をより正確に解析するための改訂版と言える。

実験医学増刊 Vol.36 No.17
【特集】教科書を書き換えろ!染色体の新常識
【特集】教科書を書き換えろ!染色体の新常識 新しい実験法、生物物理の理論を取り入れ、染色体の立体的な姿が立ち上がってきました。その基本から、いま最も熱い本当の姿の解明まで、染色体研究の決定版となる1冊!

Modern Physician Vol.38 No.11
2018年11月号
【今月のアプローチ】妊産婦は怖くない!周産期を知って内科疾患を診よう
【今月のアプローチ】妊産婦は怖くない!周産期を知って内科疾患を診よう 妊産婦の診療に怖さを感じている医師は多いが、管理や薬剤の特徴を知っておけば問題なく対応できる。
本号では妊産婦診療の基礎知識から、疾患別に知っておきたいポイントまでを紹介。
さらに近年増加しているハイリスク妊娠や合併症に関するアドバイスも掲載。

整形外科専門研修マニュアル
2018年春より施行される新専門医制度のために日本整形外科学会が策定した「整形外科専攻医研修マニュアル」の「整形外科専門研修カリキュラム」の構成に完全準拠した専攻医向けのポケットマニュアル。慶應義塾大学整形外科教室および関連病院の医師による執筆で、記載の水準等も統一されている。評価の際に具体的な到達水準の参照が容易であり、専攻医にも指導医にもきわめて効率のよい参考書となっている。

臨牀消化器内科 Vol.33 No.12
2018年11月号
消化管粘膜下腫瘍(SMT)の診療
消化管粘膜下腫瘍(SMT)の診療
消化管粘膜下腫瘍に関しては、何処までが治療対象で、どんな腫瘍は経過観察すべきか、明確なエビデンスがないのが現状である。

病院 Vol.77 No.11
2018年11月号
特集 働き方改革の行方
特集 働き方改革の行方 厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」では中間の論点整理がなされた。応召義務など医師の特殊性を踏まえた対応が必要である一方、医療崩壊の懸念を払拭する対策も重要だ。医師の負担を軽くしても医療が成り立つためにはどうすべきか、今こそ医療の構造改革と生産性の向上を図るチャンスである。

呼吸器ジャーナル Vol.66 No.4
2018年11月号
特集 結核・非結核性抗酸菌症 エキスパートが教える実臨床に役立つ最新知見
特集 結核・非結核性抗酸菌症 エキスパートが教える実臨床に役立つ最新知見 -

脳神経外科 Vol.46 No.10
2018年10月号
-

総合診療 Vol.28 No.11
2018年11月号
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」 今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」 今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ -

臨床泌尿器科 Vol.72 No.12
2018年11月号
特集 何が変わったのか? 性感染症の動向
特集 何が変わったのか? 性感染症の動向 -

臨床皮膚科 Vol.72 No.11
2018年10月号
-

ハイリスク薬とサプリメントの相互作用ハンドブック
ハイリスク薬とサプリメントの相互作用について解説した実践書。約250品目のサプリメントと医薬品の相互作用は表形式で示し、サプリメントの概要や臨床現場で注意すべきことをワンポイントアドバイスとして掲載。相互作用を調べるノウハウや、服薬指導の実際についてもわかりやすく解説。患者さんにサプリメントの相互作用を、エビデンスに基づいて説明できる。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.90 No.12
2018年11月号
特集 見逃してはならない耳鼻咽喉科疾患 こんな症例には要注意!
特集 見逃してはならない耳鼻咽喉科疾患 こんな症例には要注意! -

臨床眼科 Vol.72 No.12
2018年11月号
特集 涙器涙道手術の最近の動向
特集 涙器涙道手術の最近の動向 -

創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン 2018
待望のガイドライン改訂版。今回、名称に「褥瘡」を追加し、最新の治療を中心として患者さんや医療者、社会への貢献をめざした。皮膚科診療において創傷は最も頻度が多い疾患である。「創傷一般」の章で治療の基本的考え方を示し、創傷が生じるものの治療法が異なる「褥瘡」「糖尿病性潰瘍・壊疽」「膠原病・血管炎に伴う皮膚潰瘍」「下腿潰瘍・下肢静脈瘤」「熱傷」に分けた疾患別診療ガイドラインを最先端のGRADEシステムを採用し委員会で完成した。

臨床婦人科産科 Vol.72 No.11
2018年11月号
今月の臨床 男性不妊アップデート ARTをする前に知っておきたい基礎知識
今月の臨床 男性不妊アップデート ARTをする前に知っておきたい基礎知識 -
