
がん研有明病院のプラクティス 肺癌薬物療法レジメン 第4版
肺癌薬物療法をコンパクトにまとめた好評書の第4版が新薬・新レジメンを加え登場!
レジメンごとにスケジュールや支持療法,減量,投与中止基準などが見開き2ページで詳細かつコンパクトにまとめた肺癌薬物療法の好評書の改訂版.3版から引き続き掲載されているレジメンのアップデートともに、アミバンタブやタルラタマブといった新しいタイプの薬剤である二重特異性抗体薬を追加.さらに新規レジメンも加えますます充実した内容に.年々複雑化する治療選択肢のなかから最適なレジメンを選び,正しく投与するための助けとなり,肺癌診療に携わる全ての人たちの実務に役立つ一冊.
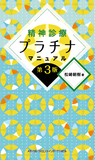
精神診療プラチナマニュアル 第3版
わかりにくい精神科を、さらにわかりやすく
精神医療に必要かつ不可欠な内容をハンディサイズに収載、臨床における迷いを払拭するコンパクトマニュアル。4年ぶりの改訂に際し、精神医療に最低限必要な知識に加えて、「もう少し踏み込んで知っておきたい知識」も記述。原則として『DSM-5-TR』に疾患名を統一し、またDSMにない概念も取り上げた。全編アップデート、30頁増。拡大版(Grande)も同時発売。精神科専門医・専攻医はもちろん、他科の医師、初期研修医、看護師、薬剤師、さらには臨床心理士・公認心理師、精神保健福祉士など、幅広い職種に。

精神科の薬がわかる本 第5版
精神科全領域の薬がこの1冊で丸わかり! ざっと広くのことを知りたい方へ。
精神科全領域の薬に関する最新かつ正確な情報を、第一線で診療を行う著者が厳選して紹介。精神科を専門とする医師、研修医、精神科看護師はもちろん、精神科以外の科の医療者で「精神科の薬」を使用する機会のある方にとっても有益な1冊。第5版では、なぜその薬が効くのかを知ることで、「精神科の薬」の誤用と乱用を防ぐことに注力しています。

DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル
精神疾患の国際的な診断基準、9年ぶりのアップデート!
米国精神医学会(APA)の精神疾患の診断分類、第5版のText Revision。DSM-5が発表された2013年以来9年ぶりに内容をアップデート。日本精神神経学会による疾患名の訳語も大幅にリニューアルとなり、全編新たな内容としてリリースする。
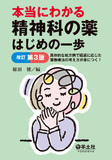
本当にわかる精神科の薬はじめの一歩改訂第3版
具体的な処方例で経過に応じた薬物療法の考え方が身につく!
非専門医のために,精神科の薬の基本と実践をやさしく解説!豊富な図表で作用機序や特徴,副作用などの押さえておきたい要点をパッと確認.症例では具体的な処方のコツがみえてくる!大人気の入門書が待望の大改訂!
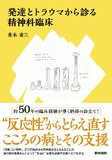
発達とトラウマから診る精神科臨床
「診断」と「理解」、2つの視点から精神症状とその治療・支援のあり方をとらえ直す
卓越した臨床家として名高い著者が、これまで多くの患者さんの診療に携わる中で得た気づきや診療・支援の工夫などを豊富な症例を交えて解説する実践書。著者の専門領域でもある発達と、近年注目を集めるトラウマ、この2つの観点から患者さんを診てみることで、これまでとは違った治療や支援のあり方が見えてくる。約50年の臨床経験が導き出す納得の診立てが随所に散りばめられた一冊。

子どものための精神医学
発達障害? アスペルガー症候群? 知的障害? 自閉症? ADHD? LD? ところでスペクトラムって何?-本書を読めば、錯綜する診断名を「認識と関係の座標軸」のもとに一望できるようになる。読めば分かるように書いてある、ありそうでなかった児童精神医学の基本書。事例の機微をすくい上げる繊細な筆さばき、理論と実践の生き生きとした融合、そして無類の面白さ! マニュアルでは得られない「納得」がここに。
●新聞で紹介されました!
《463ページにも及ぶ分厚い専門書なのに、興奮しながら一気に読み切った。タイトルには精神医学とあるが、内容は「何かにつまずく全ての子ども」についての考察と助言だ。》―鈴木大介(ルポライター)
(共同通信社配信、『熊本日日新聞』2017年5月14日 書評欄、ほか)
《著者は、日本を代表する児童精神科医の一人。育つ側の難しさを語りつつ、育てる側の難しさも平等にフォローした。》
(『読売新聞』2017年4月26日より)
《〈疾患〉ではなく〈障害〉と言われる概念の理解に主眼をおき、教員・保育士・看護師・心理士向けにわかりやすく解説する。》
(『東京新聞』2017年6月18日より)
●雑誌で紹介されました!
《児童精神科医学者である著者は五十年間の研究の末、子どもの「精神発達の座標軸」を発見した。その原理と実践をつないで体系化したのが本書だ。》―本田哲也(toBe塾主宰)
(『児童心理』2017年8月号 BOOK REVIEWより)
《この書物は、児童精神医学の教科書ではない。しかし、その道へ進みつつある臨床家に向けての教導書ではある。》―清水將之(三重県立看護大学理事)
(『こころの科学』2017年7月号、BOOKS ほんとの対話より)

研修医・総合診療医のための
精神科ファーストタッチ
●コンパクトだけど精神科の悩みを解決できる1冊!
●向精神薬の選び方・心のケアのポイントがシンプルにわかる!
●「スタンダードな治療のながれは?」「向精神薬のリスクと限界は?」「副作用?それとも増悪?」一度でも悩んだことのある人必読!
精神疾患への向き合いかたに迷子になっているすべての研修医へ。せん妄や抑うつなどの精神症状を一度でも診たことがある人なら知っておきたい診断・治療のエッセンスをまとめました。重要なポイントにしぼって、スタンダードな治療のながれをぎゅっと解説。数値・画像でとらえづらい疾患・症状でも、パッと引いてすぐに実践できます。さらに、よく使われる向精神薬の適応症や適用外使用がサッと確認できる一覧表付き! コンパクトながら、疾患・薬・副作用を網羅的にカバーした万能な1冊です。
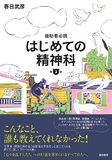
援助者必携
はじめての精神科 第3版
きれいごと一切ナシ! 口は悪いが役に立つ! 同じ精神科の最前線で働く者だけが知る共感力を全開にした「超実践的アドバイス」集は、いよいよ第3版へ。クレーマー対策、援助者としてのアイデンティティの保ち方、当事者・家族に対峙する時のちょっとしたコツなど、「こんなこと、誰も教えてくれなかった」度はますますアップ! はじめて精神科に足を踏み入れたなら誰もが感じる「不安」が、優しく解きほぐされます。

しくじり症例から学ぶ精神科の薬
病棟で自信がもてる適切な薬の使い方を精神科エキスパートが教えます
レジデントノートの好評連載が単行本化!入院患者さんが精神症状を発症したとき,起こりうる「しくじり」を防ぎ,病棟トラブルを解決!研修医・非専門医が精神科の薬を使うなら必ず読んでおきたい一冊

≪シリーズ・高次脳機能の教室≫
失行の診かた
「動きとは何か」から始める、これまでにない失行の入門書!
高次脳機能障害のなかでも、最も難解な概念の1つ──「失行」。この複雑なテーマをエキスパートがトコトンわかりやすく解き明かす。「なぜ失行は理解しにくいのか?」。その問いに向き合い、まずは前提となる「動き」のしくみから丁寧に解説。そして失行を「発見」したLiepmannを軸に、彼以前以後まで広く歴史の流れを俯瞰し、点の知識ではなく、立体的な全体像として失行を捉えます。カラーイラストも豊富に収載。

厄介で関わりたくないアルコール依存症患者とどうかかわるか
依存症は「回復する病気である」ことが分かると,かかわりかたも見えてくる.
アルコール依存症というだけで,「厄介でかかわりたくない患者」とされる.著者自身もかつてはそう思っていた.患者と会うことさえ嫌になったこともあった.しかし今は,外来に来てくれる患者を心から歓迎できるようになった.著者は言う.「依存症は,人とのかかわりにおいて回復する病気である」と.本書では,治療者や支援者側の誤解と偏見を詳らかにし,アルコール依存症患者とのかかわりかたを丁寧かつ包括的に解説した.

ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
「ストール本」旗艦テキストが8年ぶりに全面改訂!
さらに洗練、さらに使いやすく
難解なため敬遠されがちな精神薬理学の基本原理を、著者Stahlのユニークな文章とオールカラーの図により、できるだけ平易にわかりやすく解説するベストセラーテキストの全面改訂版。すべてのカラー図版を新しい色や陰影を使いアップデート、さらに見やすくなり、解説と合わせて精神薬理のメカニズムを概念的に学べる工夫が凝らされている。参考文献の総数は旧版の2倍となり、より深く学習する際に有用。精神薬理学の定本として、臨床医、研修医、研究者必読・必備の書。

五訂 精神保健福祉法詳解
精神保健福祉法の解説書の改訂版。法の逐条解説として唯一の書籍であり、制度の歩みや改正法の新旧対照表などの資料も多数収録し、精神保健福祉法のすべてを網羅した。令和4年の法改正(令和6年4月1日施行)を反映した最新版となっている。精神保健福祉に携わる方に必携の書。

注意欠如・多動症―ADHD―の診断・治療ガイドライン 第5版
●子どものADHD診療の“現在地”がわかる!6年ぶりの改訂版
第4版の刊行後に、臨床では2剤の新薬が登場するなど大きな変革がありました。それらを含むADHD薬物療法や心理社会的治療の臨床経験が蓄積されてきたいま、子どものADHDにおける新たな診断・治療の方向性を明確にすべく、改訂されたのが本書です。第5版では、現在のADHDの臨床と研究の現状に即した現実的な内容にアップデートすることを目指し、実践的な検査法や評価尺度の開発・導入に関わる研究者や、各治療法について深く関与している第一線の臨床家など、多数の執筆陣へのアンケートをもとに新たなガイドラインを作成。豊富な解説がますます充実し、この1冊で子どものADHD診療が丸ごと理解できます。専用ウェブサイトからダウンロード可能な「患者用パンフレット」をはじめとする好評の「資料編」も引き続き収録。医療者や学校・児童福祉機関の職員、ADHD患者の家族など、ADHDに関わるすべての方に手にしていただきたい1冊です。

せん妄診療実践マニュアル 改訂新版
せん妄診療の定番書が,「ハイリスク患者ケア加算」に合わせて内容を刷新!現場に即した診療フローと豊富な図表を用いた解説で,効果的・効率的なせん妄対策のために「いま,何をすべきか?」がすぐわかる!

精神科レジデントマニュアル 第2版
レジデントにも、専門医を目指す方にも。精神科臨床のエッセンスがつまった一冊。精神科レジデントや若手精神科医が日常的に遭遇する精神症状・疾患や診療場面で直面する諸問題への対応などについて、コンパクトにまとめ、気になる事柄をすぐにその場で参照できるマニュアルの改訂第2版。
*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です。

てんかん学ハンドブック 第4版
てんかんなら、『てんかん学ハンドブック』てんかん診療の第一人者による、その診療哲学と最新の情報をギュッと詰め込んだミニ百科全書、6年ぶり待望の改訂! 「てんかんは難しい」「どこから手をつけたらいいかわからない」と悩む若手医師、非専門医には最良な入門書として、経験豊かなてんかん専門医にも必ず気づきをもたらす奥深い1冊。「新規抗てんかん薬」はもちろんのこと、ILAEの「2017年分類」および『てんかん診療ガイドライン2018』にも言及。

ケースで学ぶ 認知症の診かた
症例から体系へ―実臨床に根ざした,認知症診療の新しいバイブル.
本書は,若手神経内科医や精神科医,総合診療医などが臨床現場で迷いやすい「認知症の診かた」を,実際の症例をベースに体系的に学べるよう構成されています.陥りやすいピットフォールや最新のトピックスを織り交ぜながら,診断のプロセスと臨床思考を丁寧に解説.近年のトピックスを入れ込み,可能なかぎり新しい認知症診療にも対応しました.科学としての医学と,人としての患者に向き合う姿勢,その両面から“診かた”を磨く,すべての臨床家必携の一冊です.

熱性けいれん(熱性発作)診療ガイドライン2023
日常診療でよく遭遇する熱性けいれん(熱性発作)の初期対応,検査,薬の使い方,注意すべき薬剤,予防接種についてCQ形式でわかりやすく解説.2023年版では前版に寄せられたご意見を踏まえ,CQの内容の更新,遺伝に関する項目,保護者向けの発熱時ジアゼパム坐剤予防投与のパンフレット例や海外の熱性けいれんのガイドラインの紹介を加えより充実した1冊に.
