
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第3版
大好評参考書がオールカラーになって大改訂! 実習でよく出合う78疾患について,看護過程の展開に必要な医学的知識,病期・治療に沿ったアセスメント,看護計画とケアの「根拠」「留意点」がますます充実.好評の「関連図」では発症から病態生理学的変化,治療経過,看護問題の抽出までを図式化し,患者の経過が一目でわかる.さらに第2部以降で「治療別看護」「経過別看護」「感染症看護」「臨床検査値一覧」を収載し,患者の状況に応じたアセスメントと臨床判断ができる.看護学生や新人看護師の「なぜ・どうして」に応える,実習で役立つ頼れる味方!

あの研修医はすごい!と思わせる 症例プレゼン
ニーズに合わせた「伝わる」プレゼンテーション
勝負はプレゼンの前に決まっている!?臨床でまず身につけるべきプレゼンの秘訣を伝授.聞き手・状況に応じた内容や順番,さらに専門科別のコンサル等,アウトプットまでの過程からわかるので本物のプレゼン力がつく

小児の薬の選び方・使い方 第5版
小児科専門医の手の内を公開!
小児の日常診療で頻繁に遭遇する26症状・49疾患について,薬を選び使うまでのステップを経験豊かな小児科専門医がその手の内を公開.いつ何をどう使えばよいか使うべきでないか,わかりやすく解説.改訂5版は新規項目の追加でさらに内容充実,薬用量の表や処方例も最新動向に沿ってアップデート.小児を診るすべての医師,研修医,薬剤師必携.

精神科の薬がわかる本 第5版
精神科全領域の薬がこの1冊で丸わかり! ざっと広くのことを知りたい方へ。
精神科全領域の薬に関する最新かつ正確な情報を、第一線で診療を行う著者が厳選して紹介。精神科を専門とする医師、研修医、精神科看護師はもちろん、精神科以外の科の医療者で「精神科の薬」を使用する機会のある方にとっても有益な1冊。第5版では、なぜその薬が効くのかを知ることで、「精神科の薬」の誤用と乱用を防ぐことに注力しています。

高血圧診療ステップアップ 改訂第2版
「高血圧管理・治療ガイドライン2025」に準拠した学会公認テキストの改訂第2版.
最新の診療指針やエビデンスを踏まえ,ガイドラインの“行間”を丁寧に解説した充実の内容.高血圧専門医や高血圧専門医を目指す医師の知識と実践力を高めるための必携書であり,高血圧診療にかかわるすべての医師にとって信頼できる新版ガイドブックです.

循環器治療薬ファイル 第3版
薬物治療のセンスを身につける
村川ワールドの原点、7年ぶりに改訂
「その状況では何を考えて治療するか」「その薬をなぜ/どのように使うのか」という処方前の考え方を、病態、薬剤の両面からのアプローチで解説。エビデンスだけでなく著者の考え方・使用経験を交えて、現場で知りたいポイントをストレートに提示、村川先生ならではのフレンドリーかつ超絶的な筆致で説きほぐす。改訂に際し、約40頁増。専門医のみならず、一般内科をはじめ広く日常的に循環器治療薬を使う臨床医・研修医必携の手引。

老年医学ケースディスカッション
総合診療編
『あめいろぐ高齢者医療』から5年。老年医学の考え方は広まり、マルモ・多剤併用・フレイルなど高齢者診療の特異性と重要性は認知された。しかし多くの医療者にとって実際の高齢患者を前にした時の具体的対応、つまり「実臨床のノウハウ」は未だわからない部分が多い。そこで、老年科医は高齢患者の疾患を前にした時、具体的にどのように考え、どのようにアプローチするのか。誤嚥・背部痛・認知症・せん妄など、高齢者診療で超コモンなテーマを厳選し、対話形式のケースディスカッション(症例検討)で徹底分解!老年医学の5つのMで高齢者診療を俯瞰、「次の一手」が見える実践書。この本を読めば、老年医学の臨床現場を疑似体験できる(QRコード連動の動画付き)。

DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル
精神疾患の国際的な診断基準、9年ぶりのアップデート!
米国精神医学会(APA)の精神疾患の診断分類、第5版のText Revision。DSM-5が発表された2013年以来9年ぶりに内容をアップデート。日本精神神経学会による疾患名の訳語も大幅にリニューアルとなり、全編新たな内容としてリリースする。
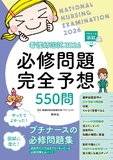
看護師国試2026 必修問題完全予想550問
国試合格のカギとなる必修問題について、最新の出題基準に沿った予想問題を分野別にまとめて掲載。
国試合格に必要な知識が身につけられるよう、問題の解説とその周辺知識を、図表をふんだんに使って解説。
別冊付録として模試を5セット付き。
・最新の出題基準の小項目の全範囲を網羅しており、知識の確認に最適
・“必修問題対策のポイント”で傾向と対策を確認できる
・550問すべて予想問題なので、過去問と重複せずに実力がつけられる
・必修模試50問×5セットは、使いやすい別冊付録
・必修模試の解答・解説も、図表を多用して充実
この本の使い方[1]…必修予想問題300問を解く
必修問題出題基準の全小項目を網羅しています。
まずこの300問を解いて解説を読むことで、国試合格に必要な知識を身につけます。
↓
この本の使い方[2]…別冊付録 必修模試にチャレンジ!
必修模試50問×5セットを、解答用紙を使って試験本番のつもりで解いて、
必修模試解答・解説で答え合わせをしましょう。
↓
この本の使い方[3]…繰り返し解いて知識を確実に!
使い方[1]、[2]で間違ってしまった問題など、苦手なところは繰り返し解いて、
解説をじっくり読んで知識を確実にしましょう。

レジデントのための腹部エコー教室
研修1年目の先生方のために、腹部エコーのエッセンスを一冊にまとめました
◆動画を見ながら、まずは基本の走査法をマスターしましょう。ファントムからヒトへ、段階的なトレーニングで無理なく学べます。
◆各臓器の重要な超音波所見(577画像)を提示。多くの画像を見ることで「目」と「頭」を鍛え、診断のレパートリーを増やしましょう。

「考える」外傷整形外科!
外傷にかかわるすべての整形外科医の羅針盤
外傷整形外科治療の第一人者による、治療の理論や原則を系統的に学ぶためのテキスト。エキスパートも悩んで熟考した諸問題を、豊富な経験と膨大なエビデンス、筆者が積み重ねた症例検討会の議論をベースにQ&A形式で解説。「筆者の推奨する治療方針」では現時点での治療の最適解を提示し、「ちょっと深堀り」ではいまだ解決しないトピックスを独自の視点で読み解く。外傷にかかわるすべての整形外科医の羅針盤となる1冊。

レジデントのための腎臓教室 第2版 2
研修医のための『ベストティーチャー』シリーズ ガイドライン・新薬の動向を踏まえた待望の改訂版
◆腎機能検査、糸球体疾患の分類、水電解質、酸塩基平衡・・・みんながつまずくポイントを「わかりやすさ最優先」で解説しました。腎疾患の診かたを、基礎から無理なく学べる入門書です。
◆成人の8人に1人が慢性腎臓病と言われる今、どの診療科においても腎臓病学の知識が必須となっています。これから腎臓内科をローテートする方はもちろん、腎臓病診療のエッセンスを身に付けたい他科の先生方にもお勧めします。
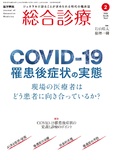
総合診療 Vol.36 No.2
2026年 02月号
特集 COVID-19罹患後症状の実態 現場の医療者はどう患者に向き合っているか?
特集 COVID-19罹患後症状の実態 現場の医療者はどう患者に向き合っているか? ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊

≪消化器画像診断シリーズ 2≫
消化管内視鏡診断テキスト II 小腸・大腸 第5版
消化管内視鏡の“みかた”をわかりやすく解説した定番テキスト,下部消化管(小腸・大腸)編が7年ぶりに大改訂.第1版からの「極力シンプルな記述」「厳選しかつ豊富な写真」のコンセプトのもと,解説と写真を全面刷新.症例画像の模式図は元画像を白黒加工し,矢印や線で病変の位置や範囲を明示し,ポイントが一目でわかる.多忙な研修医や若手医師,医学生が下部消化管内視鏡のエッセンスを身につけるのに最適な一冊.

これで心配ない電解質異常 若手医師/腎臓内科医が市中病院で困らないために
ひとり当直,専門医がいない,頻回な検査が難しい,困る状況で頼れる1冊!
ひとり体制で気軽に診療相談できる人のいない若手や中堅の腎臓内科医,腎臓・内分泌専門医のいない病院や,大学病院のように頻回に検査ができる環境にない病院で電解質異常を安全に管理するためにどうすればいいのか悩んだ時に,実際にできること・すべきことを最大限具体的にまとめました!
1.急いでいるときにここだけパッと見てすぐに動ける「クイックリファレンス」
2.詳しい解説は後から読めるようにエビデンスも合わせて後半に紹介
3.いまさら聞けないけど,実はよくわからない,という疑問に簡潔に答える「若手Drのmemo帳」

終末期ディスカッション
外来から急性期医療まで 現場でともに考える
患者と家族が「これでよかった」と思える意思決定のために
・本書のゴールは,患者と家族が「これでよかった」と思える意思決定支援に向けて必要な考え方を身につけること。
・「患者中心の意思決定」に取り組むにあたり,まずPart 1では「臨床倫理での基本的な考え方」を学ぶ。Part 2では患者,家族,医療従事者がそれぞれ「どのようにコミュニケーションをとっていくか」を豊富な事例と重要なエビデンスに基づき解説する。Part 3では「ACPの実際の方法」を扱う。
・急性期医療の第一線に携わる著者による、「患者中心の意思決定支援」を現場でともに考え、実践していくためのエッセンス。臨床倫理の基本、コミュニケーションの取り方、ACPの実践の3パートで構成。全編対話スタイルをとり、豊富な事例を挙げて解説、あわせて「患者さんとご家族へのメッセージ」を掲載した。「Hospitalist」「INTENSIVIST」からの解説もMEMOとして扱い、知識のまとめとしても有用。急性期医療に携わる医師を中心に医療者必読の一冊。

レジデントのための腹部エコーの鉄則 [Web動画付]
プローブを握る前にこの1冊!
解剖学的知識、走査法といった基本から、画像の解釈、病態の把握、そして日常臨床でよく出会うものの、実はどこにも対応法が載っていないものまで、腹部エコーを行ううえで知っておきたい“鉄則”をまとめた1冊。悩みがち・迷いがちなテーマを中心に取り上げ、症例をもとに実践的な対応策を示す。実践編1「超音波解剖とプローブ走査法」では、丁寧な解説とWeb動画でハンズオンセミナーのように走査のコツを修得できる。

透析患者の糖尿病治療ガイド2025
日本透析医学会ブックシリーズ待望の第2作!
糖尿病に携わるすべての透析・腎臓内科の医療従事者へ。
運動療法や腹膜透析患者の糖尿病管理など最新情報も網羅した必携書!

≪みんなの呼吸器 Respica 2025年冬季増刊≫
波形がもっと読める!人工呼吸器トレーニングドリル
【ドリル形式で波形の読解力を鍛えよう!】
臨床で必要な人工呼吸器グラフィックモニタリングの知識が身につく実践ドリル。ベッドサイドで知っておきたい観察項目や注意点が整理でき、50波形が一度に見られるので知識の振り返りや後輩指導にも使いやすい。1年目からベテランまでチームで楽しくレベルアップできる一冊。

運動療法のための
機能解剖学的触診技術 動画プラス 下肢・体幹[Web動画付] 改訂第2版
頼れるロングセラーが動画を加えてさらにパワーアップ!
書籍の内容はそのままに,アプリ版『動画でマスター! 機能解剖学的触診技術』収載の動画127本/122分を追加。紙面のQRコードから関連する動画をストリーミング配信で視聴可能。
複数カメラで撮影したエキスパートの手技によって写真だけではイメージが難しい立体的な動きがよくわかり,ちょっとした移動時間にも観られるので知識・技術の学習に役立つ内容となった。
