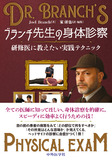
ブランチ先生の身体診察
研修医は必修!全ての医師に役立つ身体診察の技
あなたのこれからのドクターライフすべてが変わる!全ての医師に知ってほしい,身体診察を的確に,スピーディに効率よく行うためのコツとポイントがよくわかる!
豊富な画像と動画で実際のブランチ先生の動きを見て学べるので,現場で明日からすぐ動けるように!
長年の研修医指導で生み出したブランチ先生の独自メソッド「身体診察の9ステップ」とオリジナルの語呂合わせで鑑別診断スキルをレベルアップできる!
※ 本書中で掲載している「語呂合わせ」に併記のQRコードは、「語呂合わせ」を文字データ化としたものです。

眼科医ぐちょぽいpresents 世界でいちばんわかりやすい眼光学の教科書
眼科専門医試験・視能訓練士国家試験 完全攻略
眼科医・視能訓練士のための 眼光学マスターの第一歩
大人気のオンライン勉強会を主催する眼科医ぐちょぽいによる,渾身の眼光学教科書が登場.眼科専門医試験と視能訓練士国家試験の過去問を駆使しながら,臨床現場で理解しておくべき要点を1冊で網羅できます.試験対策本としてだけでなく,とっつきにくい眼光学の超入門書としても活用できる二刀流の内容となっています.「難しいことを,簡潔に,誤解なく伝える」を信条とするぐちょぽい先生の解説のおかげで,眼光学素人の編集者でさえ過去問をスラスラ解けるレベルに達しました.合格への最短ルートはここにあり!

フローチャート 眼科外来 初診・再診マニュアル
本書はPART1からPART4の構成となっており、まず「診断学の基本的な考え方」を解説することで、眼科診療における診断の思考プロセスを明確にします。続くPART2では、見えづらさや眼痛、視野異常など、患者の主訴ごとに診断の進め方を整理し、即座に活用できるフローチャートを掲載。PART3では成人の疾患を、PART4では小児の疾患を詳しく解説し、日常診療に役立つ情報をコンパクトにまとめています。
本書は、著者が欲しかった辞書的に外来診療で困ったときに、すぐに役立つ実践的な本を目指して作成されており、初学者から経験豊富な眼科医まで、臨床の現場で頼れる存在となること間違いなしの一冊です。

点眼薬の選び方 3版
この5年間の変化をふまえて全面改訂。
とくに,投与中に眼科診察を定期的に行う必要がある薬剤,副作用予防のための点眼使用がプロトコールに入っている抗がん剤などの情報を充実させました。
処方薬のほか,患者さんによく聞かれる市販薬もカバー!

眼科疾患最新の治療2025-2027
3年毎の改訂で,眼科疾患における治療指針と最新の情報を簡潔に提供.巻頭トピックスでは,話題のガイドライン,再生医療,AI診療,スマホ内斜視,萎縮型加齢黄斑変性の治療など,注目の10テーマをレビュー.各論では主要な眼疾患の治療を網羅し,コラムを豊富に掲載.日常診療のアップデートに欠かせない一冊.

白内障手術ロジカルテクニック
あなたはロジックに基づいて白内障手術をしていますか?本書では合理的な手術手技が身につくよう、1つひとつの動作に対する理由や考え方が解説され、術中合併症を未然に防いで安全に手術を進められるスキルが習得できます。本書で理にかなった白内障手術の「型」をマスターすれば、直面するさまざまなトラブルに対処し、症例を見てあらかじめ困難な展開を見通せる眼科医を目指せます。
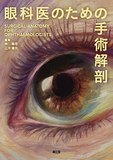
眼科医のための手術解剖
眼科手術全般において,低侵襲あるいは無駄のない合理的な手術を実現するためには「局所解剖の熟知」が必須である.本書は各専門領域のトップサージャンの視点から,手術解剖を究めるために必要な写真と数百枚に及ぶリアルな解剖図で満たした最高の指南書である.基本的なアプローチに加え,術野をみやすくする一工夫も掲載され,手術前に読むだけで自信をもたらしてくれる一冊.

もう迷わない!眼内レンズの選び方
患者の満足度を高めるためのコツと方法
「いかにして患者に最適な眼内レンズを選択するか」──これこそ,白内障術後の患者満足度を左右する最重要ポイントといえる.本書は「最適な眼内レンズ選択」に特化した新しい書籍.問診・検査に始まり,得られた情報を分析し,最適な見え方を実現する眼内レンズの理論・テクニック,さらに,Vision Simulatorや現在国内で使用可能なIOLスペック一覧表など最新情報まで余すところなく掲載した.白内障診療に携わるすべての眼科医必携の一冊.

蛍光眼底造影ケーススタディ
エキスパートはFA・IA・OCTAをこう読み解く
眼循環の評価における基本的検査である蛍光眼底造影の読影ガイドブック。蛍光眼底造影読影のエキスパートたちが、豊富な症例を交え読影ポイントやコツを解説する。蛍光眼底造影の基本を身につけ、カラー眼底写真、OCT、OCTアンギオグラフィなど他の検査と組み合わせれば眼循環はここまで見える。これから蛍光眼底造影を学ぶ初学者だけでなく専門医にも必携の書。

神経眼科学を学ぶ人のために 第4版
神経眼科医・三村治先生が伝授する診療のコツ、神経眼科学を貴方の得意分野に変える!
わが国の神経眼科学の権威・三村治先生が積み重ねた44年にわたる豊富な臨床経験と、最新の文献情報をまとめた入門書。改訂第4版。難解に思われれがちな神経眼科学を分かりやすく解説。初学者の苦手意識をなくし、得意分野へと変える一冊。眼科医のみならず、脳神経内科医、視能訓練士など、視覚・神経分野への理解が求められる医療従事者の強い味方。本改訂ではWeb上にて無料で閲覧できる文献をアイコンで分かりやすく表示。

眼科診療の基本!
細隙灯顕微鏡スキルアップ
細隙灯顕微鏡を用いた診断は,眼科医にとって基本であり,必ずマスターしなければならない。角膜を観察するための検査というイメージが強いが,白内障診断,緑内障診断のための隅角や視神経乳頭の観察,網膜の観察など多種多様な疾患に対応する検査であり,そのためには各部位ごとに観察する際のポイント,所見のみかた等を身につけることが大切である。豊富な具体的所見に加えて類似や鑑別の所見も示し,迅速に正しく判断するコツを写真で理解し習得できる書籍。

眼科レジデントのためのベーシック手術 第2版 2
◆「基礎から学べるこんな手術書が欲しかった」を集約! 基本手術の手技とピットフォールをわかりやすく解説した「はじめての手術」書です。
◆多数ある眼科手術の中から、実際にレジデントが行う機会が多い術式や、手術件数が多く、携わる可能性が高い術式を厳選。
◆フルカラーで見やすい紙面とともに、術野写真やイラストに解説を充実させました。
◆まるで手術室を見学しているかのような動画はすべて字幕解説付き。本文と動画を相互に繰り返し参照することで、効率良く理解を深めることができます。
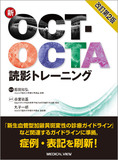
新OCT・OCTA読影トレーニング 改訂第2版
『新OCT・OCTA読影トレーニング』をアップデート。掲載項目・症例数は増加し,初版掲載症例よりも貴重な症例に差し替えた項目もある。また,最新の「新生血管型加齢黄斑変性の診療ガイドライン」など関連するガイドラインに準拠し刷新している。
この一冊にOCT, OCTAの画像を余すことなく載せているからこそ,読影力が自然と身につく必携書!

実況! 硝子体手術Tips165
エキスパートによる「手術討論」動画6本(320分)付き
【最前線で活躍する硝子体術者の技が満載】
教科書では一つの正攻法のみ提示されていることが多いが、実臨床では術者ごとの細かな工夫や差異(Tips)がある。本書では、最前線で活躍する硝子体手術のエキスパート12名がさまざまなTipsを紹介。本書を読めば、術式のバリエーションが必ず広がる。執筆陣が実際の手術を見ながら活発な議論を交わした「手術討論」動画6本(320分)付き。

≪新篇眼科プラクティス 8≫
ぶどう膜炎の心得
すべての眼科医のために
ぶどう膜炎診療に必要な知識を,過去に類を見ないほど徹底的にビジュアル化.所見はたくさんのイラスト・典型写真でポイントをわかりやすく提示.フローチャートも満載で,第一線で活躍する先生方の考え方がわかる.すべての眼科医の先生にご覧いただきたい一冊.【シリーズ概要】「日常臨床にすぐ役立つ」をコンセプトとした「眼科プラクティス」の最新シリーズ.今シリーズでは図版をより効果的に示すことで,さらにビジュアル面を大幅強化.直感的に理解できる「視る教科書」を目指した.
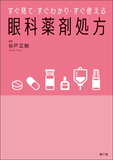
すぐ見て・すぐわかり・すぐ使える 眼科薬剤処方
眼科診療のあらゆる場面を想定し必要な薬剤情報を解説した,眼科に携わる全スタッフの“新”必携書.基本薬剤は作用機序,薬剤一覧表,処方例,禁忌に絞ってまとめ、「すぐ見て・すぐわかり・すぐ使える」のコンセプトを具体化した.また手術用剤や検査薬剤に加えて,難渋する全身管理や感染症対策については病棟管理として解説し,単なる薬剤処方の参考に留まらない“実臨床”で本当に役立つ構成となった.
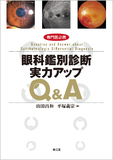
専門医必携 眼科鑑別診断実力アップQ&A
確定診断までに頭を悩ませる107症例を厳選。全症例をQ&A形式で解説し、鑑別診断の“勘どころ”が実践的に学べ、日常診療における疑問・迷いがなくなる。エキスパートが臨床現場で問診結果(年齢・性別・主訴・病歴など)や臨床所見、検査所見からどのように鑑別をすすめているのかがよくわかり、実力アップに直結する一冊。

写真でわかる! オルソケラトロジーフィッティング
学童の近視抑制 お悩み相談室
好評書『クリニックではじめる 学童の近視抑制治療』の実践編.いざ,臨床で近視抑制治療を始めた際に,教科書通りにいかない場面に困る場面は珍しくありません.本書は,そんな近視抑制で遭遇するトラブルについて解決までの道すじを,写真とポイントで丁寧に示した症例解説集.オルソケラトロジーフィッティング以外にも,低濃度AT点眼・多焦点SCL・近視管理用眼鏡・レッドライト治療などの近視抑制最前線の情報も盛り込みました.

スタートアップ!子どもの近視進行抑制治療ガイド
豊富なエビデンスに基づく治療戦略と診療判断を最短距離で臨床に実装!
最新のガイドラインに完全準拠!!
『小児の眼鏡処方に関する手引き』
『低濃度アトロピン点眼液を用いた近視進行抑制治療の手引き』
『近視管理用眼鏡(多分割レンズ)ガイドライン(第1版)』
小児の近視が増加の一途をたどる現在、進行抑制治療は眼科外来に不可欠となり「介入の必要性をどう判断し、どの治療をいつ始めるか」という臨床的判断が大きな関心を集めています。
本書は近視治療の第一線で活躍する著者が、国内外のエビデンスをもとに日本の実臨床に即した適応と課題を的確に整理し、科学的根拠を日常診療の判断に応用できる形で解説しました。低濃度アトロピン点眼、オルソケラトロジー、多焦点ソフトコンタクトレンズ、近視用眼鏡、レッドライト療法など、国内で承認済・承認予定の治療選択肢について、使い分けや併用戦略、副作用・リバウンド対策までポイントを絞って提示。各治療の作用機序、単独・併用時のエビデンス、年齢別の適応、合併症対策までを構造的に解説しています。また、眼軸長に基づく治療評価法や、二次性近視の鑑別、不同視近視への対応も取り上げ、治療の導入から継続・変更に至るまでの指針となる視点を提供します。実臨床で多くの眼科医・視能訓練士が直面する「見え方の不満への対応」「保護者への説明」などの課題にも触れ、説明にすぐ使える“伝え方のコツ”も収載しています。
近視進行抑制治療をどのように導入するかの検討段階では方針を明快に示すスタートアップマニュアルとして、すでに治療を導入している場合は自身の診療をアップデートする手引きとなる1冊。多忙な眼科医・視能訓練士にこそ届けたい、実践的で臨床直結型のコンパクトなガイドです。

フローチャートでみる神経眼科診断
眼科の外来で比較的多くみる神経眼科の主要な所見ごとに,診断手順をフローチャート形式に凝縮した.フローチャートのステップごとに,豊富な症例写真とポイントを絞った解説を加え,診断に至る早道と鑑別すべき所見を提示.難解きわまる神経眼科診断をクリアカットにまとめた一冊.
