
即実践!ICUのこれだけ栄養療法
どんな重症病態にも対応するための基礎知識と判断力が身につく14講
重症患者に対する栄養治療を始めるなら,まず読んでおきたい一冊!経腸栄養と経静脈栄養の始め方・考え方,病態ごとの栄養療法,refeeding syndromeの対処,栄養評価,synbiotic therapyなどの必須事項について,最新のエビデンスと現場での経験を合わせてわかりやすく解説.どんな病態にも悩むことなく,“及第点”以上の対応ができる知識と判断力が身につきます!

医師1年目からの わかる、できる!栄養療法
患者にあわせた投与ルートや輸液・栄養剤の選択など、根拠をもって実践するためのキホン
その栄養処方,本当に適切ですか?投与経路の決定,栄養剤・輸液の組立て方,段階的な増減量など症例をまじえ解説.なぜそうするか?どう実践するか?がわかれば自信をもってできる!臨床にでたらまず読むべき1冊
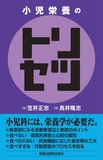
小児栄養のトリセツ
小児トリセツシリーズ第7弾。子どもは食べることで栄養を摂取し、成長していく。疾患によって栄養障害が起こった場合には、基礎疾患の治療とともに子どもの成長をサポートするための栄養管理が必要である。また、器質的な疾患によらない栄養障害も小児では問題になりやすい。乳幼児期や学童、思春期の「食べない・食べられない・食べすぎる」悩みは医学的なアプローチだけでなく、栄養学的な視点を加えることで解決に導けることも多い。
本書は小児医療に携わる人がはじめて栄養について学ぶための「トリセツ」である。
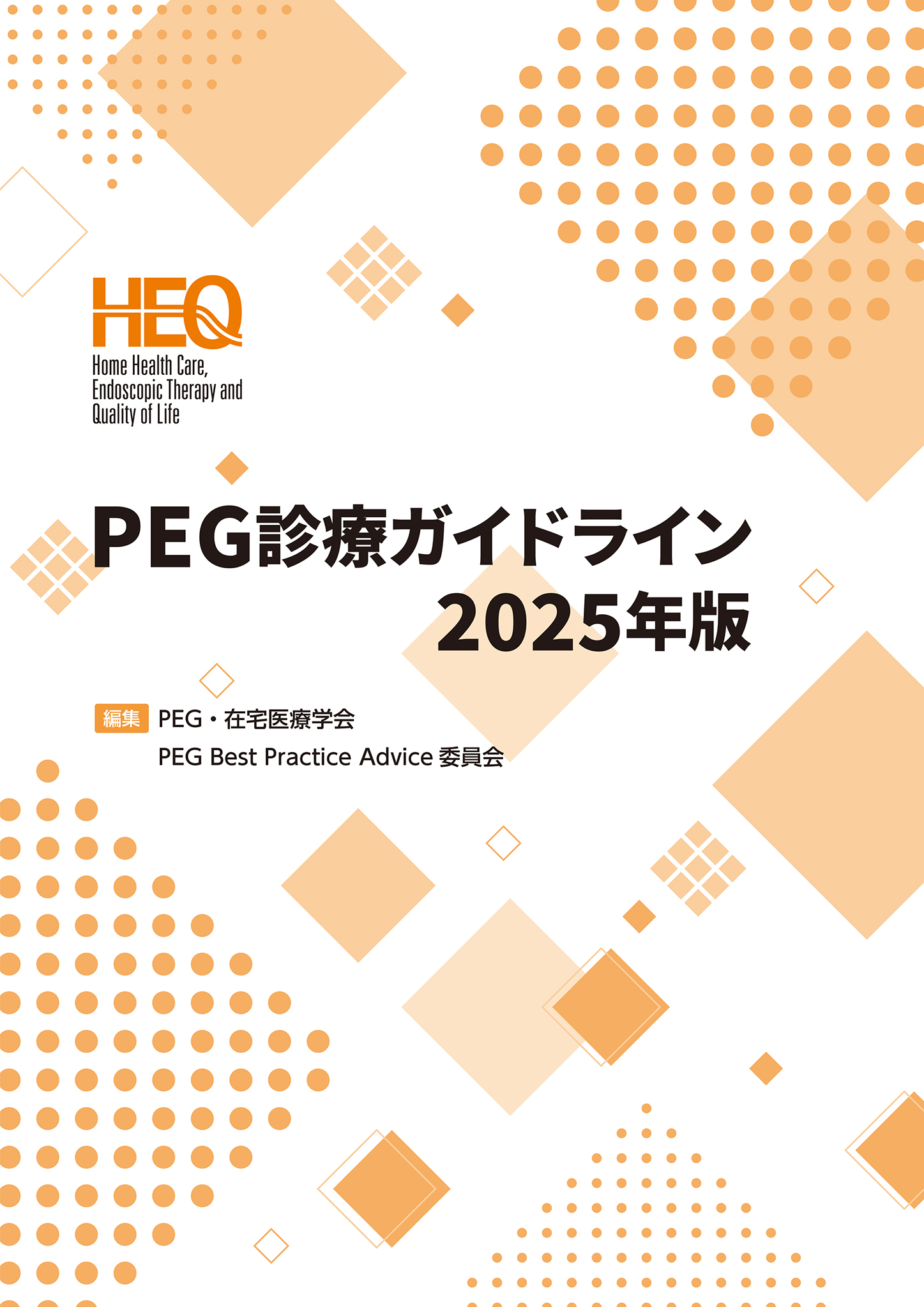
PEG診療ガイドライン 2025年版
●本書は,実臨床における真に必要なメッセージとしてPEGを冠する本学会の総力を挙げて作成されました。
<発刊に寄せてより>
今回刊行されたPEG診療ガイドラインの基本コンセプトは,実臨床において真に必要なメッセージを作成することで,そのためにエビデンスのみに縛られることなく,経験豊かな専門家の意見も柔軟に汲み入れられているはずです。海外の学会でも新定義の厳しい診療ガイドライン(PG)と区別してBest Practice Adviceという実臨床で役立つ支援ツールが開発されていますが,本ガイドラインは正にBest Practice Adviceとして,PEGに関連する診療に携わる方々を支援する有益な情報源となることを確信しています。(上野文昭)
<本書の刊行にあたってより>
胃瘻よりもCVポートの方を希望します,とか,誤嚥性肺炎の人には胃瘻がいいのでしょうか?とか,胃瘻からの栄養剤投与はどうしたらいいのですか?とか,胃瘻を造ったら口から食べられなくなるのですよね,といった声が近頃,医療従事者から私に届くようになりました。20年くらい前には想像がつかないような状況です。栄養投与には患者さんごとに最適の投与ルートがあることや,嚥下訓練には適切な栄養投与が必要なことや胃瘻の基本が理解されていないのだと痛感しました。(中略)
PEGは単なる「内視鏡を使って胃にカテーテルを留置することができ,胃内に栄養剤を注入することができる」投与ルート造設法です。胃瘻は造設することが目的ではなく,造ってからの栄養投与が目的なのです。胃瘻が出来てから医療が始まるのです。(中略)
このガイドラインはPEGと栄養に関する,現時点での標準的な扱い方が記されています。本書を読むことで,PEGを有する患者さんに真摯に向き合うようになってほしいと考えています。
多くのPEGに携わる方々に本書を読んでいただきたく思います。そして本書を手に取られた方々にとって,PEGの理解のために少しでも有用であれば望外の喜びです。(西口幸雄)

フローチャートで出来る!
小児輸液のトリセツ
脱水でグッタリしている子どもが救急外来に来たとき、是正輸液療法を行えばたちどころに具合が良くなる..輸液療法は魔法のようなツールである。ところが多くの小児科医療の現場では、誤った輸液療法が漫然と行われている。それは「輸液療法をきちんと勉強していない」ためである。実は小児の輸液療法において求められることは次の4つしかない。「1.脱水の評価 2.輸液製剤の選択 3.輸液の投与量 4.輸液の投与速度」である。この4つのポイントさえ理解すれば、すべて脱水の子どもたちを適切に治療できる。
本書は小児輸液のエキスパートの考え方をフローチャートに凝縮し、輸液療法を開始してから終了するまで、一連の流れをひとつひとつ解説していく。本書の示すとおりに沿っていけば、誰でも簡単に正しい輸液療法を行うことができるようになる。臨床で知りたいことがすぐわかる! 小児トリセツシリーズ第3弾。「トリセツ」で小児科医療はもっと面白くなる。

日本栄養治療学会JSPEN NST専門療法士認定試験 過去問題集
NST専門療法士認定試験対策本の『一般社団法人日本静脈経腸栄養学会NST専門療法士認定試験過去問題集Ⅰ』待望の改訂新版.近年の出題傾向をふまえて過去問題を精選し,丁寧でわかりやすい解説を付記.「関連する重要事項」も併せて掲載し,試験対策としてはもちろん,NST業務に求められる幅広い知識の習得にも役立つ一冊.

レジデントのための食事・栄養療法ガイド
医学部では教えてくれない臨床栄養の入門書。
病棟ですぐに役立つ栄養療法の基礎知識をまとめました!
◆ 医師となり、初めて患者さんを担当すると直面する多くの課題を解決する一冊!
◆ 種々の病態に応じて食事療法、経腸栄養、静脈栄養を実践するための知識を分かりやすく解説しました。
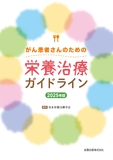
がん患者さんのための栄養治療ガイドライン 2025年版
さまざまな疾患において栄養障害が治療を受ける上で負の影響を与えることが明らかとなり、がんもその代表的な疾患のひとつです。栄養障害を改善するための栄養治療を並行して行うことで、治療効果を上げ、副作用や合併症を軽減し、生活の質を改善することもわかってきています。
栄養治療の重要性が再注目されていることから、患者向けガイドラインが刊行される運びとなりました。患者さんやご家族の疑問にQ&A形式で丁寧に答えます!

サルコペニア・フレイルに関する栄養管理ガイドライン2025
日本臨床栄養学会/日本サルコペニア・フレイル学会の共編による,サルコペニア・フレイルに関する栄養・食事のガイドライン.サルコペニア・フレイルの予防・治療に中心的な役割を果たす栄養・食事に関するエビデンスを国内で初めてガイドラインとしてまとめた.

レジデントのための 栄養管理基本マニュアル
NSTディレクターになるための必読書
レジデントやコメディカル向けに,栄養管理の実際をわかりやすく実践的に解説したポケットマニュアル.栄養アセスメントや病態別の栄養管理の実際などのほかに,「病院食とは?」といったベーシックな項目も取り入れ,これから栄養管理を始める人にも一から学べる内容となっている.NSTのメンバーを目指す医師,看護師,薬剤師,管理栄養士の必読書.

低Na血症
体液・水電解質異常の臨床とその理解
世界中の低Na血症専門家が結集した低Na血症診療のバイブル! 低Na血症の歴史から近年解明が進む疫学・病態生理,新規治療薬トルバプタンなど最新の知見や,鑑別が難しく,原因によらない対応が必要な高度低Na血症へのアプローチまで具体的に解説.翻訳なのに読みやすい!これまでの臨床マニュアルと一線を画す本質的理解を促す1冊.

メディカルスタッフのための栄養療法ハンドブック 改訂第3版
臨床栄養に必要な知識・データをポケットサイズに凝縮.今改訂では,各種ガイドラインや経腸栄養剤等の最新知見を反映した.解剖・生理,代謝,各種栄養素,スクリーニングとアセスメント等をコンパクトに解説した「準備編」,現場で必要となる経腸・静脈栄養,病態栄養等を網羅した「実践編」の二部構成とし,巻末付録には輸液一覧表,各種評価ツール,食事摂取基準を掲載.チーム医療に携わる全スタッフで共有すべき情報を簡潔にまとめた充実の一冊.

病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック 改訂第8版
日本病態栄養学会による「病態栄養専門管理栄養士」認定のための教育セミナー指定テキスト.今改訂では目次構成の大幅な見直しを行い,『臨床に必要な基礎知識』の章を新設し,「日本人の食事摂取基準」,「GLIM基準」,「リハビリテーション」,「健康医療データの活用」,「医療安全」など日常臨床に直結する項目を追加した.その他にも「腸内細菌と栄養」,「症例報告の書き方」の項目などを追加し,より使いやすい書籍を目指した.

エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の考え方
メディカルスタッフが知りたかった『なぜ?』
メディカルスタッフの現場の「なぜ」がわかる!持ち運びサイズで病態ごとの栄養・経路切り替えの基準を解説し,実際の処方例も交えて輸液・栄養剤選びの実際の考え方が身につく一冊!

輸液・静脈栄養の管理の実際とコツ
カテーテル・ポート・輸液組成から感染対策まで
<推薦のことばより抜粋>
・本書は,静脈栄養管理を正確かつ安全に行うためのバイブルとも言え,適切な栄養管理を志す医療人には必読の書となることを確信している。(大柳治正)
・薬剤師にとっては,薬学教育にない未知の分野でもあり,本書を常に傍らに置き,栄養・輸液療法の管理について正しく理解できるまで,繰り返し読み直すことをお勧めする。(島田慈彦)
・「むずかしいことをわかりやすく,わかりやすいことを深く,深いことをおもしろく」まとめた実践書です。すべての看護師の方々に,身近なテキストとしてお勧めしたい一冊です。(山田繁代)
・静脈栄養のバイブルとなるこのような本を出版されたことは,本当にうれしいことです。栄養管理やNSTに参加されるすべてのスタッフの必読書として,本書を推薦します。(中村丁次)<はじめにより>
NSTの普及とともに経腸栄養一辺倒の傾向が出現し,(中略)同時に,経腸栄養一辺倒の考えを再考し,静脈栄養も理解しておかなければならない,という流れも出てきました。私は経腸栄養も重要だけど静脈栄養も重要だ,両方が理解・実践できて初めて本物の栄養管理のプロだ,と言い続けてきました。
(中略)私が考えている内容を,図や写真もたくさん使って,具体的に,誰にも理解できるように,という意図で書かせていただきました。(中略)リラックスして読んでいただけるよう,文章は読みやすい雰囲気にしたつもりです。(中略)「これは!」と胸にズンと感じていただける部分があれば,著者としてこのうえない幸せです。(井上善文)

総合診療ブラザーズの臨床栄養講座
「総合診療ブラザーズ」に山田悠史医師を加えたシン・総合診療ブラザーズ,ここに見参! 医学系YouTuber松本朋弘医師・小澤秀浩医師による「総合診療ブラザーズ」に日本や米国で活躍中の山田悠史医師と仲間たちが加わり、「patient journeyに寄り添う栄養摂取の提案」を軸に入院中・治療中の患者が効率的に栄養を摂取する際のポイントや、臨床で役立つ栄養指導・栄養療法に切り込みます。さまざまな症状・疾患をもつ症例ごとに、Q&A形式で実践的な栄養投与法を、老年医学の専門内容もプラスして徹底レクチャー!

小児臨床栄養学 改訂第2版
日本小児栄養消化器肝臓学会編として,初版からのアップデートに加え,栄養評価・食事指導の実際や診療報酬制度など,小児のNST活動に役立つ実践的な内容を盛り込みました.「スポーツと栄養」,「小児の在宅栄養管理」など新規項目も充実!小児栄養の教科書として,小児科医,栄養士,看護師ほかメディカルスタッフだけでなく,小児の発育に関わる保健師,教育・保育従事者の方々にもぜひ活用していただきたい1冊です.
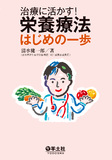
治療に活かす!栄養療法はじめの一歩
“なんとなく”行っていた栄養療法に自信がつく!「疾患治療に栄養が大切なのはなぜ?」「経腸栄養剤の違いと選び方は?」など基本的な考え方から現場で役立つ知識まで自然に身につく医師のための入門書

三ツ星シェフへの道 「経静脈栄養」実践GUIDE
経静脈栄養って,面白いですか?
「難しい」「苦手だ」と思っている医療従事者も多いかもしれません.でもそれは,臨床栄養について学ぶ機会や興味をもつ機会が今まで少なかったからです.本書を読めば,臨床栄養や経静脈栄養はさほど難しくなくなるはずです.
臨床現場での栄養管理は,療養生活を乗り越えるエネルギー・活力や,疾患や侵襲的治療によって生じた創傷部を治癒する材料のほか,日常生活を支える強い筋肉や骨をつくる材料を得るために必須のファクターです.もし,それが,それぞれの患者の生活・状態や今後のロードマップを満足に考慮していない,愛がなく,不十分なものだったらどうなるでしょう? 臨床現場にはいまだ医原性低栄養が生じやすい素地があり,それによる回復の遅れや治療強度の不足は,患者にとって大きな損失になります.そうならないためにも,経静脈栄養の管理法や輸液製剤の選びかた・組み合わせかたを楽しく学びながら,臨床栄養の実践に必要な“意識”と“知識”を身につけましょう!
輸液の1滴に栄養と愛をこめて….さあ目指そう,経静脈栄養の三ツ星シェフを!

ミニマム輸血学
医療者ならば最低限の輸血学の知識は必須である.しかし,日進月歩で発展する医療業界においては最新かつ火急の項目に時間を取られ,輸血学を十分に学ぶ機会は無いに等しい.そこで本書では,輸血学の重要知識を凝縮し,コンパクト且つ分かりやすく整理・解説した.見た目はミニマムながらも,系統立ててまとめられた内容は奥が深くて必要十分.医療系学生にも,医療系学生を教える教員にも薦めたい,新しいテキストである.
