
NANDA-I看護診断 定義と分類 2024-2026 原書第13版
NANDA-I 看護診断のオフィシャルブック最新版
NANDAインターナショナルで承認された看護診断を収めたハンドブック。56の新しい看護診断を追加、123の看護診断を改訂。診断の軸構造を大幅に改訂し、各診断に一貫した軸値を割り当てた。診断指標は、MeSHの用語を使用することで、明瞭性・一貫性が高まった。アセスメントから適切な看護診断確定までのプロセスについての解説も充実。臨床でのレファレンスに、また看護診断の学習に役立つナース必携の書。

≪シリーズ ケアをひらく≫
傷の声
絡まった糸をほどこうとした人の物語
現在の精神科医療に不足している視点を教えてくれる。
本書は複雑性PTSDを生きた女性が、その短き人生を綴った自叙伝である。過酷な家庭環境に育ち、複雑性PTSDを持つ著者が、ふり幅の大きな人生を描く。なぜ自分を傷つけるのか、という疑問への回答と、傷ついた人に必要なのは、権力や物理的力で抑え込むことではなく、ケアであるべきではないかという気づきとヒントを医療者に与えてくれる。
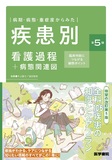
病期・病態・重症度からみた
疾患別看護過程+病態関連図 第5版
臨床判断につながる観察ポイント
ほしい情報が全部入り! 臨床判断能力の養成につながる疾患別看護過程の決定版!
全科106疾患について、医学解説と看護診断名をアップデート! 病気がみえる、カルテが読める「イラストでみる病態生理、症状、診断、合併症、治療、薬剤一覧」。病期・病態・重症度からみたケアのポイントがみえる、臨床判断につながる観察ポイントがみえる「看護過程フローチャート、情報収集、アセスメント、ケアプラン、評価」。患者の全体像がみえる「病態関連図」。ほしい情報がオールインワンになった1冊。

パッと見でつかむ! 認定・専門看護師が教える急変対応クイックチェック
予測から症状別・疾患別の対応まで
新人・若手ナースの多くが経験不足のため不安に感じている急変対応。本書はアセスメント項目や検査値、評価法、薬剤や略語などいざという時に使える急変の知識を2頁ごとの構成と豊富なイラストで解説しているのでカンタンに調べられる。これで突然根拠を聞かれても怖くない!

看護教育の当たり前を問い直す
悪しき連鎖を “今” 断ち切って、もっとワクワクする看護教育へ
「看護学生に人権はない」「看護学校はパワハラの温床」──そんな言葉を耳にしたことはないだろうか。本書は、看護教育のハラスメント的指導、“べき論”の連鎖に終止符を打つ、覚悟と希望の書。「看護を教える」とはどのような営みなのか、看護も教育も本来の目的に立ち返り、もっと楽しく、ワクワクする看護教育へ。方法論? 否、教育の<本質>を問う、すべての“育てる人”に贈るバイブル。
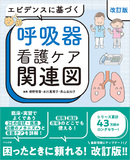
エビデンスに基づく呼吸器看護ケア関連図 改訂版
急変~急性期~慢性期の知識が必要な呼吸器看護。本書は3症状、19疾患、周術期、呼吸リハ、緩和ケアを病態生理・診断・検査・看護ケアと関連図で詳解。気管挿管、酸素療法、人工呼吸療法等もコラムで解説し最新エビデンスを反映したオールカラーの超パワーアップの改訂版。

実習でよく挙げる
看護診断・計画ガイド 第2版
「来週から実習!でも看護計画ってなにをどうするの?」なあなたへ!看護学生のつよい味方がボリュームアップ!
各領域・病棟に共通で、実習でよく挙げる60の看護診断について、どんなときに挙げる看護診断なのか、標準看護計画を掲載。
Part1では看護実習の前におさえておきたい看護診断と看護過程の基本がおさらいできます。
どのように看護診断を挙げて看護計画につなげるのか、考えかたとその流れがわかります
Part2では各領域・病棟に共通して実習先でよく出合う看護診断を60個収載しました。
受け持った患者さんの看護計画を立てるとき、実習記録を書くときに何度も役立ちます
Step1 看護診断を挙げてみよう
患者さんの状況を観察して情報を集めたら、「どんなときに挙げる診断?(診断の意味)」を読んで、似たようなケースがないか探してみましょう
↓
Step2 看護計画を立てよう
標準的な看護計画とその根拠を知り、どのような看護介入ができるか、どんな要素が実習記録に必要なのかを確認しましょう。
個別のケアとして考えることが大切!
↓
Step3 看護目標を設定しよう
「期待される結果(看護目標)」を参考にしながら、患者さん一人ひとりの状況に合った目標を設定しましょう

エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 第3版
臨床・実習でよく出会う25疾患について、誘因・原因から病態生理学的変化、看護ケアまでを図式化した看護ケア関連図ガイドの第3版。疾患のメカニズム、症状、検査・治療の知識、観察のポイント等もオールカラーで解説。看護ケアの根拠が一目でわかる!

看護学テキストNiCE
看護理論 改訂第3版
看護理論21の理解と実践への応用
看護実践の支えとなる代表的な21の理論を読み解くテキストの改訂第3版。理論家の人物像や彼らの生きた時代背景から解説し、理論が打ち立てられるまでの過程と理論の枠組みをやさしく学ぶことができる。事例を通じて、臨床現場での応用に結びつける思考力を育む。今改訂では実際の講義の経験をもとに、総論解説を刷新。また各論にはキャサリン・コルカバのコンフォート理論を追加した。

根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第3版
大好評参考書がオールカラーになって大改訂! 実習でよく出合う78疾患について,看護過程の展開に必要な医学的知識,病期・治療に沿ったアセスメント,看護計画とケアの「根拠」「留意点」がますます充実.好評の「関連図」では発症から病態生理学的変化,治療経過,看護問題の抽出までを図式化し,患者の経過が一目でわかる.さらに第2部以降で「治療別看護」「経過別看護」「感染症看護」「臨床検査値一覧」を収載し,患者の状況に応じたアセスメントと臨床判断ができる.看護学生や新人看護師の「なぜ・どうして」に応える,実習で役立つ頼れる味方!

≪からみた看護過程≫
緊急度・重症度からみた
症状別看護過程 第4版
+病態関連図
必要な情報・知りたかったことがわかる! 症状別看護過程の決定版
実習でよく出会う62症状の医学の基礎知識とケアプランを掲載した症状別看護過程の決定版。第4版では医学情報と看護診断などのアップデートを行い、臨床現場に必要な知識を網羅しました。イラストやチャートを使ったビジュアルな医学解説と、ケアの流れやポイントだけでなく患者の全体像がみえる「病態関連図」で理解を深める看護解説。さらに観察やアセスメントと並行して対処すべき緊急対応もカバーした、実習必携の1冊です。

輸液カテーテル管理の実践基準 2025年版 第2版
輸液治療の穿刺部位・デバイス選択とカテーテル管理ガイドライン
輸液カテーテル管理の実践基準を示したガイドラインの改訂2版.今版では,近年使用が広まっているミッドラインカテーテルについての推奨基準に加え,カテーテルだけでなく輸液ポンプやシリンジポンプ,また小児の輸液カテーテル管理についての内容も新たに盛り込みました.既存の内容についてもエビデンスを見直し,初版より広くご活用いただいていたデバイス選択のアルゴリズムについても,使用薬剤から考えるデバイス選択の図を新たに加えてアップデート!輸液治療に携わる医療従事者の方々に向けて,安全な輸液治療のために是非お手元に置いていただきたい一冊です.
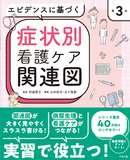
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 第3版
臨床・実習でよく出会う24の症状について、その病態生理と看護ケアがつながる「看護ケア関連図」で解説した大好評ガイドブックの第3版。ガイドライン、治療・検査・看護ケアなどを最新情報にアップデート。急変時から生活期・地域まで役立つ入門書。オールカラー。

看護における危機理論・危機介入(第5版)
日本の看護界に危機理論を紹介した一人で,またフィンクの危機モデルの研究家の第一人者である著者が,看護学生や臨床の看護師のために危機理論,危機の考え方,とらえ方,危機モデルについて解説,書き下ろしたわかりやすくやさしいテキスト.危機理論を学び,その傾向を知り,患者をみる,といったプロセスのなかで,危機理論とは何かを概説,喪失と危機,医療の現場での危機状況,危機モデルと危機看護介入を解説した改訂版.

≪からみた看護過程≫
ストレングスからみた
精神看護過程
+全体関連図,ストレングス・マッピングシート
『ストレングスモデル実践活用術』の応用として,臨床で活躍する看護師の方にもお勧め
対象者自身が望む「自分のなりたい姿」を目標に、対象者の考えや経験等をストレングスとして活かす視点から看護過程を解説する待望の書。ストレングスモデルで把握できる強みだけでなく、生物学的・心理学的・社会的情報(BPSモデル)、セルフケアに関する情報も併せたアセスメントのポイント、ストレングス・マッピングシート、取り組むことの見出し方、全体関連図、看護計画の立案と実施、評価までを指南する。

看護研究における文献の調べ方・活かし方
代表的な文献データベース6種類の検索方法を、豊富な画面例でわかりやすく紹介!
看護の臨床現場で抱く臨床疑問(クリニカルクエスチョン=CQ)を研究テーマとしてふさわしい研究の疑問(リサーチクエスチョン=RQ)に洗練させていく過程について、章を追ってやさしく解説した看護研究の入門書です。
医中誌Web、PubMedなど、6種類の代表的な文献データベースの検索方法を、豊富な画面例とともにわかりやすく紹介しています。
≪本書は第1版第1刷の電子版です≫

臨床判断ティーチングメソッド
高度化、また地域へ移行が進む医療現場では、看護師の臨床判断能力の向上が求められています。本書は、タナーが開発した臨床判断モデルをもとに、学習者が実践的な思考を獲得する方略をわかりやすくご紹介します。学習者中心の考え方や、生涯学習を続けるためのかかわりなど、教育学の最新の知見とともに、基礎教育から新人、エキスパートへと、看護師の熟達を橋渡しする1冊です。

エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図
胸痛、動悸等の症状別、急性心筋梗塞、大動脈解離、刺激伝導系の異常、弁膜・心膜・心筋疾患、心不全等の疾患別、周術期、心リハ、緩和ケア等の病期・治療別に詳細に解説。フィジカルアセスメント、心電図の基本をカラーで示した、新人からベテランまで活用できるテキスト。

エビデンスに基づく脳神経看護ケア関連図 改訂版
脳神経看護の6症状(意識障害、高次脳機能障害等)と18疾患(パーキンソン病、脳腫瘍等)のほか、手術、周術期、リハ、緩和ケアなど病期・治療別にオールカラーの関連図で詳細に解説した。脳卒中や認知症などの最新ガイドラインに基づいてバージョンアップした改訂版。

新訂版 実践に生かす看護理論19 第2版
19人の看護理論家の看護理論と看護過程のつながりと、中範囲理論を事例を用いた看護展開で解説している。
